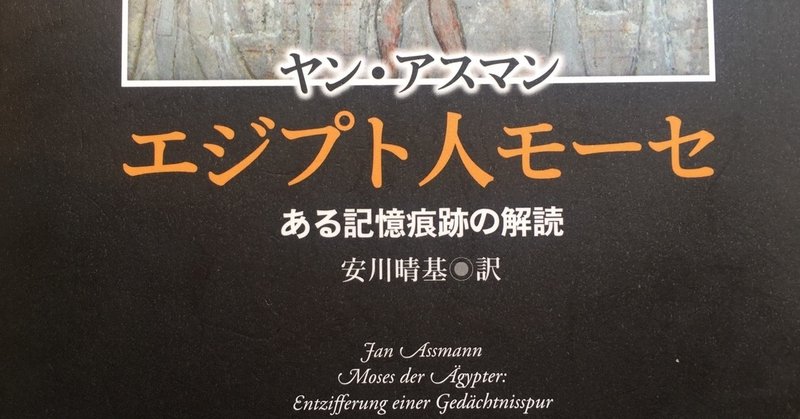
エジプト人モーセ/ヤン・アスマン
自然と文化。
このnote上でも紹介してきたように、これまで二項対立的に扱ってきた両者を、最近の哲学の流れでは区別できないものとして扱われるようになっている。
境のない状態をどう捉えるかは、いろんな考えがあり、『ポストヒューマン 新しい人文学に向けて』(書評)のロージ・ブライドッティは、自然-文化連続体という概念で唯物論的な捉え方をするし、このスタンスは『社会の新たな哲学: 集合体、潜在性、創発』(書評)のマヌエル・デランダの考えにも近い。
また、科学人類学を提唱するブルーノ・ラトゥールは『虚構の「近代」―科学人類学は警告する』(書評)で、人間と非人間を完全に分離することを善とする近代の「憲法」的なものが両者を区別しつつ背後でその両者のハイブリッド(混淆物)を大量に生み出したことを指摘しつつ、二項対立の背後にあるハイブリッドを生みだす仕組みをアクターネットワークとして分析しているし、さらに『四方対象: オブジェクト指向存在論入門』(書評)などで知られるグレアム・ハーマンはまた異なる考えで、すべてを非唯物論的なオブジェクトとしてみる姿勢をもって、人間と非人間、文化と自然という伝統的な二項対立を乗り越えようとしている。
もはや自然と文化、非人間と人間を区別することの無意味さが様々な角度から明らかになってきているように感じていた。そもそも、この二項対立の乗り越えは、非西洋人である僕らには、果たしてそれが問題なのか?と思えるほど、その作業に困難があるとはあまり想像ができない。
しかし、どうやらそうではないようだ。
今回、このエジプト史学者であるヤン・アスマンが、従来の事実をベースとした歴史とは異なる記憶の変遷を扱う記憶史的なスタンスで、モーセという歴史的には存在の証拠が示せない、けれど西洋の文化においては大きな存在である想起的対象を巡って考察を行った『エジプト人モーセ』という本を読んでみて、それを感じた。存在したかわからないモーセがこれだけ深く時代を超えて西洋の文化に存在してきたのと同様、自然と文化あるいは非人間と人間の二項対立も根深くその文化や生活のなかに入り込んでいることに気づかされた。僕らが思うほど、この二項対立を乗り越えることは容易ではないかもしれない。

宇宙即神論と一神教
では、著者のヤン・アスマンはどのような形で、モーセを巡る西洋の記憶の歴史的な移り変わりのうちに、自然と文化あるいは非人間と人間の二項対立を見いだしたのか?
まずは、この文章の引用からはじめてみよう。
わたしが宇宙即神論と呼んでいる、この広く行き渡った宗教上の確信の圏域には、宗教間の敵対関係の入り込める余地などなかった。これが、なぜユダヤ教やキリスト教といった対抗宗教の敵対的力が、古代の教養人にかくも強い衝撃を与えたのか、その理由である。宇宙即神論と一神教の対立、あるいは自然と啓示の対立は、決して解消されたわけではなく、ただ、キリスト教会の輝かしい発展の裏で抑圧されただけだった。この対立がルネサンスにおいて回帰したこと、そしてこの対立が近代の形成期にたどった緊張に満ちた歴史が、エジプト人モーセをめぐる論争のサブテクストをなしている。
宇宙即神論と一神教の対立。まず、アスマンがいう「宇宙即神論」とは何か。
これは後にスピノザが「神即自然 (deus sive natura) 」といって一元論を唱えたものに近い。神は自然という形で顕現しているという汎神論的な考えで、古代エジプトの宗教はそもそもこうした思考に基づいていたらしい。八百万の神をもつ日本古代の信仰にも近いといえる。
これに対して、モーセの名の下に創唱されたと考えられている一神教はこれとは異なる。十戒に、主が唯一の神であること、偶像を作ってはいけないこととされるように、モーセの神は超越的かつ絶対的である。それは自然として顕現することはなく、モーセのような者を通じての啓示としてのみ現れる。
もとより一神教が歴史的に登場してくる前の宗教は多神教的なものであった。一神教が先ではなく、多神教が先なのだ。
発明としての一神教
そして、当時の人々は、自分たちとは異なる民族の神々が自分たちの神々とは異なっていたとしても、敵対したり排除したりすることはなかった。
たとえ文化や言語や風習がどれほど異なっていようとも、諸宗教には常に1つの共通基盤があった。それゆえに宗教は、文化間の翻訳を可能にするメディアとして働くこともできたのだ。神々は国際的だった。なぜなら神々は宇宙的だったからだ。異なる民族は異なる神々を崇拝した。しかし、よその神々の現実性や、それらを崇めるよその形式の正当性を否定する者は誰もいなかった。古代の多神教にとって、偽りの宗教という概念は、まったく馴染みのないものだった。他の宗教の神々は、偽りの虚構とは見なされず、多くの場合、別の名前で呼ばれている自分たちの神々と見なされた。
宇宙的である神々。宇宙であるからグローバルに共通基盤を持ちやすい。
その立場においては、よそを否定するのは宇宙そのものを否定することになる。自分たちは異なる神々の名で呼ばれていたとしても、それは言葉の問題であって、偽りの神々を信仰しているということにはならなかった。宇宙は民族間で共有できていたのだから、そこに偽りが入るこむ余地はなかった。
だからこそ、モーセがエジプトを脱出して、エジプトの多くの神々を偽りのものとして排除し、主を唯一の神として崇めたのはきわめて特殊なこと、異例のことだった。一神教というのは、ある意味、新たな宗教的発明だったわけだ。
モーセは自身の宗教をこれまでの宗教とは「区別」した。
しかし、モーセのそれはあくまで、これまでの宗教の否定形で成り立っていた。
モーセの区別は、この区別が設けられた世界を著しく変えた、何か根本的に新しいものだった。この区別によって「截断、あるいは分割」された空間とは、単に宗教一般の空間ではなくて、まったく特定の種類の宗教の空間である。わたしはこの新しい宗教のタイプを「対抗宗教」と名づけたい。なぜならそれは、自らに先行するものや自らの外部にあるものすべてを、「異教」として除外するからだ。
いわゆる「ポスト〜」というものが、先行するものを否定的に乗り越えようとしながら、あくまで否定すべき対象として先行するものの存在の上に成り立っているように、モーセの対抗宗教としての一神教も、偶像=自然に存在するあらゆるものに神を見る従来の宗教観を否定することで自らのアイデンティティを保つものだった。
この発想が後のプラトンのイデアとエイドスの分離にもつながっていくことは容易に想像がつく。そして、自然と文化、非人間と人間との二項対立にも。自然や非人間的なものを排除することで、人間は神やイデアの側に近付こうとする。そして、ヨーロッパの文化は自然や異教徒のように野蛮ではなく、理性的なものだと。
父殺し―反復と抑圧
だからこそ、このモーセの対抗宗教は、容易に、神話的かつ精神分析的な「父殺し」の物語に重なってくる。
それはモーセが父としてのエジプトの神々を否定して、新たな自分たちの神を打ち立てたことだけに関してのみいえることではない。著者のアスマンは、ここでフロイトによるモーセ論を紹介している。「〈殺害されたモーセ〉は、宗教の起源と本質に関するフロイトの理論と分かつことができない」といい、そのモーセ論において、フロイトがモーセが2人いたと考えていて、最初のエジプト脱出をはかったモーセは民によって殺されたのだと考えていることを示す。
エジプトから民を率いて脱出した第1のモーセは、原父のように民たちによって殺害された。そして、その殺害をなかったものとするかのように、2人目のモーセを立てた。
「この元型的な出来事は、フロイトの場合、奇妙なことに1回性と反復の間を揺れ動いている」とアスマンはいう。反復することで、抑圧するというフロイトのモティーフがここでも展開されているのだ。
「われわれは唯一の偉大な神が今日存在しているとは思わない。しかし、太古には1人の比類ない人物がいたと思っている。この人物は当時、途方もない存在と思われたにちがいなく、そして神性にまで高められて人々の思い出の中に回帰してきたのだ」とフロイトは書いている。
「「1人の比類ない人物」とはどういう意味だろうか」とアスマンは問う。
反復という考えが登場してくるのは、ここにおいてだ。「フロイトによれば、原父の殺害は、数千年にわたって、いつも繰り返されてきた」という。
ただこの反復の力によってのみ、この殺害行為は人間の魂に消すことのできない痕跡を残し、その「太古の遺産」を形成することができた。この痕跡の秘められた深部では、「人間は、自分たちがかつて1人の原父を持ち、その原父を打ち殺したことを常に知っていた」。太古の経験を、人類普遍の永続的な所有物に変える決定的な機制が、反復と抑圧だった。
モーセを巡る論争自体が、アスマンのこの本で紹介されるように、歴史の中で何度も繰り返し取り沙汰される記憶の形象だった。「古典から引かれてきた同じ文章のコレクションを、スペンサー、カドワース、トーランド、ウォーバートン、ラインホルトの著作のように相異なる本の中に見つけるのは、唖然とするし、また面白くもある」とアスマンが書いているように、彼らが「古典、教父文献、ラビ文献の引用からなるこのコレクション」は、「変化した時代状況や新たな問題と論争を背景にして、自らの特殊な目的設定に従って、自分なりの仕方で」、あたかも原父のことなど無視しつつも、その形象をうまく反復的に利用することにより「幾千もの引用箇所がつなぎ合わされて、その都度、新たな論証の秩序を形成した」のだった。
このモーセ論争を反復と抑圧からなるものと論じるために、原父の役割を担う存在として、モーセそのものを歴史化しようとしたのが、フロイトの試みであったとアスマンは指摘するのだ。
モーセ論争は、(異教徒の)神々を歴史化するという方法を啓示にまで拡張して、啓示を、エジプトの儀式や神観念の転用、それどころかエジプトの密儀の漏洩に変えた。啓示はいまや、真理をエジプトからイスラエルに移譲したものと解された。しかし最後の一歩を思い切って踏み出し、真理そのものを歴史化したのは、フロイトが最初だった。彼は「唯一の偉大な神」を、あの太古の「比類ない人物」に還元した。「この人物は当時、途方もない存在と思われたにちがいなく、そして神性にまで高められて人々の思い出の中に回帰してきたのだ」。宗教の創唱者にして民族の創建者としての「偉大なる男」というコンセプトも、この論争にとってもフロイトのモーセ像にとっても、等しく中心的である。それゆえにフロイトはモーセの人身にこだわり、彼を「モーセという男」と呼んでいる。
モーセという想起の対象を、反復と抑圧に利用可能な歴史的な実在として論じるため、フロイトは、いまだ存在の歴史的証拠のないモーセを「モーセという男」に是が非でもする必要があった。
それによってはじめて、モーセという歴史的存在の抑圧と反復が、ユダヤという民族を可能にし、彼の創唱した一神教を持続可能なものになるのだった。
しかし、アスマンが明らかにするのは、このモーセの一神教の発明自体、じつは抑圧されたエジプトの歴史の反復だということだ。
反復される一神教の発明
古代エジプト第18王朝の王アメンホテプ4世は、それまでの多神教を廃止し、アテン神=太陽を唯一の神とするアテン教を創唱し、自ら、アテン神と交信できるアクエンアテンを名乗った。
アクエンアテンは、それまでの偶像の破壊を命じ、王朝発祥の地テーベを放棄して首都を現在のアマルナ(アケトアテン)に移した。これがアマルナ改革と呼ばれると同時に、アテン神を唯一の神とする世界最初の一神教を創唱したのが、このアクエンアテンを名乗ったファラオだった。
しかし、この世界最初の一神教も、アケトアテンという首都も、アクエンアテンの死後、すぐに彼自身の存在もろとも抹消される。その存在が公の知るところのものとして回帰するのは、18世紀後半にナポレオンがエジプト遠征のあと、アマルナの詳細な地図を作成させたのを皮切りに、19世紀に入って、ようやく砂に埋もれた墓が発見されるまで待たなくてはいせなかった。

このアクエンアテンのアテン教は、偶像崇拝の否定や唯一の神以外を認めないことなど、モーセの一神教のベースとなる対抗宗教的な性格を持っていた。
自然と文化の分離
しかし、明らかに異なる面もあり、それはアテンが太陽そのものであり、太陽の力が様々なものの生成を司っていると考えた点で、モーセが否定した宇宙即神論的な性格を色濃く持っている。
アスマンはそれを物理学的な視点であるとさえ言っている。
この宗教の合理主義的な性格は見紛いようがない。アクエンアテンは、モーセ、イエス、ムハンマドのような宗教創唱者の列に連なるばかりでなく、同様に、タレス、アナクシマンドロス、プトレマイオス、ニュートン、アインシュタインのような、世界を物理学的に説明した人々の列にも連なるということを、わたしは幾度も強調してきた。光と時間を、一切を説明する2つの太陽エネルギーとする彼の説は、宗教的啓示というよりも、はるかに物理学的な発見である。
最初の一神教がこうした性格を持ち、いまでいう科学的な視点と、宗教、そして政治的な視点までが統一されていたのだとしたら、後に、モーセの名の下に現れることになる一神教は、何故、自然と人間的な文化や政治などを分離しなくてはならなかったのか。
そんな疑問が当然わいてくる。特に西洋的な二項対立を心の底から信じたことのない彼らからみれば異教徒である僕らからすれば。
しかし、アクエンアテンにとっては、自然と人的なものが統合された宗教でも、民にとってや、王に敵対する人々にとってはそうではなかったのだろう。
だから、より政治的に、そして、文化的に「使える」宗教が必要だったのだ。そのことがアスマンが書く、このようなことから見てとれる。
この神的なものとは、世界を内から生み出し、動かし、生気を与える自然だった。この神性は国家を支える宗教とは結び合わせることができなかった。それゆえ、人間により近く、人格性をもっと備えた神々が必要とされた。この脈絡で重要になるのが、神学の3つの形態についてのストア派の理論だ。つまり〈自然神学〉、〈国家神学〉、そして〈神話神学〉である。〈自然神学〉は哲学者たちの神学であり、これは秩序を必要とする国家にも、意味を必要とする人間にも手に負えない代物だ。それゆえほかの2つの神学が存在する。これらは不可欠の虚構という意味での「秘密」に基づいている。〈国家神学〉は、秩序を可能にし共同体を確立する、神々および神々の礼拝の形式に配慮する。そして〈神話神学〉は、人々の生活を意味づける物語の構築物を発展させる。真理の希薄な空気はごくわずかの者にしか呼吸できない。
自然についての「真理」だけでは、政治も文化も維持できない。それらの維持にはより「人間的な」神が必要になる。
そして、その神は、自然そのものからは切り離された絶対的、超越的なものとして位置づけられる。もちろん、それは絶対性や超越性は自然を顧みない人間中心主義的なものだ。
聖書のエジプト像が象徴しているのは「偶像崇拝」という概念、それも、現世の偶像化あるいは宇宙即神論という意味でのそれだ。イスラエルはエジプトから脱出することで「現世」から、つまり、外面的な幸福、世俗的な成功、市井の安寧、物質的な富、政治的な権力を志向する文化から抜け出る。エジプトの偶像崇拝の本質は、根本においては、図像を崇めることにあるのではなく、あまりに徹底してこの世界に根を下ろすことにある。
現世から脱出した者たちの宗教、徹底して世界に根を下ろしていた宗教観からの脱却。だから、モーセ的な一神教が、それぞれキリスト教、ユダヤ教、イスラム教と分化しつつも世界宗教化した時点で人間中心主義的な思想が蔓延し、いまの人新世の世が到来するのは避けられなかったのかもしれない。
この人間中心主義的思想の根の深さ。自然と文化を分離してしか考えることのできないモーセ以来の伝統を打ち破るのは一筋縄ではいかないのかもしれない。
事実偏重を超えて
そんな風にこの本は、歴史を事実からだけ読むのではなく、実在したかどうかわからない「モーセ」のような人物が歴史の中で、いつどのように想起の対象として現れてきたのかを問う、とても興味深い試み。
いまさらながらフェイクニュースだの、ポスト・トゥルースだとかいうものの、もとよりFactなるものを真実と捉える考えがそもそも怪しいし、歴史的な事柄でしかないことを西洋人はともなく、どうして僕ら日本人まで忘れてしまっているのか?
人間が事実のみで動いていないことなんて、当たり前すぎることだし、事実以上に記憶やその想起が人やその社会を動かす要因であることなんて、考えるまでもなくわかること。
だのに、歴史を科学的にみるさいに、なぜ事実なんてものだけを対象にして、歴史が語られなければならないのか?
そんなごくごく、当然のことをあらためて示してくれたのが、このヤン・アスマンの『エジプト人モーセ』という一冊だ。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
