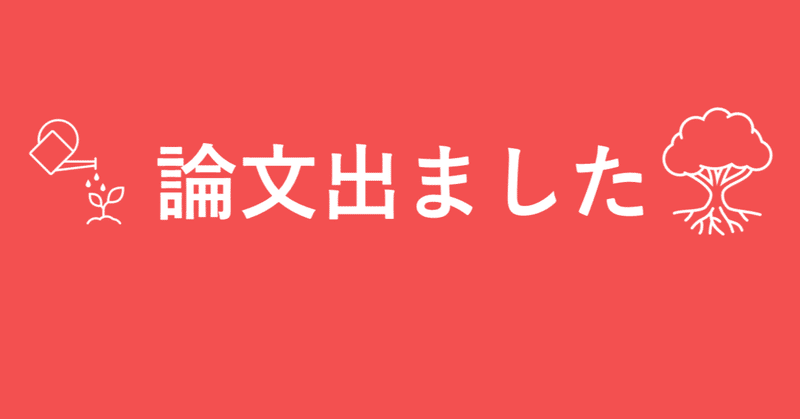Asumi Takahashi
自殺や喪失を研究テーマとしている私立大学教員です。臨床心理士、公認心理師。
自殺研究や自殺予防対策に取り組みたい人や自分に向けて、色々まとめてみます。
研究者としてのプロフィール→https://researchmap.jp/asumi03takahashi
最近の記事
- 固定された記事
- 固定された記事
マガジン
記事

Reflection of Suicidal Ideation in Terms Searched for by Japanese Internet Users
NPO法人OVAで取り組ませていただいている研究のShort Reportが、オンライン公開されました。 Asumi Takahashi, Hajime Sueki, & Jiro Ito. (2022). Reflection of Suicidal Ideation in Terms Searched for by Japanese Internet Users. Crisis. https://doi.org/10.1027/0227-5910/a000854 自殺