
初めての翻訳出版
2023年8月に、『メディアと自殺:研究・理論・政策の国際的視点』(トーマス ニーダークローテンターラー ・スティーブン スタック (編著)・太刀川 弘和・髙橋 あすみ(監訳)田口 高也・白鳥 裕貴・菅原 大地・小川 貴史(訳))を人文書院より出版させていただきました。

経緯
企画を立てたのは、まだ博士課程に在籍中のときです。メディアによる自殺報道の問題は、2020年以降に特に高頻度で議論となっていました。私はそのころ、報道とは異なる角度で「有名人の死」に関するレビュー論文を書いていたのですが、メディアと自殺の問題についても改めて調べて関心も強くなっていました。
"Media & Suicide"は、パパゲーノ効果を提唱した気鋭の研究者ニーダークローテンターラー氏と、自殺報道研究でベテランの社会学者スタック氏が編者の論集で、各章のタイトルからしておもしろい。師匠に翻訳したいと話したところ、二つ返事で企画に賛同してくださったので、いそいそと企画書をつくりました。
【企画書の構成】
本の概要
訳者の情報
原著者プロフィール
仮の目次と内容紹介
想定される読者層
翻訳の意義
イントロダクションの翻訳
本を出すときは編集者とのコネクションが重要と聞いていましたが、私は知り合いがおらず、先生のご著書『つながりからみた自殺予防』を担当してくださった人文書院の編集者さんに企画書を送ってもらいました。その後、企画を無事に通していただき、翻訳出版のスタート地点へ。
翻訳の準備
出版前にこちらのnote記事を繰り返し読み、参考にさせていただきました。動機づけにもなりました。本当にありがとうございました。
また、こちらの本で翻訳について少しおさえました。専門的で難しかったです…。
ちなみに私は残念なことに英語力は全く大したことがない(それを証明するテスト結果すらない)のですが、チームに助けられたことや、論文の作法やもともと持っていた知識などで、そこは何とかなったかと思います。
翻訳の実際
翻訳の体制
文量が多かったため、自殺を研究テーマとしていたり、英語に造詣の深かったりする研究室の先生方に協力を依頼して6名で翻訳チームをつくりました。訳者のおひとりで兄弟子の白鳥先生はnoteも書かれています。
言い出しっぺの私がチームの取りまとめを担当したのですが、翻訳開始時期に研究室を巣立ってしまいましたので、Googleグループでメーリングリストを作成して連絡に用いました。またGoogle Driveに共有フォルダをつくり、本書のPDFファイルや訳文、工程管理表などを格納しました。監訳と編集者さんとのやりとりは、師匠と共に2人で行うこととなりました。
スケジュールと編集者さんからのサポート
編集者さんとのメールを読み返すと、2021年5月5日(水)から、原稿を校了した2023年7月11日(火)まで、翻訳ややりとりが停滞している時期と、怒涛に作業をしている時期とずいぶん波があることが分かりました。
まず企画の段階では編集者さんより「往々にして、大きな翻訳は、逃亡者や行方不明者が出ます。期限がふつうにきれます。雑な人にはむかない仕事です。」と言われており、私は「血反吐はいてでも完成させます!」と豪語した記録が残っておりました(汗)。
どうやら夏の段階では2021年中に翻訳し終えることになっていたのですが、私も初めての就職で忙しくなり、翻訳の管理がおざなりに…。
学会等で会ったときに師匠と打ち合わせ、訳者の先生方からは2021年夏~2022年春頃になんとか第1稿を提出してもらいました。その後の作業は監訳者に任せると言ってもらいましたので、残りの作業は師匠と私で頑張るのみでした。しかし、こちらの作業もあれよあれよと後ろ倒しに。
2022年11月に編集者さんにお尻を叩いてもらって覚醒し、急ピッチで翻訳原稿を統合。年末年始をまたいでしまいましたが、みっちり監訳の作業に集中しました(幸い血反吐は吐かなかった…)。
2023年2月に第1稿をようやく編集者さんに送ることができました。その後はコンスタントに紙での校正のやりとりをして、計3回の校正を行いました。(北海道から京都の出版社に送り返すのに、関東より余分に時間がかかる等、地方の格差を感じるなど)
装丁は、こんな感じもあんな感じも良いな、等とイメージをお伝えしていたのですが、上がってきたデザインからすぐに決まりました。
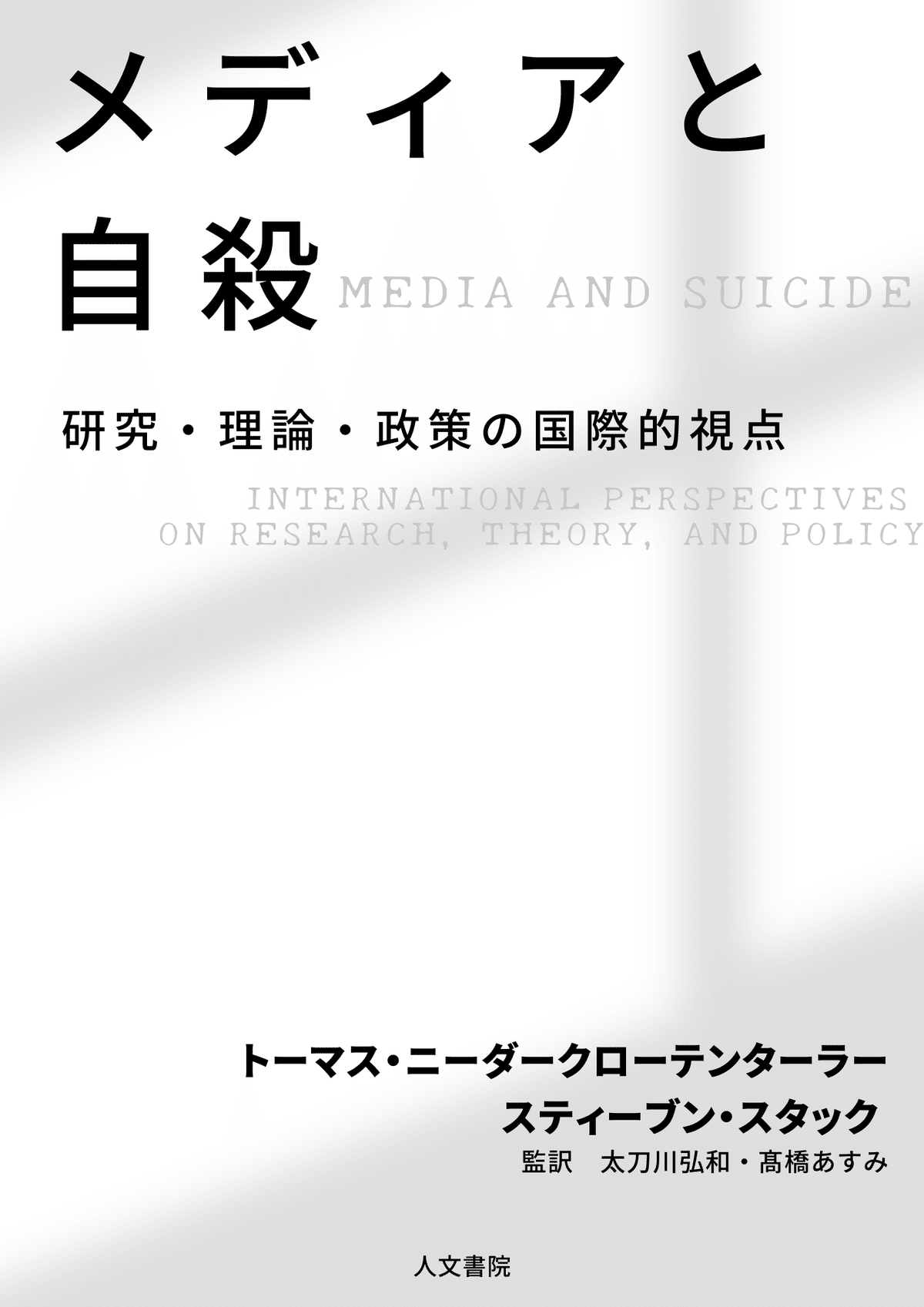
2023年7月5日に第3校を返送して、ようやく校了しました。
共同翻訳で苦心したこと
今回は6名での翻訳だったので、下記に留意するように編集者さんよりご助言いただいていました。
学術的タームの統一
語訳、訳しもれ、数字の引き写しの間違い
訳者注
表記や形式、調子の統一
図版の入る箇所の記入
タームの統一については、原著に索引がついていましたので、専門用語(suicidal ideationなど)の対訳のみ師匠を中心に先に決めておくことができました。一方で、"Media & Suicide"は34人の著者がいる論集でしたので、それぞれ使っている語句や英語の調子などが全く異なり、統一作業は大変でした。
また、校正段階では日本語がおかしくないか、情報に誤りがないかを中心に確認していたため、文章の流れに違和感⇒原文を確認⇒訳しもれに気づく、ということが何度かありました。
図表も第3校まで隈無く確認しました。

校正で大変だったこと
今回私が翻訳を担当したうちの第4章『大量銃撃と殺人自殺:伝染に関する実証的エビデンスのレビュー』は、概念の整理が論点の一つとなっていたため、類似している多数の英単語にどのような日本語を割り当てるのかが、監訳時にも議論になりました。
例えばmurder-suicide、すなわち「殺人自殺」は、日本語では「拡大自殺」という言葉を当てることができるのですが、この言葉自体に解釈が入っており、日本語で使用することについては批判的な議論もあります。また、タイトルの大量銃撃は"mass shooting"の対訳ですが、日本では銃で複数人が撃たれる事件を「(銃)乱射事件」と表記することが多いと思います。このあたりどうすべきか悩みました。
校正に最も時間がかかったのは、第8章『英雄と犯罪者、美しさと醜さ:芸術の鏡に映し出された自殺』です。こちらの章は、主に絵画などの芸術作品がどのように自殺を描写してきたのか解説している章で、初見の作者名や作品名が多く登場しました。登場する作品のリストを作り、作品や作者が日本でどのように呼称されているのか一つ一つ調べ、美術館のホームページで写真を探すなどして、ひたすら内容を確認しました。そもそも視覚的な表現を文章にするのは日本語でも難しいと思うのですが、実際に作品のイメージを見てみても、それが文章で表現したことと合っているのかどうかが悩みどころでした…。
ちなみに8章の著者のクリシンスカ&アンドリーセンは、ポストベンションでも著名な研究者なのですが、芸術と自殺の関連についてここまで書けるのは本当にすごいですね。
研究者としての翻訳出版のメリットは
研究者個人としては、本書の出版を通してメディアと自殺の関係について非常に詳しくなり、新たな研究テーマを手に入れたことで大きな成長につながりました。また原著者の2人とやりとりができ、訳書をお送りしたところ喜んで写真を送ってくださったのも貴重な思い出です。
翻訳出版のプロセスを理解したので、またチャレンジしたいなと思っています。

アサヒグループ大山崎山荘美術館の庭園。
今話題のモネの睡蓮が観れました。
『メディアと自殺』を改めて読んで
自殺について初めて知る人には少し難しいですが、重要な知見ばかりなのでぜひ読んでもらいたいです。さまざまな研究方法が使われているので、自殺に関する研究を考えている学生の方にも役立つと思います。
また、メディア関係の方とは、第3部『自殺対策』を参考に悪影響を防ぐメディア報道のあり方についてぜひ共に検討していきたいと思います。
なお、本書は和光大の末木新先生が書評を何度も書いてくださり、noteでも紹介してくださいました。ありがとうございました。
他の研究者やメディア関係者の方からの感想もぜひお待ちしております。
【補足】引用文献の書き方
本書は著者やチャプターが細かに分かれていて、各チャプターでの引用が結構面倒くさいので、下記をコピペしてお使いください。(念のため誤りがないか各自ご確認ください)
本そのもののの引用
Niederkrotenthaler T, Stack S. (Eds.): Media and Suicide: International Perspectives on Research, Theory, and Policy. Routledge, London, 2017. (太刀川弘和, 髙橋あすみ監訳: メディアと自殺:研究・理論・政策の国際的視点, 人文書院, 京都, 2023.)
日本語で著者を記載する場合
トーマス・ニーダークローテンターラー、スティーブン・スタック編著、太刀川弘和, 髙橋あすみ監訳(2023)『メディアと自殺:研究・理論・政策の国際的視点』人文書院
APA式
Niederkrotenthaler, T., & Stack, S. (Eds.) (2017). Media and Suicide: International Perspectives on Research, Theory, and Policy. Routledge.
(太刀川 弘和・髙橋 あすみ(監訳)田口 高也・白鳥 裕貴・菅原 大地・小川 貴史(訳)(2023). メディアと自殺:研究・理論・政策の国際的視点 人文書院)
各章の引用
1 はじめに
トーマス・ニーダークローテンターラー、スティーブン・スタック
Niederkrotenthaler T, & Stack S. Introduction.
2 なぜ男性は女性よりも銃器を選ぶのか:1900 年から2013 年の映画におけるジェンダーと銃器自殺の描写
スティーブン・スタック/バーバラ・ボウマン
Stack S, & Bowman B. Why Men Choose Firearms More than Women: Gender and the Portrayal of Firearm Suicide in Film, 1900–2013.
3 アメリカメディアにおける自殺の記事:稀であり、若者に集中している
シルビア・サラ・カネット/フィリップ・T・テイタム/マイケル・D・スレイター
Canetto SS, Tatum PT, Slater MD. Suicide Stories in the US Media: Rare and Focused on the Young.
4 大量銃撃と殺人自殺:伝染に関する実証的エビデンスのレビュー
マデリン・S・グールド/マイケル・オリバレス
Gould MS. & Olivares M. Mass Shootings and Murder-Suicide: Review of the Empirical Evidence for Contagion.
5 ネットいじめは自殺念慮者から自殺企図者を振り分ける
スティーブン・スタック
Stack S. Internet Bullying Distinguishes Suicide Attempters from Ideators.
6 自死後のソーシャルメディアの利用:イギリスでの質的研究から得られた知見
ジョー・ベル/ルイス・ベイリー
Bell J, Bailey L. The Use of Social Media in the Aftermath of a Suicide: Findings from a Qualitative Study in England.
7 自殺と新興メディア:良い影響、悪い影響、あいまいな影響
ジェーン・ピルキス/キャサリン・モク/ジョー・ロビンソン
Pirkis J, Mok K, Robinson J. Suicide and Newer Media: The Good, the Bad, and the Googly .
8 英雄と犯罪者、美しさと醜さ:芸術の鏡に映し出された自殺
カロリナ・クリシンスカ/カール・アンドリーセン
Krysinska K, Andriessen K. The Heroic and the Criminal, the Beautiful and the Ugly: Suicide Reflected in the Mirror of the Arts.
9 歌舞伎座での自殺
カロリナ・クリシンスカ
Krysinska K. Suicide in Kabuki Theater.
10 なぜ自殺のメディア報道は自殺率を高めるのか:認識論的レビュー
シャルル= エドゥアール・ノートルダム/ナタリー・ポーウェルス/マイケル・ウォ
ルター/ティエリー・ダネル/ジャン= ルイ・ナンドリノ/ギョーム・ヴァイヴァ
Notredame CE, Pauwels N, Walter M, Danel T, Nandrino JL, Vaiva G. Why Media Coverage of Suicide May Increase Suicide Rates: An Epistemological Review.
11 パパゲーノ効果:メディア研究における有害なメディア効果の知見に関連した進歩と理解
トーマス・ニーダークローテンターラー
Niederkrotenthaler T. Papageno Effect: Its Progress in Media Research and Contextualization with Findings on Harmful Media Effects.
12 映画の自殺描写が観客に与える影響について:質的研究
ベネディクト・ティル
Till B. The Impact of Suicide Portrayals in Films on Audiences: A Qualitative Study.
13 ウェルテル効果とパパゲーノ効果の狭間:自殺の伝染に関するメディアの有益な効果と有害な効果に関する曖昧な知見の命題メタ分析
セバスチャン・シェール/アンナ・スタインライトナー
Scherr S & Steinleitner A. Between Werther and Papageno Effects: A Propositional Meta-Analysis of Ambiguous Findings for Helpful and Harmful Media Effects on Suicide Contagion.
14 自殺とマスメディアの報道:1980 年代ウィーンの経験のはじまり
ゲルノット・ゾンネック/エルマー・エツァードーファー
Sonneck G, & Etzersdorfer E. Suicide and Mass-Media Reporting: The Very Beginning of the Viennese Experience in the 1980s.
15 メディアによる自殺報道に関する提言の発展
ダニエル・J・ライデンバーグ
Reidenberg DJ. Development of the US Recommendations for Media Reporting on Suicide.
16 スイスのフランス語圏におけるメディア啓発の向上:ベストプラクティクス
イリーナ・イノストロザ/ジョアン・シュワイザー・ロドリゲス
Inostroza I, & Rodrigues JS. Raising Media Awareness in French-Speaking Switzerland: Best Practices.
17 自殺の責任ある描写の推進:イギリスとアイルランド共和国から得られる教訓
ローナ・フレイザー/リサ・マルツァーノ/キース・ホートン
Fraser L, Marzano L, Hawton K. Promoting Responsible Portrayal of Suicide: Lessons from the United Kingdom and the Republic of Ireland.
18 地域の文脈で国際的なメディアガイドラインを実装する:香港の体験談から
チジン・チェン/ポール・S・F・イップ
Cheng Q, & Yip, PSF. Implementing International Media Guidelines in a Local Context: Experiences from Hong Kong.
19 おわりに
スティーブン・スタック/トーマス・ニーダークローテンターラー
Stack S, & Niederkrotenthaler T. Conclusion.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
