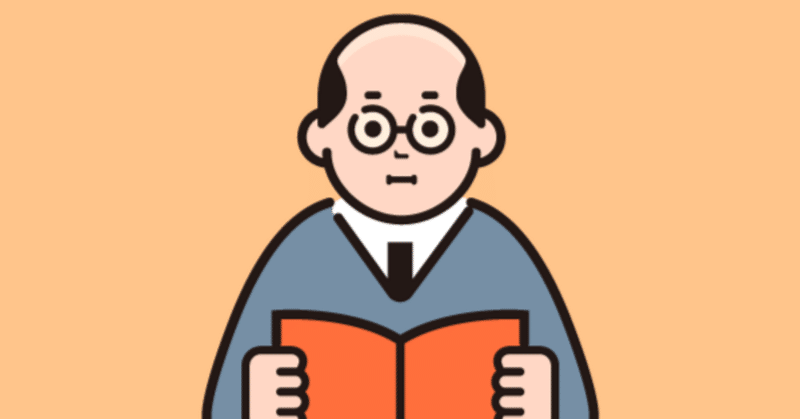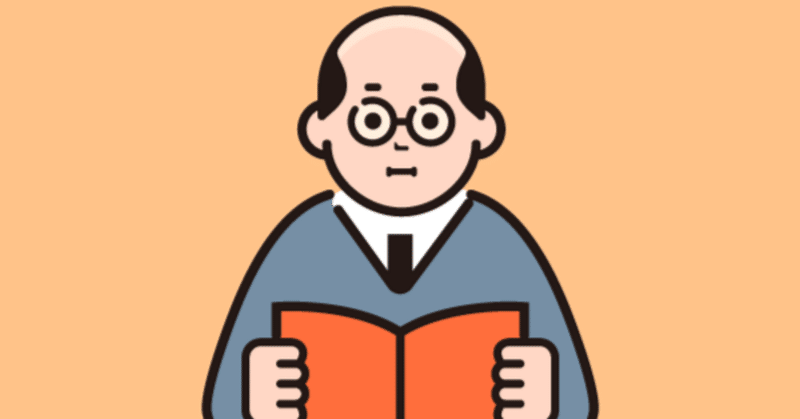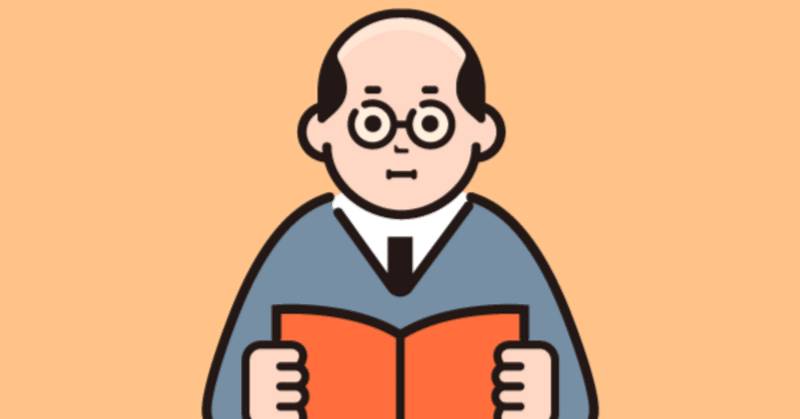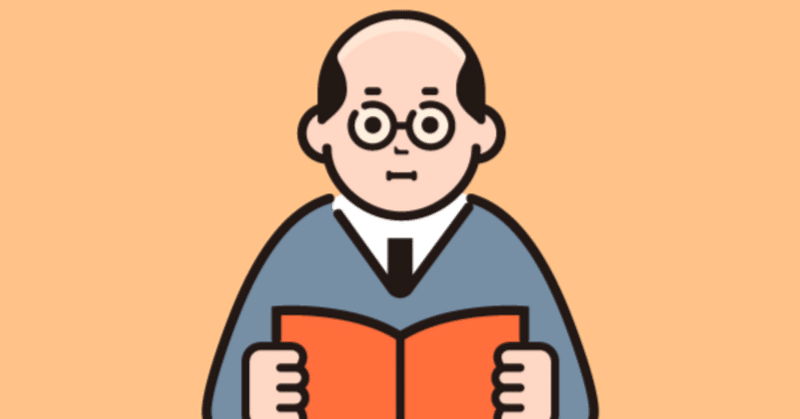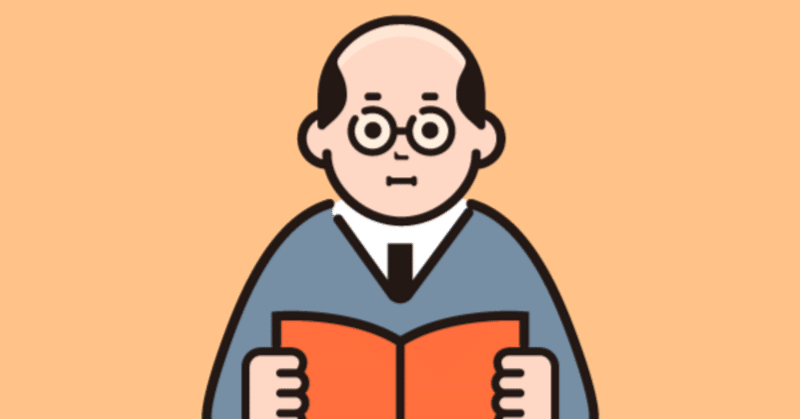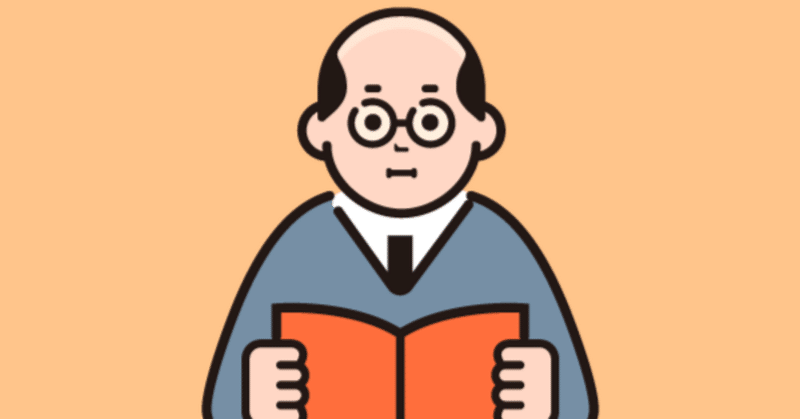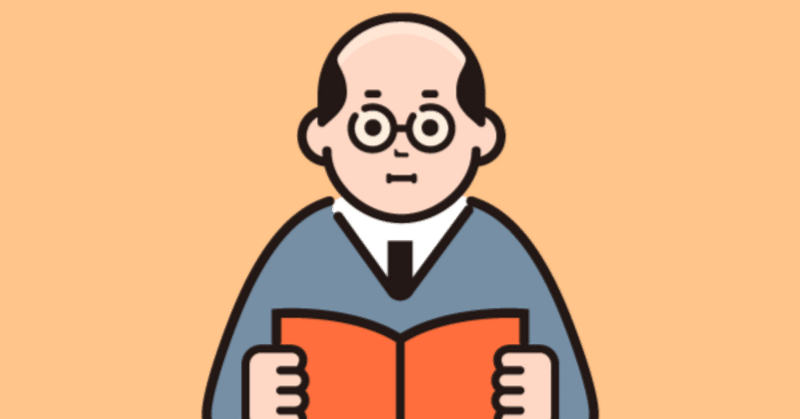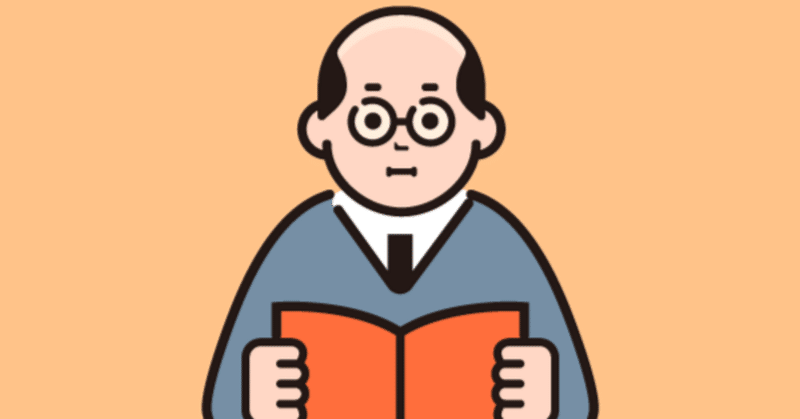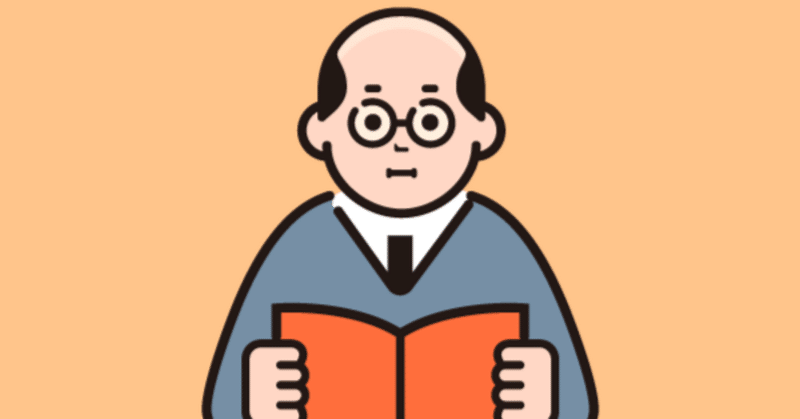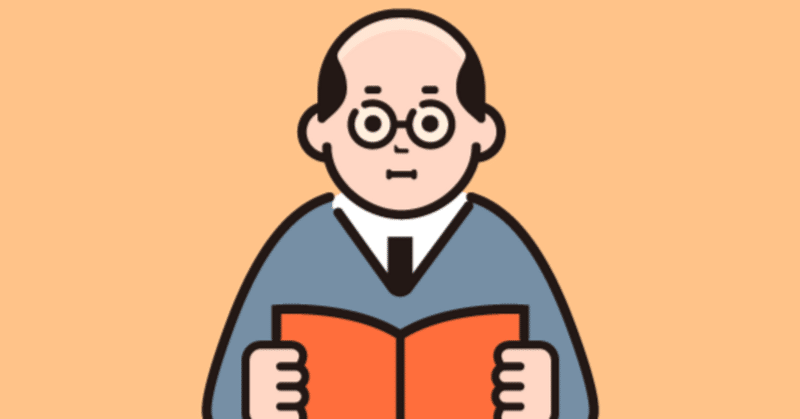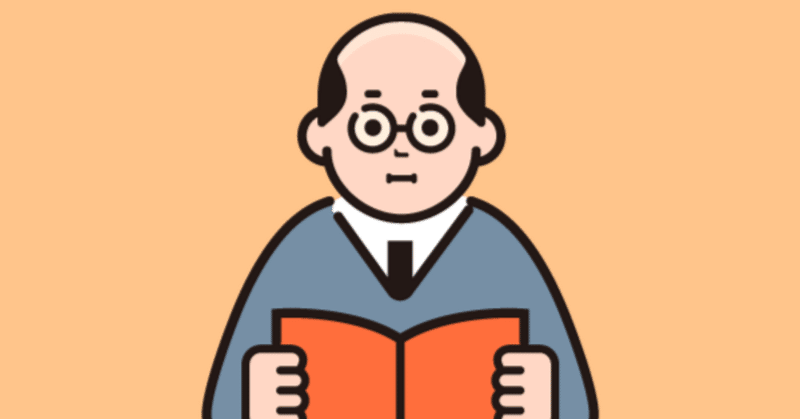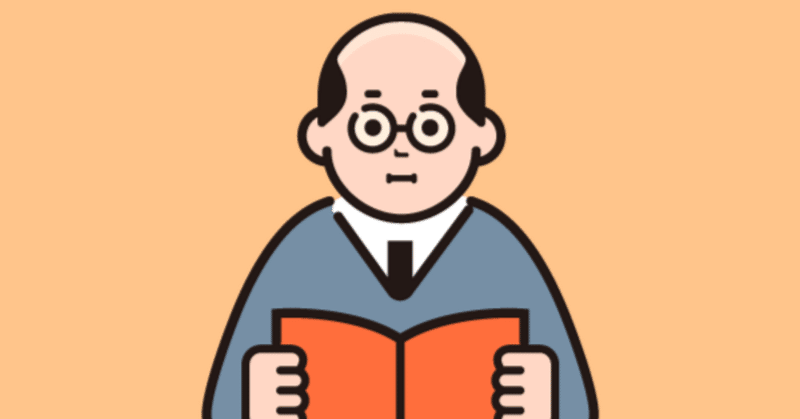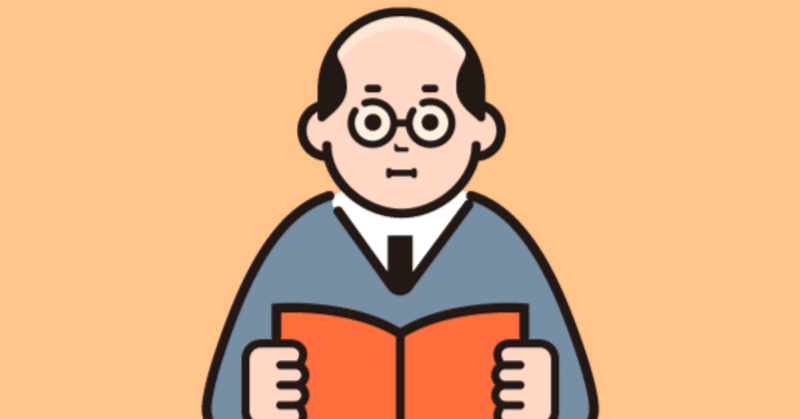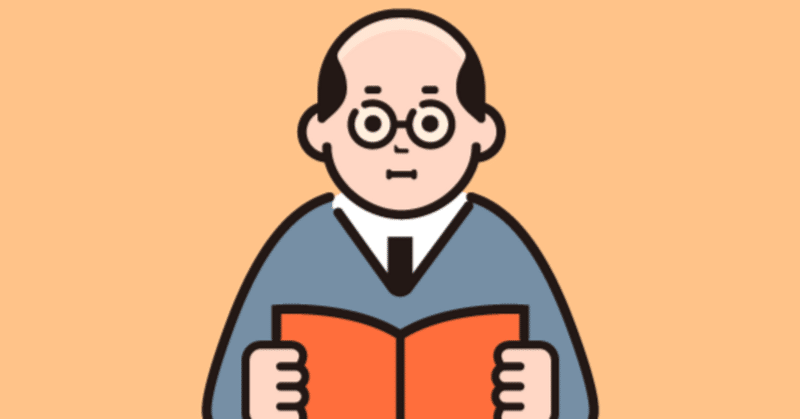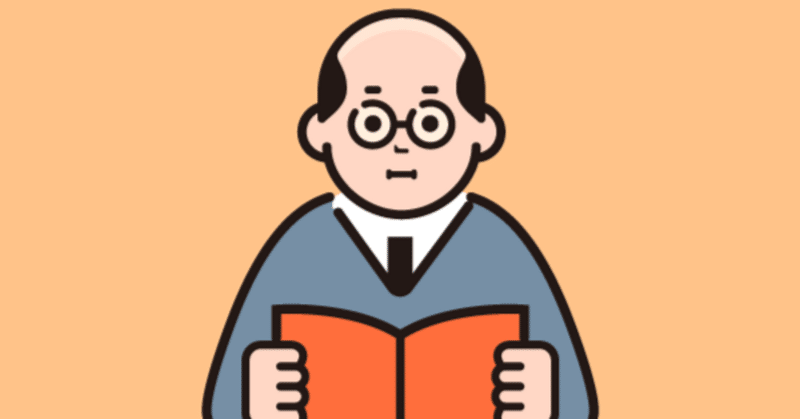記事一覧
「みっともない老い方」by 川北義則
60歳もそこそこ進んだ身ではあるが、改めて恥ずかしい老人にならないためにこの本で書かれていることを確認したいと思った。
各章は以下の通り。
1.こんな年寄りは嫌われる
2.60歳からの老いる作法
3.まだ枯れるには早すぎる
4.もっと冒険心をもて
5.死ぬときは死ぬがよろしく候
いろいろ参考になる内容でした。
評価は、5/5です。
「経済評論家の父から息子への手紙」by 山崎 元
今年1月1日に亡くなられたエコノミストの山崎 元氏が、息子さん宛に残された最後のメッセージがこの本の元となっている。ご自身の状況を把握された上で、本当に残しておきたいことをこの本に詰め込まれていると思う。
働き方や稼ぎ方、お金の増やし方、そして幸福論について語られている。
ご自身の経験から、「リスクを取って勝負する側の人間にならないといけない、資本主義社会はそういうルールになっており、リスクを取
「恋ははかない、あるいは、プールの底のステーキ」by 川上弘美
主人公の女性は、小さいころアメリカで育った60歳台の女性作家で、ある文学賞の審査員もしているとのことで、作者を彷彿とさせる。
時代は新型コロナ期で、アメリカ時代一緒に過ごした女性と男性と時々会って食事をしたり、小旅行へ行ったり、お酒を飲んだりして、まったりとした時間が過ぎていくような小説である。
自分も同じ60歳台ではあるが、まだまだバタバタ、ドタドタとした毎日を送っているので、もう少し落ち着
「ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人」by 東野圭吾
東野圭吾の本は、エンターテインメントということで、軽い気持ちでサックと読める。この本は、元マジシャンが主人公として初めて登場し、新しいシリーズになるらしい。
彼の作品のミステリー力は、若干マンネリ化していなくもないが、冒頭に書いたようにあまりごじゃごじゃ考えずに、楽しみたいと思います。
本の評価は、4.5/5です。
「多様性の科学」by マシュー・サイド
この本のテーマは、「画一的な組織は凋落し、複数の視点をもっている組織は問題を解決できる」ということである。
「なぜ、CIAは同時多発テロを予測できなかったのか?」等の様々の事例をもって、多様性の重要性をこれでもか、これでもかと迫ってくる。
多様性の必要性について、この本に限らず語られており、その正しさは証明されていると思われるが、日本においてはなかなか進まない。自分の会社でも女性の部長はゼロ、
「電通マンぼろぼろ日記」by 福永耕太郎
電通という超有名な企業ながら、最近はブラック企業ということでも悪名を轟かせたので、実際どうなっているのかという興味本位で読んでみた。
書かれている内容は全て本当だと思うが、なかなか強烈な企業風土だということが理解できる。東京オリンピック関連でもいろいろ問題が示されていた。
それにしても著者の人生が破滅してしまったのは何とも悲しいが、自己破産した著者がこの本を書くことで、これまでの自分の人生に向
「破天荒フェニックス」by 田中修治
著者の田中修治氏が、メガネのチェーン店であるオンデーズを買収し再生していくノンフィクション的物語である。
30歳を少し越した田中氏が買収したオンデーズは大きな負債を抱えて、債務超過状態のため、金融機関からは新規の融資を引き出せない中、なんとか投資家から資金を調達して、国内や東南アジアに新規に店舗を出したりして、オンデーズを再生する物語である。
次々に起こる問題を何とか解決していく姿に感動と勇気
「財務3表一体理解法 管理会計編」by 國貞克則
ベストセラーになった財務3表一体理解法シリーズの最新版で、この本は「管理会計」に特化している。
自分は中小企業診断士で基本的な管理会計の知識があるので、書かれている内容は問題なく理解できたが、改めて頭の整理の本としては有効だった。
管理会計の初心学習者でも、抵抗感なく読める内容になっていると思う。もちろん、ここで書かれている内容は基本の基本なので、これで管理会計に興味が出てくれば、もう少し詳細
「日本の会社員はなぜ「やる気」を失ったのか」by 渋谷和宏
日本の会社員の「やる気」が他国に比べ極めて低いという事実は有名だが、改めてその理由を整理したというのがこの本である。
まず、第1章で「なぜ賃金が上がらないか」を分析し、第2章で「社員を追い詰める減点主義の弊害」を解説し、第3章で「コストカッターによる弊害」、第4章で真因である「マイクロマネジメント」について解説している。
本の最後に明るい材料の紹介もあるが、全体的には過去の分析が中心で、それら