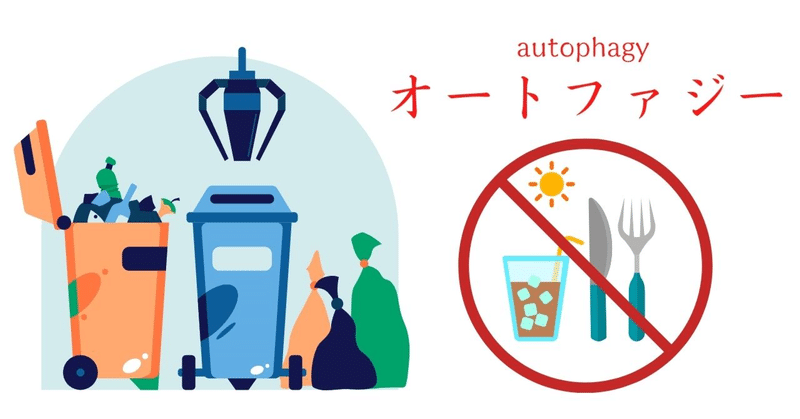
ファスティング×オートファジー
こんにちはSHOです。僕のnoteを読んで頂きありがとうございます。
今回のテーマは【オートファジー】です。
オートファジーという言葉を初めて見た方もいらっしゃるかもしれないので、ここで丁寧にお伝えしていくことにします。途中、専門用語を出さざるを得ない箇所もあるので、少し難しい内容となってしまうかもしれません。
タイトルにも書かせて頂いたように、こちらはファスティングをすることによってオートファジーを促進させることが可能となります。
前回の投稿で「ダイエット効果以外でファスティングを勧めたい理由」について糖尿病対策を触れましたが、今回もそれに近い内容になります。
ただし、オートファジーを促進することで、結果的にダイエットを成功しやすい体にすることも可能になります。
長くなりますが、ご興味ある方は是非最後までご覧ください。
○そもそも「オートファジー」とは?
オートファジーとは、ギリシア語が由来で「auto(自己)」と「phagein(食べる)」、すなわち、自分を食べる(自食)を意味します。2016年に東京工業大学名誉教授の大隅良典さんがその研究がノーベル生理学・医学賞を受賞しました。今もなお研究が進めてられていて、老化の抑制、アンチエイジングなどにその他にも健康の分野における新しい発見がこれからもされていく可能性があります。
人間は、細胞の集合体であり、細胞の中でたんぱく質が作られます。
そのたんぱく質が分解されるとアミノ酸になり、さらにそのアミノ酸がたんぱく質に再合成されることになります。1 日の食事から摂るたんぱく質量は約 60~70gだと言われています。 それとは別に、自分の身体のたんぱく質を 1 日に約 200g分解して再利用しています。
すなわち、食事から得たアミノ酸と、体内でたんぱく質を分解して得たアミノ酸を合わせてたんぱく質の再合成がなされることになります。体内のたんぱく質を分解して、再利用する働きのこと、これがオートファジーです。
○なぜ、自食するのか?たんぱく質を食べる?
我々が生きている最中、自分の体の中では「自食」ということが行われていると言われても、イメージがつかない…僕だってそうです。
なんでこんなことをしているのか?その理由なのですが、これを一言で申し上げるとしたら【飢餓の備え】です。
食べ物が得られなくなるということは、食事でたんぱく質を摂ることが できなくなるということです。
ただ、食事からたんぱく質を得られなくなっても、細胞は日々生まれ変わるので、身体の中では日々新しいたんぱく質は必要です。それでも生きていけるように身体が用意した仕組みがオートファジーです。仮に食べ物が得られずとも、今ある身体の中のたんぱく質をもう1 度分解して再利用できるようにしたのです。
さらに、オートファジーは同時に細胞の中をキレイにして浄化するという役割を担っています。
これはどういうことかというと、日々生きていく中で、細胞内には古いたんぱく質が溜まっていきます。 実際、家具や家電製品が老朽化して壊れることもあるのと同じように、細胞内の器官も使い物にならなくなることもあります。オートファジーが起きると、古いたんぱく質が分解されて、新しいたんぱく質に作り変えることが出来ます。
また、細胞内にある「ミトコンドリア」も古くなると活性酸素を大量発生させます。オートファジーが起きると、古いミトコンドリアが分解され、新しいミトコンドリアが作られます。
ミトコンドリアは「体の中の最大のエネルギー生成工場」です。ミトコンドリアについてはこちらの記事についても書かせて頂いています。
エネルギー代謝が高いと、ダイエット効率も良くなりますので、ダイエットの観点からもオートファジーを促進させるのは意味があります。
ちなみに、先に1つお伝えしておくことがあります。
オートファジーはいわゆる「飢餓状態」にならないと起きないものではありません。常に行われているものなのですが、飢餓状態であると活性化されるのです。なので、ファスティングをして意図的に飢餓状態を作ることでオートファジーを促進させようということなのです。
古い細胞成分が蓄積されていくと、加齢によって多くの影響が出てくる可能性もあります。オートファジーによる自食作用が定期的に起こらないと、不要な細胞成分が時間とともにどんどん蓄積されていくのです。
○ラパマイシン標的タンパク質(mTOR)
オートファジーは「ラパマイシン標的たんぱく質(mTOR:エムトア)複合体」の働きが抑制されることで誘発されます。逆をいえば、mTORが活性化している時には、オートファジーは頻繁には起きません。これがオートファジーのスイッチON/OFFを行なっていると考えて良いでしょう。
さて、ここからは分かりやすいように
・スイッチON:成長モード、オートファジー停止
・スイッチOFF:修復・自己浄化モード、オートファジー活性化
というように二極化してお伝えしていきます。
これ、今回はオートファジーの話をしているから常にmTORのスイッチをOFFにしておきましょうねっていうような話をしたいわけではありません。このONとOFFをうまく調整することによって、人間は健康でいられるわけです。
しかし、現代人はこのスイッチがONのままになりやすく、常に「成長」の方向にかかり、「修復」の方向にはほとんど回さないような生活を送りがちです。
修復機能を果たさないようになると、細胞内の廃棄物を取り除く能力が低下し、そのままでは異常たんぱく質や病原体が体の中に溜まり続け、いずれ不調をきたしてしまいます。だからこそ、適切な知識を身につけ、スイッチのオンオフを上手く切り替える方法を学ぶことが現代人には必要になってきます。
○mTORの働き
簡単にmTORの働きをざっくりとお伝えすると、主に抑制モードと活性化モードがあるとしておきます。
(抑制モード)
細胞の自己浄化モードで、オートファジーが起動し、脂肪を燃焼させるだけではなくて、細胞内に生じた有害物質だけではなく増殖しようとしているがん細胞を除去しようとします。
(活性化モード)
細胞の成長モードで、タンパク質の生産、エネルギーの蓄積、細胞の形成などが促進されます。
現代の私たちの生活習慣はこちらにあたるのですが、こちらが長すぎると、細胞修復や自己浄化のプロセスを抑制し続ける結果になってしまい、デメリットが大きくなります。
○オートファジーは日常的に発生している
上でもお伝えした通り、オートファジーは日常的に起こっていると言われているのです。特定のホルモンや成長因子による生物学的刺激によってもオートファジーは誘発されます。
栄養が豊富に手に入る時には、強度を調整するダイヤルを下げたり、飢餓時にはダイヤルを上げたりと調整しているのです。オートファジーの期間が長期化し、細胞の生存に不可欠なたんぱく質や細胞小器官が分解され続けると、細胞死に至ることもあります。なのでバランスが大事なのです。
○具体的に行うべきことは何か?
では具体的には、何をすればオートファジーを促進できるのか?という話をしていきます。ありきたりな言い方ですが「食事」と「運動」です。
●食事
食事は「低糖質/低たんぱく質/高繊維」がポイントです。これを実現するための食事法としてファスティングを推奨します。食事に関してはまた別の機会にお伝えしていくことにします。
●運動
新陳代謝の促進、心肺機能の向上だったり、運動がオートファジーを促すための健康的なストレスとなります。代謝に関連する臓器(膵臓/肝臓/筋肉/
脂肪細胞)などがオートファジーを誘導します。
激しい運動、強度が強い運動をしても、その効果には限りがありますので、まずは有酸素運動を行うようにしましょう。
有酸素運動の習慣がない人は、まずは毎日20分を目標に、心拍数が安静時よりも50%以上になる強度で運動を行うようにしましょう。慣れてきたら時間をふやしてもOKです。
すでに運動習慣がある人は、すでに週に5日、1日30分以上の運動を目標にしましょう。まとめて運動をする必要はありません分けても問題はありません。
○mTORのスイッチをONにするものとは?
mTORのスイッチが入ると、体は成長モードに切り替わるので、オートファジーは抑制されることになります。また、現代人の生活は成長モードになりやすいため、オートファジーを促進させたいのであれば、mTORのスイッチをオフにしておきたいところです。
mTORのスイッチをONにし、細胞を成長モードにするものは
・インスリン
・IGF-1(インスリン様成長因子)
この2つとなります。
細胞を増殖、生存能力を高める作用があると言われていて、まだ研究段階ではっきりとしたことがわかっていないのですが、IGF-1のシグナルの伝達を低下させると哺乳類の寿命が伸びると言われているのです。
IGF-1のレベルが常に高いと、ミトコンドリアの機能障害、細胞の生存率が低下します。ミトコンドリアの突然変異や機能障害は加齢とともに増加するため、機能不全のミトコンドリアを除去する能力が落ちると、加齢に伴う不調や病気を発症しやすくなります。
要するに、IGF-1は歳を重ねるごとに下げていったほうがよく、適切な量の分泌が必要になるということです。この分泌に大きく関わっているのが【成長ホルモン】です。成長ホルモンについてはまた別途まとめさせて頂きますが、これは若者だけに出るものではなく、成人になってからも分泌されるものであり、組織の成長・エネルギー代謝に大きな役割を果たしています。
ちなみに、成長ホルモンは肝臓を刺激し、IGF-1を産生するのですが、これはインスリンが分泌されている時だけです。すなわち、インスリンが分泌され、成長ホルモンも分泌されている時だけIGF-1が分泌されるのです。
では、ファスティングを行うとどうなるのでしょうか。
ファスティングを行うと成長ホルモンは上昇し、インスリン値は下がります。要するに、IGF-1の値は上がらないということになります。
オートファジーが促進され、古いたんぱく質や細胞の残骸を除去することができます。空腹状態の体は成長ホルモンの分泌を促し、新しい細胞や組織を作るように指示が出されます。体は古いものから新しいものへと絶えずリノベーションをすることで健康強度は高められていきます。
ここまでIGF-1のことを「悪いもの」のように連想させる書き方をしていますが、ある程度のIGF-1は生きるために必要です。成長過程だったり、妊娠中や授乳中など、成長・発達、怪我からの回復などに役立つものなのです。このような場合には、IGF-1のシグナルはONにしておくべきでしょう。
要するに、ここでもバランスを取ることが重要になってきます。
年齢を重ねてくるにつれて、体の状況も変化してきます。成長期を終えた成人にとっては、細胞の成長は促すよりも遅らせるべきと言えるでしょう。
○たんぱく質はとった方がいいの?
では、IGF-1を減らしてオートファジーを促すためにはどうしたら良いのか?それは糖質(主に精製されたもの)と動物性たんぱく質を控えた食事をすることです。植物性タンパク質については、IGF-1を増加させるアミノ酸の量がわずかなので、年を重ねるにつれて、動物性タンパク質から植物性たんぱく質に置き換えていくことが良いと言われています。
「たんぱく質」とは第一の栄養素とも言われていて、積極的にプロテインを飲んでいらっしゃる方もいると思うのですが、オートファジーを促進させるためにはたんぱく質(主に動物性)を控えるべきでしょう。1つは、インスリンが分泌されるのは、糖質だけではなく、たんぱく質を摂取した時もであるということと、たんぱく質を過剰に摂取しすぎても問題があるということなのです。これついては、別途またお伝えしていくことにします。
たんぱく質摂取量を減らすということは、ファスティングと同じくらい効果的であって、たんぱく質の供給が減ると、体はあらゆる手段を使って既存のたんぱく質を再利用しようとするのです。
というわけで、栄養素ごとにまとめると
・糖質:控える(特に精製されたもの)
・脂質:オレイン酸&オメガ3系脂肪酸で賄う
・たんぱく質:控える(主に動物性たんぱく質)
・ビタミン:積極的摂取
・ミネラル:積極的摂取
・食物繊維:積極的摂取
ということになります。
ちなみに、この生活を1年間フルですると健康になるかと言われると、そういうわけでもないようです。目安としては、1年間のうち約8ヶ月をオートファジーを促し、約4ヶ月はオートファジーを抑制するような生活を送ると良いと言われています。バランス的には2:1ということになります。
○まとめ
今回は【オートファジー】についてお伝えしてきました。
最後にまとめを行います。最初からここを読んでも構いませんが、お時間ある時に全文を読んで頂けると嬉しいです。
・mTOR(エムトア)の働きが抑制されると「細胞の自己浄化モード」であるオートファジーが促進される。逆に、mTORが活性化すると「細胞の成長モード」に入る。
・オートファジーを促進させるには、食事と運動が効果的である
・インスリンやIGF-1は、mTORのスイッチをONにし、細胞を成長モードにする
・IGF-1は生きるために必要であることは間違いないが、量が多すぎるのは問題となってしまう
・IGF-1を減らしてオートファジーを促進させるためには、精製された糖質と動物性たんぱく質の摂取を控えること
・1年のうち、8ヶ月はオートファジーをON、4ヶ月はOFFになるような食生活を実践することで健康長寿に近づくことができる
今回は以上となります。
ここまで読んで頂きありがとうございます。

<stand.fm>
https://stand.fm/channels/5f523fd46a9e5b17f7280815
Instagramもやっていますので、こちらも是非フォローしてください^^
https://www.instagram.com/mental_fasting_diet/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
