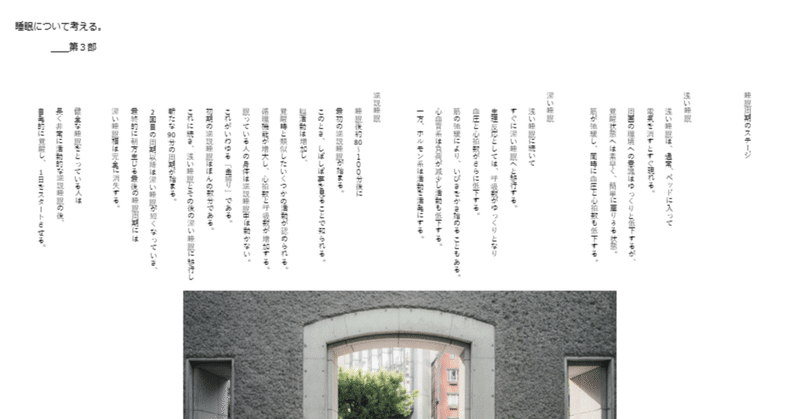記事一覧
睡眠について考える __完
ありがとうございます。
今回睡眠について勉強したことを少しまとめてみました。
いかがでしたでしょうか。
私自身、今回の学習で一番良かった所は、
睡眠周期が90分で、
ほとんどが深い睡眠ではなく浅い睡眠の繰り返しである。
という事を学んだことです。
私は現在、もうすぐ2歳になる娘と妻と布団で川の字のように寝ています。
小さな子供は寝返りや寝相が悪く、夜中に何度も起きることがありました。
夜中
健康について考える _第6部
刺激物と睡眠
寝る30~60分前の
中等度のアルコール摂取は、
睡眠障害を引き起こすとされている。
睡眠維持の乱れは、
一旦アルコールが身体から代謝されるとき
最も著しい。
血中アルコールレベルが0.06~0.08%、
その後1時間あたり0.01~0.02%低下する
中等度のアルコール摂取状況の場合、
アルコールが除去されるのに
4~5時間かかり、
ちょうど8時間睡眠の後半にあたるため、
睡
睡眠について考える _第4部
睡眠不足の影響
睡眠パターンの乱れは
生理学的な状態の変化を
引き起こす可能性があり、
身体の適応に影響する場合がある。(Halson 2008)
睡眠不足は、内分泌反応を変化させ
リカバリーの過程が遅れる可能性がある。(VanHelder and Radomski 1989)
睡眠時間が減少すると、
血中コルチゾール濃度が増加し、
成長ホルモン活性が低下する。
これは異化作用(分解)の
スト
睡眠について考える _第3部
睡眠周期のステージ
浅い睡眠
浅い睡眠は、通常、ベッドに入って
電気を消すとすぐ現れる。
周囲の環境への意識はゆっくりと低下するが、
覚醒状態へは素早く、簡単に戻りうる状態。
筋が弛緩し、同時に血圧と心拍数も低下する。(Lee-Chiong 2006)
深い睡眠
浅い睡眠に続いて
すぐに深い睡眠へと移行する。
生理反応としては、呼吸数がゆっくりとなり
血圧
睡眠について考える _第2部
睡眠周期
ヒトは人生の1/3
およそ1日6~10時間眠って過ごす。(Walters 2002)
その睡眠は、周期的に調整されている。
睡眠周期は、浅い眠り、深い眠り、
そして逆説睡眠(夢を見る事を経験)
各ステージからなる。(Lashley 2006)
これらのステージは
電気的な脳活動、血圧、心拍数、
呼吸数、筋活動と眼球運動など
各パラメータにより分類されている。(Lashley 200
睡眠について考える _第1部
睡眠とは
睡眠は
感覚器官により知覚は働いているが
意識は消失していて
自然に繰り返される
コントロールされた状態のこと。(Beersma 1998)
しかし、
これまでのところ
睡眠の明確な役割は
曖昧なままである。(Beersma 1998)
おそらく睡眠は、
広範囲にわたる
認知機能と身体的側面に対する
再生あるいは準備のための
様々な生理的、心理的機能を
確保していると考えられる。(