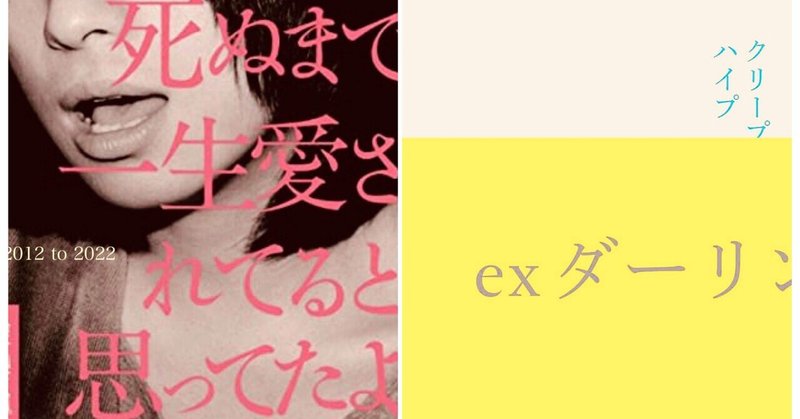
[前編]僕らが言ってきた“メンヘラ”って何なのか…クリープハイプ『死ぬまで一生愛されてると思ってたよ』10周年に寄せて
2012年4月18日、クリープハイプのメジャー1stアルバム『死ぬまで一生愛されてると思ってたよ』がリリースされた。行き場のない虚しさ、生活に潜む愛憎、忘れがたい日々や恋、それらを独特の比喩/語彙と言葉遊びを絡めて丁寧に描かれた歌詞。ヒリヒリとした情感を届けるのにうってつけな尾崎世界観(Vo/Gt)のハイトーンな歌声と、それを最高潮の状態で送り出す多彩でしなやかなギターロックサウンド。テン年代のロックシーンに与えた影響は計り知れず、この作品の強度はリリース当初以上に時を経て更に実感することになる。本稿は本作のリリース10年に際して勝手ながら記したものである。
クリープハイプと"メンヘラ"
クリープハイプの10年を語る上で、"メンヘラ"という言葉が良くも悪くも外せないと思う(精神科医になった今の身としては、"メンヘラ"という言葉を使うのも憚れるのだがこの記事ではこの言葉にしっかり向き合うべく"メンヘラ"と呼称させてもらう)。下のツイートは自戒を込めてここに晒す醜文だ。
あと大学の同期のメンヘラ系女子クリープハイプ好きだと発覚。「ラブホテルが切なくて仕方ない」と言っていた。「さすがメンヘラ」と言いかけたがぐっとこらえた。最近ようやく大人の対応を覚えた。
— 月の人 (@ShapeMoon) October 19, 2013
一体なぜ当時の自分はこんなツイートをしていたのかと頭を抱えたくなるのだが少なくとも8年半前は自分の認識もこの程度であった。今となっては恥ずべきことを面白がって書いていた。しかしこの後、具体的にはこの翌週に初めて観たワンマンライブ以降、大熱狂を少し過ぎレーベル移籍と格闘するクリープハイプに本格的にのめり込んでいき、この認識は徐々に外れていく。
しっかりとしたリスナーであれば、彼らの音楽を“メンヘラ”で片付けることなどをしないはずだが、2012,13年頃の自分のように雑に言及していた人は少なくはなかった。そしてその声や表現法をネタとして扱ったり、揶揄する目的で聴き続けてきた人々には未だに「クリープハイプはメンヘラ」「クリープハイプを聴いてるやつはメンヘラ」という認識のままでいるのはやはり事実である。ほんの少しTwitter検索をするだけでもその現実は明白である。
2016年のananwebにて尾崎世界観は自身の歌詞の扱いについてこう語った。
僕の歌詞、“メンヘラ”で片づけられちゃいますからね。ほんとうに腹が立つ。解釈が間違っているのは全然構わないんです。ただ、もっと踏み込んで、どういう意味なのか、考えてほしい。わからないから“メンヘラ”って言葉で逃げるんでしょうね。
真っ当な切り返しである。尾崎世界観の書く複層的な意匠が施された歌詞を評する際、流行り物を揶揄する目的や少し穿った目線で手っ取り早く形容すべく用いられるこの“メンヘラ"というワード。女々しさは断罪すべきものだというマッチョイズム、精神的な健康という当人にはどうにもならない事柄で優位に立とうとするような口ぶりをこの言葉遣いには感じる。
当時の自分のツイートもそうだが、未だにクリープハイプについて"メンヘラ"と形容している人も単に嫌いだから"メンヘラ"と言っているわけではない。共感や〈寄り添ってくれている〉という思いからあえて"メンヘラ"を用いているファンも多いように思う。しかし個人的にはクリープハイプを深く好きになるにつれ、そして医学生として勉強をする中で精神疾患を学び、"メンヘラ"という言葉への違和感を持ち始めるにつれ、当時のワードチョイスがいかに的外れでともすれば差別すら招きかねないことだと猛省した。
そして今。精神疾患を意味する2ちゃんねる発祥のインターネットスラングである"メンヘラ"がそもそもなぜここまでキャッチーな言葉として認知されているのか、という点に興味が向いた。当然だが"メンヘラ"は医療用語ではなく、精神科に関わる医療スタッフで"メンヘラ”という言葉を用いている人間は少なくとも今までの職場にはいない。昔は自分も気軽に使っていたこの言葉。結局僕らの言ってきた"メンヘラ”って何なのか。真摯に考えてみる。
"メンヘラ"とは何か
"メンヘラ"の定義を解説するもの、特に心理士や精神科医の監修が入っているものを読み、その共通項や納得したものをまとめると以下のようになる。
・親しい相手を過度に束縛する、依存する
・感情の起伏が激しい、感情のコントロールが困難
・マイナス思考、極端にネガティブ
・構ってほしがる、過剰にアピール的な振る舞い
・嫌いな人を執拗に攻撃する
・不規則な生活、自傷行為
何となくは掴めるし、自分もこのような認識だった。しかしこれらの特徴は言うなれば印象や状態に過ぎない。ここに病名がつくとしたら何なのか。上記のような症状を抱えてくる患者は確かに外来に多くいるが、一律の病名がつくわけではない。
例えば摂食障害や不安障害、うつ病に至る背景に"メンヘラ"とされる要素がある人もいるし、"メンヘラ"とされる言動の根底に双極性障害や発達障害がある人もいる。"メンヘラ"の辛さそのもので来院するケースに限ると境界性パーソナリティ障害が近いのかもしれないが、この病名も実際のところは詳しく掘り下げていかなければ判別はできない。そしてその状態から診断名をつけることのできないと判断されることもある。病名を決めるのはラベルを貼るように簡単なことではないのだ。
診断がついてもつかなくても上記のような"メンヘラ"的とされる振る舞いを行っている人は日常でもSNS上でも多くいる。時に深刻で見逃せないが、時にはまるで自虐の1ネタのような形でも存在している。または揶揄されるもの、いじられる対象としても見かける。ポップカルチャーの世界に目を向ければ、時に架空のキャラクターの属性(これについてはヤンデレという呼称も古来からある)や性的消費の1ジャンルのような形でも散見されている。
「病みかわいい」などファッションの1つとして享受されているものや、「地雷系」「ぴえん系」といった派生的かつより親しみやすい呼び方など、現代においてすっかり“メンヘラ”はすっかり定着しきった概念と言えるだろう。女性を指す言葉が多く、男性はカテゴライズされづらいという差異はあるようだが性別無関係に“メンヘラ”は馴染み深いワードなのだ。
このような言葉としての定着を経て現代において“メンヘラ”は単に精神疾患を指す用語ではなくなった。「推しへの想い」「一方的な恋心」「依存し合う関係性」「浮気や不倫といった交際」「恋愛感情のない肉体関係」などの精神に強く影響を与える関係性に心を支配されている人々の感情を幅広く総括するワードとなったのだ。2016年に立ち上げられた「メンヘラ.jp」というサイトが精神疾患当事者からの具体的なエピソードを収集して公開していたのに対し、現在ポピュラーな“メンヘラ”が示しているのはまだ診断名のない、様々な生き辛さにまつわるものが多い印象だ。
なぜ"メンヘラ"が定着したのか。まずこの10年間が他者(恋愛/推し活など)や飲酒に傾倒していきやすい不安定な時代へと突入したという前提がある。そしてLINEやSNSの発達による他者との心理的距離の急接近が当たり前になったというインフラ面の進化が大きな理由にあると思う。顔の見えづらいスピーディーなやりとりが常識になったことでインスタントな安心感と心に余裕のない状況が生まれやすくなった。そして恋愛に限って言えば最初のラフな付き合いを生みやすいマッチングアプリがその流れで躍進していったことも見逃せない点だろう。
また「愛がなんだ」を始めとする先鋭的な恋愛映画の大増加もあった。これまで"メンヘラ”を描くとするならば、サスペンスな作風が多かったが本作の穏やかで日常的なムードを纏った依存の描き方は共感ツイートや感想note/ブログを量産した。SNS発の恋愛ポエム本のブーム(代表的な筆者の名は〈メンヘラ大学生〉だ)、大勢の共感が拡散のブースターとなる「純猥談」といった実録モノなど、自身の"メンヘラ"的とされる振る舞いを重ね合わせやすいエモいコンテンツが2010年代後半から大増加したことの影響も大きいはず。
恋愛系に限らずにネタツイやユーモラスな文章/漫画として人生の生き辛さをコンテンツ化した経験談的なエッセイ/物語が数多く見受けられるようになったのもここ10年だろう。そんな環境要因に加え、誰しもがInstagramやTikTokをカジュアルな自己表現ツールとして使う時代性も重なり、”メンヘラ“は日常風景に定着したのではないかと推察している。
生き辛さを発信する手段が装備されたことで、発信者の”メンヘラ“的な感情や思考が外の世界へと開かれていき、そこには共感や承認という付随要素も生まれる。「#メンヘラさんと繋がりたい」などのハッシュタグや〈病み垢〉の存在が、連帯を生むまでに至っているのが現状だろう。“メンヘラ”であることはアイデンティティであり個性であり、キャラづけ。そんな認識にまで至っている人はきっと少なくない。
そして結果として自分や身近な他者の状態を指すのみならず、受け取り手にとっては突飛に思えるテレビタレントなどの言動や、不安定な心情を描く映画/文学/音楽といった作品を形容することにも“メンヘラ”が用いられるようになる。自分を重ねたり、やや批判的な目であったり、様々な理由で”メンヘラ“というワードが飛び交うことになったのだ。後編は「音楽」にフォーカスし、特にこの10年間の作品形容ワードとしての”メンヘラ“を紐解いていこうと思う。
[後編]
◎本稿はシリーズ記事「2012 to 2022」と「メンタルヘルスとポップカルチャー」の合併記事です。
「2012 to 2022」は10年前に発表された作品を起点にして、この10年間の作り手やシーンの変容についてあれこれ記していく記事のシリーズです。
「メンタルヘルスとポップカルチャー」は一端の若手精神科医が日々の診療で感じていること、そこから連想したポップカルチャーの話をまじえながら書き残していく文章のシリーズです
#コラム #エッセイ #音楽 #邦楽 #音楽レビュー #音楽コラム #クリープハイプ #メンタルヘルス #死ぬまで一生愛されてると思ってたよ #exダーリン
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
