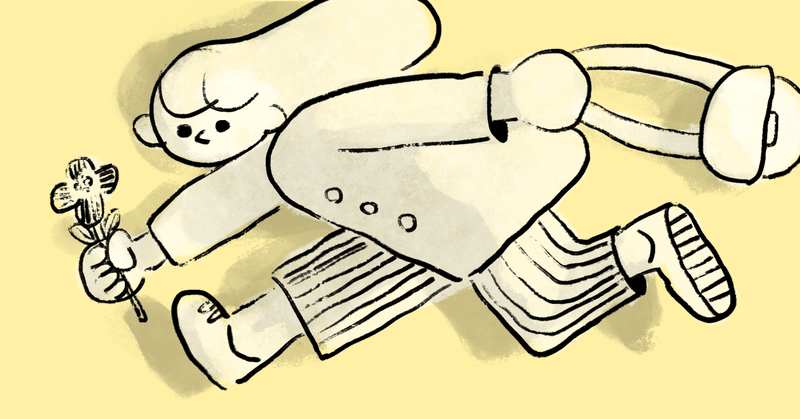
ゴール、どん!(創作小説)
<あらすじ>
web 制作会社に勤める松野ひかるは、転職活動をするも惨敗中。そのうえ現職では、両手で抱えきれないほどの業務量が滝のようにひかるの肩を打ちつけ続けていた。深夜まで続く残業。常態化した休日出勤。会社の歯車と化した毎日から脱出できないうちに、ひかるの心は少しずつ"何か"に蝕まれていってーー。
---
「成果を出せない人間は価値がない。私は社員みんなにそう伝えているよ。どんなに頑張って努力に時間をかけたとしても、結果が生み出せなければ価値がない。人間として生まれておきながら社会の役に立てないなんて魂の無駄遣いだと思わないかい?」
薄暗い部屋に今日最後の陽光が差し込んで床に影をつくる。六畳部屋の一角。白壁を頭の後ろにおいて画面向こうのエイリアンと相対する。
「君はどうなの? まあ、デザインの経験だけは長いんだね。努力する態度で乗り切ってきたタイプだろう? ほら、学生の時なんかは試験の点数は低いけど内申点がやたら高くてさ、そこそこ成績が良く見えるタイプ。おっかしい教育システムだよねぇ」
エイリアンはしゃべりたいだけしゃべると、手元のペットボトルの蓋を開けて耳障りな嚥下音を鳴らした。
デザイナー職採用の最終面接、それも社長面接を受けていたはずなのだが、果たしていつ時空が歪んだのだろうか。
社長……の形を模したエイリアンが放つ言葉の真意が測りかねて、僕はあからさまに眉を上げた。
「あの、僕は、人の価値は他人が判断できるものではないと思います。成果だけでは人の価値を本質的に測ることはできません」
「え、君さぁ……」
エイリアンは右手を顎に当てると、面白い玩具を見つけたように目を光らせる。「あ、くる」と、直感で分かった。
「君、女性だよね? 会社の最終面接で一人称が僕っていうのはどうなの? “ボクッコ”って言うんだっけ? 子どもまででしょ〜。立派な社会人が使っていいもんじゃないよ。礼儀がないね、君」
僕のなかで、何かが弾けた気がした。
「僕からすれば、あなたの驕った態度こそ礼儀のなさを感じます」
「……は?」
「僕の時間はタダじゃない。そちらさんが社員に価値を求めるように、雇用される側だって会社に所属している時間に価値を求めてンですよ。なんで会社ばっかり偉そうなんだよ。どちらか一方が価値を搾取する雇用関係なんて、安月給渡してふんぞり返る暴君と王に心を消耗させられる人民と同じなんだよ。こっちだって選ぶ側なんだ。いつまでも会社が社員を選んでやってるなんて思うなよ糞野郎!!!!」
息が上がる。肩もあがる。目の前がかすかに霞んでみえる。霧がかったような視界から見える画面の向こうでは、呆気に取られたエイリアンがだらしなく口元を開けていた。
暫くして、エイリアンは初めて人類に語りかけるかのように、ぎこちなく音を紡いだ。
「……キミ、メンセツニ、キタンジャナイノカネ?」
「あんたの会社なんか、こっちから願い下げだ」
間を置かず“接続終了”ボタンをクリック。震える指先でPCのシステム終了ボタンを選択すると画面はあっという間にブラックアウトした。
「ンンンン〜〜ッ」
ベッドに飛び込んで、お気に入りのクッションを顔面で抱きしめる。
「言ってやった」という爽快感と「やっちまった」という後悔の念。そして「終わった……」という虚しさが心を埋め尽くす。それから数時間、クッションは瞼から溢れるそれを吸い込み続けた。
---
終わりに悲しみを感じたことはない。たとえば別れを惜しむ涙の多い卒業式でさえ、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学と泣いたことは一度もない。さらに言えば思い出を振り返って悲しんだ記憶もない。
高校の卒業アルバムなんて面倒が上回って、ほとんど寄せ書きをしてもらわなかった。おかげでページはスカスカで、他人が見たら憐れみたくなる殺風景が形として残っている。けれどその白いページを不憫だと他人が撫でようとも、僕の記憶のなかにはちゃんと色づいた思い出のページが残っている。僕はそれだけで充分に満足できた。
そうは言っても「卒業するんだよ。ずっと一緒に学校生活を送ってきたのに、どうして悲しくないの?」と友人に異を唱えられることも少なくなかった。そのたびに僕は小学生の頃から変わらない答えを返しつづけている。「悲しくないよ。会いたい人には、会いに行けばいいでしょ」と。
僕たちはその環境を卒業するだけであって、友達という関係性を卒業するわけではない。たとえば海外へ移住したり、国内であっても飛行機や新幹線に乗らないと会えない場所へ引っ越したりするのであれば、相手との会いづらさに寂しい気持ちは生まれるけれど、それは卒業の悲しさではない。友達との距離の話だ。だから僕は終わりに悲しむ経験が乏しい。というより、理解することができなかった。
新卒入社して五年勤めた会社から苦楽を共にした同期が転職する今も、一抹の悲しみさえ生まれない。むしろ諸手を挙げて祝福したほどだ。それに彼女は新天地でも得意のトークを活かして輝くのだろうと容易に想像ができてしまうから心配の破片さえ残させてくれないのだ。
「ひかる、先に行くね」
新天地へ羽ばたいた同期の鈴代有紗(すずしろありさ)がウインクを飛ばす。いや、僕の目に映るのはLINEのトーク画面なのだけれど、右目でウインクする姿が勝手に脳内にやってくる。
前下がりのボブを揺らして、淡水パールのチタンピアスを光らせながら、ネイルの施された指先を艶々の頬にのせて華麗に片目を閉じるのだ。
「僕もすぐに追いつくよ」
人差し指と中指を伸ばし、口元に触れて、そうっと放す。微かにリップ音を立てる投げキッスをイメージしてLINEを返した。
---
最寄り駅から電車で二駅。改札から徒歩一分の位置にあるカフェ&ダイニング『Cafe Graphic』。十階建てファッションビルの五階。
モデルよろしくポージングを決めたマネキンの群れ、レトロな趣のあるセレクトショップを通りすぎ、甲高く響くアパレル店の声を背に受けながら奥へ進むとフロアから一線を画す風合いのお店が見えてくる。
オセアニア地域のカルチャーを取り入れた異国感溢れる入り口は、一歩踏み入れただけで世界旅行へ誘うようだ。
壁一面にはオーストラリアの絵師が描いたという巨大なクジラの絵画が飾られ、絵師のタッチに気を遣っているのか、ベージュやアイボリーを基調とした配色でインテリアが並んでいる。横長のキッチン沿いにはカウンター席が四つ。手前には四人掛けのラウンドテーブル席とくすんだオレンジ色のボックス型ソファー席。さらに奥へ進むと二人掛けのスクエア型ダイニングテーブル席と背の低いローテーブルの席がある。ソファーの背にはエスニック柄のブランケットがかけられ、天井まで続く大きな窓からは陽光がいっぱいに差し込んでいた。
見慣れたボブカットの後頭部に「おっす」と声をかけるとスマホを覗き込んでいた鈴代がパッと顔を上げた。二重の丸い瞳を爛々と輝かせて、飼い主が帰宅したときの子犬みたいだ。
「おっす! ひかるぅ待ちくたびれたよ〜。も〜話したいことたくさんあるんだけど。最近どうなの? てか、エイリアンと遭遇したんだって?」
「飼い主に飛びつく子犬かよ」
「え、子犬みたいに可愛い? ありがとう……」
「言ってないし、褒めてないわ」
ソファに深く腰掛けてカフェモカを吸い上げる鈴代は同じ年に新卒入社した同期であり、五年来の友人であり、先日退職した元同僚だ。たしか浪人しているから歳は一つ上のはず。
「ひかるはミルクココアでしょ。そろそろ着く頃かと思って注文しておいたよ」
「え、さすがじゃん」
鈴代が華麗にウインクを決めると、タイミングを見計らったように湯気の立つサーモンピンクのマグカップが運ばれてきた。鈴代は時折、こういうことをスマートにやってくるから感心する。すごい。僕なんて「先に注文しておこう」という発想すら浮かんでこないというのに。
「鈴代って、たまにイケメンだよね」
「まあね? とくに好きな人の前では、はりきっちゃうんだよね〜」
「あのときもかっこよかったよ。会社辞めますって宣言した後に脅すようなこと言ってきた人たちいるじゃん」
「脅すようなこと? なんだっけ」
「ほら、『転職先で変な上司に当たるかもよ』とか『今より忙しい職場だったらどうするの! 後悔するよ!?』みたいなこと言われてたじゃん」
「あーはいはい。あったね。忘れてた。あたし何て答えてた?」
「たしかー、『心配してくれてアリガト。その時は、また転職するよ』みたいなこと」
「あたし、かっこい〜」
「……じぶんで褒めてる姿見ると興醒めだな」
「なんでよ! ひかるがイケメンって褒めてくれたんでしょ〜。しかも子犬みたいに可愛いって」
「可愛いとは、ひとことも言ってないからね!?」
マグカップを両手で包むとカカオの香ばしい香りが鼻を通って喉を抜けていく。ひとくち含めば、あまい香りがふんわりと広がっていって心の空気が入れ替わるようだった。心の奥底に生えたモヤモヤ、トゲトゲしていた神経が少しだけ解れた気がする。
「まっ、転職に難癖つけてくる人の言葉なんて、右から左よ。会社に幸せにしてもらう時代は終わったからね。“わたし”を幸せにするのは、いつだって“わたし自身”なのよ。ひかるも、自分のことは自分がちゃんと幸せにしなさいよ」
「鈴代は幸せそうだよね」
「そりゃもう幸せよ。元の性格もあるけど、欲望に忠実だからね」
「あと現実主義」
「たしかに。終身雇用制度が崩れたいま、転職が悪なんて考え方してたらあっという間に置いていかれるわよ。自分の生活は、自分で守る。そして自分のキャリアは、自分で向上させる。これ大事! テストに出ます!」
「何のテストよ」
キルティングネイルが施された人差し指を向けられて、なんとなく顔を背けた。転職成功者の言葉は真っ直ぐすぎて、痛いくらいに身体中に降りかかってくる。僕もいつか転職を成功させて、こんな風に豪語できる日がくるのだろうか。
「鈴代、本当に会社辞めちゃったんだね」
「あら、寂しくなってきちゃった?」
「それはない」
「ほんっとにツンデレだなぁ〜寂しがってよぉ〜」
「なんか、成功者感があふれてる。まぶしい」
「うそ。オーラ出ちゃってる? さすがあたし」
「うるせー」
鈴代とは部署が違ったため一緒に仕事をする機会には恵まれなかったけれど、同期の懇親会で妙に気があって、よくカフェで駄弁ることが多かった。鈴代はカフェモカ、僕はミルクココア。時間も忘れて他愛のない話で盛り上がり、気が済んだら「また明日」と帰路に着く。それがいつものお決まりで、仕事に行く日の唯一の楽しみだった……のかもしれない。当たり前だった時間も、もうすぐ終わってしまうのだけど。
「ひかるとこうやって話すのも最後なんだね〜。なんか感慨深くない? 五年間、何かあっても何もなくても語り合ったよね」
「鈴代は八割方、男の話だったけどね」
「えー、そんなに話したかなぁ」
「ウンザリなくらい聞かされたよ。名古屋行ったらちゃんとした彼氏見つけなよ」
「あはは、そうだっけ! 名古屋で良い人いたら、ひかるにも紹介するね」
「遠距離恋愛とか無理だから」
「東京、名古屋間ならギリ中距離じゃない?」
「新幹線に乗ったら遠距離だよ」
「そうかなぁ〜?」
刹那、「っていうかさ!」と語尾を強めながら鈴代がテーブルから身を乗り出す。勢いに押されて、テーブルに置かれたカトラリーが驚くようにカチャカチャと揺れた。
「な、なに……」
真剣にものを言う時、鈴代は身を乗り出してくる癖がある。そして二重の瞳ぱっちり開いて、僕の目を射抜くのだ。首元にナイフを突きつけて、僕が現状から目を背けないように攫わんとする、獲物を猟る瞳。鋭くも優しい刃を向けられて、僕は無意識に背筋を伸ばした。
「ひかる、あんたも早いところ脱出しなよ」
どこから、とは聞かなくても分かる。いま勤めている会社からの脱却だ。転職活動を開始した時期は鈴代の方が三ヶ月ほど早かった。今後のキャリアを考えあぐねいていた僕に「転職にリスクはあっても転職活動にリスクはない!」と豪語した彼女の勢いに押されたのが転職活動をはじめたきっかけだった。
転職活動は時間と労力はかかるけれど、お金は一切かからない。絶対に面接を受けなきゃいけないわけでもなければ、受かったからって絶対に入社する必要もない。自分を知るため、会社を知るため、市場を知るため、情報収集を目的にしても良い。今の会社にはない新しい世界に触れて、知見が広がったり、見え方が変わったりするだけでも全然違う。
転職活動をはじめて数ヶ月。僕たちは知らないから何もできないだけで、知識があればどんな挑戦だって始められることを知った。知らないと怖い。だから行動できなくなる。でも、勇気を出して、まずは知る。それだけでも得られるものは計り知れないのだ。
……とは言いつつ、半年で華麗に転職活動を終了させた鈴代が眩しくて仕方がない。「欲しい物がたくさんあるから」と年収アップを第一に転職活動をして、結果的に年収が二倍近くまで上がったと言うのだから恐れ入る。
今日もお高そうなローズクォーツのシングルピアスにパールリングを身につけて幸せそうだ。そういえば自分の転職祝いに革専門店で特注のトートバッグも作ったと話していた。鈴代の隣に座る黒革のカバンがそうなのかもしれない。
「脱出しないとな〜」
「そうよ! 脱出、だっしゅつ!」
「どうしたら鈴代みたいに転職成功できるんだろ。早く会社辞めたくても、上手くいかないことばっか」
「まぁねー。妥協して転職先を決めちゃうのは良くないもの。納得いくまでじっくり時間かけなよ」
「うん。でも、三十社応募して書類通ったのがたったの三社。面接で二社落ちて、一社はエイリアンと遭遇。さすがに転職活動疲れたって感じ。というか落ちるたびに人格否定されているみたいで自信を失いつつある」
「分かる! もう雇ってくれる会社なんて、この世にないんじゃないかって思うよね」
「僕の価値って何なんだろう、みたいな」
空になったマグカップに視線を落として、モヤモヤとした心を代わりに注ぐ。湯気の立たない言葉の果てには何も生まれないことくらい分かっているけれど、僕の転職活動は何かを吐き出していないと気が狂ってしまいそうな状況だった。
書類を出しても通らない。面接に進んでも「カルチャーミスマッチを感じる」と対処しようのない返答で選考が終了する。投げても返ってこないボールを見つめつづける時間に苦痛を感じ始めていた。
「エイリアンは酷すぎるよ。そんな奴のこと考えてる時間がもったいない! 忘れよ! 怒って当然」
「だよね? やばいよね、エイリアン」
「やばいってもんじゃないくらい、やばいでしょ。見透かしたように人を下に見る態度も、一人称の指摘もすべてにモラルがなさすぎる。人間を理解していないエイリアン同然よ。ひかるはよく戦った。だからこそひかる自身のために、もう忘れな」
「うん、もう忘れる」
「そうそう。価値判断を相手に与奪されちゃダメよ」
鈴代の言葉はナイフのように切れ味がよくて、たびたび僕の胸をドキッと唸らせる。
「うん、分かってる。ありがとう。大丈夫」
「全然、大丈夫そうに聞こえないんだけど。……いや、ごめん。口煩いのは分かってるんだけど、ひかるを置いていくって思うと心配でね。ちゃんとご飯も食べて栄養摂るんだぞ」
「お母さんみたいなこと言うね」
「本気で言ってんの。会社だって正直ここ数年売上落ちてて経営層が揉めてるって話だし、人件費削減の影響で組織の空気も良くない。業務配分だっておかしいでしょ。ひかるの部署、法定残業時間超えてる社員が多いって噂で聞いたよ」
「ひかるは大丈夫?」と丸い瞳が覗き込む。キラキラとした瞳に写る自身の姿を見ていたくなくて、すぐに目を逸らした。
心許無く「大丈夫」と返すと、鈴代は盛大に溜息をついた。それから徐にメニュー表を広げると、FOODと書かれた欄を差し出してきた。
「なんか食べよ。あたしからの餞別」
「餞別って、ふつう逆じゃない?」
「あんた頑張り屋さんなんだもん。新しい道に踏み出そうと一生懸命。転んで泣いて、ボロボロなのに。ひかるの一歩の無事を祈ってはなむけさせてよ」
鈴代は腕を伸ばすと、隈のできた僕の目元を指の腹でそうっと拭った。
「焦らなくていいよ。自分で自分を傷つけないでね。転職はゆっくりで良い。だけど会社の業務が圧迫しているなら上司に相談しなさい。眠れなかったり、食欲がなかったりするのは身体が悲鳴を上げている合図だよ。ちゃんと休息も取りなさい。自分を一番に守ってあげられるのは自分なんだからね」
「お母さん……」と呟くと「こんなでかい娘はいらん」と文句が飛んできた。メニュー表に並んだパスタの名前が少しだけ滲んで見える。
「ひかるは、どんな生活がしたい?」
僕は「どんな?」とオウム返しする。
「あたしはね、金銭的なステータスが保たれる生活をできるかが重要なの。欲しい物を欲しい時に買えて、行きたい時に行きたい場所に行ける。あたしの欲望ってお金で解決できる部分が多い、なんて言えばカッコつくけど、要するにプライドが高いのよ。だから転職に求める譲れない条件も金銭的なキャリアアップだった」
「……つまり、どんな生活を送りたいか考えることで、転職によって自分が叶えたいことが何か分かるって言いたいの?」
「そうそう! さすがの読解力」
僕が願う生活、人生とは、なんだろう。小さな頃から絵を描くのが好きで気がついたらデザイナーの道へ進んでいた。今はWeb制作会社でHPやLP、バナー、ロゴなどのグラフィックデザインを担当している。
仕事自体は結構、いや、かなり好きだ。デザインの魅力は底なしで触れるたびに何かが僕の足を掴み、さらに深みへと落としてくる。しかしそこは真っ暗な洞窟でも出口の見えない迷路でもなくて、まるで見たことのない生き物に出会える深海のような優雅で美しい世界だった。
ビジュアルを作る過程はもちろん大好きだけれど、なによりも僕を深みに連れていくのは「デザインの本質はビジュアルを作り上げることではない」という昔お世話になった先輩の言葉だ。
人や商品が抱く課題を解決するためには、買いたい、見たい、行きたい、楽しい、面白いといった感情を動かすための要素が必要で、それは美しさで着飾るだけでは生み出されない。もっとありのままで、真実を魅せるものにこそ人の心は動かされる。それを発掘して輪郭づけることこそデザインの醍醐味だと教えてもらった。
だけれど鈴代が言っていたように、会社は業績が低迷中。人件費削減のしわ寄せが大きく波打って、両手では抱えきれないほど業務量も膨れ上がっている。日によっては、眠る時間も食事の時間も確保できないこともしばしば。最近は疲れが溜まって集中力が低下しているのかデザインの進捗も悪い。納得できないまま締切を迎えてしまい、苦渋を噛みしめながら納品する機会も増えた。
今の上司は「割り切って仕事をしろ」と言うけれど、感情を捨てて、ひたすら書類に判を押すだけのデザインに何の価値があるというのだろう。僕はもっと真摯に、もっと繊細に、デザインに向き合いたいだけなのに……。
このままではいつしか会社という名の工場に流れる案件を全うするだけの歯車になってしまう。僕が僕でなくても回る世界で、僕は生きていられるのだろうか。
「時間と心に余裕がほしい」
「うん、どうしてそう思うの?」
「一つの仕事にかけられる時間が短すぎて、デザインにちゃんと向き合えない。体力的にもきつい。最近はデザインも納得いかないことも多くて、そのまま納品するのが辛い」
「うんうん。ひかるはデザインにしっかり向き合える時間がほしいんだね。量をこなすよりも、質にこだわってデザインがしたいんだ」
「そう、割り切るとか、したくない。中途半端なデザインで納品するなんて申し訳なくて不甲斐ない。もっと、じっくり関わりたい。仕事としてのデザインにも、個人的に好きなデザインにも触れる時間がほしい」
「良いね! ひかるが納得できるデザインを生み出せて、ひかるが大好きなデザインにいっぱい出会える生活へ、転職をきっかけに変えていこ!」
「うん……。変えたい」
「よし! 叶えよう」と鈴代は意気込むと右手の拳を真っ直ぐに掲げた。そのまま「えいえいおー」と言うので僕も胸元まで拳をあげて繰り返すと、気合いが足りないと怒られた。結局、頭の上まで拳を振り上げたところで店員さんと目が合ってしまい、「ご注文ですか?」と尋ねられてしまうハメになったのだけれど、鈴代は笑って、ジェノベーゼとカルボナーラそして僕の好物であるチョコレートブラウニーを二つ注文した。
「えいえいおーが良かったからブラウニーもサービスしちゃうぞ」と笑う鈴代につられて、僕の口角も自然と持ち上がる。鈴代との最後の晩餐は少ししょっぱくて、胸が締め付けられるほど甘かった。
---
街頭がオレンジに灯る。辺りはすっかり夜の帳が下ろされていた。鈴代と歩く最後の帰り道は面接でエイリアンにかましてしまった口の悪さが話題に上って、次からは慎んだ言葉遣いでいなせるようにウェディングドレスで面接に望んだら良いんじゃないか、という何の意味もない話で大層盛り上がった。
鈴代はドレスを着てお姫様気分になれば口元も上品に装飾されると言う。何色のドレスだと印象が良いだろうか。ハートカットの胸元はエロすぎるかもしれない。くだらない議論を繰り広げて、夜の街に僕たちの笑い声が木霊した。転職を目的にウェディングドレスの話をしていたのは世界できっと僕たちだけだろう。
人が吸い込まれていく駅の入り口に立って、鈴代は「あ!」と声をあげて振り返った。
「言っておくけど、LINEおよび電話での大丈夫は禁句ね」
「なにそれ?」
「ひかるの大丈夫は信用できないの! 約束ね」
そう言って鈴代は僕と反対ホームへ進んでいく。別れ際はいつも淡白な彼女に今日は少し寂しくなって、その背中が見えなくなるまで手を振り続けた。
ーー
「はい。松野です。ーーあ、お世話になっております。え、原案届いていないですか? あ、あーーなるほど。分かりました。再度わたしからお送りしますね。ーーいえいえ。ーーはい、大丈夫です。ありがとうございます。はーい、失礼いたします」
カチカチ。カタカタ。
受信ボックスから特定の送信メールを見つけ出して、メッセージを添えて転送する。その傍らでスマホの連絡先一覧を左手でさっとスクロールしてタップする。
「お世話になっております。御社よりデザイン制作のご依頼を受けております松野と申しますが、担当の佐々木さまいらっしゃいますでしょうか? あー、そうなんですね。今週末入稿予定のデザインがございまして、明日までに校了いただけるようご確認いただきたく……。よろしくお願いします。はい、失礼いたします」
カチカチ。カタカタ。
「ーーーーはぁ」
知らず、ため息が漏れる。
鈴代が名古屋に旅立って三週間。僕は抱いて背負って肩車しても溢れる仕事量に、まともに転職活動を進めらずにいた。
入社当時は良い会社に就職できたと素直に喜んでいたのに、一体どこで道を踏み間違えたのだろう。
けれど一つだけ言えるのは、これほどデザインの仕事が好きになれたのは、当時教育係についてくれた糸井先輩との出会いがあったから。この出会いを生んでくれたのは、間違いなく今いる会社であるということだ。「デザインの本質はビジュアルを作り上げることではない」と教えてくれた糸井先輩。先輩と出会えただけでも入社した意味があると声を大にして言える。
先輩は真夏も真冬も晴れの日も雨の日も、ダメージジーンズにサンダルスタイルでペタペタと床を鳴らす、少し変わった人だった。百八十センチほどの高身長で上から視線を突き刺しながら「よぉ、新卒」と声をかけられた時はヤバい奴に当たったと落ち込んだものだ。けれど人は見た目で判断してはいけないもので、蓋を開けてみたら、かなりの世話好きでお人好し。あと、甘党。ランチをご馳走してくれた時、食後のコーヒーに角砂糖を五個放り込んでいるのを見た時はあんぐりとしてしまって「見せもんじゃねぇぞ」と睨まれた。
後輩を「おい」呼ばわりするものだから、同期からは「虐められていないか」と大層心配されたものだけれど、口の悪さからも滲む優しさが僕は好きだったし、怖くもなかった。僕にとってはデザインのイロハを一から懇切丁寧に教え育ててくれた大切な恩師だ。それに良いものができると「ひかる、よくやったじゃねぇか」と、自分のことのように嬉しそうに笑ってくれる表情が今でも忘れられない。その表情見たさに頑張っていた部分もあると思う。ただ僕が入社三年目を迎える年に会社を辞めてしまった。それ以来、疎遠になってしまったけれど、先輩の存在は僕の背骨となって今でも足腰を支えてくれている。またいつか、会えるだろうか。
奇しくも先輩が辞めた年、事業の体制が変わりはじめた。毎日、雨のように新しい仕事が絶え間なく降ってくる環境にいつの間にか放り込まれていたのだ。最近では雨の勢いが増してすでに洪水状態。言わずもがな日々は締切との戦いになる。それも一日置きに締切がやってくる豪雨のデッドレース。一度でも転んだらコース外に埋め込まれた銀色の棘に貫かれる壮絶なレースだ。
早朝出勤。深夜残業。土日残業。削られる睡眠。失せる食欲。それでも仕事は終わらない。次から次へと腹の上にのしかかるタスクに吐き気さえ感じる。これまでは稀に取れる長期休暇でレースから一時離脱することでエネルギーを回復できていたが、最近は休む暇さえ設けられない。そろそろHPゲージもギリギリだ。
これだけ逼迫したレースは、会社の売上低迷から人件費削減が命じられ、矛先が僕たちの部署に向いたのが大きな要因だろう。メンバーの三分の一が異動・出向となり、業務のしわ寄せはすべて僕たち既存社員に放り投げられた。いつまで忙しさが続くのかを考える暇もなく、仕事をこなすだけの日々がつづく。家に帰る時間が惜しいくらいで、いっそのこと会社で暮らした方が賢明だと思うほどだ。
作業していたIllustratorの画面がフリーズする。イライラと足を揺らしながら時計を見ると、世間一般的には定時と呼ばれる時間から針がすでに三周分も進んでいた。
「松野さーん! ねえ、今、忙しい?」
「……忙しいですけど」
フリーズしたデスクトップを覗き込みながら声をかけてきたのは入社九年目でお局ポジションを獲得した佐藤さんだ。肩まで伸びる黒髪を後ろで一つに束ね、黒いカーディガンに黒いフレアスカート、黒いパンプスを履きこなした全身モノクロスタイルが特徴的で、陰ではクロさんと呼ばれている。
クロさんの口から発せられる「今、忙しい?」は、かなり危険だ。疑問符を付けながらも百二十パーセント仕事を押しつけたいという強い意志を感じるし、大体が面倒事だったり雑務だったりする。
僕は大抵、とくにクロさんからの誘いには「忙しい」と返すようにしている。そもそも今は新しい仕事を受ける隙間さえ残っていない。断固として拒否しなければならない。だけれど「今、忙しい?」モードのクロさんは、飢えて人里に降りてきた熊並みに恐ろしくて、強い。
「あら、松野さんも忙しいのね。あたしも案件持ちすぎてキャパシティ超えちゃって。今週だけで三本も校了取ったのよ。明日も朝一で打ち合わせがあってね、資料も作成しないといけないのよ。これがまた面倒くさいクライアントでね」
適当に頷きながら未だフリーズしてグルグルと回っている青いアイコンの軌道を目で追いかける。作業を先へ進ませたいのに動けないもどかしさと、熊を突っぱねたいのに無下に追い払えない自分に唇を噛んだ。
「――それでなんだけど、他部署の部長さんに頼まれた案件があってね。あたしの技術じゃ応えられないと思うのよ。優秀な松野さんにぴったりなお仕事だと思うわけ。松野さん、お願いできる?」
「えっと、他部署の部長さんが佐藤さんにお任せしたいと思って、頼ってきた案件なんですよね。しかもそれを引き受けたのは佐藤なんですよね。だったら部長さんの期待に応えるためにも、佐藤さんが担当するべきではありませんか?」
「そうよねえ。せっかく部長さんが頼ってくれたんだし、あたしが引き受けられたら良いんだけど、ほら、松野さん優秀でしょう。あたしなんてもう歳よ。感性は若者には敵わないわ。この案件、松野さんが適切だとあたしは思うの。大丈夫よ、部長さんにはあたしが責任持って伝えておくから。気にせず取り組んでちょうだい」
「いやいや、僕もう手一杯で。新規の案件を引き受けている余裕ないですよ」
「あら、あたしも手一杯なのよ。もう、みんな手一杯なのよねえ。でもほら松野さんは優秀で若いから、部署で一番元気もあるでしょう。あ、それにこの案件ね、糸井くんが営業担当なのよ。ほらほら、松野さんの教育担当だったデザイナーの糸井綾瀬くんの弟。綾瀬くん、ウチ辞めて映像制作やってるって聞いたけど、弟の方が営業で入ってくるなんてねえ。……じゃ、お願いね」
「え、ちょっと……!!」
「メール転送してあるから」と言葉を吐き捨てる背中に反論の槍を投げるけれど、遂に強靭な熊の皮膚を貫くことはできなかった。全身真っ黒な服装の上から黒いジャケットと黒いトートバックを装備して「おつかれさま」と各所へ笑顔を向けながら、お腹が満たされた熊は颯爽と森へ帰っていく。
オフィスに残る同僚たちに目を向けるけれど、誰も目を合わせてはくれない。みんながみんな、容量を超えているのだ。自分に仕事が回ってきたら困る。触らぬ仕事に祟りなしだ。僕だって立場が違えば、きっとそうしていた。
今一度、Illustratorの画面を見るが、未だ動かないまま。諦めて再起動した方が良いかもしれない。ついでに集中力も切れてしまった。
「さいあくだ。あーつかれた……」
気の抜けた拍子に、全身に蔓延る疲労感から朝から何も食べていないことも思い出した。忙しさに追われていると、つい食事の存在を忘れてしまう。鈴代に見つかったら心底怒られそうな状況だ。今日の仕事が終わりを迎えるのはまだまだ先だろう。一旦、休憩だ。コンビニにでも向かおう。
ジャケットを羽織り、スマホを持って立ち上がると、やけにスマホが重く感じた。
タイピング音が響くオフィスの出口に向かって歩きながら、仕事の予定を頭のなかで組み立てる。戻ったら、まずはIllustratorを再起動しよう。その間に熊に押し付けられた仕事の内容を確認して、ロゴデザインの修正を仕上げて。そうだ、明日初稿のバナー制作も進めなければ。それから企画資料を作ってプレゼンの準備も進めて、あ、クライアントから修正依頼も入っていた気がする。戻ったら先に確認しておかなければ。
「おっと……」
何かに躓いて、壁に手をついた。
後ろを振り返るけれど、足元には何も見当たらない。けれど足首は枷を嵌められたかのように重く、前に踏み出すのが難しい。
「あれ…………」
身体を壁に沿わせながら、ゆっくり一歩ずつ前へ進む。身体が重い。なんだか、首元が苦しい。酸素が足りない。身体が熱い気もする。熱い、熱い……。
見慣れたオフィスの景色がぼやける。だんだん斜めに歪んでいく世界を見ながら目頭がカッと熱くなるのを感じた。外の空気を吸いたくて鉛の足取りで急いでオフィスを出た。
耳鳴りがひどい。霧が充満したような廊下を進む途中で、たまらずトイレへ駆け込む。奥へ細長く個室が並ぶ一室に身を隠して、崩れるようにしゃがみ込んだ。便器に向かうと堰を切ったように、僕のなかの何かが吐き出された。
心臓が身体中に飛び散ったかのように、全身でドクドクと一斉に鼓動を打ち鳴らす。
なに……?
こわいこわいこわい!
「うう……」
声を大にして喚いたつもりだったけれど、喉は呻き声を出すので精一杯なようだった。
息が浅い。世界が回る。全てがどうでもよくなる。
便器の上で両腕を組んで突っ伏す。
どこからか、止め処なく流れる僕のなかの何かを前に、僕はその泉が枯れる時を待つ他なかった。
脳裏にぼんやりと浮かんだのは「眠れなかったり、食欲がなかったりするのは身体が悲鳴を上げている合図だよ」という、いつかの鈴代の言葉だ。身体中が悲鳴を上げているとは今の状態を言うのだろうか。しかし重い頭を振って言葉を追い返す。
たとえ悲鳴を上げているのだとしても、早く立ち上がらないと。仕事は待ってくれない。身体が悲鳴を上げてしまうのはきっと心が弱いからだ。仕事が終わらないのは、作業スピードが遅いからだ。新規の仕事を断れなかったのも、僕の意志が弱いからだ。僕はもっと強くならないと。そのためにはもっと頑張らないといけない。早く、立ち上がれ。先へ進め。でないと、すべて終わってしまう。
息を吸って、ゆっくり吐いて、呼吸を整える。壁に手をつけながら立ち上がる。頭は重く、身体は熱い。肩に何かがのしかかったように全身がだるいけれど、動けないわけではない。
やすみやすみ前へ進んで、やっと自席にたどり着いた。周囲では相変わらず会社の歯車たちがカタカタとキーボードを鳴らしながら回転している。ぬるくなった水をひとくち含んで、息を吐き出す。Illustratorは未だ、固まったままのようだ。強制終了してPCごと再起動させる。
「あっ……。あーーもう」
右腕が掠って積み上げていたデスクの上の書類がバサバサと床に落ちた。すべての事象に気怠さを感じる。疲れた。もう疲れた。これ以上、僕の仕事の邪魔をしないでほしい。
拾おうと身をかがめると視界がグラリと揺らいだ。目が痛い。うまく、開けない。チカチカとして周囲がぼやけて見える。なんか、やばい。今日はさすがに、やばいかもしれない。
目を擦りながら時計を見ると、今出ればギリギリ終電に間に合いそうな時間だった。少し早いけれど、今日はもう帰ろう。仕事は何も終わっていないけれど、明日の僕が死ぬ気で頑張れば納期には間に合うはずだ。散らばった資料もそのままに立ち上がり、カバンを掴んでオフィスを出た。
遠くの方から「お疲れさまです」と声をかけられた気がしたけれど、まともに返事をする気力もない。適当に相槌を打ってひたすら足を動かす。一度でも止まったら、すべてが終わってしまう気がしていた。
電車に乗り込んで手すりに身体を預けながら、ぼんやりと高速で流れていく景色を眺める。そこにたしかにあるはずの物体は電車の移動速度と夜の帳により、黒い塊となって眼前を流れ去っていく。まるで自分の心のなかを見ているようだった。
あったはずの物が、どんどん色を失くして、形を無くして、闇の世界へ消えていく。手探りで輪郭に触れようとしても空を切るばかりで何も掴めない。気づけば中身は空っぽ。一人暗闇に取り残される喪失感。この感覚には覚えがあった。
小さな頃、ドーナツの穴を埋めていたものはどこへ行ってしまったのか、家中を探し回っていたことがある。500円玉やペットボトルのキャップなど丸い形状のものを見つけてはドーナツの穴にはめて「これじゃない、これでもない」を繰り返していた。母親に食べ物で遊んではいけないと怒られて以来、ドーナツの穴を埋めることは諦めたけれど、穴を埋めていたものは世界のどこかに取り残されて今も寂しがっているかもしれないとずっと考えていた。穴を埋めていたもののことを思うと可哀想で堪らなくて、部屋でこっそり枕を濡らした夜もあった。
その時と同じだ。僕のなかに、たしかに存在していたはずの何かが抜け落ちている。「これかな?」「こっちかな?」と探すけれど、「これじゃない、これでもない」を繰り返す。代わりに哀愁の雫を零すばかりで片鱗さえ掴むことができない。
何かを失くした僕はこれから何を目印に進めばいいのだろう。息継ぎをするタイミングはどうやって計ればいい。息はどうしたら深く吸えるんだったっけ。生きるって、どうすれば良いんだっけ。
「……れる」
震える口が、終わりの音を紡ぎだす。
「殺される」
なぜそんな言葉を口にしたのか、僕にも分からない。
「仕事に、殺される」
音が遠い。目が痛くて、うまく開かない。光を失いながら全身から力が抜けていくのを感じた。
「終わりだ……」
ラブストーリーは突然に、というけれど僕の元にはラブストーリーにはほど遠い物語がやってきたようだ。重力に従うまま揺れる車内に身体は沈み、僕の終わりは唐突にやってきた。
---
目を開けると知らない天井が見えた。ドラマでよく見るアレだ。一命を取り留めた主人公が青白い蛍光灯に照らされるなか白いベッドに横たわって、目を覚ます時のアレ。だけれどドラマで見る様子とはいくらか雰囲気が違う。見知らぬ天井ではあるがスス汚れているし、電気は消されて薄暗い。そもそも部屋というよりも、部屋の一角をカーテンで区切っただけの簡易スペースのようだ。ベッドも硬いし、かけられた毛布は薄いピンク地に花柄だ。
場所を確かめるべく身体を起こそうと身じろぐと、すぐ真横からもじゃもじゃの毛玉が飛び出してきた。もじゃもじゃの毛玉はタレ目を潤ませながら「せぇんぱぁい……」と情けない声をあげた。
「……あれ、糸井Jr.じゃん。なにしてるの?」
「なにって! 一緒に帰ってたじゃないですかぁ」
「心配したんですからぁ」と営業部の後輩であり、僕がお世話になった先輩である糸井綾瀬の弟、糸井水瀬(いといみなせ)、通称・糸井Jr.はもじゃもじゃのパーマ頭をブンブンと揺らした。あまり記憶にないが、天然パーマが視界の端にいたような気もする。
「倒れて起きて開口一番がそれですか! 元気そうで、ちょっと安心しましたぁ!」
怒っているのか、安堵しているのか。情緒不安定な糸井Jr.を眺めながら、ゆっくり身体を起こす。なるほど、病院ではない。おそらく駅の医務室だろう。
糸井Jr.はベッドから起き上がる僕の目線に合わせてしゃがみ込むと両の手を掴んで真っ直ぐに僕の瞳を捉えた。鈴代の視線とはまた違う。抱き締めて離さないとでも言いたげな熱い炎に覆われているようだ。
「松野先輩、具合はどうですか。頭は痛くない? 気持ち悪くない?」
「うん、大丈夫そう」
「電車で倒れたんですよ。覚えてますか」
「なんとなく」
「俺、先輩が具合悪いの、全然気づいてなくて……。本当バカですよ。すみません」
「いや、糸井Jr.が謝ることないよ。こちらこそ迷惑かけて、ごめんなさい」
「謝らないでください! とにかく一旦、落ち着いたみたいで良かったです。ここ駅の医務室なんです。家まで送りますから一緒に帰りましょう」
「……糸井先輩は口悪かったけど、糸井Jr.は丁寧だよね」
「なんで今、兄貴の話なんですか」
話し声に気がついたのか、カーテンの影から水色の制服を羽織った初老の男性が覗き込む。身体の安否を訪ねてくれるやさしい声にお礼を伝えて、僕は糸井Jr.と共に深い夜の街へ出た。
身体は重くだるかったけれど、夜の風が心地よくて幾分が気持ちに晴れ間が差し込む。終電の過ぎさった駅は祭りのあとのような静けさで寂しさを感じるけれど、どこか放課後の学校に居残りしているような特別な感覚もある。
大通りまで出ると居酒屋の明かりが僅かに煌めいていた。車道を走る車の影は少ないが、タクシーならすぐに拾えるだろう。
「糸井Jr.は最寄りどこだっけ? 終電ないよね。ごめん」
「良いんですよ。俺のことは気にしないでください。あ、タクシー発見! 乗りまーす!」
右手を挙げて駆けていく背中をゆっくりとした歩みで追いかける。糸井先輩と違ってシュッとしたパンツルックに茶の革靴がコツコツと上品な音を立てていて、兄弟でこんなに違うものかと驚く。しかしタクシーの後部座席から「松野先輩」とお姫様よろしく伸ばされた手をみて、世話好きでやさしいところは兄弟揃って似ていると、すぐに考えを改めた。糸井Jr.が目的地を運転手に告げると、車は静かに発進した。
「糸井Jr.の家は、どの辺なの?」
「俺は良いんです。松野先輩は何も気にせず、家でゆっくり休んでください」
「……糸井Jr.が帰る分のタクシー代、教えてね。全額明日払うから。あ、日付的にはもう今日か」
「もう、気にしいだな。要りませんよ。自分の身体の心配をしてください。それに明日は会社休んでくださいよ。家でゆっくり眠るなり、病院行くなりして、心身を整える時間を設けないと」
「ダメだよ。明日はプレゼンがあるもの」
「だけど」
「大丈夫。たぶん寝不足だと思う。最近忙しくて眠れてなくて。心配してくれて、ありがとね」
糸井Jr.は腕組みした手をじっと見下ろした後、「松野先輩」と唸るように声を出した。
「なに?」
「息ができる場所は一つじゃないんですよ」
「……なにが言いたいの?」
「松野先輩は、仕事だけが息をする場所になっているように、俺には見えます」
「そうかな」
「そうですよ。僕はね、松野先輩に憧れているんです。思いやりを真っ直ぐにクリエイティブに向ける姿勢、凛とした仕事ぶり。職は違えど、一緒に仕事してみたいって僕の士気を勝手にあげてくるんです」
「え、ありがとう……」
「うん、でも聞いて。憧れているけどね、自分を傷つける姿だけは放っておけません」
「……傷つけてる、つもりはないんだけど」
「先輩はそうかもしれない。じゃあ、最近美味しいご飯を食べたり、朝から晩までゲームしたり、好きな場所へお出かけしたり、何もしないでボーッとしたりとか、好きに過ごす時間ありました?」
「んーーーー……」
「ね? 日常に息をできる場所をつくりましょ。休むって、生きることなんですよ」
「でも、仕事、もっと頑張らないと……」
「頑張っていることなんて、みんな知ってますよ! なんたって営業部に評判が届いているほどですからね。もう充分頑張ってるんです、先輩は。だから、バットの振り方を変えてみるのはどうですか?」
「バット?」
「松野先輩はホームランバッターじゃないですか」
「……野球はやったことないんだけど」
「たとえです、たとえ! あのね、どんな変化球や剛速球が来ても松野先輩は絶対にホームランを打とうと思考を巡らせて、限界突破してバットを振るんです。そして見事ホームラン。あっぱれ! だけどね、物凄いパワーを使いますから、打ったあとはヘトヘトなんです。思わず地面に膝がついちゃうみたいに、ガクッてなるんです。イメージできてます?」
「…………まあ」
「でね、膝をついちゃうんですけど、先輩は立ち上がるんです。震える足を叩いて、頬を引っ張って気を引き締めて、ホームランを狙って再びバットを構えるんですよ。それが俺から見える今の先輩の姿」
「……ほう。凄まじいホームランへの執念だね」
「そうなんです。カッコいいですよ。少年マンガなら人気キャラ投票第一位確定です」
「だからこそね」と、水瀬は一度言葉を切ってから、腫れた僕の目元を指の腹でそうっと拭った。
「他のバットの振り方も先輩ならできると思うんです。だってね、野球ではヒットも素晴らしい成果なんです。ホームランは一度で点が入るけれど、ヒットだって数を重ねることで一点になる。一つのヒットがチームを勝利に導くこともある。だからヒットという及第点を持ってみるのはどうでしょうか。松野先輩は毎日ちゃんと合格点に達してる。成功につづく道を切り開いてきた。怠けてない、弱くもない、むしろ俺が憧れて止まないほど強くて優しい人なんだよ。だから、たまにはバットを置いて、休んで生きようよ」
「ね?」と、水瀬は微笑む。
目尻にできたクシャッとした皺。右頬にだけできるエクボ。まるっとした大きな瞳。羨ましいくらい綺麗な二重。力説してくれた水瀬に怒られそうだけれど、顔が可愛い、なんて感情が生まれてきて、錆びれた心を磨くように撫でていった。
「パグみたい」
「え、パ、パグ? 俺が? そうかな……?」
水瀬の言葉は度数の高いアルコールのように熱く身体を蹂躙し、やがて、すべてを呑み込んだ。目頭が熱くて、痛くて、瞼をそうっと下ろした。
頭に浮かんでくる仕事の山々を思うと息が苦しくなった。休んだらキャリアに傷がつく。だって世間は休んだ人間に厳しいから。人生の汚点だと嘲笑ったり、哀れんだりして、弱い人だと決めつけるから。鈍化していた転職活動は一層、勢いを失うだろう。休んでいる間に何をしていたのか、次の職場ではどうすれば休みを発生させずに活躍できるのか。人事に問われずとも、どこかで話さないといけないのだろう。面接のたびに明るい振る舞いで答えなければならないのだろう。ますます自分の価値を伝え、理解してもらうのが困難になっていくのだろう。
だけれど、もう辛い。彼の言うとおりだ。ホームランを狙いすぎた。バッターボックスに立ちすぎた。きっともう今は、バットを握る握力すら残っていない。息をするのさえ辛い。どうしてこんな苦しい思いをしているんだろう。いつ道を間違えたんだろう。
「水瀬ぇ……」
「はい!」
「僕、死にたくないけど、生きられないよ」
「…………。着いたら起こしますから」
水瀬の大きな手に促されて頭を肩にもたれさせる。もじゃもじゃした毛が耳にかかってくすぐったかったけれど、強張った心が解されているような気もして、悪くなかった。閉じた瞼から溢れる涙が肩を濡らしても、水瀬は何も言わない。
終わりに悲しさを感じたことも、涙を流したことも、一度だってなかったのに。僕は初めて終わりに悲しみをおぼえた。
---
「休むって、生きることなんですよ」。
糸井水瀬の言葉のとおり、たしかに生きている感じがする。休むという行為は不思議なもので、いざ休もうと思うと何をしたら良いのか分からなくて物凄く疲れる。全く、休み気分にはならない。だからこそ生きている感じがするという矛盾。
窓際に腰掛けて不毛な思考を巡らせながら、お手製のカフェモカを嗜む。コーヒー、ミルク、チョコレートソースで割ってつくる鈴代仕込みの逸品だ。お湯にインスタントコーヒーを粉ごと入れて、溶けるまで混ぜ合わせてからミルクとチョコレートソースを加えるのがポイント。甘みは気分に合わせてチョコレートソースの分量を変えて調節する。最近のお気に入りは大さじ1.5杯分。さらにホイップを乗せてカラースプレーを散らしたら最高なんだけれど、そこまでする気力は湧かないので想像のなかで楽しむことにする。
七階の部屋の窓から見える十メートル四方程度の小さな公園ではピンクのボールがあっちこっちへ跳ねて、子どもたちがキャッキャと身体を揺らしていた。いいなあ、と知らずため息が漏れる。
弾ける黄色い声に交じる豊かさを感じたくて、息を吸い込むようにカフェモカを味わうと、いつもよりまろやかさが増した気がした。もう一口味わおうと息を吐いたところで、床に置きっぱなしにしていたスマホがバイブ音を鳴らし出した。見慣れた表示に通話ボタンをタップすると「あ、松野先輩? いえーい」と気の抜ける水瀬の声が聞こえてきた。スピーカーをオンにして窓脇に置き、頬杖をつきながら「いえーい?」と返してみる。
「ねえねえ、今日はカツ丼か親子丼を食べようと思ってるんだけど、どっちが良いと思います?」
「昨日、牛丼食べてたじゃん。また丼ぶり?」
「だって白飯をかきこみながらうまい具を食べられるって最高じゃないですか」
「うまい具……」
水瀬の声を聴きながら青いストライプの入ったストローでカフェモカを吸い上げると、今度は香り立ちのよいカカオが顔を出して濃厚な甘みを感じさせてきた。
タクシーで送ってもらったあの日から、水瀬とは頻繁に連絡を取り合っている。それこそ動けなくなった僕をメンタルクリニックに連れて行ったり、会社の上司に話を通したりして、生きる道をつくってくれたのは水瀬だ。デスクに置かれたパソコンは、もう一ヶ月開かれていない。締切が詰まったカバンも戸棚に仕舞い込まれ、荒れ狂っていたデッドレースが嘘だったかのように今ではなりを潜めている。
人生で初めて体験する休職という時間は思っていたよりも苦しかった。こじらせた風邪のように精神を蝕んだウイルスはなかなか体内を出て行ってはくれなくて、「休みの時間を有効活用して新しい挑戦をしよう!」みたいな考え方は眩しすぎて直視できない。むしろダメージを受けるばかり。あまつさえ何かを頑張ることは、何かを失うこと、という種族のトラウマを心が飼い始めたようで馴らすまでは遥かに時間とエネルギーを要しそうだ。生きているだけで精一杯な日々にハイライトを挙げるとしたらゴミを捨てに行ったことくらいだろう。
そんな日々だけれど楽しみもある。それはお昼や夜にかかってくる水瀬からの電話を取ること。彼のやさしい響きのある声を聴いていると、陽だまりに包まれたように心の奥が火照るのを感じる。何度か電話を繰り返していると、やや天然気質な部分が垣間見えたり、細いくせして意外によく食べることを知ったり、水瀬の生態を少しずつ知れる時間が案外楽しい。彼の新しい一面を発見するのが生き甲斐になりつつある。心の火照りに名前を付けるのはまだ早い気がしているから、あくまで生き甲斐だ。
兎にも角にも僕の生き甲斐は仏のようにやさしくて「どうやって休んだら良いか分からない。明日が不安で怖い」と漏らしてからは「じゃあ明日の過ごし方を一緒に決めよう」と、必ず電話をかけてくれるようになった。
夜の電話では明日はカフェモカを飲むやら、明日は窓を拭くやら、他愛のない過ごし方を一つだけ決めて「また明日」と通話を切る。夜は気分が落ち込みやすいのか、自分の不甲斐なさに嗚咽を漏らす日も多いのだけれど彼は変わらずに接してくれた。水瀬がいなかったら僕は今頃、本当に野垂れ死んでいたかもしれない。
「いま、何してるんですか?」
「カフェモカ飲みながら公園で遊んでる子ども見てる」
「めちゃ平和じゃないですか」
「このあと、お散歩に出かけてみるよ」
「そうでした! 今日はお散歩デーでしたね。良いお天気だし、青空も綺麗でしょうね。写真、撮って送ってくださいよ」
「気が向いたらね」
明日にはもう忘れてしまうような会話から生気を補充する。程なくして休憩時間を終える彼を言葉で見送ってから、引き戸式のクローゼットを勢いよく開いた。
今日の予定はお洒落なお散歩だ。久しぶりにパーカーにスウェット姿から、ちょっと格上げして服を選んでみる。ゆったりと着られる白地のローゲージニットに足首丈まであるロングのプリーツスカートを合わせて、昔に買ったデジタルカメラを首から下げる。足元は歩きやすさを考慮してオーカー色の靴下にネイビーのスリッポン。肩口まで伸びた髪は一つに縛り、結び目にパールの乗ったヘアカフを差し込んで完成。
オートロックのマンションを出ると、ごみ捨て以来の太陽光に身体が反応して足りない養分をグングン吸い込んでいくようだった。仕事に明け暮れていた頃はオフィスに引き篭もっているばかりで休日すら家で残業をこなしていたから、こんな風に陽光を浴びる機会なんて片手で数えられる程度だった。
空に向かって腕を伸ばすと身体の内側に気持ちの良い空気が入り込んできて、太陽の気持ちよさを実感する。雲ひとつない青空に向かって、一つシャッターを切った。
住宅街の小道を抜けると川沿いに辿り着く。サワサワと風に揺れる草木の音、せせらぐ川の飛沫の音、ヒュッと耳をすぎる風の音を感じて懐かしさに耳を澄ました。普段の生活のなかでは紛れてしまう小さな音たちを一つずつシャッターに収めながら僕の世界へ迎え入れる。忘れていたものが戻ってくる感覚に音から視界が開けていく気がした。
靴が砂利を踏みしめる音、ニットの裾が擦れる音、デジカメの画面に触れれば、伸びた爪が当たってコツコツと音が鳴る。忙しくて、疲れていて、いっぱいいっぱいで、ギリギリで、日常や生活に馴染む音をキャッチすることもできないほど、心に余裕がなかったことに気づかされる。今度はもう少し遠くへ行ってみたいと、久しぶりに心が動かされた。
---
地元から電車に揺られること二時間三十分。僕の時間はタダではない。だけれど今日は往復三百分かけてでも行く価値があると思うから、行く。東海道線沿いから見える景色は普段なら青い空がだんだんビルで埋まり出して慌ただしい足音が聞こえてくるのだけれど、今日は至って穏やかな気配を漂わせていた。
都会を離れゆく電車に揺られる窓景色は一面を彩る青い空から、次第に古風な一軒家の屋根を映し出し、なだらかな畑も描き出す。太陽が爛々と地上を照りつけ気温を上げている様子も伺えた。換気のために開けられた窓の隙間からは悪戯好きな風が入り込んできて、僕に目をつけるやいなやスカートの裾をヒラリヒラリと持ち上げて遊んでいた。
風たちに別れを告げて駅に降り立つとさん然たる太陽が挨拶のごとく日差しを強めてきて、眩しさに目を細める。耐えきれずお出かけ用の小さなエナメルバッグから紺地の日傘を取り出て秋の日差しに向日葵柄のバリアを開いた。吹く風はやや冷たいけれど、まだまだ夏の名残を感じる気温だ。
コンビニを背に交差点を左に曲がって大通りに出ると、ちらほらと人影も見えてくる。向日葵柄のバリアは充分に力を発揮してくれていたのだけれど、道幅の狭いコンクリートの道には合わないようで、敢え無く開いたばかりのそれを閉じることにした。二人並んで歩くのがやっとな幅ではバリアは忽ち向かいから来る人の道を塞いでしまうのだ。
気を取り直して歩を進めると八百屋、洋服屋、ラーメン屋、リサイクルショップ、カフェと通りすぎるたびに色を変える店景色が面白くて、いつの間にやら歩幅も緩慢になる。そんな自分にまわりの景色を楽しむ余裕が生まれてきたか、と嬉しくなって一層歩幅を小さくした。
ふと店景色が途切れて舗装のされていない小道に行き当たる。目を向けると、ところどころ雑草が茂る空き地の一角に目を引くワゴンが止まっていた。黄色の車体に麻色のパラソルがかけられたキッチンカーだ。「ベーグルとタピオカ」と書かれたのぼり旗が風にはためいて、その姿がどうにも「おいでよ」と手を振っているように見えてしまい、少し寄り道することにした。
すでに数人が並ぶ隙間から覗いてみると10種類のベーグルとタピオカミルクティーのメニューが見えた。ベーグルの売れ筋は抹茶とブルーベリーのようで前に並ぶ女性たちもこぞって選んでいく。売れ筋も気になるけれど、やっぱり好物のチョコレート系統は欠かせない気がする。探偵さながら顎に手を当てて悩んでいると「どれも絶品だよ」とベージュのキャスケットを被った店主が得意げに歯を見せた。
「じゃあ、ホワイトチョコベーグルとタピオカミルクティーください」
返すようにこちらも歯を見せてベーグルとタピオカを受け取る。元の道を戻りながら太いストローでタピオカを吸い上げると、モチモチなタピカオのトリオが勢い良くやってくるものだから少し咽た。けれど、タピオカの甘さにミルクティーの茶葉の香りが相まって癖になるほど美味しい。
今度は左手に持ったベーグルに齧り付く。米粉を使用しているからかタピオカとは違ったもちっふわっとした食感がある。一噛みするたびに口内に溢れるホワイトチョコレートの甘さも堪らなくて、いよいよ手と口が忙しい。
美味しいものをちゃんと美味しいと感じられる、そんな自分にも安堵するとコンクリートを蹴る足も軽くなった。
なだらかな下り坂を降りきって短い信号を二つばかし超えると大きなサルスベリの木が見えてくる。淡いピンクと濃いピンクでグラデーションされた花々を目印に足を進めれば、到着。今日の目的地である、三嶋大社だ。
三嶋大社は伊豆国一宮と呼ばれ、伊豆の国でもっとも格の高い神社といわれている場所だ。奈良時代から平安時代の間に建てられたとされる、古くから三島の地を守りつづける由緒ある土地。源頼朝をはじめとした武士とも縁が深く、戦勝祈願のため頼朝をはじめとした将軍たちが参拝したともいわれている。なんとも待ち合わせ場所に指定してきた人とは似つかわしくない場所ではあるけれど、澄み切った空気と安穏な気配に満ち足りた気持ちが訪れる。来てよかった。
境内の砂利道を踏みしめる時のジャリジャリという音を楽しみながら拝殿へ向かう。五円玉ではなんとなく心許なくて五十円玉を握りしめ「五十に縁がつながりますように」と、お参りした。
「鹿の前で」と雑にLINEを送りつけてきた姿を探しながら宝物館の裏手にある神鹿園に足を踏み入れると、四十頭ほどの鹿が出迎えてくれた。大正時代に春日大社から神様の使いとして譲り受けたことから神鹿園と名付けられ、幾年も鹿が大切に育てられている場所だ。
鹿の近くまで寄ると体長九十センチは優に超えそうな大きさに驚く。同時にクリっとした大粒の黒い瞳が可愛らしくて虜になる。人間慣れしているようで柵越しに近づいても気にせずのんびと過ごしている姿がまた愛おしい。売店で鹿のおやつを買ってこようかと腰を持ち上げたところで懐かしいしゃがれ声が聞こえてきた。
「よぉ、よく来たな」
振り向くとサンダルにダメージジーンズ姿の男がバケットハットから長い前髪を垂らして、こちらに手を挙げている。「お久しぶりです」と返すと、あの頃と変わらない笑みを浮かべて、かつての先輩である糸井綾瀬は「おー」とかったるそうに応えた。
綾瀬が会社を辞めてから疎遠になっていたけれど、なんとなく気になって弟の水瀬を通じてつなげてもらったのだ。とくに大きな用事があるわけではなかったけれど、水瀬がうまく話を通してくれたらしい。
「糸井先輩、変わらないですね」
「見た目で人を判断すンじゃねぇ。おめぇは変わってねぇのか?」
「あー、変わりましたね。良い意味でも、悪い意味でも……」
先輩はふうん、と返すと「ほらよ」と米ぬかで作られた丸状の鹿のおやつを譲ってくれた。ありがたく受け取って、数年ぶりの再会にも関わらずムシャムシャとおやつを頬張る鹿に二人して夢中になってしまう。綾瀬の隣は会話がなくても心地良いから不思議だ。
「先輩、会社辞めたあと、何してたんですか?」
「んー適当に」
「クロさんから映像制作にいったって聞きましたけど」
「あのババァ、まだいンのかよ」
それから綾瀬は、ポツポツと土砂降りの予兆を感じさせる雨粒のように話してくれた。
映像制作会社へ転職した後、人間関係の折り合いがつかなくて、すぐに辞めてしまったらしい。その後はアートディレクターとして独立して美術館の広告を手掛けたり、インディーズバンドのジャケット制作をしたり、スタートアップ企業のホームページをデザインしたり、お菓子のパッケージ制作をしたりと、多岐に渡るデザインを手中に収めているという。圧倒的なスキルの差に卒倒しそうになるけれど、先輩からすると「のらりくらり生きている感じ」らしい。
「先輩はすごいですよ、かっこいい」
本心の言葉に先輩はフンっと鼻だけ鳴らすと出口へ向かって歩き出した。先輩なりの「ついてこい」の合図だ。半歩後ろをついていくと、案の定「なに食いたい?」と言葉が飛んできた。食い気味に「うなぎ」と返すと「良い判断だぁ」と横顔で笑った。
---
三嶋大社を出てから駅方面へ戻るゆるやかな坂道を十五分ほど歩くと、池のほとりの隣に構える古民家風の建物が見えてくる。おじいちゃん、おばあちゃんの家を想起させる引き戸をガララと音を立てて開ければ、昔ながらの小粋な店内が僕たちを迎え入れた。
大正ロマンなダイニングテーブルにベロア地がゴールドスタッドで縫われた座面の椅子。こだわり抜かれた店内にお上りさんのごとく辺りを見渡している間に「うな重二つと白焼き。それから瓶ビール。グラス二つね」と両手でピースサインを掲げる先輩にすかさず「うまきも!」とピースサインを伸ばした。
ほどなくてしてお重が乗ったトレーが運ばれてくる。まずは昼間に不相応なビールで乾杯を交わすことを忘れない。それから宝箱を開けるような心持ちでお重の蓋に触れる。そうっと開けばホカホカの湯気が顔面に広がって、うなぎの甘い香りが鼻を抜けていった。
早速、割り箸でつつくと柔らかな表面は、ほろっと雪のように解けた。タレのかかった白飯と一緒に箸に乗せ、満を持して口の中へ運ぶ。柔らかな舌触りと甘く香ばしい繊細な味が広がって、とろける美味しさに目を閉じれば、枯れた枝木に花がつく様子が浮かんだ。もう一口と目を開くと割り箸をもったまま頬杖をついた先輩がこちらをジッと見つめて、憎らしいニヤつき顔をしていた。
「なんですか」
「うまそうに食うなぁと思ってよ」
先輩はお重を持ち上げて大きな口で豪快にうなぎをかきこんだあと、肝の入ったお吸い物を喉へ流し込んで「たまんねぇなぁ」とつづける。口元に米粒をつけながら笑う姿に心のなかで「子どもか」と突っ込みを入れた。
「先輩もうまそうに食うじゃないですか」
「そのさぁ、先輩ってのやめろ。同僚じゃねぇし。鳥肌が立つ」
「じゃあ、綾瀬さん?」
「そこは糸井さんだろうが」
「だって綾瀬さんの弟、同じ会社にいるんだもん。糸井が被る」
「はぁ〜〜。弟はなぜ兄の跡を辿るのかねぇ」
「けど水瀬は綾瀬さんと違って、もっとやさしいですよ」
「へぇ〜〜〜? 水瀬に気ぃ合んの?」
ケラケラと笑う姿にムカついて、綾瀬のグラスを一気に煽ってやった。次いでに綾瀬の奢りとふんでうざくと角煮を追加注文してやるけれど「なんだ、めっちゃ食うじゃん。日本酒も飲もうぜぇ」とご機嫌になるばかりで、うまい仕返しはできなかった。それにふっくらした白焼きも、出汁が詰まったうまきも、さっぱりするうざくも、柔らかく煮込まれた角煮もどれもこれもが美味しくて、対抗意識も甘美に溶けてしまうだけだった。
「お前、これから何すんの」
最後に残った角煮を口にしながら、気だるそうに言葉が飛んでくる。
「……分かんない。いま休職中だけど、会社に戻って今までみたいに仕事を頑張るのは、もうできないと思う。というか、戻りたくない。休んでみて気づいたんです。仕事で雁字搦めになって自分自身を蚊帳の外に追い出した生活をしてた。すべてが仕事中心に回っていて仕事が止まれば自分も死ぬ、くらいに思ってたって」
きっと水瀬が助けてくれなかったら、我を忘れたまま会社に尽くす歯車と化して一生を終えていただろう。会社のためにするデザインも、お金のためにするデザインも、今はどちらもしたくない。もう自分自身が分からなくなってしまう場所に身を置くのは嫌だ。二十四時間、三百六十五日、会社のために稼働するのが当たり前という感覚を持った自分にも戻りたくない。
「ずっと思ってたんだけどよぉ。おめぇのやりたいこと、デザイナーじゃねぇよ」
「……は?」
角煮に入っていたコンニャクが箸から溢れ落ちた。
「え? どっ……それは、どういうことですか?」
「おめぇのやりたいことって、イラストレーターなんじゃねぇの」
イラストレーター。考えたこともなかった用語が出てきて吃驚する。たしかに小さな頃から絵を描くことは好きだったし、他の誰とも被らないキャラクターや世界観で表現するのは好きだった。けれどグラフィックデザインを専門にデザインやアートディレクションを手掛けてきて、ここでイラストレーターとは。
「まあ、厳密に言うとお前の場合はグラフィックデザインを活かしたイラストレーターになると思うけど」
「なんでイラストレーターなんですか?」
「おめぇは、デザイナーの役割はなんだと思う?」
「えっと、クライアントの課題をデザインの力で解決すること」
「だなぁ。お前の豊かな発想力と表現力は大いにクライアントに貢献したことだろう。でもな、お前の作風には味がある。ビジュアルだけじゃねぇぞ。ものの見方、思考する角度、表現の突拍子のなさ、あぁ、良い意味でな。そういう物を模る過程から他人にはない色と愛がある。正直、広告的な売上効果や数字なんてクソ喰らえって思ってんだろ? それよりも受け取り手がどう感じるのか、心を動かされるのかってことに価値を感じてる。数字なんぞ、そこをクリアすれば後から付いてくるもんだと思ってる」
「……たしかに根底にあるのは、人の心をポジティブに動かせるかどうかだし、よくないと思うけど、数字にはあんまり興味が持てないのも事実ではある」
「だろぉ? そもそもクリエイティブは数字的な根拠を計測しづらい世界でもある。それを無理くり数値化して価値を判断されるから仕事に追い込まれるんだよ」
「あーなるほど。たしかに会社では、いくつの量をこなしたかっていう、質より量を評価軸に置いているとこもあるし、無理やりCVRやNPSを出して評価されている部分がほとんど」
「そうなンだよ。もちろん数字があることで力を発揮できる奴もいる。どっちが良いか悪いかじゃない。ただ、お前は“そっち”じゃない。自分の個性を世界に見せろ。クライアントワークをするにしても、ロボットになるな。自分の持ち味を活かせるアウトプットの場を選べ。……まぁ、決めるのはおめぇだけどな」
真剣な眼差しがふっと、そっぽを向く。
その視線を追いかけると、僕のなかで今まで見たことのない扉が開いた気がした。扉の隙間からは、季節外れの春風が朧げな不安を巻き込んで、高く高く、それは高く吹き上がった。
春風を追いかけるように、どこからか桜吹雪がやってきて、僕の中にいる形のない何かの底に根を張ると、やがて何かは噴水のように湧き上がり、美しい飛沫に変わって光に溶けていった。
「綾瀬さんは、どうして僕以上に僕のことが分かるの?」
「おめぇが分かりやすいんだよ」
すでにテーブルの上には空のお皿とグラスしか残っていなくて、ほんのり火照った頬を携えて僕らは店を後にした。
駅に向かうみちすがら、明るい青空の隙間からポツリポツリと雫が垂れたかと思うと、程なくして雨粒は音を立てて地面を叩き出した。盛大なお天気雨に小走りでシャッターの閉まったお店の小屋根に避難するも、すでに服に水が染み込んでしまった。
「天気予報は晴れって言ってたのに」
「どうせ通り雨だろぉ。急ぐ理由もねぇんだ。待ってやろうやぁ」
空を仰げば、晴天の光がこちらを向いているのに、止め方を忘れたみたいに雨は振り続けている。
「空も溜まってたんだろうなぁ」
「溜まってた?」
「胸を張って言葉にしたかった想いを飲み込んで、咀嚼して、もう一度出そうと頑張るけれど、やっぱり飲み込んで。そのうち何を言いたかったのかも分かんなくなって。どうしたら良いのか、右も左も分からねぇで、溢れちまうンだよなぁ」
「綾瀬さんにも、そういう時あるんですか?」
「あぁ? そんなんばっかに決まってンだろ」
「えぇ……。ほんとに?」
「おめぇに嘘ついても得がねぇだろうが。……完璧に生きたくて、心殺して仕事したこともあったさ」
「完璧に生きる……」
「けどなぁ、”完璧に”なんて誰も生きられねぇよ。そもそも完璧ってなんだって話でさぁ。俺たち人間は何十年もかけて、自分様が何に喜んで、悲しんで、興奮して、嫉妬して、感動するのか取材しながら生きてくしかねぇンだよ。輪郭を掴めたと思ったらまた崩れて、新しい顔に変わろうとする。密着取材したって追いきれねぇよ。今の自分が良いか、悪いか、未来の自分が幸せか、不幸かなんて、誰にも分からねぇ」
「だからさぁ」と言葉を切る。空を見上げる綾瀬につられて顔を上げると、いつの間に雨足は過ぎ去っていた。
「俺もな、独立したなんて言えばカッコイイだ、真似できないだ、すげぇだと持ち上げられるが、知ってっか? 開業届って紙っペラ一枚出しゃあ、誰でもなれんだぞ。独立だって選択肢の一つにすぎない。本音を言えば、映画を撮るのが夢なんだ。今の道が夢の遠回りになっているのか、それとも近道なのかなんざ分からねぇけど、道草食いながら進むしかねぇのよ」
「それでも、挫けた時はどうするんですか」
「ハッ。思う存分、挫けたらいいじゃねぇの。挫けた側から見る世界にも発見があるかもしれねぇぞ」
「それは一理ある」
ここ数ヶ月の日々を美談にするつもりはないけれど、通ってきたらからこそ見えたもの、失ったからこそ得たものは、間違いなく僕の胸に宿っている。
「けどなぁ、ひかる。これだけは憶えておけ。俺らは俺自身のことすら分からねぇんだ。それこそ他人様になんざ分かるわけねぇよ。人の生き様に価値つけて、なんなら価値がねぇと腑抜けたこと抜かす奴はこっちから願い下げろ。そんで離れろ。そいつへ怒り、悲しむ時間はお前には勿体ねぇ」
「うん、わかった」
「それからな、世の中には会社の評価基準やら採用基準やら善し悪しつけて順位つけねぇと経済回んねぇ部分もある。それは仕方ねぇ。社会様が相手じゃあ、おかんむりしてるだけ無駄だ。居場所は一つじゃない。自分らしく生きて、働くために、何度だって変えていい。もっと遊ぼうぜぇ、人生を」
「やっぱりすごいよ、綾瀬さんは」
「ハッ。言葉の重みは水瀬より上だろぉ?」
「弟に対抗してる時点で水瀬の方が上です」
「チッ……生意気に育っちまって。お前はもっとそうやってなぁ、自我を出した方が魅力的だぞ。まるだしを愛してくれる奴ってのはぁ、意外にいるもんだ」
綾瀬の言葉は乾いた唇を潤してくれるようで、スルスルと心の奥を引き出してくるから不思議だ。弱くても、失敗しても、勢いが途絶えても、それでも良いんだ。受け入れようとせずに、隠してもがくから苦しいのかもしれない。
ぜんぶ曝け出して、身を委ねて、胸の内に手を当てて、聞こえてくる心根を大事にしよう。恐怖、焦燥、期待、混線した感情回路を紐解いて、中心でうずくまる、まるだしな僕をまずは僕自身で愛してみよう。
「ありがとう、綾瀬さん。僕、綾瀬さんに出会えて本当に良かった」
「そうかい。まあ、ゆるーく生きていきましょうや」
その日の帰り道は、近所にある雑貨屋に寄った。無邪気に心ゆくままお絵かきを楽しんでいたあの頃の自分にもう一度出会いたくて、大きなスケッチブックと色鉛筆、クレヨン、それに絵の具も一式、カゴに詰め込んでレジへ並んだ。
久々にワクワクと高鳴る鼓動が気持ちよくて、知らずうちに鼻歌しそうになる。高揚の勢いに乗ってスキップをして帰るのも良いかもしれない。
きっと真っ白なキャンパスを色で染める内に想いが溢れて、涙も零れてしまうのだろうけど、それでいい。きっとその涙は僕を先へ進ませる新たなる涙だと思うから。
---
エスニック柄のブランケットがかけられたソファーに座る後ろ姿に「やほ」と声をかけるとスマホを覗き込んでいたボブカットの女、鈴代がパッと振り返って、二重の丸い瞳を爛々と輝かせた。
ブンブンと揺れる尻尾が見えて、やはり飼い主が帰宅したときの子犬みたいだ。
飛びついてくる背中をよしよしと擦るけれど、彼女の温もりを求めていたのは僕の方で、強くつよく抱き締め返した。
「本当に来てくれた」
「言ったでしょ。欲しい物を欲しい時に買えて、行きたい時に行きたい場所へ行ける。そんなあたしであるために転職したんだから」
「会いたい」とメッセージを送ってすぐに「週末いつものとこで!」と新幹線を飛ばしてきた鈴代のフットワークの軽さには驚かされた。
数ヶ月ぶりに鈴代と訪れた『Cafe Graphic』は変わらずオセアニアの空気を感じさせ、僕たちを忽ち現実世界から切り離して特別な時間へ連れて行ってくれる。
今日の鈴代は耳元をオパールピアスで飾り、指元ではニ種類のアメジストリングが色艶を放っている。首元にはグリーン基調のスカーフがゆるく巻かれていてエレガントなスタイルだ。ソファーには雑誌でよく見かける高級ブランドのロゴが入ったのボストンバックが鎮座していて、彼女のアップグレードさが容姿から感じ取れて思わず笑いが溢れた。
「え、なになに?」
「ごめん、なんでもない。やっぱり鈴代の隣は安心するな〜」
「そりゃそうでしょう。こんな良い女、他にいないわよ?」
冗談めかしくウインクを決める鈴代に、また破顔する。
「失礼します」という声とともに注文していたパスタが運ばれてきた。
鈴代は季節野菜がたっぷり入った食べごたえ抜群のアラビアータ。僕は自家製の生ハムが贅沢に一面敷かれた生ハムとレモンのクリームパスタだ。
「いただきます」と両手を合わせてフォークをくぐらす。太麺にレモン風味のクリームソースをたっぷり絡んで口に入れると鼻を抜ける爽やかな香りがたまらなく癖になる。いま思うと美味しさを味わうにもエネルギーが必要だったとは知らなかった。一口を噛み締めるたびに幸せが心を埋め尽くした。
「んふふ。ひかうは、いあわへほうに、たふぇるねぇ」
「んん、なんて?」
鈴代はもぐもぐとほっぺを膨らましながら、満足そうに微笑んできた。よく分からないけれど、喜びは伝染するのだろう。どうしようもなく温かいものが注ぎ込まれて、胸を締め付けるやさしい温度に景色がかすんだ。
「ひかるって泣き虫だよね」
「感情が豊かなの」
「強がっちゃって。可愛いねえ」
「やめてよ。もう」
揶揄う鈴代をあしらって、パスタをもう一口。互いに頬を美味しさで膨らませながら、しばらくは近況報告で盛り上がった。
鈴代の話は相変わらず男の話ばかりで、名古屋でもブイブイ恋の花を咲かせているらしかった。三人目の男の話に移った辺りで、お決まりのミルクココアとカフェモカを注文する。湯気立つサーモンピンクのマグカップから甘い香りが漂って、やさしい気持ちに包まれた。
「それで、ひかるの話したいことってなに?」
カフェモカをストローでくるくるとかき混ぜながら、鈴代が言った。
「うん。僕、会社は復帰せずに退職するよ」
「まだ次の道は決まってないけど」と付け加えて、なんとなく返ってくる反応を見るのが怖くなって、マグカップを飲む振りをして顔を隠してみるけれど、すぐに明るい声が飛んできて杞憂に終わったことに安堵する。
「そっか! おめでと! ひかるが自分で選んだ答えだもの。あたしは応援するよ」
「ありがとう。それでね、転職活動は少しずつ再開する。もっと色んな会社を知ってみる。だけど正社員として雇用されるだけが働き方じゃないなって思って、業務委託でイラストの仕事を請け負えないかチャレンジしてみるつもり。綾瀬さんに世界に個性を見せろって背中押されて。自分の表現力をもっと試してみたくなった」
「ふうん、めちゃめちゃ良いじゃん。なんか、カッコいいよ。会社にいた頃より、すでに輝いてる」
終わりに悲しさを感じることがあるなんて、思ってもいなかった。会社と仕事が自分のすべてだと勘違いしていた。仕事を取り上げられたら、生きている価値のない棒きれになってしまうんじゃないかと恐ろしくて、終わりを迎えるのが酷く辛く、悲しかった。
だけれど僕は片足で簡単に跨げる段差をずっとずっと睨んでいるだけだったんだ。一段登れば世界はもっと広く豊かで可能性に満ちあふれていることが分かる。僕たちは元より自由で、豊かな場所を目指して歩く方向を好きに変えて良い。生き方も、働き方も、自分が熱狂できる方を指差してマイペースに向かえば良い。
旗印を目指して歩く道のりでは、また終わりを迎える日もあるかもしれない。終わりは怖い。今まで目の前にあったものが失われるのだから当たり前だ。この先どうなるのか、未来を知る術のない僕たちは定常的に有りつづけるものを手放すことに酷く恐れを感じてしまう。
だけれど終わりは喪失ではない。絶望でもなければ、不幸の始まりでもない。終わるという概念に僕たちはどうしてもネガティブな印象を持ってしまうけれど終わるからこそ、始められることがある。新しい出会いや喜び、幸せな体験や感情は、意外にも往々にして終わりから始まっているのだから。
終わることを許そう。始まりを受け入れよう。そうすれば、終わりのつづきはちゃんと描ける。
そう思うと、見えぬ未来に不安は残るし、堪らず涙する夜もあるけれど、やっぱり終わりは悲しくはない。
もしかしたら人生とは、自分を幸せにする終わりを見つけつづけることなのかもしれない。
「松野先輩〜! 鈴代先輩〜!」
耳馴染みのあるテノールボイスが店中に響いて、顔だけ入り口へ向ける。もじゃもじゃした髪をブンブン揺らしながらやって来る男に鈴代は「こっちこっち〜!」と手招きして、散歩中のワンコのように足を弾ませる糸井水瀬を迎え入れた。
「久しぶりだね、元気にしてた?」
「俺はもうロケット級に元気ですよ。鈴代先輩もお変わりなさそうで」
「え、なんで? なんで水瀬がここに……」
状況が飲み込めない代わりにテーブルにあるセルフサービスの水を飲み干してから、鈴代と水瀬の顔を順番に見比べる。
どうしてか、水瀬の唐突な登場に動揺が隠せない。胸の内が熱い。相手が鈴代だからと油断して今日は着古したボーダーのワンピースを着て来てしまった。髪の毛も梳かした程度で洒落っ気もないし、アクセサリーも何も身につけていない。そもそも眉毛とリップを整えたくらいでまともに化粧もしていない。水瀬とは電話でのやり取りは多かったけれど、こうして会う機会はほとんどなかった。久しぶりに見るクシャッとしたパグスマイルになぜか視線のやり場に困ってしまう。
「あたしが呼んだの。ひかるの心のなかにいるひかるが、会いたがってるかなって思って」
「な、なん、なんなのだ、それは」
「ほら、ひかる、そっち詰めて。糸井Jr.も座んなよ。なに飲む?」
「じゃあ俺はカフェラテにしようかな」
呑気に隣で笑う水瀬を見ていられなくて、視線をあちこちへ飛ばす。華麗にウインクを飛ばしてくる鈴代が憎らしくて、手元にあるカフェモカを飲み干してやったけれど、ケロッとした様子で追加注文していた。
「松野先輩、今日はラフな感じで可愛いっすね。髪の毛おろしてるのも良いなあ。会社だとよく結ってましたもんね」
「あ、そうかなあ。適当だけど」
「ちょっとちょっと糸井Jr.よ。その褒め言葉は完璧だけど、未だに松野先輩呼びはどうなの。ひかるも会社を卒業するんだし、それこそ同僚の域くらいは飛び越えてる関係なんじゃないの。名字に先輩呼びはどうかなあ〜」
「あー、言われてみれば。先輩はすでに俺のこと名前で呼んでくれてますし、松野先輩呼びはおしまいにしようかな。先輩が良ければ、下の名前で呼びたいです」
「オッケーオッケー! なんなら呼び捨てでもいいんじゃない? ねえ、ひかる」
「……な、なんでもいい」
前のめりな鈴代に押されるように答えると、水瀬は「じゃあ」と僕の両の手を取って真っ直ぐに瞳を捉えた。
熱い炎に覆われているみたいに暖かくてやさしい視線に、きっともう抜け出せないのだろうと知った。
「ひかるさん、から始めます」
休んでも。辞めても。変わっても。好きな人たちとの関係性は終わらない。むしろ時を経て深まったり、新しい関係性になったり、美しく揺れ動く。僕たちはこれからも、小さな終わりと始まりを揺籠のなかで繰り返して、何度もなんども新しい感情や体験を孵化させていくのだろう。
未来のことなんて分からない。この先どう転がっていくのか皆目検討もつかない。けれど、すべての愛しい終わりを迎えるたびに、愛すべき始まりを抱き締めていたいと思う。
僕はやっぱり、終わりに悲しみを感じたことはない。終わりはいつだって、始まりの合図なのだから。
Fin.
<あとがき>
当作品はもともと2022年1月19日に、一度公開していた作品だ。いろいろと作品に関して思うことがあり、非公開にして、その約1年後。再編集を経て、今一度投稿しようという気持ちに至った。
2022年当時、わたしは「会社」や「社会」に怒りをおぼえていた。
当作品はフィクションではあるけれど、ところどころで、わたしの実体験や本音が入り混じっている。
転職活動中の社長面接で「成果が出せない奴は価値がない」と言われたことが事実だったり、「仕事に殺される」と思っていたことも本当だったりする。
どうして会社が偉そうに社員を支配するんだろう。
どうして社員は仕事に支配されやすいのだろう。
どうしてわたしは、現状の生き方を選んでしまっているのだろう。
日本という国が嫌になって、いま生きている世界も嫌になって、何か社会に物申したいという気持ちが、低温の水が少しずつ煮立って沸騰していくように上昇して、やがて言葉になって激しく吹きこぼれていった。
そしてもし、ひかるのように見えない圧力に押し潰されそうになっている人がいるのであれば、社会の歯車になるのではなく、別の選択肢があることに気づいてほしい。
終わりはゴールではなく、始まりだから。
勇気を出して「自分を苦しめている事柄や環境や人間関係」を終わらせてほしい。
そんな思いを込めて、ひたすら何かを殴るように当作品を書き上げた。
けれど読み返してみると自身の気持ちが熱すぎて、憎しみが全面に出てしまって、血の滲むような乱暴な文章を書いてしまった……と少し後悔した。
そうして非公開にしたわけだけれど、1年のときを経て、冷静になった自分の目を通して編集し、改めて投稿するに至っている。
強すぎる言葉やストーリーには関係のない不平不満を消して、「終わりは始まりだから、終わる勇気を持ってほしい」ことを伝えられる物語で在れるように、新たに言葉と想いを紡ぎ出した。
これを読んだあなたが何をどう受け取ったのかは分からない。けれど、終わりの先にも道は果てしなくつづいていることを胸においておいてほしい。
辛くてどうしようもない日に、「よーい、どん!」じゃなくて、「ゴール、どん!」があることを思い出してほしい。
終わりを愛して、生きていこう。
by セカイハルカ
「ゴール、どん!」(創作小説)
→ 松野ひかる/まつのひかる(26)
→ 鈴代有紗/すずしろありさ(27)
→ 糸井綾瀬/いといあやせ(32)
→ 糸井水瀬/いといみなせ(24)
top画像 : あまのこさん(心を和ませるかわいさ!)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
