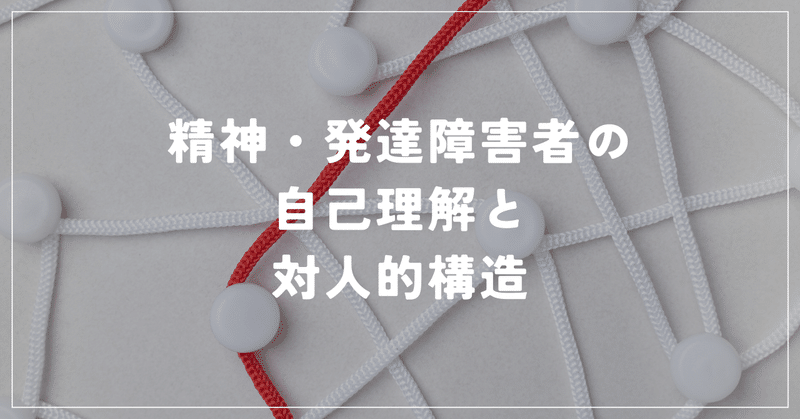
精神・発達障害者の自己理解と対人的構造
代表の久馬です。
蚕都Grantsプロジェクトやクラウドファンディングにご支援ご指示ご協力いただいている皆々様、本当にありがとうございます。
必ず達成することを目指して頑張っています。
達成率50%を超えると、クラファンサイト内で広告を打つことが可能になります。全国的にご支援いただけるチャンスを逃したくないのです。
もう少しで50%です!
厚かましい限りではありますが、ご賛同いただける方がおられましたら、ご支援をどうかどうかお願いいたします。。
蚕都Grantsをはじめたキッカケの一つ
精神・発達障害のある方の支援や訓練のメニューには、様々なものがあります。そのほとんどが、社会適応や職場適応をベースにしたものになっているように感じられます。障害を社会モデルとして捉えると、いろいろツッコミどころがあるのですが、今回は「自己理解」について書いてみます。
精神・発達障害者が強いられる自己理解の問題
自己理解は字義通りのメニューです。端的に言うと、自分とはどういうキャラクターや個性の持ち主なのかを自覚するということです。
ぼくは今の精神・発達障害のある方々の就職をサポートする仕事を始めてすぐに「なんで障害者だけ特別にわざわざ”自己理解”を強いられるのか?非障害者として生きてきた30年以上、一回もそんなこと言われたことないけどな。意図的にやるのが、すごく難しいことを強いられてないか。生きて通所するだけでも精一杯の人もいるのにな…」といった疑問と不満を感じました。
これは、やや偏った考え方だったかもしれないと思って、肯定的に捉え直してみると、「他者と共生するしかない上で”自己理解”は確かに重要」と考えなおしました。
しかし、現場で(自分を含む)当事者らに自己理解を促しても、むしろ当人らの気が滅入ってしまうケースがみられました。とくに二次障害的に「普通でなくてはならない」と思っておられる方にとっては、自分がいかに普通じゃないかを突き付けられることになります。サポートのつもりがかえって苦しめてしまう。そんなことになっては本末転倒です。当然ながら、伝え方やタイミングも重要ですが、ぼくが考えている大きな問題は「自己の理解を自己処理できない対人的構造(自己内完結型)」にあると考えています。もちろん自己内完結型でよい効果を自覚される方もおられますが。
しかし「自己理解と理解ある他者との接触はセットにする」という条件をメースにしないと本末転倒になってしまうことがあるのです。
そして、これは構造の問題です。
「(自己完結的に)自己理解したのに、結局、トラブルが起こって何も変わってないじゃないか!」と責められる障害者個人だけの問題ではありません。
支援者や支援機関は、訓練や支援のメニューを、単品で捉えてしまっていることが多いと感じます。
また、社会側(支援者側)の問題や、政治や法律、あらゆる問題が複雑に絡み合っているので、一筋縄では解決しません。
ぼくの意見を「理想論」として一蹴し、門前払いになさる支援者の方々もおられるでしょう。目の前の問題や課題をスルーされるおつもりなら、それはそれでぼくがとやかく言うことではありません。
ぼくは、難題だけど、どうにか解決の方へ向かいたい。と思うので、構造を俯瞰して見て、思考し行動します。
そのひとつが蚕都Grantsでもあるのです。
この活動は今の国政と行政主導ではできないけど、スルーすることもぼくにはできないのです。
ご支援をどうかお願いいたします!!!
私たちの活動に興味を持ってくださった方は、ぜひサポートをお願いします! 蚕都Grantsは精神・発達障害者の「経済的自立」を目指しています。頂いたサポートは、プロジェクトの活動資金にあてさせていただきます。
