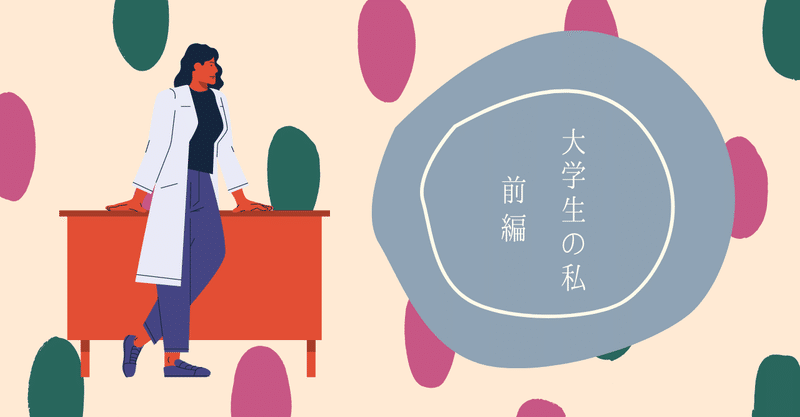
5. 大学生の私 前編
精神科を受診する前のわたし
2012年、晴れて私は大学生になった。
志望校ではなかったものの、高校受験に失敗した私が国立大学に合格出来たことは何より誇らしかった。
大学へ来たからには意欲的に勉学へ取り組もうとした。せっかく教育大に来たのだから、元々好きだった日本史の高校教師を目指したいと思った。
意欲的に取り組もうとは考えていたものの、入学式の翌日にあった健康診断は早速欠席してしまった。意欲のある日と無い日の差が薄っすらと顔を覗かせていた。
1年生の前期は、自然あふれる土地に位置するこの大学まで実家から1時間半かけて通学していた。後期からは母親の「一人暮らしは経験しておきなさい」という理念のもと、大学近くのアパートで一人暮らしを始めた。
完璧な妻であり母親を努める人間からの家事の手解きは、初めて一人暮らしをする大学生の私にとって少々過酷なものであった。
それでも母親が絶対的存在であったことや、新たな生活への期待から、家事とはそういうものだと信じて律儀に実行した。
2、3日に1回の洗濯は必ず物干し竿と窓、網戸を拭いてから干した。おかず、ご飯、汁物を必ず作った。トイレは週に1回掃除した。引っ越して最初に家具を配置した綺麗な状態にまで日頃から部屋を片付け、こまめに掃除機をかけた。
やる気に満ち溢れた私は、2つのサークルとアマチュア吹奏楽団に入った。オーケストラに軽音楽、吹奏楽と音楽三昧の日々だった。
軽音楽部では念願のドラムに再チャレンジした。見よう見まねで叩く拙い私に、経験者の友人は褒めてくれた。練習のモチベーションを上げるのが上手い人たちだった。
教育大であるこの大学には音楽棟があり、空いていれば自由に使える個人練習室も多く備えられていた。
音楽科の先輩と共にオーケストラサークルで活動することはとても刺激的だった。先輩に負けたくない一心で練習した。1限前や空きコマの度に練習室に引きこもった。それでも足りない気がした。
学業に3つの音楽活動、それに加えアルバイトも始めた。
初めてのアルバイトはブライダル業界だった。結婚披露宴で料理を出しては皿を引く。体力勝負な上、少しでも笑顔が欠けると怒られた。
見ず知らずの他人が食べた食器を素手で触ることが気持ち悪くなり、すぐに辞めてしまった。
それから他のアルバイトに就くも長く続かず、勤務先を次々と変えた。アパレルショップ、塾講師、喫茶店、ガールズバー、コールセンター。学生がやりそうなアルバイトは一通り手を出した気がする。
転々としたアルバイトは、職場の人間に嫌悪感を抱いて辞めてしまう傾向にあった。店長からの強い言葉や自分の納得出来ない指摘は、頭ごなしに怒られているようで気に食わず、裏でこっそり泣いてしまうこともあった。店長を尊敬出来ないとその傾向が強く出た。目の笑っていない人間に「笑顔で接客して」と言われることが、よくわからなかった。
不調を訴える身体
自分のキャパシティーはとうに超えていた。手帳は常に真っ黒だった。忙しそうにしている周りの友人を見ていると、それが普通なように思えた。忙しくしていないといけない、と焦っていた。
気づけば生理が止まっていた。女の身体である自分を醜く感じていた私は、かえって好都合だと開き直った。帰宅後に玄関で倒れたまま朝を迎える日もあった。
身体の不調はありながらも、充実感を得る楽しい毎日だった。特別良い成績を狙っていなかった私は、計画的に授業を休みつつも履修科目全て単位を落とさず、順調な大学生活を送っているように見えた。
一人暮らしを始めて約1年半が経過した2年時の終わり頃、不真面目な学生が気になり出した。
出席の代筆を頼む者。講義はろくに聞かず、先輩や同輩のノートで課題を終わらせる者。講義中に隣に座る友人と喋り続ける者。
ここは教育大だったはずである。将来教員になるであろう学生たちが講義の手を抜いている。不真面目に学業へ取り組むこの学生らがのうのうと卒業し、教育者になることへ絶望した。
中学生の頃付き合っていた彼女と別れてから久しく恋愛をしていなかった私に恋人が出来た。今度は男性だった。
性に溺れた私は次第に彼へ依存していった。一緒に寝過ごして授業をさぼってしまう日もあった。
とっくに身体を蝕んでいた活動量、周囲の学生への絶望、恋人への依存。徐々に精神を貪られた私は、次第に講義へ顔を出せなくなった。友人との約束や音楽活動の練習を無連絡で休んでしまうこともあった。他者との連絡が怖くて仕方がなかった。
歪んだ完璧主義の持ち主である私は遅刻というものが億劫だった。遅刻してしまうくらいなら休もうとした。講義の途中で家を出られそうな気配がしても、途中入室が困難で結局は欠席してしまう。2限を欠席すると3限すらどうでもよくなってしまい、自主全休(※)をする日が増えた。
※ 1日の講義を全て休んでしまうこと
午前中は億劫で活動が出来なくなった。悲観的な思考回路は次第に歪曲した。死を渇望した。それでいて死が怖かった。自殺者が英雄のように見えた。
完璧主義の私は、もうこの望月冴空という人間の汚れてしまった人生を修復することは出来ないと考えた。だから人生を終えてしまいたかった。完璧でない人生に用はなかった。
心配性で過干渉な母親は、一人暮らしの私へ頻繁に連絡を寄こしていた。中学高校と登校出来ない日のあった私が講義へ出られなくなることは、母親にとって想定済みだった。講義は欠席しても、日中は体が重たくとも、日が沈む頃に始まるオーケストラサークルには顔を出していた。そのオーケストラをも欠席するようになった私に、母親が「帰っておいで」と言った。
私はアパートを引き払って実家に帰った。
この頃の記憶はほとんど残っていない。気づけば母親に連れられ、精神科を受診していた。
双極性障害と診断された。大学はしばらく休学することになった。
精神科を受診したわたし
元々寝つきの悪かった私は、ほとんど眠れなくなっていた。
寝付けないほど「眠らなければ」と焦り、焦るほどに寝付けない悪循環。数時間かけてようやく寝付いたかと思えば1時間ほどで目が覚めてしまう。細切れの睡眠で寝不足の毎日だった。
初めて処方された睡眠導入剤の効き目は抜群だった。「飲んだ後はふらつくから動かないでね」という医者の言葉に疑いを持ちながら飲んだその薬で、私は階段を転げそうになった。力の入らない身体に感動し、母親に支えてもらいながら二階にある自室のベッドで横になった。いつ眠りについたのか分からないまま朝を迎えた。ぐっすりと眠ったのは久しぶりだった。
睡眠導入剤の効き目に感動したのは、この一回だけであった。毎日飲むそれは次第に効かなくなった。薬は次第に強いものに変更され、量が増えていった。
日常生活における必要不可欠な活動が、学業や就労、娯楽と同水準に感じた。起き上がる、着替える、歯磨きをする、顔を洗う、入浴する、どれも私にとって大変な作業だった。
母親と娘
私と父親の会話が減ると同時に、母親の父親嫌いが顕著になった。夫婦仲は良いように見えなかった。三人家族のその家は、たまたま同じ空間に三人の人間が居合わせているだけのようであった。
父親の行動にグッと涙を堪えていた母親は、露骨にため息をつくようになっていた。
母親は母親という生物ではなく、私と同じ一人の人間だった。
「私には冴空ちゃんしかいないの」と泣いて縋った。「あんたが小さい頃からお父さんが嫌いだった、離婚したくても出来なかった」と嘆いた。
母親と父親のちぐはぐな関係を繋いでいたのは一人娘である私だった。
二人の結婚指輪を一度も見たことがなかった私は、幼少期のアルバムを見返した。生まれたばかりの頃、二人の手にはお揃いらしき指輪があった。私が3歳を迎える頃にはそれが無くなっていた。
母親にとって私は、彼女の人生そのものであることに気づかされた。
思い返せば「私は大学に行きたくても行かせてもらえなかったから、あんたは大学に行きなさい」と何度も言われてきた。服飾の勉強がしたいと服飾関係の資格を持つ母親に言うと「あんたには無理だ」と否定された。
母親の嫌だった出来事を上げて「だから冴空ちゃんはこうしなさい」という言葉ばかり言い聞かせられてきた。私は母親の実現出来なかった願望をなぞる媒体だった。
実際、母親にそんなつもりはないのだろうが、私は母親の理想の人生を実現する人間として扱われていた。
何年も前から望月家は崩壊していたのだ。
その事実に耐えられなくなり、私は一人暮らしを再開した。
深夜の記憶
半期の休学を終え復学するも、登校はやはり難しかった。
優先順位をつけることが出来ず、自己責任であるものを後回しにしがちだった。サークル活動など、他者に迷惑がかかるものを先にこなし、自分の単位にのみ影響が出る学業は疎かになった。
食事は2日置きだった。何も食べない2日を過ごし、深夜のコンビニで3食分をゆうに超えそうな量の弁当やお菓子を買って一気に胃へ詰め込んだ。かと思えば1、2週間固形物を口にしない時もあった。自分の容姿が受け入れられず、BMIが17を切りそうになっても太っているように見えた。
シャワーを浴びるのが億劫で、人に会う前だけ身体を洗った。歯磨きも洗顔も、トイレに行くことすら重労働だった。
精神科でもらった薬を何錠も一気に飲んだ。薬を過剰摂取して得られる多幸感に酔いしれた。しばらくふわふわとした心地を味わった後は、吐き気と喉の渇きで藻掻き苦しんだ。
いつの間にかカッターで利き手と反対の腕を切りつけていた。自分がどこにいるのかわからない不安を拭ってくれる気がした。
痛みは感じなかった。滴る血液に快感すら覚えた。
手や足の指の皮を血が滲むまで何度も剥いた。眉毛や髪の毛を頻りに抜いた。
40度のジンを何で割るでもなくそのままラッパ飲みしていた。胃が焼けるような感覚がした。
試しにドアノブに延長コードで首を吊ってみたこともあった。息苦しさが心地よくて、それからは寝る度にベルトで首を絞めた。
原因のわからない不安と恐怖に支配されて突然声を上げて泣くこともあれば、きっかけなくケラケラと笑い出すこともあった。
暗闇の中、ひとりぼっちだった。
学校に行くために玄関から一歩外に踏み出そうとするだけで強烈な吐き気に襲われた。
他人の目が渦巻く学校の敷地内に入ることを考えると怖くて仕方がなかった。笑われている、罵られている、あいつはクズな人間だと思われていると感じた。酒を飲んでから登校する日もあった。
初めての一人暮らしでは頑張れていた片付けも出来なくなった。部屋や台所は散らかり、捨てることを忘れられたごみ袋が溜まっていった。
出会いと別れ
4年生に上がった2015年、私は再び休学した。
依存していた彼とも別れた。オーケストラの最後の定期演奏会が終わって引退した。とにかく休まねばならないと決意した。
双極性障害と出会ってから冬季うつの傾向にもあった。
学園祭のある秋を過ぎると寝込む日が増え、暖かい季節に移ると活動的になった。その年の夏、私はイギリスの大学に通う友人の元を訪れた。初めての海外旅行は、1ヶ月使って3カ国を回る長旅であった。
たくさんの人に出会った。拙い英語でも急かすことなく丁寧に聞いてくれる。ボディーピアスや眉を全て剃った私の姿に「それはどうしてやっているのか」と興味津々で、かつ真剣に話を聞いてくれた。
タトゥーやピアスをした人々が働く姿をよく目にした。知らない世界がそこには広がっていた。
卒業式、スーツや袴に身を包む同級生と写真を撮った。単位の足りていない私は卒業出来なかった。
5年目の大学生。私は当時出来た新しい恋人の住む街へ引っ越した。少しでも多くの時間を彼と共に過ごしたかった。恋人へ依存してしまう傾向は、まだ拭いきれてはいなかった。
教育大に来たのならば日本史の高校教員を目指そうと考えていた私の目標は、大学を卒業することに変わった。
教育実習や国際科の必修ではない社会科の科目を受けることまで手が回らなかった。
「卒業」の文字に恋い焦がれる私の大学生活が始まった。
ーーーーー
書籍紹介
謝るとき、感謝を伝えるとき、自己紹介するとき、思考が停滞して混乱しがちな人へ、オススメの一冊
ーーーーー
『9年かけて大卒を手に入れた人間の話』
目次
どうやら学士取得に9年もかった人間がいるらしい
どうやら大きな荷物を持って生まれてきたらしい
その人間の人生旅行へ続く搭乗口
1. 就学前の私
2. 小学生の私
3. 中学生の私
4. 高校生の私
5. 大学生の私 前編
6. 大学生の私 後編
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
