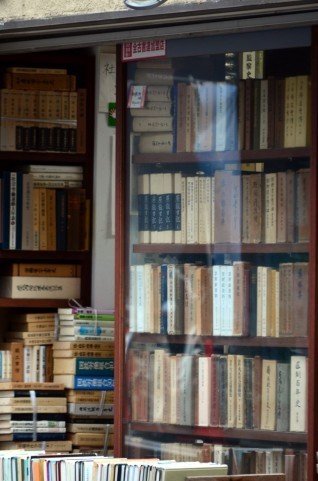
- 運営しているクリエイター
#贈与論
モノを人にあげると極楽往生出来ると言う思想の源流
マルセル・モースの贈与論では、古典ヒンドゥー法についても触れています。
かなり古い時代の叙事詩に登場するような「贈与」についての考え方が、現代でも生き残っている事を述べています。
物を人に与えれば、そのよい報いがこの世であれ、あの世であれ生まれる事になる。この世ではそれと同じ物を自動的に贈り主にもたらす。贈り物は失われる事なく再生する。あの世では贈り主が送った物を再び見出すが、それは増えている
売買の「売」と「買」の間に起きている事
お店に行って、品物を手にしてお金を払う。
日々普通にしている事ですね。
では、品物を手にした時からお金を払う時までの間に起きている事はなんでしょうか?
いや、スーパーマーケットやコンビニでレジカゴに入れただけで会計が済ませていない品物は、元の棚に戻せば、自分が買った事にはなっていないはず・・・
確かにその通りです。
では、もっと「時」を限定してみましょう。
品物がレジに持ちこまれ、登録
「お返しがない」と怒る人がいると言う事
マルセル・モースの贈与論には、次のような記述が出てきます。
これらの交換はかなり頻繁に行われるが、地域の集団や家族は別の機会に道具などを自給しているために、贈り物は、発達した社会の取引や交換と同じ目的を果たすものではない。
その目的は何よりも精神的なものであり、交換した二人の間に親しみの情をもたらすことになる。贈り物が互いの親近感を引き起こさなければ、すべてがうまく運ばなくなる。
これは、農
贈与は物々交換でなく、信用を前提にしていると言うこと。
マルセル・モーセの贈与論は、非常に示唆に富んでいます。
面白いと思ったのは、贈与経済と言うのは、物々交換ではないと言うこと、信用を前提にしていると言うこと、銅器が「名前」を持っていると言うお話です。
三番目の件は、また後で書くとして、僕もそういう言い方をしてきたことがありますが、通俗的な「貨幣」についての説明と言うのは、
ある人がお米を持っている、別な人が布を持っている、
でまあ、お米と布
「往来」が途絶えた先にあるもの
食物、女性、子供、財産、護符、土地、労働、奉仕、宗教的役割、位階など全てのものは譲渡され、返還される物体であると言うことである。
人と物を含む霊的な物体の永続的交換が位階、性、世帯に分かれたいくつものクランや個々人の間にあるかのように、あらゆるものが往来するのである。(マルセル・モース 贈与論 ちくま学芸文庫)
ポリネシアなどで「ポトラッチ」と呼ばれる全体的給付制度について、モースはこう述べてい
「贈与」経済の限界・・・文明化
「ダヤク族(ボルネオ)は、よそで食事に居合わせたり、食事の準備をしているところを見たりした時は、必ずその食事に加わらなければならないと言う義務に基づいた法と道徳の全体系を発展させさえした」
(マルセル・モース「贈与論」ちくま学芸文庫)
この件については、同書の注釈の中で、制度の比較研究のために「正しく確認すること」が難しいとしています。
例えば、「ボルネオのブルネイ国における強制的取引と言う
モノがやり取りされる時、モノの「霊」もやり取りされていると言う思想は現代社会でも生きている
「ハウは生まれたところ、森やクランの聖地、あるいはその所有者のところに帰りたがるのである。タオンガないしハウはそれ自体一種の個体であり、一連の保有者が祝宴、祝祭、贈与によって、同等あるいはそれ以上の価値の財産、タオンガ、所有物、労働、交易をお返ししない限り、彼らにつきまとう。
そうしたお返しによって、その贈与者は、最後の受贈者になる最初の贈与者に対して権威と力を持つようになる」
(マルセル・モ







