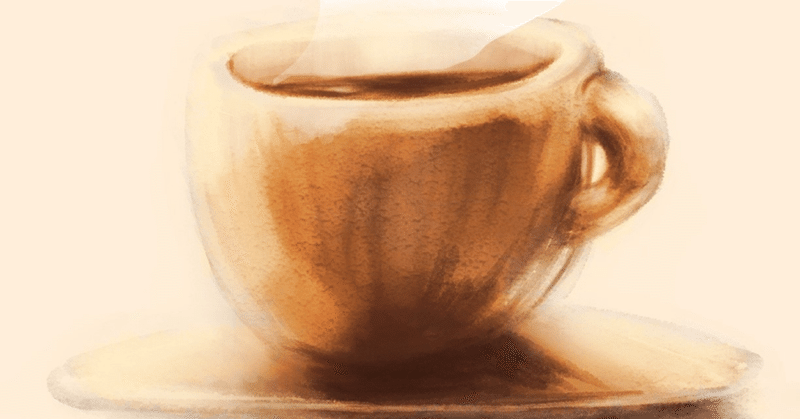
幽霊執事の家カフェ推理 第四話・マーメイドのパルフェ6
じゅうにがつ ふつか 雪
きょうはクリスマスツリーのしたに、プレゼントをおきました。
リボンがしてあるおおきなはこです。これはぼくので、クリスマスのあさにあけるのだそうです。
ぼくもママとパパのプレゼントをおきます。おにいちゃんのところでかいています。
パパはことしは、かなえさんのプレゼントをおきません。びっくりさせるので、みえないようにします。
アドベンカレンダーのなかにあるチョコレイトはおいしい。
クリスマスまでいっこずつ、たべるのです。
パパがいないので、はんぶんこできない。
塔子は外出から戻って来たとき、ちょうどイヴを見かけた。彼はビルの離れにある小さなオフィスから、パタパタと小走りで出てきた。
塔子が軽く手を振ると、イヴは目をぱちぱちさせた。ときどき大志のカフェに行く人だ、と気づいているようだ。
彼の作るハーブティーを思い出して、塔子は社員食堂に寄って行こうと決めた。昼の営業が終わった後でも、セルフサービスで飲めることになっている。
帰社してから、訪問先のオフィスがひどく乾燥していたことに気づいた。
顔にも何となく違和感がある。塔子は早くミストの化粧水をかけたいと、文字通り渇望した。
イヴはちょうどこれから帰るところだったらしい。いつもより遅い気がして塔子は時計を見た。もう夕方に近く、外も暗くなり始めている。
このビルも冬は湿度がひどく下がるから、ハーブティーがたくさん出てイヴも残業したのかもしれない。
通り過ぎるとき、彼からふと香水のような匂いがした。ムスクだろうか。
前にイヴと会ったときに感じたハーブの香りとは異質の、人工的で男性らしい香りだ。
それにつられるように振り返ったとき、香苗がイヴのそばに来るのが見えた。いつも送り迎えしているのだろう。彼女は、中途半端な姿勢でいる塔子に気づくと、笑顔で会釈した。
塔子は慌てて笑みを返しながら、二人が帰って行くのを見送った。
麻美はまだ社員食堂に残っていた。
塔子は挨拶もそこそこにハーブティーを一気に飲んで、おかわりを注ぎ足した。
イヴのブレンドは、すっきりしているがまろやかな味わいだ。普段ハーブティーなど飲まないという男性陣にも、自然と受け入れられている。
しっかり食べた後でも寝る前でも、合わないタイミングがない。
飲み会の後にもいいだろうな、と塔子は思っていた。
麻美は、塔子を待っていたかのようだった。塔子がひと息つくのを見て、すぐにテーブルに近づいてくる。彼女は汚れた瓶を手に持っていた。
「駐車場の植え込みに落ちてたの」
テーブルに直接置くのは抵抗があるようで、紙ナプキンを敷く。
塔子はその空き瓶を見つめた。中に飴状の黄色い液体がはりついている。それが何なのかは、ラベルを見れば明らかだった。
外にさらされて剥がれかけた部分もあるが、カフェ・ハニービーで見たハチミツの瓶に間違いない。
「大志くんの店のだよね」
「・・・うん。それも、うちで使ってたものなの」
塔子の声が淡々として聞こえたのか、麻美は疑惑と不安を一気に口にした。
「私だって、鈴森さんがやったなんて思ってないよ。理由がないじゃない?室田さんのこと、お店にも来てくれる人だって言ってたし」
麻美のあまり要領を得ない言葉を、塔子は注意深く聞いた。要所要所で質問も交えていくと、何となく全体像が見えてきた。
大志はハチミツを買いに来る客が室田、車にいたずらされた人物であることを、麻美に聞いて初めて知ったということになる。
そう考えると、以前から大志が室田に恨みを抱いていたとは考えにくい。
大志の口ぶりからは、室田とショップの間でトラブルがあった様子も感じられなかったという。
「そんなに気にすることないんじゃない?たまたま、いたずらした犯人がそのハチミツ使ったってだけで。大志くんなはずないと思うよ」
塔子の明るい声に、麻美は釈然としない顔で頷いた。
それとも、と思って塔子はハーブティーを一口飲んでから訊いてみた。
「もしかして大志くん、ハチミツ使われたことわかっちゃって荒れてる?」
「ううん。鈴森さんは全然知らない。ただ・・・ね」
麻美は声を落として、左右に目を配った。
「先輩が何人か、この瓶見ちゃって。けっこう噂になってるみたいなの」
「大志くんが犯人じゃないかって?」
「そう。もし上に知れたら蓋開けっ放しにしたこととか、経費のことで怒られそうだから、表向きは皆、黙ってるけど。でも、鈴森さんなら納品のとき厨房にも入れるだろうって・・・」
塔子は思わず大志の印象について考えていた。高級車に対するヤンキーの腹いせだというのは、確かに他人から見ればもっともらしく感じるのかもしれない。
それにしても、こじつけが過ぎると塔子は思った。
そもそも取引先のスタッフを安易に疑い、面白おかしく話のタネにするのも感心しない。
塔子は聞いているであろうリュウの気配を追って明後日の方向を見たが、やはり手ごたえはなかった。
聞くまでもなく、リュウは塔子と麻美の会話もイヴとの遭遇も、すべて目撃していた。
塔子は、リュウが手際よく夕食を並べていくのを眺めながら先にワインを飲んでいた。
今夜は野菜やキノコを優しく煮込んだミネストローネ。後からごはんを入れてリゾットにするようだ。メインは薄切り肉とチーズを何層にも重ねて揚げたミルフィーユのようなカツで、サクッと軽い噛みごたえの後をトロトロのチーズが追いかける。ワインが進まないわけがない。
塔子は週末なのをいいことに、飲みかけのボトルを空にした。
飲んでも、塔子はそれほど言動が変わらない。二日酔いになることもないし、平日の飲み会も苦にならない。
会社でもそれが知れているので、やたらと飲みに誘われやすいという、得なのか損なのかわからない体質だった。
ワインに食欲を刺激された塔子は、夢中で料理を味わっていた。そのせいで食事の間じゅう、褒め言葉以外はほとんど出なかった。
カタラーナとカフェインレスコーヒーで一服するころ、ようやく塔子はハチミツ瓶のことを思い出した。
見ていただろうと思いつつ一連の話を説明すると、リュウは恭しく頷いた。
「わたくしも拝見しておりました。確かに大志さまのお店にあったハチミツでございますね」
「そう。で、どう思う」
ここでは誰も聞いていないのだが、塔子はつい声を低くしていた。
「私は誰かが意図的に、大志くんのハチミツを使ったんじゃないかと思ってるんだけど」
リュウは少し沈んだ様子で、カトラリーを磨き始めた。そして、
「生きていらっしゃる皆さま方は、どなたも秘密をお持ちのようでございますね」
とだけ言った。
香苗は、イヴの洗濯物を整理していた。丁寧にたたんでクローゼットの引き出しに収めていく。一部はつぶれないように、そっとトートバッグに入れた。明日、職場に持たせる分だ。
それから香苗は、ドレッサーの前で丁寧にメイクを直した。ベッドに座って足をぶらつかせているイヴと鏡越しに目が合い、笑いかける。
イヴは、母親のドレッサーを使う彼女をじっと見ていた。ママのものはすっかり片づけられ、今は香苗の化粧品が並べられている。
重そうで、ドレッサーがかわいそうだ。そう思って前に化粧品やポーチを窓辺に移動させたときは、パパにたしなめられた。
女性の大切なものに触ってはいけないと言われ、それ以来イヴは香苗のものには手を出さない。
ママが残した小さな香水瓶だけは取っても叱られなかったので、イヴは眠れないときはそれを握って寝る。ローズやジャスミンのブーケのような香りがあると、ママがそばにいてくれるとわかるのだ。
怖い気持ちがほどけて、息も苦しくならない。
香苗は筆で唇を丁寧に染めた。ティントタイプの口紅は一日中落ちずにもつので、一度使うとやめられない。
絵の具が彼女の唇を、元の色とは全く別物に仕上げていく。
「イヴくん、今日はお仕事があるからね。私が迎えに行くまで、おじさんのところで待ってようね」
後ろから見る彼女の髪は冷たい艶を放っているのに、鏡の中から笑いかける顔は温かい色をしていた。
「あ、それから明日は検査の日だからね。朝さきに病院に行くよ」
よく動くボルドー色の唇を、イヴは首を傾けたまま眺めていた。それから、グレイスのところに行った。
香苗は、イヴが返事もせずに、部屋を出ていくのを呆然と見ていた。
まただ。
明日の予定を聞いていたのかもわからない。
これだけイヴに付き添っていても、香苗には到底理解できないことがたくさんある。
人の話をちゃんと聞かないから忘れ物をするのもしょっちゅうだし、職場に向かう途中、急にスタスタとどこかへ行こうとすることもあった。
リビングの出窓にせっかく飾ったオブジェを、すべて逆向きにする。
まったく脈絡のない状況で、同じことを延々と言い続ける。
そんなとき、つい苛立った声で話しかけてしまいそうになるのを、香苗はこらえる。
・・・この子にそんな顔を見せてはいけない。好かれなくては。
どんな状況でも、自分は彼の管理者でいなければならないのだ。
#小説
#連載小説
#執事
#家カフェ
#おうちごはん
#読書
#ミステリー
#推理小説
#執事
#幽霊
#グルメ小説
#ミステリー小説
#社会
#しごと
#社会の不条理
#独身女性
#生き方
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
