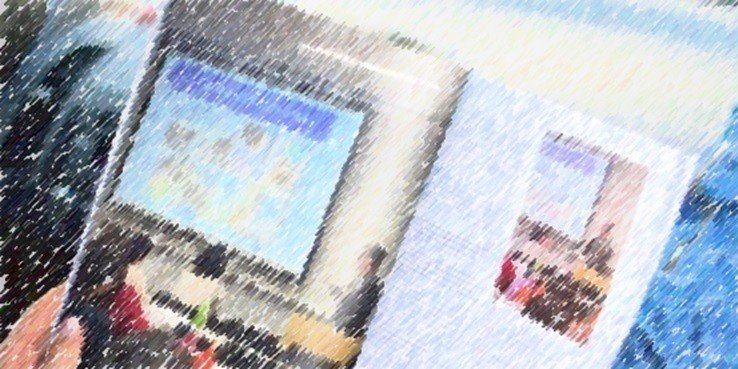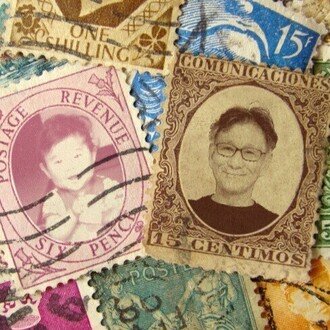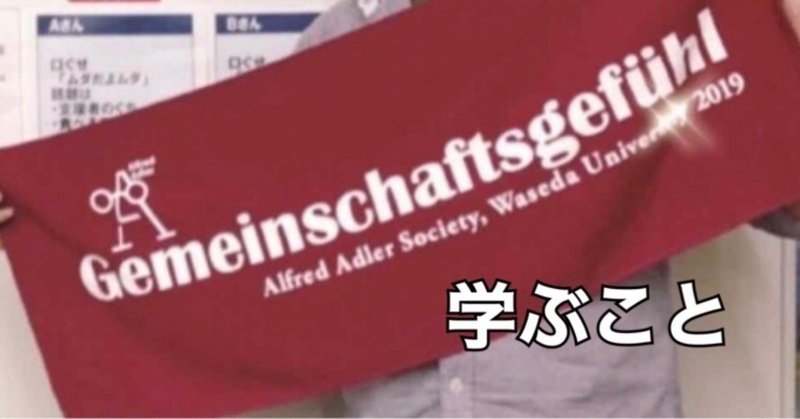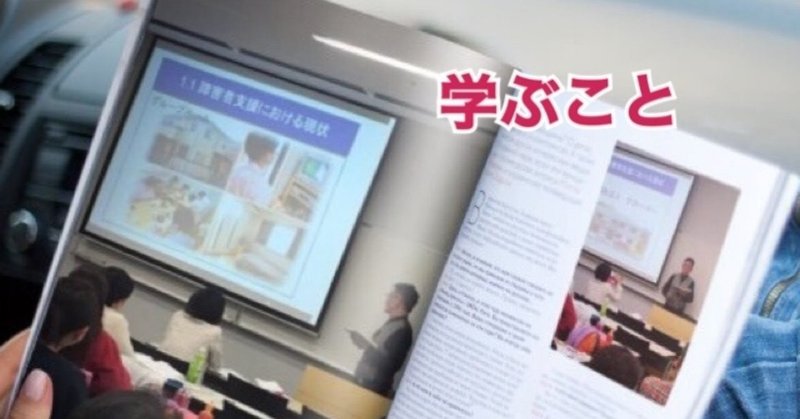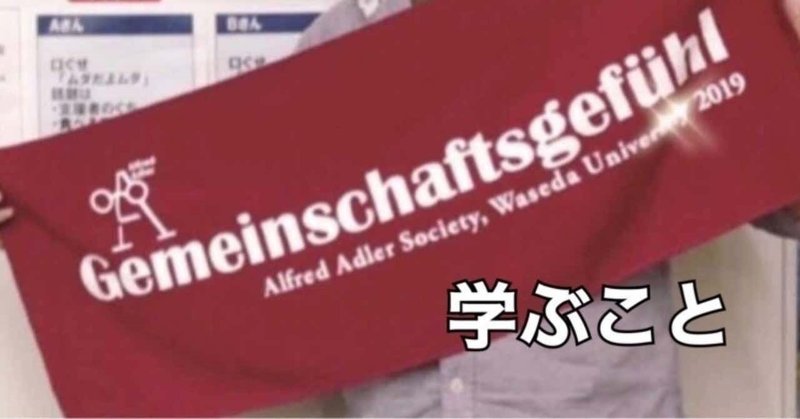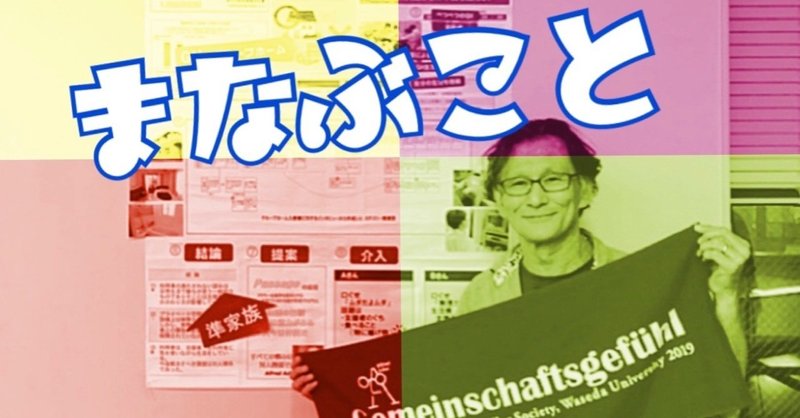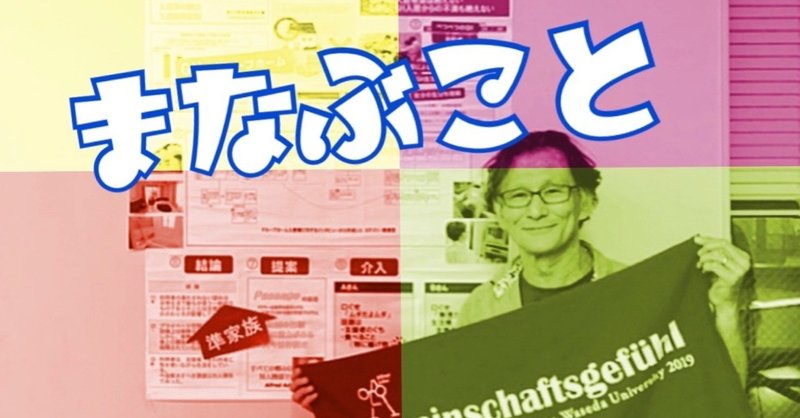#教える技術
マイクロフォーマットを使ってみよう(教える技術6回目より③)
01月09日(木)から早稲田大学のエクステンションセンター中野校で向後千春先生の「教える技術」が始まりました。(02月13日で終了)今回もそこで学んだことを障がいのある方への支援場面で活用すること、また支援者の働き方改革への活かし方を考えて書いていきます。
6回目(最終回)は、コースのデモンストレーションです。向後先生からコース設計についての解説がありました。今日は、その中からマイクロフォーマッ
折り紙の折り方を伝える(教える技術6回目より③)
01月09日(木)から早稲田大学のエクステンションセンター中野校で向後千春先生の「教える技術」が始まりました。(02月13日で終了)今回もそこで学んだことを障がいのある方への支援場面で活用すること、また支援者の働き方改革への活かし方を考えて書いていきます。
6回目(最終回)は、コースのデモンストレーションです。まず先生が、前回の講義についての質問に答えたあと、受講者が自分で作ったコースをグループ
メリルの第一原理を事例検討会に応用する(教える技術 6回目より②)
01月09日(木)から早稲田大学のエクステンションセンター中野校で向後千春先生の「教える技術」が始まりました。(02月13日で終了)今回もそこで学んだことを障がいのある方への支援場面で活用すること、また支援者の働き方改革への活かし方を考えて書いていきます。
6回目(最終回)は、コースのデモンストレーションでした。そこで学んだ「メリルの第一原理(First Principles of Instor
ヴィゴツキーの最近接領域を支援に取り入れる(教える技術より)
01月09日(木)から早稲田大学のエクステンションセンター中野校で向後千春先生の「教える技術」が始まりました。今回もそこで学んだことを障がいのある方への支援場面で活用すること、また支援者の働き方改革への活かし方を考えて書いていきます。
講座は02月13日で終了してしまいました。今回も障害福祉分野に転移できそうなことがたくさんありました。向後先生は、笑いながら、同じ講座を何回も受けるなんてと、おっ
福祉業界にARCSモデルをひろめる(教える技術 6回目より①)
01月09日(木)から早稲田大学のエクステンションセンター中野校で向後千春先生の「教える技術」が始まりました。今回もそこで学んだことを障がいのある方への支援場面で活用すること、また支援者の働き方改革への活かし方を考えて書いていきます。
6回目(最終回)は、コースのデモンストレーションです。まず先生が、前回の講義についての質問に答えたあと、受講者が自分で作ったコースをグループ内で発表しました。今日
強化としてのフィードバックとアドラー心理学の正の注目の組合せる(教える技術 5回目より④)
01月09日(木)から早稲田大学のエクステンションセンター中野校で向後千春先生の「教える技術」が始まりました。今回もそこで学んだことを障がいのある方への支援場面で活用すること、また支援者の働き方改革への活かし方を考えて書いていきます。
5回目は、コースの設計の続きです。コース設計においては、フィードバックを上手に取り入れることが大事です。そのフィードバックには、「強化としてのフィードバック(即時
コミュニケーションとしてのフィードバックを応用する(教える技術 5回目より③)
01月09日(木)から早稲田大学のエクステンションセンター中野校で向後千春先生の「教える技術」が始まりました。今回もそこで学んだことを障がいのある方への支援場面で活用すること、また支援者の働き方改革への活かし方を考えて書いていきます。
5回目は、コースの設計の続きです。コース設計においては、フィードバックを上手に取り入れることが大事です。そのフィードバックには、「強化としてのフィードバック(即時
理にかなった教え方をする (教える技術 5回目より②)
01月09日(木)から早稲田大学のエクステンションセンター中野校で向後千春先生の「教える技術」が始まりました。今回もそこで学んだことを障がいのある方への支援場面で活用すること、また支援者の働き方改革への活かし方を考えて書いていきます。
5回目は、コースの設計の続きです。先生が、前回の講義についての質問に答えたあと、コース設計についての説明がありました。昨日は、コース設計におけるリソース(資源)に
「1分間でわかる○○」(教える技術 5回目より①)
01月09日(木)から早稲田大学のエクステンションセンター中野校で向後千春先生の「教える技術」が始まりました。今回もそこで学んだことを障がいのある方への支援場面で活用すること、また支援者の働き方改革への活かし方を考えて書いていきます。
5回目は、コースの設計の続きです。まず先生が、前回の講義についての質問に答えたあと、コース設計についての説明がありました。その後、自分が教えたいコースの具体的な活
褒めて良いのか悪いのか…(教える技術 4回目より③)
01月09日(木)から早稲田大学のエクステンションセンター中野校で向後千春先生の「教える技術」が始まりました。今回もそこで学んだことを障がいのある方への支援場面で活用すること、また支援者の働き方改革への活かし方考えて書いていきます。
4回目からは、コースの設計です。コース設計に入る前に、前回の講義についての質問に対して、グループごとに質問会議を開きました。今回、取り上げた質問は、苦手意識を持つ分
「情熱」や「優しさ」の時代から「技術」の時代へ(教える技術 4回目より②)
01月09日(木)から早稲田大学のエクステンションセンター中野校で向後千春先生の「教える技術」が始まりました。今回もそこで学んだことを障がいのある方への支援場面で活用すること、また支援者の働き方改革への活かし方考えて書いていきます。
4回目からは、コースの設計です。自分が教えたいコースについて設計を始めました。
教える技術におけるコース設計と、私が仕事とする対人援助の支援(支える)には共通点が
教える技術と支援(支える技術)の共通点を探す(教える技術 4回目より①)
01月09日(木)から早稲田大学のエクステンションセンター中野校で向後千春先生の「教える技術」が始まりました。今回もそこで学んだことを障がいのある方への支援場面で活用すること、また支援者の働き方改革への活かし方考えて書いていきます。
4回目からは、コースの設計です。まず前回の講義についての質問に答えたあと、コース設計について説明がありました。その後、ワークで自分が教えたいコースについての設計を始
「~しちゃいけません」は効果がない(教える技術 3回目より④)
01月09日(木)から早稲田大学のエクステンションセンター中野校で向後千春先生の「教える技術」が始まりました。今回もそこで学んだことを障がいのある方への支援場面で活用すること、また支援者の働き方改革への活かし方考えて書いていきます。
3回目は、態度技能の教え方でした。講義では、前回の講義についての質問に答えたあと、OECDが報告した21世紀スキル、社会・情動的スキルについての説明がありました。そ