
【心とは何か】健康雑学
こんにちは(*^^*)整体×ヨガのプライベート隠れ家サロン【Refresh Labo R.I.T】整体師の伊藤です。
今回は「心とは何か?」という抽象的なテーマをロジカルな感じで紹介していきます!
ここ最近の【健康雑学記事】のまとめ的な内容になります。
何か参考にしていただけると嬉しいです(^^♪
この記事はこちらの本を参考にさせていただきました。ぜひおすすめの本です!
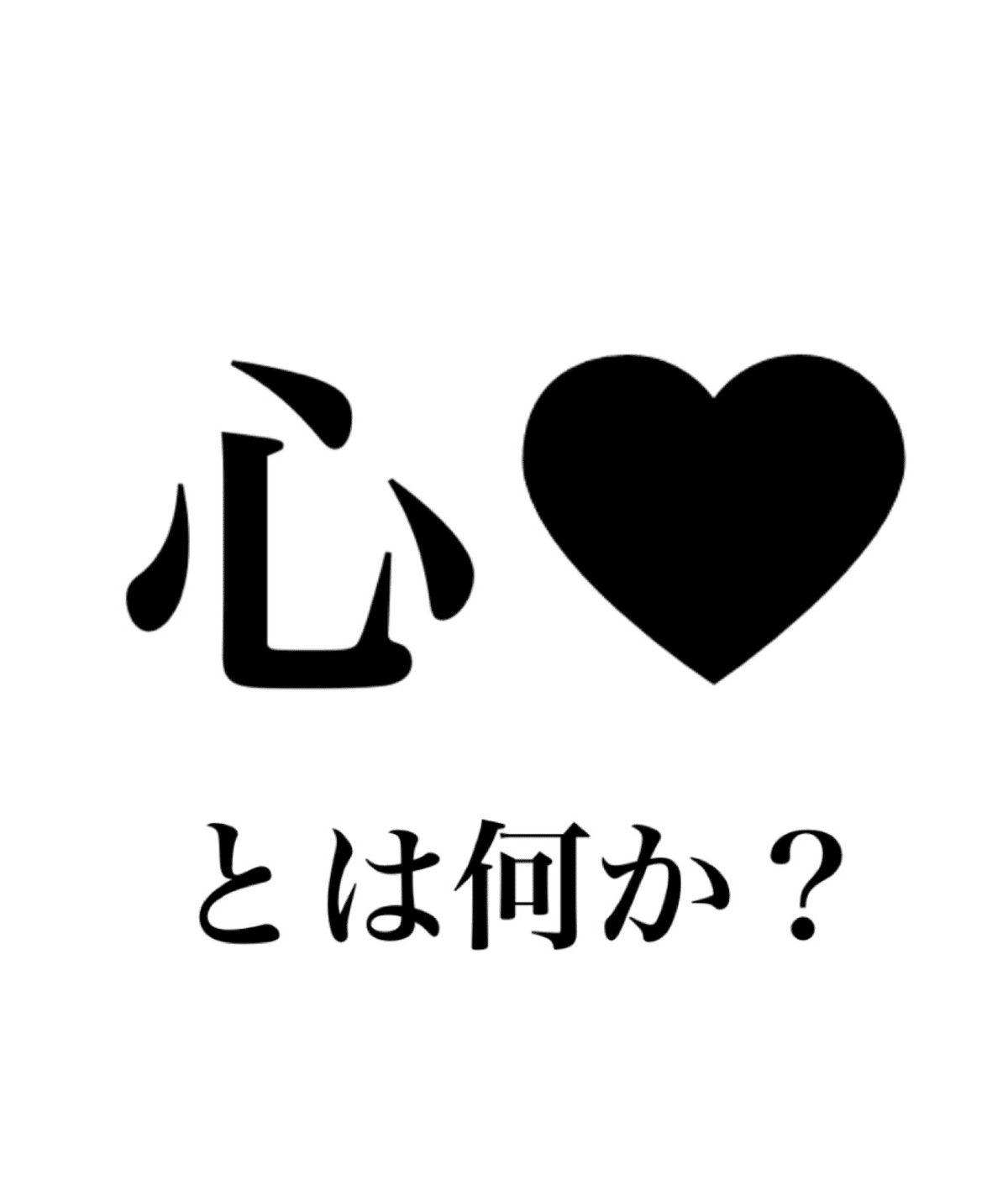
動物の本質とは?
「心」を考えていく前に、
そもそも「動物とは?」というところから考えていきます。
動物とは、読んで字のごとく「動く」「行動する」ことが本質としてあります。
各感覚器官によって、外界の情報をキャッチし
その情報に対して行動を起こし生存確率を上げています。
どの動物もこの「インプット」とそれに対する「アウトプット」を繰り返すことで生きています。
下等な動物、進化前の動物たちは
情報に対して、「定型的にプログラムされた応答」を持っており
たとえば
・「危険だ」と感じると”すくみ”行動をとる
・「餌だ」と認識すると口に入れる
ように、動物には元来シンプルな行動パターンが備わっています。
しかし、様々な環境の変化や、生存を続け個体数が増えていく過程で
進化した動物には「社会」が生まれていきます。
哺乳類に顕著ですが、”群れ”をつくり、その中で「リーダー」がいたり
集団で生活し子供を守ったり、
社会性が生まれたことで動物たちの生活環境は複雑になっていきます。
社会性が生まれ、求められることは”個の生存”だけではなく”集団の生存・繁栄”となります。
こうなると、「定型的にプログラムされた応答」だけでは
情報に対して柔軟な対応がとれません。
そこで、動物は「脳」を進化させることで
共感性や記憶といった情報処理の能力を向上させてきました。

ヒトの社会
動物の中でも「ヒト」は非常に複雑な社会形態を作り上げています。
このような高次な社会性をつくることができたのも脳の発達によるもので、
特に
■前頭前野
脳内でシュミレートする機能
■頭頂葉・前頭葉
他者に共感する能力
の著しい発達によると言われています。
脳が進化し、情報処理が発達したことで
様々な状況に応じて柔軟に対応し行動することが可能となり、
「インプット」に対する「アウトプット」の幅が非常に広がっていきました。
進化した脳の機能の中には「メタ認知」という機能があります。
これは「認知していることを認知する」という機能になります。
自分を客観視できる能力、といったところです。
こんな能力までついたもんだから、
ぼくらヒトは
「自分で認知し考えたうえで判断し、行動している」と思いがちです。
しかし、実際のところ脳の働きから分析した結果
「行動」と「認知」は並列的に同時に起こっており、
たとえ「認知」ができていなかったとしても「行動」は起こる、ということが分かっています。
下等な動物時代に備わっていた「定型的にプログラムされた応答」は
消えてしまったわけではなく、
むしろそれをベースに「行動」は起こされており、
情報処理能力が向上したことで、
情報の細かなカテゴリ・ジャンル分けが可能となり
「定型的なプログラム」もそれに応じて多様になっていったわけです。
「細かく分類された情報」とそれに対する「定型的な応答(行動)」
これらは同時に「認知」がなされていきます。
「認知」の役割は「情動」を発動させ自律神経や内分泌系の働きを活性化すること、情動の発動に伴って「記憶」をすることで
同じ状況を再現する、または避けるために学習していくことです。
また、「認知」によって行動に対する”後付けの理由”もつくられていきます。
ヒトが「自分で考え〇〇という理由で行動した」というとき、その理由はほとんどが後付けであって、
実際は情動によって記憶され「定型的にプログラムされた応答」をしている場合が多いといいます。
ちょっとショックですね。。自分の意志で考えているつもりでも、ほとんどは情動に突き動かされているんです。。

行動のほとんどは無意識
前述しましたが
動物の中でもヒトは特に「前頭前野」が発達しており
「認知」の能力が非常に高い動物です。
しかし、行動に関しては結局多くの場合は
「定型的にプログラムされた応答」をしているだけであり
すべて「無意識」だといえます。
「無意識な行動」を起こしているのは脳の深部で原始的な部分
「大脳辺縁系」などが関わっています。
また、行動だけでなく”感情””気分”といった、より「心」に近い概念も
「無意識」に作られており「無意識」に行動で表現(表情やしぐさなど)がされています。
人間も”思っているよりも動物”なんだと感じますね。

「心」はどう生まれる?
動物のこと、ヒトのことを振り返れたところで「心」について考えていきます。
心はどのように生まれるのかというと、
①感覚系から情報をキャッチします。
眼や耳・鼻・口・手足・皮膚…全身の色々な器官から常に情報をキャッチしています。
特に「眼」や「鼻」は情報が脳に届くスピードが速いため
「第一印象」や「香り」の持つ印象付けの力は強いと言われています。
②前頭前野と偏桃体で並列に処理されていく
前頭前野では「認知」の処理を、
偏桃体では「定型的な応答」としての自律神経や内分泌系など内的状態の変化を促していきます。
それぞれが同時に、並列処理でなされていきますが、
これらの処理は互いが互いに影響を及ぼしあい、「認知」による情動の変化によって、上書きで修飾がなされていきます。
※「感覚系からの情報」が”報酬”なのか”恐怖”なのか、などのジャンルによって内的状態や情報伝達物質に変化が現れます。
この”ジャンル分け”は生活環境や学習によって書き換え可能なプログラムであり、住んでいる地域や教育などの影響によって反応に個人差が生まれるとされます

ヒトの複雑な心
そもそも「心」という言葉自体も色々な意味を含んでおり、複雑な概念ですが
動物全体で考えたとしてもヒトの「心」は非常に複雑だとされています。
その理由の一つが、突出した「共感性・社会性」です。
ヒトは、他者の”幸不幸”などの感情や行動を脳内でシュミレートし疑似体験することができます。
これは一部の動物にも備わっていると考えられていますが、
コミュニケーションの能力と、
それを伝える技術・作り上げたテクノロジーの発達によって
他の動物にはない次元で情動の共有がなされ
そういったベースの上に社会ができているため、
動物の中でも群を抜いて共感性が高い動物だといえます。
ここまで紹介してきた、
情報の処理と、それに伴う定型的な応答(行動)・認知・情動の発動
をまとめて「心」の表出だと考えると
”ヒトの心”は共感性をより強く纏ったことで、他の動物よりも
”より高次な精神機能”だといえます。

心の進化
ここまで長々紹介してきたことが「まとめて心」ということですが、
その源泉となるものを、ひとつだけ挙げるとすれば、
それは「情動」になります。
入ってきた情報を「どう処理するか?」
それは「報酬」なのか「恐怖」なのか・・・
学習や体験の記憶などによって無意識化で処理がされていくのですが、
この判断プログラムは書き換え可能なものであり、
現代の変化に富んだ社会では、「報酬」「恐怖」などの対象もどんどん変化をしてきています。
現代社会では「食べ物を手に入れる」という報酬は希少価値が下がりつつあります。
また、「猛獣に襲われる」という恐怖も少なくなってきています。
代わりに「社会的地位を手に入れる」「SNSでいいねを沢山もらう」などの報酬や、「仲間外れにされる」「生きる意味を見失う」といった恐怖など
昔と今では情動のトリガーが変化してきています。
おおまかにまとめると、
現代人の情動を動かすものは「他者からの承認」へと変化してきています。
このように、その時々の社会の変化によって「心」の在り方は常に変わっていき、そのたびに学習し進化します。
そして、
進化した「心」によってまた社会は高次のものへと作り変えられていき、「心」と「社会」は相互に作用しあいながら進化していくことでしょう!(個人的意見)

まとめ
とてもややこしい話でした。けど、こうして考えることはとても楽しい!
マニアックだし、僕の個人的見解も多々含まれており
解釈が間違っていたり、言葉足らずな文章でしたが
何か参考にしていただけると嬉しいです(^^♪
今回のお話はこちらの本を参考にさせていただきました!ぜひおすすめ!
というわけで、この記事に「スキ」をいただけると
その承認は僕にとって報酬として認知されるので
とても喜び、次の記事も頑張ってかけます!
僕の喜びに共感するあなたもとても嬉しい気持ちになると思います!(笑)
よろしくお願いいたします!
最後まで御覧いただきありがとうございました!

よろしければサポートお願いいたします。いただいたサポートは、記事にするためのインプット活動費に充てさせていただきます!
