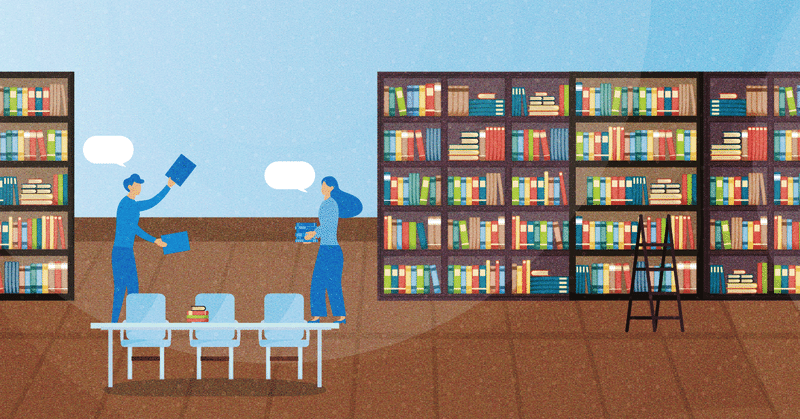
ショートショート 29 図書館のお姉さん
無意識にあげたかかとをゆっくりとおろす。机の上にある用紙は、もう隅々まで何度も読んだというのに、まだ時間がこない。
たった一枚のカードを作るためだけにどんだけ時間かかってんだよ、という言葉は頭の中に置いておく。
もしかしたらめちゃくちゃすごいカードなのかもしれない、あのお父さんが一度だけ見せてくれたエジプトの剣士みたいな男が横を向いている、カードというにはずしりと重い銀色のやつみたいなのかもしれない。
なんとなく、ほんとうになんとなく、未来さんを見やる。未来さんは、脚立の一番上にまたがって座り、本棚の一番上で作業をしていた。片手には七冊くらいの本の山を抱えて、もう片方の手で、その山のてっぺんの本を取り、戻していく姿は凛々しい。凛々しいってこういう意味なのか。聞かれても多分、ちゃんと説明はできないだろうけど、分かった。
でも、同時にひやひやもした。本を落としはしないだろうか。それを取ろうとして、脚立がひっくり返ってしまわないだろうか。気が気でなくて、用紙になんて書いてあったのかもう忘れてしまう。
「おーい」と呼ぶ声にぼくと未来さんの両方が振り向く。彼女は自分を呼んだのではないと気がつくと、また作業に戻った。
ぼくはもっと未来さんを見ていたかったけど、仕方なく声に従って、カウンターまで向かう。少し小走りで行こうとすると、未来さんにしーっ! とささやくような声でぼくに注意する。注意されてうれしいのなんて初めてだ。
「あら、あなたが走らずにここに来るのなんて珍しい」
「珍しいって、俺ここに来るの初めてですよ」
「そんなことないわよー! 小さい頃、あんたここで走り回ったり、本を読んでいる他の子どもたちにちょっかいかけたりして、本当大変だったんだから」
「そんな小さなときのこと、覚えてないっすよ。のーかんのーかん」
本当に覚えてはいなかったけれど、我ながら簡単に想像することができた。
ぼくは本を読むのが嫌いなのだ。読んでいると全然分からなくてぼーっとしてくるし、身体を動かせないからうずうずしてしまう。さっきも机の上で、図書館についての説明を読んでいて頭がくらくらした。なんとか足をぶらぶらさせたり、かかとをついては離したりして、なんとか最後まで読み切ったけれど、今ここでクイズを出されても一問も答えられない自信がある。
ぼくは子どもの頃の失敗を話されるのも、本当にクイズを出されるのも嫌だったので、
「それより……」と手を差しだした。
「本当に小さなときだけのことだったら、いいけどね」
ぽん、と少し強めに手の中に置かれたのは名札。それも名刺みたいなカードをを入れて首からぶら下げるタイプのやつ。たくみ、とひらがなで書かれてあった。
馬鹿にするな。漢字くらいなら読めるわい! しかも自分のだぞ! と言おうとしたのを察したのか、
「それと、これ」ともう一枚上にカードを置かれた。今度は、普通のカードだ。残念ながら、銀色でもないし重くもない。地味なえんじ色に白の文字で、ここの図書館の名前とその横に自分の名前が今度は漢字で書かれてあった。
「お助け隊のメンバーとはいえ、君もここを利用するお客さんだからね。一応渡しとくよ」
「うす」
「返事が違うでしょ」
「あっ、はい」
「よろしい」
そう言うとさっさとカウンターの奥に行ってしまう。
ぼくはひとつあくびをした。したあとで、もしかしたら未来さんに見られてはいないかと一瞬振り返る。けどそこにはもう未来さんはいなかった。
「おーいたくみくん。もうすぐ朝礼、はじまるよー」
「あっ、はーい!」
いつの間にか未来さんはカウンターの奥にいて、ぼくのことを呼んでいた。
カウンターの奥には事務所があって、そこでは毎朝朝礼が行われるらしい。家の事情や、距離がある人は、昼から来るので朝礼がない。
ぼくはというと、歩いて十分くらいのところに住んでいるし、家に事情なんてなく、むしろ用事がない日も早起きを強制させるような家だったので、これにこれから毎回参加しないといけない。そう思うと気が重かった。
ぼくが入ったのを確認すると、館長はすぐに話し始めた。後ろの方に並んだのに、
「今日から近隣の小中学校が夏休みに入るので、それに合わせて図書館の来客も増えることが予想されます。毎年のことではありますが、今年も中高生にお助け隊をお願いすることになりました。……では前に出て自己紹介をしてください。まずはたくみくんから」とみんなの前に出されてしまった。
「あっ、たくみです。よろしくお願いし、ます」
パチパチという拍手の中には、なんでたくみくんが? といった意味の言葉がちらほら聞こえた。ほかには、懐かしいとか、あのたくみくんが敬語? 成長したねぇとか、本当に大丈夫? とか、とにかく聞きたくない言葉がたくさん聞こえた。
ぼくはこの人たちをほとんど知らないのに、この人たちはぼくのことを知っているんだ。そう思うと、少し怖かった。
「未来ちゃん……は小学四年生くらいから毎年手伝ってくれているから、もう皆さん知ってくれていると思うけど……」
館長が言い終わる前に、未来さんは一歩足を踏み出すのが見えた。
「今年もこうしてこの図書館で、お助け隊ではありますが、図書館の人として働けてうれしいです。よろしくお願いします」
未来さんが頭を下げると、後ろにやっていた髪が肩からずるっと落ちる。顔を上げながらそれを直す姿に思わず見とれてしまった。
「たくみくんのお世話は、未来ちゃんにお願いします。今年は余計な仕事が多いけど、頑張ってね」
未来さんのスピーチに対しての拍手と、ぼくを笑う声が混ざる。
お世話って何だよ、もう子どもじゃねぇよ。
心の中でそう言いながらも、これから夏休みの間、未来さんと一緒にいられる。そう思うと、そんな些細なことなんてどうでも良くなって、
「うす! よろしくお願いします!」と思いきり頭を下げた。未来さんをまねたつもりだったけど、
「図書館で大声を出さないの」と軽く館長に頭をはたかれる。
また笑い声が起きた。なんだか恥ずかしかったけど、未来さんも口に手を当てて笑っているのが見えて。
だから、まぁいっかがんばろって思えた。
一目惚れだった。それもはじめての一目惚れ。だから、それが一目惚れだと分かるのに時間がかかったし、分かってからはそこに未来さんがいるわけでもないのになんだかどこからか見透かされているような気がして恥ずかしかった。
でも、それと同じくらい。いや、それ以上に、好きだとしか言いようのな胸の高鳴り。体を動かさずにはいられなかった。
もう、スキップしちゃうもんね。
それは小さい頃にした未知のおでかけよりも、親せきがたくさん集まるバーベキューよりも、学校の体育でする球技大会よりも、なんだったら遊園地に行くとか、欲しいゲームを買ってもらえるときよりもわくわくした。それらを簡単に超えていく感情は、読書が嫌いっていう事実をこれまた簡単にねじまげることができた。
あれは、ほんの二ヶ月前。急遽始まった朝読書の時間のために、本を持ってこないといけないことになった。漫画は禁止、絵が付いたものは禁止だったので、ぼくの家にはなかった。いや、両親の部屋にはあったのかもしれないけど、勝手に部屋に入るのは怒られるのは怖かったし、相談して難しい本を読まれるのも嫌だった。
つまり僕の部屋や共同の部屋には読む本がなかった。
だから本屋に行ったけど、どれを買ったらいいか分からなくて、気づいたら結局、欲しかった漫画を買ってた。
何も読まないことも考えたけど、そうすると呼び出されるし、ひどいければ罰で、貴重な夏休みの大半をボランティアに費やすことになる。それで簡単な本でも教えてもらおうかと図書館に立ち寄ったときだった。
未来さんはいた。
彼女は、外のウッドデッキのテラスのところで本を読んでいた。青い色のカバーをつけていて何を読んでいるかは分からなかったけど、それよりも気になったのは、彼女が泣いていたことだった。
本なんか読んで何が楽しいんだよって文句を言いながらここまで来ていた自分が恥ずかしくなった。そして同時に、いつもの自分なら、本読んで泣くとかキモとか思うはずなのにすぐに恥ずかしくなったのに驚いた。どうしてだろうかと思っていると、目が合った。彼女は涙を拭きもせずに微笑んだ。
多分、それが恋に落ちたって瞬間だと思う。
けどぼくはそれが何かわからず、数日謎の感情に悩まされた。結局、悩むなんて自分らしくない! となるべく図書館の外に通いつめ、そうしてお助け隊の存在と、彼女がそれに参加するらしいということと、彼女の名前がみらいではなくみくと呼ぶことと、自分より年齢が一つしか上じゃなくて自分が通っているのとは別の中学校の人だと知った。
急いで、お助け隊に参加しようとしたぼくだったけど、そのときにはもう締め切りは終わってたから、本当に落ち込んだ。図書館に入って話しかけようかとも思ったけど、本を読むのが嫌いなぼくは本がある空間も嫌いで、学校でも図書室の近くを通るときは息を止めるようにしてたくらいだったから、万事休すかと本気で思った。
しばらく元気がないぼくを心配した両親が話を聞いてくれ、お助け隊に入りたかったけど、締め切りをすぎてしまっていたと正直に話した。
もちろん、気になる女の子がいるなんていうのは伏せて。
そのときの両親の反応というと、ほんとにぽかんって感じだった。シーン……じゃなくてぽかん。目が覚めたみたいにハッとしたかと思えば、すぐに大喜び。
「あぁ、ようやくうちの子にも社会性が生まれたのね」
「ほうら、だから言ったろ。そのときが来ればたくみもちゃんとするって」
その日の晩は焼き肉に連れてってもらえたけど、なんだか申し訳ない気がして、美味しく食べられなかった。
親の計らいで、どうにか無理やり入れてもらえることになったけど、あんなに喜んでいた両親も、夏休みが近づくと、ちゃんとするのよとかじっとすることとか、迷惑はかけないようにとか口うるさくなってきて、申し訳ないなんて気持ちはすぐに消えた。
ちなみに昨日の夕ご飯はかつ丼。カツを入れるのよ! となぜか両親のほうが張り切っていたけど、いったい何に勝つんだか。
お助け隊初日、勝たないといけない壁は案外近くに見つけた。
図書館。
昨日の夜、ようやく会えるということでわくわくとドキドキでねむれなかったぼくは予定より早く図書館に着いた。
図書館についてようやく、図書館のお助け隊に入ったということは、図書館の中に入らないといけないことに気がついたぼくはまじでどうしようかと思った。気がついてからずっと息を止めていて、いよいよ死にそうになったところで、
「こんな早く誰だろうかと思ったら、たくみくんか!」びっくりした! とでも言いそうだなと思ったら、
「びっくりした!」と言ったから、驚いた。不審者かと思ったよ、なんて言葉つきだったけど。
「はよっす」
「おはようございます、ね。中学生だけど今日から一緒に働く仲間なんだから、挨拶はちゃんとする」
「おはようございます」
「よろしい」
館長は鍵を開けると中に入って待っているようにと言った。言われたとおり机に座って待っていると、電気がつき、オルゴールが流れ始める。ひとつひとつのパソコンをつけているのをなんとなく見ていると、
「そうだ。これ、見といて」と図書館の使用案内の紙を渡された。そうして、他の従業員も集まりだし、もちろん未来さんも来た。未来さんは誰よりも早く休憩室から出てきて、まだ開始時間じゃないのに作業をはじめた。館長さんがまだ大丈夫だよって言ったけど、とくに強く止める様子もない。
朝礼の最後に軽く体操をして作業開始。ぼくは未来さんと一緒に返ってきた本を戻す仕事を任された。
はじめに説明を聞く。僕は体を前のめりにしながら真面目に説明を聞いているように意識した。
つまり、本のタイトルが書かれた細いところの下の方に、アルファベットと数字とひらがなの50音が書かれているから、そこに戻す。それだけのことだ。すでにアルファベット順に本を分けておいてもらえていたので、作業は簡単だった。
本を手に持っていいのは三冊までだと言われたけど、未来さんはやっぱり七冊くらい持っていた。ぼくも負けじと八冊くらい持とうとしたけど、五冊目くらいからふらふらしてきて、あっ、と思ったときにはバラバラバラ……。
音を聞いてやってきた未来さん。
怒られる、ととっさに体に力が入ったけど、
「本は大事にね」とか怒ったのはそれくらいで、
「本当はダメなんだけど、本はね。自分側に倒れてくるように持つといいよ。それを胸で支えるの」
「こう、ですか?」
「そう! いいねぇー」褒められてうれしかったけど、胸、と言われてどきどきして、顔が見れなかった。できることなら顔が隠れるくらい、本を積んで持ちたかったけど、これ以上迷惑をかけるわけにはいかないし、館長にバレたら辞めさせられてしまう。
未来さんに教えられた方法を使うと、作業はスムーズに進んだ。さすがに脚立を使わないといけないところは未来さんみたいに7冊は無理で、というか三冊でも気が気じゃなくて、本当に未来さんはすごいなって思った。てか、すごすぎる。ぼくにはあんなの無理だ……。未来さんに見とれてたら、一冊でも落としそうになる。
それではいけないと、なるべく未来さんを見ていたいのを抑えて、ほんの戻し作業を続けた。
おかげで、昼ご飯までには終わることができた。
楽な仕事かと思ったけど、思ったより数は多いし、本をたくさん持ったり、腕を上げておかないといけないことが多くて、もう腕が痛い。例えるなら運動会の日の夜くらいは両腕に達成感があった。お昼後にもあるかと思うと、ゾッとしたけど、
「疲れた?」と未来さんに声をかけられて、
「全然ですよ! まだまだいけます」と言うと、疲れは簡単にどこかにいってしまった。
「じゃあ、お昼からもよろしくね。多分違う仕事だと思うけど、頑張ろうね」未来さんが微笑む。ぼくはどきりとして、返事をするのが遅れた。
「……なんでそんなところで突っ立ってんの?」
館長に声をかけられてようやく、今の今までもうお昼に行ってその場にいない未来さんに見惚れていたことと、お昼に誘おうと思っていたことを同時に思い出した。
「初日だけど、大丈夫? たくみくんのことだから、たくさん迷惑かけたんじゃない?」
疲れたんなら、今日はお昼であがってもいいんだよ、という館長の言葉に、「全然ですよ! まだまだいけます」と返したけれど、なぜかどっかに行っていた疲れが、どっと帰ってきた。
お昼ご飯を食べすぎてしまった。出来れば未来さんと分けようと思って、お母さんに多めに作ってもらっていたのだ。さすがにもう一人分作ってもらうのは申し訳なかったし、自分が作っていないものを自信満々にまるまる一人分渡すのはちがうかなと思って、渡さなかった。
それでも、食べすぎたことには変わりはないのだけど。
ぼくはもしかしたら会えるかもと期待して、図書館のテラス席で食べた。でも、来たのは未来さん、じゃなくて館長で、
「今日はお客さんが少ないからいいけど、もう少しいるときはテラス席で食べるのはやめてね」
「あれ、ここ飲食禁止でしたっけ」
「ここはOKだけど、さすがに従業員が食べているのを見られるのはよくないでしょ?」
「え、でも前未来さんがここで食べてるのを見ましたけど……」
「あのときはお客さんも少なかったし、それにお助け隊に入ってた時期じゃなかったからね。って、きみ、やけにくわしいね」
やべ、しまった。なんでそのことを知ってるんだという疑いの目を向けられる。ぼくはそらしたかったけど、ここでそうしてしまったらやましいことをしましたと認めてしまうようなものだ。しっかり見返して、
「お助け隊に参加しようと思ったから、何度かこの図書館の前まで来てたんです。そのときに見かけて」
我ながらいい嘘をとっさにつけたものだ。ぼくは念押しに、ですけど何か? というニュアンスを込めて、軽く首を傾けた。
「なんで前? 中に入ってくればよかったのに」
しまった。こっちにはとっさの嘘がつけなかった。それどころか、本が苦手だからというのがすっと喉から出てきそうになってしまう。未来さんに好きと言うことを考えたら、息ができなくなるくらいなのに、本が嫌いと言うのは本当に簡単だ。
それは……とぼくが言い淀んでいると、
「まぁ、それはいいとして。たくみくん。本をぎちぎちに入れたでしょ? あれは一冊分空白を残しておかないと、本がなかなか抜けなくなって、痛む理由になっちゃうから、次からやめてね。あと、番号違いとかジャンル間違いがあったら、ちゃんと直しとくこと」
「え、ぼくそんなことしてました? すみません」
「うん。全部直すの大変だったよ。まぁあとに言った方はできてなかった、じゃなくて、もし見つけたらって話だけどね」
さぁて、と館長は3つあるうちの残りの一席の上に置いていたお弁当を広げた。
もしかしたら、ぼくの直し作業のせいで、お昼が遅くなってしまったのかも、と思ってたら。
「あっ、別に君の直し作業だけで、ここまで遅くなったわけじゃないよ。ちょっと後ろで話してたら遅くなっちゃっただけ」
館長はそこまで言って、あ、と何か気づいたような顔をした。
「何の話してたと思う?」
気づいた顔が、含みのあるにやけた表情になったのを見て、すぐに気づいた。
「ぼくのことですよね」
え、なんでわかったの? と言わんばかりの驚いた顔をした館長。
「え、なんでわかったの?」
「顔に出てますよ……それで、ぼくの何について話してたんですか」
「え、それ聞いちゃう? 言っていいのー?」
また館長がにやけた表情をぼくに向けた。
「ぼくの悪口でしょう? さっきみたいに仕事ができてないとか、そんなところでしょう?」
館長の顔を見る。相変わらずのにやけ顔のままだ。
「残念! むしろ逆だよ。ちゃんと仕事してるなーって。ここだけの話、君をお助け隊に入れてほしいって君の親から頼まれたとき、驚いたんだから。……だって君、本が好きじゃないでしょう?」
胸がどきりとした。
「おっ、なんで知ってるのかって顔だねぇ。簡単なことさ。図書館の人はね。見ただけで、その人が本が好きか嫌いか分かるんだよ」
まさか! もしそれが本当だとしたら、未来さんにもバレてるかもしれない!
どうしようと、明らかに動揺したぼくをまたにやけた表情で見る館長。
「大丈夫、未来ちゃんには言わないでおくから」
「そ、それもバレてるんですか」
図書館の人はエスパーか! いや、ぼくが顔に出やすいだけか? それじゃあもう、未来さんにもバレてるかもしれないじゃないか!
そう焦ったのもつかの間、
「お、あたりか。やりぃ」
「カマかけたんですか」
「うん。他の大人の話なんて全く聞いてないような顔してるのに、未来ちゃんに対してだけは、身体を前のめりにして、メモまで取りながら聞いてるからね。他の従業員はただ年が近いから話しやすいだけじゃないかって言ってたけど、私は恋だとすぐに分かったね」
あの子は、私のこと恋愛脳とか言ってたけどこれでぎゃふんと言わせてあげられるわね、となぜか自信満々な館長。
「そんなに、ぼく、態度に出てましたか」
「うん、ビンビン」
顔から火が出る、という言葉があるけど、あれは嘘だ。炎だ。それも、赤なんかじゃない。なんだったら青い炎。それがぼくの全身を包んでいるかと思うほど、熱くて、よくこの木のテラス席は耐えられたものだ。
あぁ、いや本当に炎が出ているわけじゃないんだけど。
「でもね、大丈夫だよ」
「え?」
「あの子、鈍感だから。……まぁ頑張りなよ、少年」いつの間にか館長はご飯を食べ終えていて、ゴミを持って、図書館の中に入っていった。
ぼくは残り少ない休憩時間を消火活動に専念することになった。
昼からの仕事はカウンター業務だった。今までカウンター業務をしていた人が子どもが熱を出したとかで帰らなくてはいけなくなったからだった。さすがにぼく一人に任せるわけにはいかないので、今日は未来さんのとなりでいろいろ見て覚えるようにと言われた。
未来さんがするひとつひとつの説明をメモに書いていく。なるべく前のめりにならないように意識したら、なぜか反り返っていて、
「どうしたの? なんか天井についてる?」と心配されてしまった。
お客さんはほとんど来なくて、ただぼーっとカウンターに座っているだけの作業は退屈だった。未来さんは色画用紙を切って、そこにマジックで何やらかきこんだり、ときどきパソコンを叩いたりしていたけど、それも終わったようでひとつあくびをして見せた。
「あ……もしかして、今の見てた?」
こくんと頷くと、未来さんは両手で顔を隠した。きゃーっと聞こえてきそうだけど、さすが図書館の人、そこは小さくうぅーとうめくことで抑えた。
「館長さんには秘密ね。実は私昨日寝てなくて」
「ぼくもです!」つい声が出てしまって、離れたところにいる館長が咳払いをした。
しーっ、と口元に立てた人差し指を当てる未来さん。あくびといい、このポーズといい、もしカメラがあったら激写しているだろう。少なくとも今のぼくのこの鼓動の数くらいは。
(これでお話しましょう)
未来さんは余った色画用紙の一部をぼくに手渡した。書くことが決まらなくて、
(はい)と書いて渡す。
(字、きれいだね)
小学生の頃、二年だけやってすぐに辞めてしまった習字教室グッド。無理やり、とりあえず二年と言ってやらせてくれた母さん、本当にありがとう!
(未来さんもきれいです)
書いて渡してすぐに、しまった! と思った。今更取り返すわけにもいかない! ぼくはちらりと未来さんを見る。未来さんは無表情で返事を書いていた。
あれ? もしかして、ぼくが未来さんを好きなこと、バレてない? 図書館の人はエスパーじゃない? あぁいや未来さんはまだ正式には図書館の人じゃないからか。
字です! 字のことです! いや、もちろん未来さんは綺麗ですけど! という心の声はもちろん表には出ない。
(こんなこと、聞いていいか分からないんだけど、いい?)
ぼくはうなずく。鼓動はもうやばい。しつこいパパラッチのシャッター音くらいある。
(男の子って、女の子に追いかけられるのって、嫌なものかな?)
シャッター音が止んだ。彼女を見る。彼女は恥ずかしそうに手を膝の上で何度も何度もさすっている。目が合っては、そらす。その表情と、質問内容でんぼくは理解した。
あ、未来さんって、好きな人いるんだ……。
(うれしいと思いますよ)
好きな人になら、と付け足そうとして、やめた。
(よかったー!! ありがとう! よかったら、仕事終わりに相談に乗ってほしいんだけど!)
未来さんの書く文字は輝いていた。とめはねはらいなんて関係ない! っていうか、そんなこと考えている暇がないくらいに喜んでいるのが伝わってくる。ような走り書き、それでも文字単体は、女の子らしい丸字で、もうなんか、うん……輝いていた。
そのあとの仕事のことは正直、覚えてない。
「はじめての仕事、どうだった?」仕事終わり、着替え室から出たところを館長につかまった。
「大変でした」
「そうだろう。本屋さんとか図書館って空いた時間に本読んでそうとか、楽そうとか言われがちだけど、大変なんだよね。それが分かってくれただけでもうれしいよ」
「そうですか」帰ろうと一歩足を踏み出すと、肩を掴まれる。
「ちょい待ち。君、なんかあったでしょ」
「どうしてわかるんですか。あれですか、例のエスパーですか?」
「エスパー? なにそれ。誰でもわかるよ。それは仕事が疲れたーって顔じゃない。なんかこの先生きていく希望を失ったような顔だよ。なんていうか、疲れたー! 早く家買ってビール飲んで寝たい! みたいな感じじゃなくて、明日からどうしようって思ってるみたいな顔」
「はは、そんなひどいですか」
「うん、ひどい。ひどすぎるよ……よし、君も行こう!」館長はぼくの肩に手を回し、ささやく。
「行くって、どこにですか」
そういいつつも、ぼくはこのまま家に帰りたくはなかった。けれど今日は仕事初日で疲れただろうからと、仕事終わりの相談をなしにしてくれた未来さんに申し訳なかった。
あ、だめだ。
「ちょっと、少年! どうした!」
よし分かった、君の好きなものを食べさせてやろう! 寿司か、肉か? それともなんだ? アイスか? コンビニのでいいか? 高いのでもいいぞ、私は大人だからな。
館長が焦ってテキトー言っているのを見ると、ぼくはおかしくて吹き出してしまった。
「まったく君は、泣いたり笑ったり忙しいやつだな」まぁ、それが青春ってやつか。と館長はつぶやく。
館長さんは両親に連絡をしてくれた。電話の向こうで、二人が喜んでいるのが簡単に想像できた。
帰り道、ぼくは聞いた。
「そういえば、本が好きじゃない人が分かるって本当ですか?」
「え? あぁ、いや、あれは嘘だよ。単純に君の両親から、うちの子は本を読むのが苦手で、だからなんでやりたいって言ったのか分からないんですけど、でもやりたいって言いだしたのなんて初めてですから、ぜひお願いしますって言われたからだよ」
ぼくは両親に少しむかついた。かつを入れるとか言ってかつ丼をふるまったくせに、あやうく敗北しかける敵じゃないか。あぁ、まぁいや敗北はしたんだけど。
「それで、君はやめるの? お助け隊」
ぼくは言われてからしばらく悩んだ。まだこっちの好意がバレてフラれたわけじゃないし、ここでやめたら両親に申し訳ない。どうせ夏休みも暇だ。それにこの仕事終わりの疲れは悪くない。
「続けます」と言ったのは、焼き肉後だった。
「こんな毎日、おごるわけじゃないからね。まぁ、最終日くらいはやってあげてもいいけど……。夏休みの真ん中には棚卸っていうたーいへんな仕事も待ってるんだから、覚悟しときなよ、少年!」
ぼくは結局、最後までお助け隊をやりきった。そして結局毎年やったにも関わらず、好意に気づかれることなく終わった。そのあと高校ではバイトで図書館の人をやって、卒業してからそのまま図書館に就職した。
好きな人の恋人にもなれなかったし、エスパーにもまだ、というかまぁ一生なれないのは分かってるけど、それでも続けている。
本のことは好きになった。触れるたびに、どこか苦いあの子とのことを思い出してしまうけど、それもどこか心地よくなってきて、今ではそれを追い求めるために読んでいる節がある。
「先輩って、好きな本はなんすか」
今日入ってきたばかりの新人に尋ねられた。
「なんすか、じゃなくて、なんですかだろ。お客さんには絶対そういうしゃべり方すんなよ」
うーす、と返す新人。本当に分かってんのかこいつ。
カランコロン
ドアベルが鳴った。
「すみません。まだ開いてなく……て」
「久しぶり」
そう言って、髪の毛をかき分ける女性。ぼくはその人の顔を見て、胸が痛くなる。
昨年、寿退社した元館長だった。辞める前に触らせてもらった大きかったお腹はすっかり元に戻っていて、驚いた。
「ここまで戻すの大変だったよ」
「じゃあ、また焼肉行けますね」
「バカ、もう主婦なんだから、そんな時間ねぇよ。今日は、子どものための絵本を借りに来たんだ」
「そっすか、すみません」
「言い方! 気を付ける! もう私は図書館のお姉さんじゃないんだよ。お、きゃ、く、さ、ん。」
「うっす、うっす」
「この図書館の未来が不安だよ……」
二人して笑った。少しだけ胸が痛んだ。
子どもの頃の恋愛なんて、とっても些細なことのはずなのに、僕はいつまでも引きずっている。
あの日、未来さんに脈なしと分かってから、僕は放心状態のようになりながらも働いた。館長(今は元だけど)はその度に元気づけてくれた。それで簡単に恋に落ちてしまった。
館長は、僕が高校生当時二十代後半だったから、年は10歳以上も離れていた。が、そんなのは関係なかった。
結婚のために図書館からいなくなると聞いて、この思いを伝えたけど、その思いは叶わなかった。
「ごめんね、少年。あっ、もう少年じゃないか」ふふと笑って撫でてくれた館長。泣くつもりはなかったのに、自然と涙が出た。
「もう少年じゃないんだから泣いちゃダメだよ。あと君は簡単にお姉さんに恋に堕ちるから、大変だと思うけど頑張りな」
「ぼくが他の……後輩とかに手を出さないかどうか心配じゃないんですか?」
「それは心配してないよ。見たところ君は年上趣味だからね」こんなおばさんを好きになるような、と付け加えて笑った館長。僕も強がって笑った。
そのときお腹を大きくしていた彼女の相手はもちろんぼくじゃない。
すっかりお腹が図書館で働いていた頃に戻っている元館長。あなたがはめている指輪が、図書館のテラスから溢れた光を反射して、ぼくの目に届く。
「あー、笑いすぎて涙出てきちゃいましたよ」
と何度目か分からない彼女への強がりが、彼女のエスパー能力で気づかれてないと良いのだけど。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
