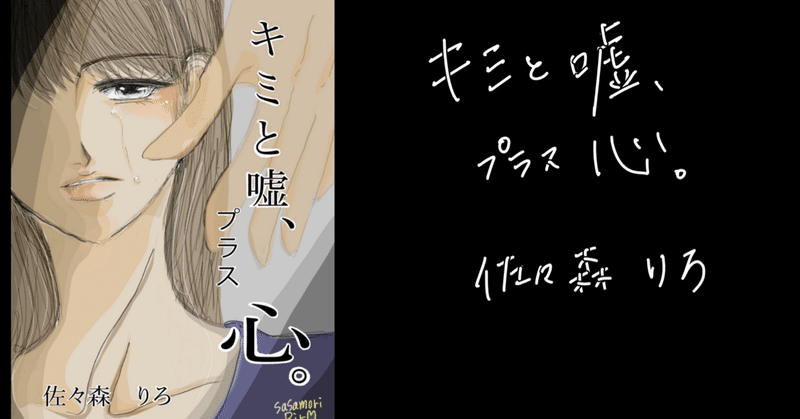
キミと嘘、プラス心。1
あらすじ
六月十八日。
見通しの良い交差点で信号無視。単独事故。ブレーキ跡もなく電柱に衝突。永田 キヨミさん(二十八歳)死亡。警察は自殺の可能性も視野に事故の原因を調査中。
仕事に疲れ彼氏に別れを告げられた雨宮詩乃は生花店を営む実家に戻って来ていた。ある日田舎には見慣れないスーツ姿で薔薇の花束を抱えた沖野優志と出会う。彼は永田キヨミの事故も彼女が亡くなったことも知らずにいた。詩乃はなぜか、キヨミがまだ生きているような嘘をついてしまう。
この嘘がきっかけで、詩乃は高校以来の友人モヨや孝弥と再会し、徐々にキヨミとの繋がりがあることを知ってゆく。
それぞれがついた嘘や心情がやがて、一本の線に繋がる……
第一章 雨、キミ去る。
昨日の夜からジトジトと降り続ける湿度の高い雨は、朝まで降り止むこと無くまだ地面を濡らしていた。空は重苦しい灰色をしていて、気持ちまでもがどんよりと沈み込むような気がして、思わずため息が漏れる。
朝早くからバタバタと忙しなく動いている母の姿に、あたしはまだ眠い目を擦りながら「おはよう」と挨拶をした。
「あ、詩乃。おはよう」
「どうしたの? 仕事?」
冷蔵庫からミネラルウォータを取り出してグラスに注ぎながら、仕事でいつも身に着けているエプロンをしている母に聞いた。
「そうなの。詩乃も着替えて手伝ってちょうだい」
「あー、うん。分かった」
あたしは焦る母とは正反対にのんびりと答えた。グラスを流しで洗うと一旦部屋に戻る。まだ閉じたままのカーテンを開けて、どんよりとした空を眺めてみると、気分までもが憂鬱になってきそうだ。
美容師を志して東京のヘアサロンに就職したものの、都会の環境と仕事と練習の多忙さに心が折れ、仕事ではミスばかりを続けてしまっていた。
その挙句、三年付き合った彼氏から別れを切り出されたあたしは、どうしようもなく落ち込んでしまっていて、逃げるように実家に帰って来てしまっていた。
“フラワーショップ・レイン“
実家はお花屋さんを営んでいる。傘と雫のマークの入った看板に、ガーベラが笑顔で華を添える。
駅前のお店の入り口は広く屋根が掛かっていて、雨宿りをする人達が集まってきて賑やかになるから、〝雨には感謝〟と言う事で店の名前はレイン。安易だけど、あたしは気に入っている。
「今日はお花よく出るね」
「そうね、でも、悲しい方のお花よ」
「え……あぁ」
華やかなイメージがある生花は、贈り物やお祝いなどの人を喜ばせるための物だと思っていたけど、別の意味での送り花がある。大切な人や身近な人が亡くなった時に贈るお花。
あたしは、母の手伝いをしながら送り主の名前を見た。
“永田 孝弥“
「あれ、これって……」
「何、知り合い?」
「もしかしたら、高校の同級生かもしれない。誰が亡くなったんだろう」
「詩乃より少し上くらいじゃなかったかしら。昨日の新聞に載ってたじゃない」
「新聞、見てない」
「ほら、そこにあるわよ」
母は空いていない両手の代わりに、奥のテーブルの上に視線を向ける。あたしはすぐさまそれを手に取って記事を探した。
六月十八日。
見通しの良い交差点で信号無視。単独事故。ブレーキ跡もなく電柱に衝突。永田 キヨミさん(二十八歳)死亡。警察は自殺の可能性も視野に事故の原因を調査中。
永田 キヨミさん(二十八歳)
あたしはその名前を見て、目を疑った。
永田、って……孝弥のお姉さん?
一気に血の気が引いたようにヒュッと全身が寒くなって、半袖から出た腕を抱えてさすった。
接点は全然なかったけど、孝弥がよく自慢げに話していたのを覚えている。一度だけ見たこともあるけれど、孝弥が自慢するのも納得するくらいに綺麗で女性らしい人だった気がする。
花を車に運び入れると、母と一緒に届け先へと向かった。
外は相変わらず梅雨独特の湿っぽい雨が降り続く。助手席に座ったあたしは、まとわりつくように幾度も落ちてくる細かい雨粒をワイパーが払うのを、ひたすらに見つめていた。
仕事を終えて葬儀会場を見渡すと、俯いたままの孝弥がいるのを見つけた。あたしは遠目からそんな孝弥を見て、かける言葉もなくその場から立ち去った。
*
いつもの帰り道、自販機で缶コーヒーを買うとマンションへと入った。ドアを開けると冷たい空気を一瞬肌に感じ、キヨミの居ない寂しさをより強く感じさせる。
今でもたまに、キヨミが居るんじゃないかと錯覚さえ覚える。
リビングのソファーに腰掛け、缶コーヒーを開けた。静かな部屋にカシャンと小さな音がやけに響く。
「いつまで経っても、慣れないな」
まるで、キヨミに話しかけるような口調で言葉が漏れる。きちんと整理整頓されていたキミのいたあの頃とは違って、今のリビングはお世辞でも綺麗とは到底言えないほどに散らかっている。
会社関係の資料や洗濯して取り込んだままの衣類や下着がそのまま床に置きっぱなしになっている。缶コーヒーの缶だって、もう何缶溜め込んでしまっているんだろう。怒ってくれるキミは、もうそばには居ない。
受け入れたくない現実に頭を振ってから一息つくと、ソファーから下りて床に座り、ローテーブルの上の資料とパソコンに手を伸ばした。最近はずっとリビングで生活している。
キミといた寝室では、寂しくて眠れない。
仕事の量が多いのはもちろんだが、それ以上にキミのことを考えなくてもいいくらいの多忙さが欲しくて、僕は寝ないでパソコンと向き合っている。
静かな部屋に、窓を叩く雨音が響きはじめた。今夜も雨か。そう感じた瞬間、目の前に置いてあったスマホの画面が光り、一定のリズムで震えはじめた。画面に表示されている相手の名前に、必然的にため息が漏れる。
「……はい」
『お疲れ様です。メッセージの返信が無いので、お電話差し上げてしまいました』
申し訳なさそうに、最後に小さく「すみません」と謝る着信相手は、父が勝手に決めた婚約者、奥田グループの長女奥田 江莉だった。
『見てくださいました? なかなかお返事が頂けないので、心配で……』
「ああ、すみません。その件なんですが……」
江莉からのメッセージが来ているのは知っていた。週末に食事に行きましょうとの内容だったはずだ。
「仕事が立て込んでおりまして、なかなか時間が取れないので……」
『社長のっ!』
江莉は言い訳は聞きたくないと言わんばかりに、僕の言葉に割って入ってくる。
『沖野社長からのご提案でしたよ。その日は優志さんに時間を与えるっておっしゃっていましたし』
電話越しでも伝わる強気な江莉の態度に怯みそうになるが、冷静な言葉を選びながら丁寧に返す。
「社長と時間の調整など話し合ってみますので。また追って連絡差し上げます」
『優志さん、私は必ずあなたと結婚します。ちゃんと、私を見てください。では、失礼いたします』
最後まで、折れることなく自分の気持ちを伝えてくる江莉に、通話の終了したスマホは脱力した腕と一緒に床直前で止まった。それを握る手に力を込める。
僕は、なんて無力だ。
父に決められたレールの上を今までなんの苦もなく走ってきた。それで良いと思ってきた。
それが、自分が幼い頃から見てきていた尊敬する父の言うことだから、間違いないと。
それなのに、ここへ来てそのレールを壊したい衝動に駆られている。見失ったとしても、もう二度とそのレールに乗れなくても、何処へ向かうのかも分からなくなっても、もうどうなっても良いと思ってしまうくらいに。
思ってしまうだけで、実際、僕は本当に無力だ。父に楯突くことを恐れている。楯突いたところで、今の僕にはキミを幸せにすることなんてできない。情けなくなる。
俯いた頭、左の手で髪を掻き上げるようにして支えた。目頭が熱くなる。額から目元へと手を下げると、抑えきれなくなった涙腺から溢れ出す涙に、そのまま天を仰いだ。
瞑ったままの目、真っ暗な視界に外の雨音がより強く、激しさを増していくのが聞こえた。
キミを想わない時なんて、一秒だってないんだ。
キミが出て行ってから、もう何日が過ぎたんだろう?
僕はずっと、思っている……キミに会いたい。
僕は、キミに何もしてあげられない。
*
梅雨はいつまで続くんだろう。今日も空を覆う灰色の雲に思わずため息が出てしまう。部屋から見える空を見つめて考えていると、スマホが鳴り出した。慌てて音の鳴る方へとスマホの存在を探しながら向かう。整理整頓の出来ていない自身の部屋に自ら呆れながらも、ようやく目に入ったスマホを拾い上げた。
着信相手の表示に一瞬動きが止まったが、次の瞬間、相手には見えもしないのに、あたしは満面の笑みでそれに応える。
「モヨ⁉︎」
『あーっ、詩乃ぉ、久し振りぃ、元気ー?』
相変わらずの艶っぽい喋り方は変わらない。
着信相手は高校からの同級生、奥田 百代。
モヨは自分の名前を嫌っている。
だから、教科書もテストの答案用紙も何もかも、すべて〝奥田モヨ〟と書くほどに徹底していた。綺麗な顔立ちと抜群のスタイルを兼ね備えていたモヨは、東京生まれ東京育ちなのに、こんな田舎の高校をあえて選んで通っていた。
当時は、あたしを含め誰もの関心を集めた。
好奇な眼差しにも臆さないモヨが放つキラキラとしたオーラが、あの頃のあたしには誰よりも格好良く見えた。
「んー、まずまずかな……」
かなり久しぶりの通話で、「元気?」とは建前で、「今幸せにしている?」と聞かれているような気がして、自分の今の状況を語るには、なかなか「元気だよ」とは言えない状態だったから、あたしはあえてそう答えた。
『そっか。詩乃、あたしやっぱそっちに戻ることにした』
スマホ越しのモヨの弱々しい言葉を聞いて、モヨもあたしと同じで、幸せな状態ではないんだろう。そう感じた。
「いつ? あたしなら、一足先にもう実家だよ」
『えっ! そーなの? やった、嬉しいー! もう、今すぐ帰るから。飲もう!』
さっきの弱々しい声は何処へやら。モヨは歓喜の声を上げて、スマホの向こうではしゃいでいるのが目に見えるようだ。懐かしさもあって、止まらない会話に先に終止符を打ったのは、モヨだった。
『あ、長くなってごめんね。とりあえず帰ったら連絡するから! またね』
そう言われて賑やかな通話を終えたあたしは、打ち付ける雨の音に気が付いて窓に目を向けた。
降ってきた。
先程よりも黒く厚い雲に覆われて低くなった空を見上げて、あたしはため息をついた。
お昼を過ぎた辺りから、雨は一旦落ち着いた。明るい雲に覆われた空には、時折太陽の筋が顔を覗かせる。久しぶりのお日様だ。あたしは嬉しくなってお店へと顔を出した。
花の香りの充満するひんやりとした店内から外へ出てみると、纏わり付く湿度と太陽の熱で、蒸発した雨がアスファルトの匂いを巻き上げる。そんな空気を、あたしは思い切り吸い込んだ。深呼吸をして駅の方に目を向けた瞬間、一人の男の人に目が止まった。
こんな田舎には不釣り合いな背格好に、着慣れているであろう皺ひとつないスーツはどう見ても高そうにしか見えない。何よりも、その手に持っている薔薇の花束が、それをより強調させている。
その人は、先ほどからスマホを片手に動きが止まっていて、たまに考え込むようなポーズを取ったり、辺りを見回したりしている。
もしかして、困っているのでは?
そう思って、その人に近づいて行った。
「あの、何かお困りですか?」
駅と言えども、ここは田舎。都会のように流れるほどの人波もなく、気が付けば駅の前にいるのは、その人一人だけだった。突然声をかけてしまったあたしに、彼は驚いた表情をする。そして、見た目の大人っぽさからは想像もつかないくらいに、無邪気に笑った。
「お声がけいただいてありがとうございます。ちょっと、人を探していまして。この辺りで永田キヨミさんという方を、ご存知ではないでしょうか?」
一瞬、冷たい突風があたし達の間を通り抜けていく。困った様に笑いながら、真っ直ぐな目であたしを見る彼に、直感した。
この人は、永田キヨミさんが亡くなったことを、知らない。
「あの……」
あたしが黙り込んでしまっていると、不思議そうにますます困った顔をさせている。
「……えっと、あの、キヨミさんは、ちょっと遠くに行くって、当分帰らないって言ってましたよ」
「え! ……そう、ですか」
何故か、あたしは適当な返事をしてしまっていて、目の前のあからさまにガッカリとした表情をみせたその人に、罪悪感を感じた。
「……と言うことは、キヨミのことをご存知だと言うことですよね?」
「え!」
「どこに行くか、聞いていないですか? 早く会って伝えたいことがあるんです」
目を輝かせて本当に嬉しそうに言うから、あたしは罪悪感を踏み潰して、小さく「何も、聞いていません」とだけ答えた。
「そう、ですか。電話も繋がらないし、当てもない……あ、すみません、いきなりこちらの話ばかりしてしまって」
丁寧に頭を下げた後に花束を脇に抱えると、ポケットから名刺入れを取り出した。そこから一枚の名刺を、両手で丁寧にあたしへと差し出してくれた。あたしは流れるままに同じように両手で受け取ると、視線を手元に落とした。
【沖野グループ 社長 沖野 優志】
社長⁉︎ あたしは思わず顔を上げてしまう。
「キヨミから何か連絡が来たら、是非教えて頂きたいんです。ご迷惑じゃなければ、あなたのお名前を伺ってもよろしいですか?」
「……あ、雨宮詩乃、です」
あたしが答えると、その人はふんわりと笑って薔薇の花束をあたしに差し出した。
「これは雨宮さんに差し上げます。キヨミとの繋がりを作ってくれたお礼です。では」
軽く頭を下げると、駅の中へと戻って行ってしまった後ろ姿を見送った。
その日、あたしの心の中には罪悪感が残って。あの人の顔が頭から離れなかった。
自分が何故あんな嘘をついてしまったのかも分からずに。
だけど、あたしのついた嘘はそんな簡単に全てを消してくれることはなくて、キヨミさんの死に、沖野と言う男が深く関わっていることを、すぐに知ることになるんだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

