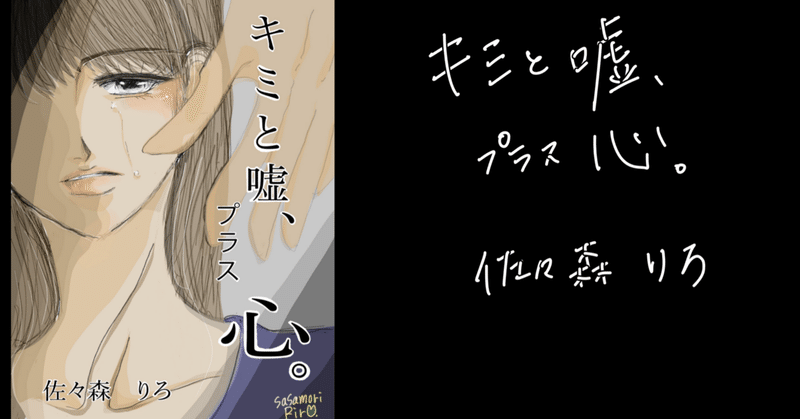
キミと嘘、プラス心。4
第四章 繋がり
眠い。今、何時だろう。
そう思って壁に掛けてある時計に目を向けた。時刻はもうすぐ日付を超えようとしていた。
こんな集中力では成長も技量も上がらないのでは? と疑いたくなってくる時間帯に、詩乃は意識が飛んでしまわないように一生懸命に目を凝らした。
目の前の何も語らない首だけのカット用ウィッグの視線が、鏡ごしに薄ら笑いを浮かべているようにも見えてくる。
すみません。お客様だったらこのカットではクレームものです。ため息をついて、また一からガイドを取り直す。
「何回やってんの? 集中力なさすぎでしょ。辞めたら?」
先輩からのゲキが飛ぶ。
集中力なんてもの、とっくになくなっています。毎日毎日、朝早くから夜遅く日付をまたぐまで、もう、集中力どころかこの仕事をする意味さえも見失ってきている。
本当なら、今日は練習はなくて早く帰れるはずだった。
だけど……
『先輩! あたしカットもう少し見て欲しいんですけど、お時間良いですか?』
向上心のありすぎる同期が放った一言のせいで、練習なしがなしになった。もちろん自分だけ先に帰るなんて、以ての外だ。当然のように付き合わなければならない。
今日は、大好きな凌二の誕生日で、偶然にも練習のない日が重なるからと、前々から会う予定にしっかりと入れていたんだ。
デニムのポケットの中でさっきから震えているスマホ。
凌二から着信が来ているのかもしれない。
先輩からの「辞めたら?」の一言に、ますます意地を張ってしまう自分に、悔しくなってくる。
辞めたくない。でも、凌二にも会いたい。
毎日が、葛藤だった。
『ごめん、詩乃。俺、他に好きな人出来た』
いつものように仕事を終えて遅くなった帰り道。
ずっと、凌二との電話が、一日の疲れを癒すあたしの心の拠り所だった。
会えなくても良い。こうやって話して、好きな気持ちを確かめあえるのなら、それでいい。それで、満足してしまっていた。
今日だって、いつもと同じだった。
最初は「お疲れ」から始まって、その日の出来事を話して、愚痴を聞いてもらって、いつも通りにまた疲れを癒してもらえた。
明日からまた頑張ろう。そう思える会話をしているはずだった。
なのに。
『別れよう』
唐突だった。
唐突……だった?
もう、何回か頭の中で感じていたかもしれない。凌二からのメッセージが少なくなってきていること。電話の会話も、こちらの話を一方的に聞き役になってくれていること。〝好きだよ〟の言葉を、言ってくれなくなったこと。
そんなこと、もう分かりきった事だから、だから、言わなくても分かるだろうと、そう思って言ってくれないんだと思っていた。
でも、それは違った。もう、好きじゃないんだ。だから、言ってくれなくなったんだ。気づかないふりしてたのに。
いつか言われるんじゃないかと頭の隅にはあったけど、ずっと考えないように押し込んでいたのに。
凌二はいとも簡単に〝別れよう〟と言葉を放った。
会えるなら今すぐに会いに行きたい。明日の朝も早くから練習と仕事。
終電も終わってしまって、走ってなんて行ける距離に凌二は居ない。
それでも、行けばよかった。
どうせ何もかも失うのなら、何も考えずに会いに行けばよかった。
そうしたら、何か変わったのかもしれない。変えれたのかもしれない。
でも、そんな事は今更思っても、もう手遅れだった。
✳︎
カーテンを開けたまま眠ってしまっていたらしい。窓から差し込む日差しが眩しくて、目を覚ました。凌二と別れたのはもう半年も前の事だ。なのに、未だにあの時の事を夢に見る。
汗ばんだ体をゆっくり起こして、差し込む日差しに目を細めた。今日は晴れてる。
もう思い出したくもない過去にしたはずなのに、こうやって夢に見てしまうと、どうしようもなくまた寂しさが募ってしまう。
小さく息を吐き出して、テーブルに置かれたスマホを手に取ると、ふとその隣に無造作に置かれた名刺に目が止まった。あの人と会ってから、一週間経った。もちろんキヨミさんの居場所なんてどこにもなくて、あたしがそれを知る由もなくて、なんの連絡もしていない。
一方的に名刺をもらっただけで、こちらの連絡先などは教えていなかったから、向こうからあの嘘を問いただされることもなくて、この名刺になんの意味もないことを感じてしまう。
捨ててしまおうか。
そう思った瞬間、スマホが鳴り出した。着信表示は〝モヨ〟
「おはよう、早いね?」
『おはよぉ、詩乃ぉ、今日会える?』
まだ寝起きなんだろう。
声は微妙に掠れているし、もしかしたら寝ずに飲んでいたのかもしれない。
「どうしたの? また飲みすぎてない?」
『ぶーっ、大丈夫。夕方までには復活するから!』
意気込んでそう言われても、こっちに来てからほぼ毎日昼夜問わずに飲んだくれているモヨのことが、そろそろ心配になってくる。
『今日はねー、孝弥を誘ったんだ、夕方来てくれるって。だから詩乃も来て? あ、あたし美味しい餃子お取り寄せしたの、ご飯も用意するから手ぶらでオッケーよん』
はははんっと最後は楽しそうに笑っていたかと思ったら、急に何も喋らなくなった。不思議に思ってしばらくこちらも黙っていると、寝息のような息遣いが聞こえてくる。
「寝たな……」
呆れて呟いて、通話を終了した。
本当に大丈夫なのかな。
高校生の頃、モヨはモデルになる夢を抱いて、自分の体の事は勿論、勉強も運動もその夢を実現させるために頑張っていた。
こんな田舎にいるよりも、実家のある東京でその夢を叶えたほうが現実的ではないのかとみんなが思っていて、先生にもそう言われたモヨは、怒っていた。
『絶対に家には戻らない』
冷めた表情で一言呟いたモヨの顔が、今でもすぐに思い出せるのは、その後にあんな事があったからだ。
✳︎
『あたし、東京に戻ることにした』
卒業間際に突然、モヨが言った。
みんな驚いていた。
あんなに頑なに家に帰ることを拒否していたモヨが、なんの気まぐれか、気持ちの変化か、そう言って寂しそうに笑った。
何か、きっとモヨなりに考えて出した結論なんだと、深く追求することはしなかった。
あたしは、それが正しいと思っていたから。
その後、同じ東京という場所に暮らしているというのに、田舎に比べたら交通の便も良く、こんなにも狭い土地の中なのに、恋人ともろくに会えなかったあたしは、モヨとの時間もなかなか取れずに、連絡も滞ってしまっていた。
モヨがその間、何をしていたのかはまだ聞いていない。
そんなに酒に溺れる毎日を送っていると、何があったんだろうと心配になる。だけど、あたしも何があって実家に戻ってきたのか、モヨには伝えていない。言いたくない事だってあるだろう。話してくれる時に、聞いてあげればいい。そう思った。
〝孝弥を誘ったんだ〟
モヨの言葉を思い出して、テーブルの上の名刺にまた視線を向けた。手に取って、眺めてみる。
『キヨミから何か連絡が来たら、是非教えて頂きたいんです』
あの人の真っ直ぐに希望を見ているような目を思い出して、詩乃はため息をついた。
そんなの、キヨミさんからの連絡なんて、くるはずがない。
もう、キヨミさんはこの世には居ないんだから。
なのに、あんな真っ直ぐに、嬉しそうに笑うあの人の笑顔を、曇らせたくないとあたしは嘘をついた。
なんて、残酷なことをしてしまったんだろう。
きっと、今日もあの人はキヨミさんに会える日を今か今かと過ごしているのかもしれない。
いや、世の中情報社会だ。知りたい情報なんてスマホと指一本でなんだって出てくる。もう知ってしまったかもしれない。絶望してしまっているかもしれない。
あたしのついた嘘のせいで、大きく膨らんだ希望に押しつぶされてしまったかもしれない。
大丈夫。あの人は社長だ。自分で命を絶つことなどはしないだろう。
そう勝手に決めつけて、あたしは名刺を普段あまり開ける事のない引き出しへとしまい込んだ。
孝弥は、もう楽しくお酒を飲めたり、ましてやモヨの話を聞いてあげられる余裕などあるのだろうか。
ふと、花を届けに行った日に見た、憔悴しきった孝弥の姿を思い出した。
きっと仲の良い姉弟だったんだろう、孝弥は中学からの同級生だけど、いつもにこやかで小さい事は気にしない、誰にでも風当たりの良い男子だった。キヨミさんの弟だけあって似てはいないけれど、顔も良い。女子には結構人気があった。
モヨが孝弥と付き合っているという噂が出たこともあったけど、その詳細はよく分からない。
モヨもその通りモテていたから、当時は横を歩いているだけで彼氏だと勘違いされて、色んな男と遊んでいるなんて、ひどい噂もあった。モヨがそんな噂を間に受ける様な子ではないから、安心はしていたけれど、実際はどうだったのかは分からない。
人の気持ちなんて、分からない事だらけだ。
いっその事、人の心が読めたらこんなに考えることも、悩むこともないのに。
だけど、そんなことはできる訳がないし、出来たとしたら全てが分かりすぎてきっと辛いのかもしれない。
自分の悲しみや辛さだけで精一杯だ。
また、先ほど見た夢のせいで、重苦しくなった頭をグッと押さえた。
✳︎
「いらっしゃーいっ」
モヨから送られてきた通りの地図でたどり着いたのは、この辺りでは珍しいと言うか、場違いな佇まいの最近建ったばかりの新築デザイナーズマンションだった。
その最上階にモヨは部屋を借りたらしい。
厳重なオートロックに言われていた番号を入力すると、元気の良いモヨの声が画面越しに響いてきた。
「入ってー。玄関開けとくからっ」
顔と喋り方からして、また酔っ払っているんだろうと思う。自動的に開いたドアから入ると、真新しい建物の匂いに何故か緊張しながらエレベーターのボタンを押した。
餃子を用意しているとは言っていたけど、酔っ払いが料理なんて出来るわけがない。あたしは駅前のカフェ【flavorful】から、つまみやおかずになりそうな物をテイクアウトして来ていた。
玄関の前に着くと、ドアに手を掛けて開けようとした瞬間に、そちらの方からドアが開いた。
「いらっしゃい……って、うちじゃないけど」
そう言いながら出てきたのは、孝弥だった。
目が合った表情は笑顔で、あたしはそんな孝弥の顔を見るなり安心した。
「何? 入んないの?」
突っ立ったまま動かないあたしに、孝弥は呆れたようにまた笑う。
「お邪魔します」
慌ててあたしが玄関へと足を踏み入れると、「どうぞ。俺んちじゃないけど」と、孝弥がまたしても言うから、笑ってしまった。
悲しい顔をしているんじゃないかと心配していたけれど、案外平気そうで良かった。それよりも、あたしはこの部屋の広さに驚いていた。
「……モヨ、凄いとこ住んでるね」
玄関だけでもワンルームある広さで、一向にこの住まいの主の顔が見えてこない。
「あぁ、俺も驚いた。モヨは今キッチンで料理してたよ」
「え! 酔っ払ってて大丈夫なの⁉︎」
会話が余裕で出来るほどに伸びた廊下を抜けると、一気にフロアが広がる。リビングキッチンからの眺めは、空が近く感じて絵画でも飾ってあるかのように素晴らしかった。
「あ、詩乃ぉー、もうすぐだから孝弥と話して待っててね」
あたしが来たことを確認したモヨは、ビールの缶を片手に手を振っている。
やっぱり、飲んでる。
「モヨ、大丈夫? あたしやろうか?」
買ってきた袋をテーブルに置こうとそこを見ると、ズラリと料理が並んでいるのに気がついた。
「え⁉︎ これ、モヨが作ったの?」
驚いているあたしに構わずに、鼻歌を歌いながらモヨは次の料理に夢中だ。
「らしいよ。東京でシェフでもやってたんじゃね? とりあえず座っとけよ」
孝弥は自分ちの様にそう言ってソファーに腰掛けるから、あたしは持ってきたつまみや惣菜がなんだか取るに足りないものに思えてしまって、思わず袋を背中に回した。
「それ、flavorfulのやつでしょ? 美味いよね」
すかさず孝弥が隠した袋に気がついて言ってくれた。
「出しとけよ。多分、モヨ知らないから」
「あ、うん。分かった」
孝弥の言葉に、先程のテーブルとは別のリビングのテーブルにそっと袋を置いた。やっぱり、孝弥はこうやって気がついてくれる所がある。優しいんだ、きっと。だったら、尚更、傷なんてまだまだ癒えていないんじゃないのかな。余計なお世話かもしれないけど、心配してしまう。
目の前でスマホを眺めている孝弥の事を見ていると、目が合って笑いかけてきた。
「なに? あー……詩乃も知ってた? 俺のねぇちゃんが事故にあった事」
考えていたことを見抜かれていて、一瞬顔色を変えてしまったのと、言葉に詰まってしまったので、孝弥は小さくため息をついた後に笑った。
「突然だったんだ。今でも本当に現実に起きた事なのかよく、分からない」
向けられた笑顔がとても寂しそうで、こちらまで泣きたくなってくる。
孝弥はもう、たくさん泣いたんだと思う。
「でも、大丈夫だよ。一人でいるよりもこうやって呼んでもらえると気も紛れるし、助かる」
しんみりと重い空気が漂っていたあたし達の元へ、それを吹き飛ばす陽気なモヨがやって来た。
「ほらぁ、出来たよー! 座って乾杯しよっ」
手に掲げたビールの缶の蓋を開けると、満面の笑みでモヨがあたしと孝弥にもズラリと色々なお酒を選んでと差し出してくる。
ビールがどうにも好きになれないあたしは甘めの酎ハイを、孝弥はとりあえずビールでと缶ビールに手を伸ばした。
同級生が集まると、自然とその頃の話題になって、話は尽きることはない。どんどん開けられていく缶がゴミ袋いっぱいに溜まってしまった。
「ビールってゴミが増えるから嫌よね。ワインにしたいんだけど、それもそれで嫌なこと思い出すから飲みたくないし」
「嫌なことって?」
「いーのー、気にしないで。あ、これも美味しいから食べてみて」
あたしの質問をはぐらかすと、モヨはミニトマトとモッツァレラのカプレーゼの乗ったお皿を差し出してくる。
「このトマトがねー、めっちゃくちゃ甘くて美味しいの。最近これしか食べてない」
取り分けてくれたお皿を受け取って口にすると、本当に美味しい。
「え、モヨってばモデルじゃなくてシェフやってたの?」
思わずあたしがそう言うと、モヨはケラケラと笑い出した。
「それ、さっき孝弥にも言われたんだけどー! シェフにはなってないけど、一流のシェフの教えは学んできたよ。嫌だったけど、色々教え込まれてきた。やりたい事もやってきた。だけど、どれも結局は上手くいかなかった。だから、あたしはまた逃げてきたのー。こっちに居れば何にも考えないで良いと思ったし、現実逃避だったんだけど、人生、そんな甘くはない、よね……」
調子よく喋っていたかと思ったら、モヨは表情を暗くして、最後は呟く様に言ってビールを飲んだ。
気持ちが安定していない様子のモヨに心配になりつつ、あたしは酎ハイをちびちびと飲む。
「詩乃は、お酒あんまり飲まない感じ?」
「え、あー、そうだね。飲まなきゃ飲まないで良いかも」
孝弥に聞かれて、あたしは答えた。
「だよね、さっきから全然進んでないし。お茶もあるよ? 要る?」
「え! ほんと? 貰おうかな」
酎ハイも、実はあまり得意ではない。そんなあたしを察してくれた孝弥が立ち上がってキッチンへと向かう。
「孝弥って優しーよねー。高校の時からそうだったけど。彼女いた話聞いたことあった?」
モヨがあたしの持ってきたflavorfulのチキンサラダをつまみながらそばに寄ってくる。
「え? モヨは孝弥と付き合ってたりしなかったの? なんか、噂なかった?」
「は⁉︎ ないないっ。あの時みんな何でもかんでもあたしが誰かと付き合ってるって噂すんの好きだったよねー。実際は誰とも……うん、誰とも付き合ってなかったよ」
一瞬考えるような間があって、モヨは笑った。
うん、気になる。けど、触れて欲しくないことかもしれない。そう思うと、あたしは何も聞けなかった。
グラスに注いだお茶を孝弥が持って来てくれて、あたしに手渡してくれた。
「ところでさ、モヨって苗字〝奥田〟だったよな?」
「え? うん、そーだけど」
孝弥は頷くモヨに、一瞬だけ暗い顔をしたように見えた。
「……ねぇちゃんとか、いたりする?」
「え?」
「おくだえりって」
孝弥の口から出た名前に、今度はモヨが明らかに嫌な顔をした。
「居ないよ。あたしは自由気ままな一人っ子だよ。兄弟はなし」
真顔で、モヨは言い切った。
そんなモヨに、孝弥は安心したような顔になって、笑う。
「そっ、か。なら、いーわ、俺の勘違いだ」
「誰なの? それ」
少し不機嫌な雰囲気を残しつつ、真顔のままモヨは聞く。
「俺の上司。俺、今奥田グループの経営する会社で働いてて、その娘がトップの部署で一緒に働いてる」
孝弥はそう言ってから、ビールをゴクゴクと美味しそうに飲んだ。
その瞬間、向かいに座るモヨが持っていたクラッカーを、添えて持っていたお皿に落っことした。
サーモンとアボカド、カマンベールチーズの乗っかったそれは、見事にお皿の上でひっくり返ってバラバラになってしまった。
だけど、モヨはそんなこと気にしてないように皿をテーブルに置いて、そばにあった新しいビールの缶を手にとって蓋を開けた。
「うちの会社凄いんだよ。経営右肩上がりで。てっきり同じ苗字だし、モヨすげぇとこ住んでるし、金持ちの娘かと思っちゃうじゃん」
孝弥の言葉に、モヨはビールを飲むけど、先ほどまでの陽気さはなくて、酔いも醒めているかのような目で笑った。
「全然知らない。まぁ、うちもお金だけはあるうちだから間違いじゃないけど、奥田グループとあたしは一切関係ないよ。だから、この話はもう終わりね」
モヨは両手をクロスさせてバツを作ると、あたしの方へ向いた。
「詩乃は? 彼氏とはまだ続いてたの?」
話題を変えたのは良いけど、あたしにとってはなんとも答えづらい話題だ。
お茶のグラスを両掌で包み込む様に持って黙り込んでしまったあたしを見て、モヨと孝弥は顔を見合わせて焦っている。
触れてはいけない話題だったと思わせてしまった。
「あたしが仕事が忙し過ぎて……全然会えなくて、凌二は他に好きな人が出来ちゃったって、半年前に、別れました」
美容の専門学校に通っていた頃に出来た、初めての彼氏だった。
友達を通しての飲み会で知り合って、あたしの一目惚れ。あの時は、自分が好きだと思ったら、こんなに行動できる人だとは思っていなかったから、凌二のおかげであたしという人間が、恋には積極的になれるトコがあるって事を教えてもらった気がする。
「そっか、半年経ってんだね。なら、もう吹っ切れてるよね。次よ、次」
モヨが安心したようにまた陽気にビールの缶を掲げて言うから、あたしは全然癒えていない心の傷を悟られないようにそっと笑った。
前回までの話はこちらから↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

