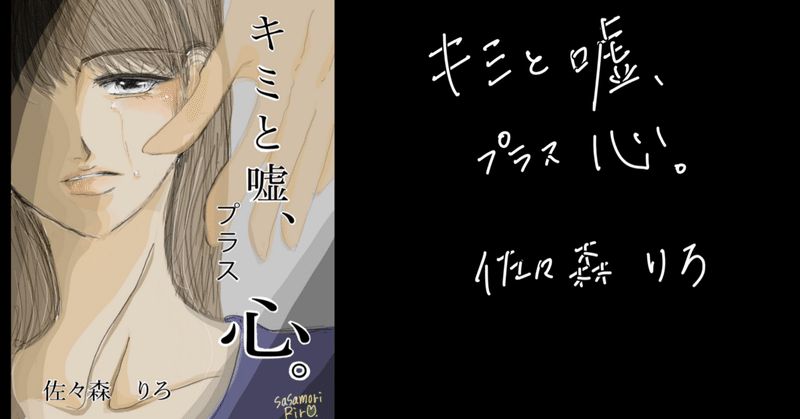
キミと嘘、プラス心。3
第三章 奥田江莉
────東京都心
高層ビルの最上階の部屋で、窓一面の夜景を背にグラスに注いだワインを口に含んだ。それを持つ手は、小刻みに震えていた。
そっと、グラスをテーブルに置くと、両掌をテーブルについて体をそこに預けるように俯いた。耳にかけていた髪の毛がハラリと頬をなぞる。
瞬間、込み上げてくる笑いに静かに肩を震わせた。
おかしいわけじゃない。心の中は真っ暗な部屋と同じで感情なんてものは感じない。
ただ、ひたすらに、恐怖心がふつふつと募っていく。怖いから振るえているのか、自分でもよくわからない。
だけど、これで優志さんは私のもの。
勝ち誇ったように、陽でも隠でもなく、一人笑っていた。
✳︎
十年前────
「あの方は?」
「ああ、沖野グループの御子息の優志くんだ」
父の付き添いで訪れた簡素なパーティーに参加していた私は、そこで初めて優志さんと出会った。
まだ高校生だった私には、二十歳の彼がとても大人に見えて、立ち居振る舞いや周りに配慮できる優しさに、恋に落ちるのには時間がかからなかった。
「いずれ、うちには娘しかいないもので、優志くんさえ良ければ貰っていただきたいものだよ」
「ははは、うちの優志で良いのか? こいつは出来損ないだぞ。私に似て」
お酒が入っているからか、上機嫌で会話をする両家の父。困ったように笑う彼を、自分の物にしたいと気持ちが疼いた。
それから、会社の関係でなにかがある度に顔を合わせる様になって、会話をしていても常に私を気遣ってくれる彼の優しさに、距離が縮んでいると思っていた。
だけど……
「沖野グループの息子さんなんですかぁ! すごーいっ」
中学三年になった妹の百代が、お姉ちゃんばかりズルいとパーティーに顔を出す様になった。
元々人見知りなんてしない誰にでも愛嬌が良く、好かれるタイプの百代は優志さんと打ち解けるのに時間なんて要らなかった。
「おや、優志は百代さんと気が合う様だな」
彼のお父様が何気なく放ったその言葉を、私は聞き逃さなかった。そして、すぐ隣にいた百代の反応も。
「えー! じゃあ結婚しちゃいます? 社長夫人なんて素敵ーっ」
私が数ヶ月かけて少しずつ築き上げてきた彼との距離を、百代は一瞬にして手に入れた気がした。百代のことが、妬ましく思った。
奥歯をギリリと噛み締めて、拳を握る。
優志さんはぜったいに、渡さない。
あのパーティーの後も、百代は優志さんと会えば持ち前の明るさで他愛無いことでも会話が弾んでいた。私の入り込む隙もないくらいに打ち解け出した百代のことが、許せなくなった。
✳︎
「お姉ちゃん? あたし、百代だよ。なーに、話って」
ビジネスホテルの最上階の部屋へ来る様にメッセージを送った。素直に騙されて部屋の中へと足を踏み入れたことを確認してから、ドアを施錠して電気の絞りを回す。
間接照明の灯りだけの、薄暗くなった部屋の窓一面に煌めく夜景が浮かび上がった。
「うわぁー、素敵だね、この部屋!」
窓に駆け寄って外の景色に放心状態になっている百代。先に用意していた人影に合図を送ると、百代へと向かっていく黒い姿に、気持ちが高ぶって口角が自然と上がってしまう。
あの子が悪いのよ。
私の愛する優志さんに色目を使うから。
沖野グループと繋がりを持つのは私一人だけで十分じゃない。あの子は要らないの。本当は消えて欲しいんだけど。そこまでは流石に、ね。だから、優志さんに百代なんて相応しくないんだと皆んなに教えないといけない。
その為の事よ。ちゃーんと、お姉ちゃんが助けてあげるから。
薄暗闇の向こう、突然ベットの上に組み敷かれて声も出せずに震えている百代を見て、思わず発しそうになる笑いを堪えてスマホをかざした。
必死に抵抗している百代のことを、いつまでも眺めていたいところだけれど、私の目的はもう遂行された。スマホの中の写真に収まったものを確認しながら、あたかも助けに来たかのように百代の名前を叫んだ。
心の中で嘲笑いを浮かべながら。
「百代!」
私の声に、一瞬気を抜いた目の前の男の腹を思いっきり蹴り飛ばした百代は、一目散に私の元まで下着姿のままで駆け寄ってきた。
「お姉ちゃんっ!」
縋り付くようにして抱き付いた百代の頭をそっと撫でる。肩がビクリと一瞬震えた気がした。私の手に握られていたスマホの画面がまだ明るいままだと気が付いた。
百代の視線は完全にスマホの中の、自分と知らない男が重なる写真に釘付けになっていた。
「大丈夫? 百代?」
優しい口調で百代の肩を抱く。小刻みに震えている体に思わず笑いが漏れそうになった口元を引き締めた。
驚いた様に怯えた目を向けてくる百代に、あたしは困った様に眉を顰めた。
これを仕掛けたのは紛れもなく私よ。百代はそれに気がついたはずだ。
静まり返る部屋の中で、もう一度百代を引き寄せようとした瞬間に、パシンッと手を払いのけられた。それから、百代はフラつきながら散らばった自分の衣服を拾い始める。
「あー、痛えなぁ」
ふいに、すぐそばで低く呟く男の声。上半身を起こしてベッドの上で胡座をかいている男は私に向かってため息を吐き出した。
「フザケンナよ江莉。もう終わり? 妹めっちゃ可愛いじゃん。俺気に入っちゃったなぁ」
拾い上げた服を震えながら着ている百代の方を見ながら、その男は不敵に笑った。私の目的はすでに遂行された。もうこの男には用はない。
「ダメよ。もう帰って」
「マジかよ、酷くない? どうすんの、これ」
そう言いながら、男は胡座をかいた足の方を指差した。
そんなの知ったことじゃない。ほとほと呆れてため息を吐くと、ハンドバッグの中から札束を取り出して、男の足元に投げつけた。
「とにかく、それ持って消えて」
いつまでも裸を晒されていたんじゃ、はっきり言って迷惑だ。目の前に投げつけられた札束に手を伸ばした男は、一気に飛び上がって歓喜の声をあげた。
「すっげ‼︎ 良いの? こんなもらって。またいくらでもやるから」
「もうあなたに用はないわ。ほんと、早く消えて」
「はいはーい、分かりましたよー」
すんなりと男は束になった現金でニヤける口元を隠しながら、簡単に服を着ると部屋から出て行った。
「あんたが悪いのよ。優志さんに色目を使ったりするから」
睨んだ先の百代は、私のことを軽蔑するような目で睨み返していた。
「ここ、今日部屋とってあるから、後は自由に使って良いわよ、じゃあね」
床にぺったりと座り込んでしまった百代を一人置いて、部屋から出た。
いつだって、欲しいものならどんな手を使ってでも、どんな事をしてでも、手に入れてきた。
地位、お金、父の権限。あらゆる全てを利用して。
「あの子、モデルになりたいがために自分の体を売るような子なの。絶対に優志さんとは合わないわ」
百代のいない隙を狙って、優志さんはもちろん、父と母、優志さんの親まで、余すことなく百代が不埒な女だと困ったように言って信じ込ませた。
知らない男に金を渡して百代を貶めた。その時の写真が、宛名不明の封筒から出てきた時には、すでに百代に対する私の言葉を信じた周りの態度や反応は、目に見えて今までとは違うものになっていた。
周りがあまりにも素直に信じ込むから、腹の底から笑いが込み上げてきたの。
────
煌めく街の灯りと車のライトが列をなして、暗い夜が華やかに彩られていた。
静けさとは無縁の地上とは打って変わって、奥田ビルディングの最上階のレストランは緩やかにクラシック音楽が流れる。まるで現実とは別空間のような場所で、優志さんと向かい合って座っている。
「今日は来て頂いてとても嬉しいです。この間のフレンチもお口に合いましたでしょうか? ここのお料理も、とても美味しいんですよ」
順調に食事会を重ねて、確実に優志さんと私の時間は増えているはずなのに、目の前にいる彼は、憂鬱な表情を隠しきれていない。
「……具合いでもお悪いのですか?」
なにがそんなに不満なのか、理由が知りたくなる。ナイフとフォークをお皿に置いて、優志さんを見つめた。
「江莉さん、この間も言った通り、僕は江莉さんとは一緒になる気はありません。僕には、心に決めた人が居るんです。なので……」
出された料理に一切手を付けずに、優志さんは俯き加減で目も合わせずに言った。
「嫌です。私は必ず優志さんと結婚します。あんなどこにでも居るような女の何が良いって言うの?」
「……え? あ、もしかして、キヨミを知っているんですか?」
先ほどからずっと泳いでいて絡まなかった視線が、急に真っ直ぐに私の目を捉えた。
「あんな田舎の女なんて、どこが良いんですか? 百代の方がまだマシです」
ため息を吐きつつ、若鶏のディアブール風を口に運んだ。
「田舎って……まさか、キヨミの居場所をご存知なんですか?」
明るい顔で、身を乗り出すように聞いてくる優志さんに驚く。
「電話も繋がらなくて、僕は恥ずかしい事にキヨミの生まれた場所さえ知らずに一緒に過ごしてきてしまっていたんです。さっき、メッセージを送りました。僕はやっぱりキヨミ以外は考えられない。会いたいんです……キヨミに。お願いです、キヨミが何処へいるのか、知っているなら、教えてください」
「お願いします」と、すがる思いで頭を下げる優志さんに、ナイフとフォークを持つ手が小刻みに震えた。
顔をいつまでもあげない優志さんの姿に、寒気がする程に苛立ちが募った。
「ちょっと、この部屋、冷房が効き過ぎていないですか?」
肩中の広く開いたワンピースを着ていた私は、出ている肌をさすって寒いそぶりをして見せる。
「え、あ……僕が伝えてきます」
すぐに席を立って個室から出て行く優志さんを見送ると、椅子から立ち上がって入り口で預けた優志さんの上着が掛けてある場所まで行き、胸ポケットからスマホを取り出した。
優志さんが食事中にはスマホは触らない事を知っていた。食事中は連絡をもらっても、出られないことがあると本人に言われたこともある。いつでも彼の行動を見て来ていたから、上着のポケットにスマホをしまっている事も知っていた。相手への配慮だと思った。
けど、それが仇になるだなんて、考えもしないだろう。
取り出したスマホを、自分のバックの中へとしまい込んだ。
戻ってきた優志さんに、何事も無かったように振る舞って、その後キヨミの田舎のある駅の名前だけを知っていると伝えると、住所までは教えずに優志さんとの食事会を終えた。
✳︎
江莉との食事を終えて自宅へと向かうために乗り込んだタクシーの中で、上着のポケットに手を入れるが、そこに何もないことに気が付いた。
横に置いたバックの中も覗いて見る。
しかし、どこにも見当たらない。
一旦落ち着いて、外を流れる夜の街並みを眺めながら、自分の行動を思い返してみる。
江莉との食事は、自分の発言で江莉の事を不機嫌にさせてしまったかと思ったが、いつも通りにある程度に会話も弾んで、キヨミの住んでいる場所の付近を教えてもらえた。
江莉がなぜキヨミの事を知っているのか、少し気になったが、あんまりしつこくキヨミの事で話を広げようとすると、それにブレーキをかけるように違う話題を振ってくる。
当たり前だ。江莉は僕の事を慕っている。
そんな僕が違う女性の名前を口にするのは、良い気分ではないのだろう。
どこを思い返しても、スマホの置き忘れなど思い浮かばない。落としてきてしまったのか。
仕方がない、帰ってからゆっくり考えよう。
何故なのか、江莉との食事会は毎回気を使ってしまって疲れる。
諦めて、深いため息と共にかっちり身に付けていたネクタイに手を掛けて、軽く緩めた。
キミは、こんな煌びやかな都会から離れて、静かで落ち着いた場所で、幸せにしているんだろうか?
あんなに近くに居た筈なのに、どうして。
僕は、キミのなにも知らない。
こんなことになってしまってから、ようやく気が付いた。
キミのいない人生など、
生きる意味もないと。
だから、僕は必ずキミを迎えにいく。
送ったメッセージの返信が、YESであることを、切に願いたい。
✳︎
奥田グループの所有するビルの一室で、優志さんのスマホを手にして私はソファーに深く座り込んでいた。
広い窓から見える、空に点滅するいくつもの赤や黄のライト。瞬く地上からの灯りが空を明るくしているが、上空の黒の闇の中に灰色の雲が低くなっているのが見える。雨が降り出しそうなその雲を眺めてから、前に盗み見ていた優志さんのスマホのパスコードを入力して、いとも簡単にロックを解除した。
すぐ様、キヨミ宛のメッセージを確認する。
「絶対にあなたなんかに優志さんは渡さない。こんなメッセージ、嘘だって送ってあげるわ」
まだ既読は付いていない。足を組み直して、メッセージを打ち込もうとした瞬間、既読の文字が表示された。
操作する指の動きが瞬時に止まって、口角が僅かに上がる。
「あら……見ちゃったんだ。だったら、話は早いかしら」
立ち上がると、一度スマホをテーブルへと置いて、グラスとワインの瓶を一本ワインセラーから取り出した。静かにガラスのテーブルへと並べる。
そして、キヨミへと繋がる発信表示を、タップした。
『……ゆう──』
キヨミになどなんの用事もない。
だだ、分からせたいだけ。
どんなに想ってもそれは届かぬ想いだと。
期待などするなと。
優志さんは、私だけの物なんだと。
あなたにはなんの価値も無いと言うことを。
耳に当てていたスマホの向こうから、なにかがぶつかるような音が聞こえた。
鈍く、鋭いような、聞いたことのない音。
そして、通話は終了した。
スマホを持つ手が、何故か震えた。
もうこれで、二度と優志さんには近づいてこないだろう。そう思うと、別に可笑しい訳でもなく、嬉しい訳でもなく笑いが込み上げてきた。
震える手でグラスを持ち、窓の外の夜景をグラスに反射させた。
口に含んだワインは、何の味もしなかった。
それを飲み干して、暗闇の中で見慣れた夜景を、何を思うでもなく見つめ続けた。
低く淀んだ雲から、細く冷たい雨の糸が静かに落ちてくる。やがてそれは、地面を叩きつけるほどに強く激しい雨の塊へと、変わっていった。
✳︎
殴りつけるような雨に最低限当たらないようにタクシーから降りると、マンションへと駆け込んだ。
家へと入るとすぐに、そのままの姿でパソコン内を確認する。すると、江莉からのメールが届いている事に気が付いた。
》先程はありがとうございました。
レストランにスマホをお忘れではないでしょうか?
さっきまで張り詰めていた心配の糸が緩んで、安堵に変わった。胸をなで下ろすようにネクタイを外しながら、脱いだ上着をハンガーに掛けて、パソコンの前に座った。
〝すぐに取りに戻る。〟
返信しようとして、それをやめた。
また江莉に会わなくてはいけないと思うと、億劫にも感じて、動く気分にはなれなかった。
外の大粒の雨が窓を濡らすほどに叩きつけてきているのも、外へ出る事を阻んだ。
キヨミからの返信がきていないか気にはなるが、その前にちゃんと父に自分の気持ちをしっかりと伝えなければならなかった。
でないと、キミに会わせる顔などないのだから。
堂々とキミのことを迎えに行きたい。
そのために、全てを捨てる覚悟さえ決めていた。
江莉へのメールの返信に、
》ありがとうございます。明日出勤前に寄ります。
手短に送って、パソコンを閉じた。
────
次の日、昨日降り続いた雨のせいでまだ所々水溜りの残る歩道を眺めながら、青空に太陽が覗くその下で僕はタクシーを待っていた。朝早くに昨日のレストランへとスマホを取りに向かう為だった。
やってきたタクシーに乗り込み、場所を伝えると、たまに渋滞に巻き込まれながらも目的地までたどり着き、そこに降り立った。
奥田ビルディングは想像以上に見上げなければならないほど高いビルな事を知った。
ここへは、夜に来ることの方が多かったからだ。ビルを見上げることなど今までなかった。その圧倒的存在感を放つ建物に、江莉同様の威圧感を覚えつつ、重たい足取りで中へと踏み込んで行った。
朝早いため、直接レストランへと向かうのは避けて、広いロビーの受付で事情を話す事にした。すると、受付でスマホは管理されていたらしく、すぐにスマホは僕の手元に戻ってきた。
江莉に会わずに用が済んだ。
思わず安堵してしまう。
取り急いで、僕はその場ですぐに父へと電話をかけた。
「お忙しいところ申し訳ありませんが、聞いてほしいことがあります。お時間いただけないでしょうか」
『なんだ、改まって。今日の私は珍しく空いているぞ。いつでも来なさい』
「ありがとうございます。では、後程伺います」
通話を終了させて、奥田ビルディングを後にした。このビルのどこかで見下ろしているであろう江莉の事を思うと、申し訳ない気持ちで頭を下げた。
あなたの気持ちには、僕は応えてあげることは出来ない。
何度断っても諦めの悪い江莉には、もう伝えることすら諦めた。これからは誘いにも応えないと、一人心に決めて、僕は歩き出した。
自身の会社へ入ると、すれ違う社員に挨拶をされる。それに一人一人応えて前へと進んだ。エレベーターに乗り、目指す階は最上階一つ下のフロア。
フロア内の社長室の前で足を止めた。緊張する胸に手を当てて目を瞑り、息を深く吸い込んだ。ゆっくりと吐き出すと、ドアノブに手をかける。
「失礼します」
重厚なドアは少し重たく感じた。中に、自身の父が寛ぐようにしてソファーに腰掛けている姿が目に入ってくる。手には本が一冊。どうやら読書をしていたらしい。
すぐにこちらに気がつくと、視線を本からこちらに向けてくれた。
「思ったより早かったな」
「すみません、読書中に」
「構わない、もう何度も読んだ本だ。内容は完全に入っている」
そう言って指でこめかみ辺りをトントンと指し示すと、にこやかに笑う父。本を閉じるとテーブルに置いて、ソファーに掛けるようにと手を差し伸べた。
それに従って、僕はソファーまで行くと「失礼します」と言ってから座った。
「前から思っていた事ですが、僕はこれまであなたを目標として日々努力をしてきたつもりです。越えようなんて思っていない、ただ、あなたに認めてもらいたくて、ここまでついて来ました。だけど、やっぱり自分の気持ちを押さえつけてまで、会社の利益を考えることは出来ませんでした。本当に、申し訳ありません」
優志は立ち上がると、深く深く頭を下げた。
「僕には、キヨミしか愛せません。会社を継ぐ事を目標としてきましたが、ここで、辞退させていただきたいと思って伺いました」
全て言い切ってから、僕はゆっくりと顔を上げた。
どんなに怒鳴られるだろうか、呆れられるだろうか、昨日の夜は考えると眠れなかった。
覚悟はできていた。
どんな罵倒を浴びせられようとも、絶対にこの思いを貫き通す覚悟を決めて、今日ここへ来たんだ。
「そうか、ははははっ」
目の前の父の顔は、想像していたものとは全く違った。
笑っている顔に、怒りも呆れも見当たらない。むしろ、優しく微笑んでいるように見えてくる。
唖然として立ち尽くす僕に、父が立ち上がって近づいてきたと思ったら、大きな手で頭を撫でられていた。
不意の出来事に混乱していると、乱れた前髪から、父のより一層笑った笑顔が目に飛び込んできた。
「お前は優秀だよ、会社からは追い出せるわけがない。どうしてそんな所まで似てしまうんだろうな。自分の愛する女性を一番に考えるのは、当たり前だ、心配するな。そこまで私はお前を縛る気などない」
張り詰めていた糸が緩んで、胸の奥から湧き上げてくるものに、逆らうことなど出来なかった。
溢れ出す涙は涙腺を超え、一気に目の縁に溜まった。ぼやける視界の中、父がソファーに座り直すのが、ぼんやりと見えた。
「私からも聞いて欲しい事がある。優志、お前に、会社を一つ任せたいんだ。頼まれてくれるか?」
もう、目の前は海で、完全に父の顔など見えてはいなかった。
まばたきと共に頬を伝った涙が流れた瞬間、手を差し伸べて握手を求める父の姿が、ハッキリと見えた。
もう、迷うことなど何もなかった。
次から次へと流れ出す涙を手の甲で拭っては、何度も頷いて頭を下げた。
「もちろんです、有り難うございます」
父の大きくて力強い手を握り、固い握手を交わす。止まらずに泣き続ける僕に、「何だ、泣き虫は母さん譲りだな」父はそう言って、また嬉しそうに笑った。
初めから読む方はこちらから
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

