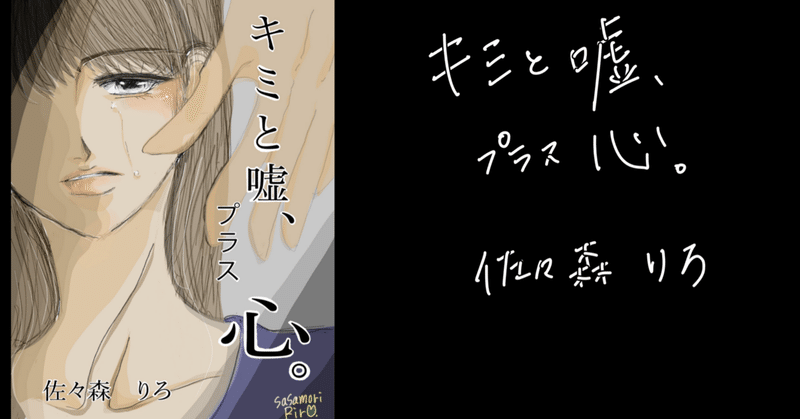
キミと嘘、プラス心。6
第六章 姉と弟
────東京
奥田ビルディング。
広いロビーに出勤してくる社員が次から次へと流れ込んで来る。高く開放感溢れるロビーの真ん中には、噴水が涼しげに水しぶきをあげていた。
一際響くヒール音と共に、スッと姿勢を正して凛として歩く江莉の姿。周りの社員たちは一斉に頭を下げて挨拶をする。
江莉は気品がありながらも親しみやすく、仕事の明確さ、正確さを持ち合わせているからと、会社の中ではどの世代からも絶大的に慕われていた。
「おはようございます。昨日頼まれた資料をまとめてデータ送っておきました。確認お願いします」
「おはよう、有り難う。いつも仕事が早くてとても助かってるわ」
「はい、有り難うございます。よろしくお願いします」
にこりと上辺だけにしか見えない笑顔を貼り付けた江莉に、素直に喜び頭を下げた。コツコツと江莉は自分の席へと歩いて行く。
「今日もお綺麗だねー。江莉さん」
後ろ姿を見送っていると、近づいて来て馴れ馴れしく肩を組むのは、同期の橋本。
「そーだな」
組まれた肩から橋本の腕をよけて、俺は歩き出す。
「あれ? 全然興味ない感じ?」
「なんの? 出来る上司ってだけだろ」
「あ、そ。まぁ、江莉さんは高嶺の花過ぎるからな、俺も狙わんけど。それよりさ、永田って彼女いんだっけ?」
デスクまでついて来ながら橋本に言われて、荷物を置きつつニヤけるその顔に目を細めて呆れるように「いない」と、一言返す。
「なんで彼女作んねーの? 飲み会でもいつも途中で帰っちゃうし。今夜の飲み会さ……」
「要らないから」
まだ話している橋本に一喝入れるように低い声で一言放つと、席に座る事なく荷物だけを置いてそこから離れた。
誰もいない休憩室で、一人窓から外を見下ろした。地上から遠く離れた下に見える人の影はとても小さくて、車もミニカーの様に見える。自販機で買った冷たいお茶を飲むと、喉がひんやりと涼む。思わずため息が溢れた。
──なんで彼女作んねーの?
橋本に言われた言葉に、姉、キヨミの姿を思い浮かべた。
今まで彼女がいなかったわけではない。何人かと付き合ったこともあったし、本気で愛そうと思って接してきた事もある。
だけど……最期に見た、嬉しそうな、でも、どこか儚げな笑顔が忘れられない。
せっかく、うちに戻って来てくれたのに、一瞬にしてまた何も言わずに俺の前から消えてしまった。
どうして、死んでしまったんだ……姉ちゃん。
まだ、俺は何も伝えていなかったのに。
伝えるつもりなんて元々なかったけれど、こうなると分かっていたら、なんと思われてもいい、伝えておきたかった。
俺は、姉ちゃんの事が、ずっと好きだったって……
涙腺が熱くなり、抑えきれなくなる。
だけど、こんな所で泣いてはいられないと、お茶を勢いよく飲み干すことでグッと我慢した。
もう何度抑え込んでいるだろう。誰にも打ち明けられず、悲しみの涙も両親を思うと自分まで泣いていてはいけない気がして我慢をして、この溜め込んだ悲しみが、いつか破裂してしまわないかと少し、自分が怖くなる。
だけど、この想いはもう自分の中で完結させなければならない。伝えて楽になれる相手は、もうこの世にはいないのだから。
だったら、姉をあんな風にした沖野優志と〝おくだえり〟を探して、姉の死を、俺の気持ちを、全部吐き出してやりたい。
どうしたって、そうでもしないと、俺はきっとおかしくなってしまいそうなんだ。
「あら、あなたは今朝の」
額に手を当てて俯いていると、聞き慣れた声が聞こえてきて顔を上げた。すぐ先に、自販機にカードを当てながらこちらを見ている江莉さんの姿があった。
「永田くん、だったかしら?」
ガコンッと落ちたブラックコーヒーの缶を手に取り、江莉さんは微笑む。
「……はい」
「どこか気分でも悪いの?」
「え、あ、いえ。大丈夫です」
心配されたことに驚いて、慌てて誤魔化すように笑った。
「話して何か楽になるのなら、私が聞いてあげるけど、本当に大丈夫?」
コーヒーの缶をテーブルに置いて、江莉さんは目の前に座った。
この人は、優しい言葉を話しながらも、どこか目の奥は冷たさを感じる。入社した時から感じていた。それが謎めいた美しさに拍車をかけている、などと橋本はいつも豪語しているが、俺にはその意味が分からない。
見た目だけで言えば、綺麗な事は確実に言えるが、その中にまで興味がない。
しかし、もしもこの人が姉の言う〝おくだえり〟だとしたら、俺の興味は一気にこの人に集中してしまうんだろう。今は、そうではない事を信じたい。
「最近……仲の良かった姉が事故で亡くなったんです。その悲しみが、まだ癒えていないだけです。完全に私情なので、ご心配には及びません」
江莉さんは「そう」と言ったきりだった。「失礼します」と頭を下げてから、俺は立ち上がった。コーヒーの缶を開けた音だけが後ろから聞こえた。
入れ違いに入ってきた女性社員が江莉さんの近くまで行き、話しかけているのが振り返った時に目に入った。
そして、次の瞬間、その女が発した名前を、俺は聞き逃す事はなかった。
「江莉さん、今朝、沖野優志様がいらっしゃってスマートフォンを確実にお返ししました」
「そう、ありがとう。助かったわ。優志さんは何か言っていなかった?」
「いいえ、特には何も。お会いしなくて良かったのですか?」
「良いのよ。あれを返すだけだもの。またいつでも食事に誘えばいいだけの話」
笑っているように聞こえる江莉さんの声。
「素敵なおふたり、憧れます。では、失礼します」
そう言って頭を下げた女性社員がこちらに向かって歩いてくるから、さっと道を譲って江莉さんの様子を眺めた。
先ほど買った手をつけていないコーヒーの缶を、そのままゴミ箱へと捨てて反対方向へと行ってしまった後ろ姿を見つめた。
受付の女性社員と待ち合わせる為にここへ来たのか。じゃなきゃ、あの人がこんな場所に現れたりなんかしない。孝弥は握りしめた拳に力を込めた。
今しがた会話の中に出てきた、〝沖野優志〟と言う名前で、確実に姉の言う〝おくだえり〟が、奥田江莉であることを確信した。
やっぱり、俺の思うあの人は、橋本が言うような容姿端麗な上司というだけでは収まらない。
きっと、あの二人と何かがあって、姉はあんな事になってしまったんだ。
だとしたら、俺は、奥田江莉を、沖野優志を、許さない────
────
『……お姉ちゃん?』
『そうよ。孝弥にお姉ちゃんが出来るの。仲良くしてね』
『ほんとう⁉︎ 俺に、おねえちゃんが出来るの? イエイッ! うれしいなーっ!』
幼稚園を卒園する頃、母と二人で暮らしてきていた俺は母にそう言われてとても喜んだ。
父は生まれた時から居なかった。その存在の意味も分からなかった。そんな俺に、突然父と姉が一気に出来て、一緒に暮らすようになった。
『孝弥くん、はじめまして。今日から、君の父親になります。そして、君のお姉さんになるキヨミだよ。宜しくお願いします』
『よろしくお願いします』
父となる人は優しそうな目尻の下がった目をしていて、その隣に立っていた三歳年上のキヨミは、幼稚園で見る女の子達とは全然違う大人な雰囲気をした、やっぱり父と同じように優しく笑う女の子だった。
姉ちゃんはあまり喋らない大人しい性格だった。
父も母も共に働いていて、小学生になってさらにやんちゃになった俺の話を、姉ちゃんはいつでも頷いてただ静かに聞いてくれた。
忙しく働く母には気を使って今まであまりたくさん話をしたりしてこなかった。話を聞いてくれる、そばにいてくれる、そんな姉ちゃんの存在が、俺にはすごく嬉しかった。
『今日さ、こはるちゃんに好きって言われた』
小学校二年生の頃、そんな話をしたことがあった。
『孝弥も、その子の事が好きなの?』
『え? んー、たぶん好きじゃない。だって、俺は姉ちゃんが好きなんだもん』
『え……』
『俺、姉ちゃんが来てから毎日すっごく楽しい。俺の話は聞いてくれるし、ただいまもおかえりも言ってもらえるし、みんなからはキレイな姉ちゃんだって、うらやましがられる。俺は、姉ちゃんがいっちばん大好きだ、けっこんしてもいい』
ああ、あの時気持ち伝えてたんだなぁ。素直で幼かった俺。頭の中の記憶を辿って胸が締め付けられる。
『孝弥、ありがとう。でもね、きょうだいは結婚出来ないのよ。きっと、孝弥にはあたしよりも素敵なお嫁さんが現れるわ。いつか、その時は紹介してね』
『えー、そーなのか? なんだよー、ちぇー』
あの時は、そんな姉ちゃんの言葉をそのまままっすぐに受け止めて、結婚出来ないことにしばらく拗ねていた気がする。
俺が、姉ちゃんをまた意識し始めたのは最近だった。中学も高校も、長続きはしなかったけれど彼女はいたし、やる事もやってきた。だけど、どの子を取ってみても、俺の心の中は埋まらなくて。いつも頭の中に浮かび上がるのは、姉ちゃんの顔だった。
兄弟なのに、そんなのは可笑しいと否定し続けていた。
そんな矢先に、姉ちゃんは東京へ行くと言い出した。
『高校を卒業したら、東京へ行こうと思うの。やりたい事が見つかったわけじゃないんだけど、何かやるなら、ここにいるよりも選択肢が広がる気がするし』
初めて、姉が自分の意見をハッキリと親に伝えた様な気がした。
驚いたのは、俺だけじゃなかった。
もちろん父も母も一瞬は引き止めようとした。だけど、意思の強い眼差しに引き止める権利なんて微塵もないと、東京へ出る事を許した。
姉に会えなくなった俺は、高校に入学すると確信を経て姉の存在の大きさを知った。
大好きだった。
本当の兄弟じゃないんだから、愛したってなんの問題もないはずだ。
そう考えるようになって、勉強をひたすら頑張り、大学も初めから東京を希望した。
姉が久しぶりに帰ってきたのは、大学受験の発表を終えたばかりの頃だった。
『孝弥、大学合格おめでとう』
変わらない笑顔で帰ってきた姉に、思わず抱きしめたい衝動を拳を握って堪えて、笑った。
『向こうで知り合った人と、今暮らしているの。とっても素敵な人よ』
それは、初めて見た幸せそうな顔で笑う姉の姿だった。
沖野優志の事を話す姉は、いつのどの時にも敵わないほどに幸せそうだった。
多くは語らないけれど、一つ一つの言葉が大切そうで愛おしそうだった。なによりも、笑顔が幸せそうで仕方がなくて、俺は姉への気持ちを二人が幸せになるのならばと、心の奥深くへと蓋をすることにした。二人のことを応援したい。その一心で。
今度は、俺が姉の幸せな話を聞いてあげたい、それが、俺が唯一、姉にしてあげられることだと思ったから。
父や母にはなかなか言い出せずにいる姉に、俺は何故なのか訪ねたことがあった。
すると、相手の男は大企業の息子らしく、節目の年でもあり、仕事に集中したくて姉との結婚はまだ視野に入れていないと言っていた。
なんとも真面目な人だな、と、その時はただ素直に感じた。
姉もそれを受け入れているらしく、二人がそれでいいのなら、と、納得するしかなかった。
早く結婚して子供でも出来れば、姉を諦める事も出来るのに。そう葛藤はあったけれど、幸せそうな笑顔を急かすことなど俺には出来なかった。
だけど、そのすぐ後くらいからだった気がする。徐々に姉ちゃんの顔に、笑顔が消えていったのは。
久しぶりに帰ってきた姉を見て、父はすぐになにかを察した。
『キヨミ、一回こっちに帰っておいで。なんだかやつれたようだし』
『ううん。あたし、もう、こっちには帰って来ないと思って……だから今日は、最後に』
『なにを言っているんだ。そんな顔をして。父さんも母さんも心配なんだ。お願いだ、もうそんな東京の男とは縁を切って、戻ってきなさい』
『優志さんを悪く言わないで! あたしは決めたの! もう戻らない!』
『……勝手にしなさい‼︎ 私は、娘をそんな風にやつれさせるような男は絶対に認めないからな!』
心配が、最後には結局姉を追い出すような口ぶりになってしまって、父は出て行ってしまった姉を追いかける事も出来ずに頭を抱えていた。
母だって同じだった。実の子ではない姉とは友達のように過ごしてきていたけれど、実際には多くを語らない姉の事を、不思議な子だといつもなかなか打ち解けられない事を父に相談していたんだ。
結局、姉の心の内を知るのは、沖野優志という男だけなのかもしれない。
そう思うと、許せない気持ちを持ちつつも、姉が愛した男がどんな人間なのか、知りたくなってしまう。
しかし、江莉さんに聞くことは不安があるし、俺と姉が兄弟だと知られる事に何か抵抗がある。直接本人とは会えないだろうか。
沖野グループは親しくしている企業でもあるが、この広い会社の中で偶然出会うのも難しいだろう。何か仕事を通して……
「永田、なにそんな思い詰めた顔してんの?」
デスクに戻ってパソコンとにらめっこしていた俺の頭上に、ポンっと小さな紙袋を乗せながら、橋本が横から顔を覗き込んでくる。
ああ、もう昼か。
壁にかけられた時計に目を向けて、時間があっという間に流れていた事に気がついた。パソコンの中の仕事はほとんど進んでいない。思い詰め過ぎていたらしい。
頭上から降りてきた袋を受け取ると、「もらう」と言ってから、開け口を破って中身を取り出した。強く掴んだら一瞬でぺちゃんこになってしまいそうな、ふわふわの一口大シフォンケーキを、口に放った。
「美味っ」
「でしょ? もともとシフォンケーキは絶品なんだけど、簡単に食べられるように一口にしてもらった」
「……してもらった?」
「flavorfulの店長俺の仲良い先輩だから、商品提案したんだよ。間違いなく売れるだろ、これ!」
「ああ、flavorfulのか。美味いわけだ」
昨日詩乃が持って来たチキンサラダとサクサクイカフリッターは間違いなく美味かった。
「あ、そんでコレ。沖野グループへ出向いて渡してきて欲しいらしいんだけど、永田飲み会行かないでしょ? そのシフォンケーキで頼まれてくんない?」
手を顔の前で合わせて片目を開けてこちらの様子を伺う橋本の言葉に、俺は耳を疑った。
「は? 今なんて……」
「そこをなんとかさー、あそこまで行ってると待ち合わせの飲み屋まで遠くなんだわー。頼むよ永田ぁ」
縋り付く橋本を剥がしつつ、俺はもう一度聞いた。
「どこへ持って行くって?」
「だから、沖野グループの沖野ビルだよ。ちょっと遠い? 無理? マジ、無理なの?」
とうとう泣き付いて来た橋本に、されるがままの俺は橋本が持っていた茶封筒を手に取った。
「行く、ありがとう橋本」
「へ? まじ? ってか、ありがとうは俺の方でしょ」
すんなりと引き受けた俺に呆気にとられながらも、橋本は上機嫌で去って行った。
なんだよこのチャンス。
今まで沖野グループとは全然関わった事がなかったのに、ちょっと流れが良過ぎないか?
ねぇちゃんが、俺を沖野優志と引き合わそうとしているとか? まさかな。でも、これで近づける事は確実だ。仕事にあんまり責任感のない橋本に、今は感謝だ。
前回までの話はこちらから↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

