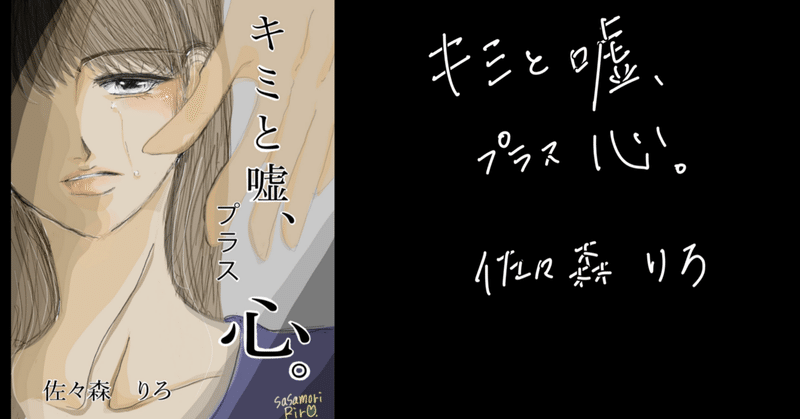
キミと嘘、プラス心。8
第八章 関わり
「じゃあ頼むな永田、彼女ほしくなったらいつでも言って、すぐに紹介するからっ。お疲れーっ」
帰る支度をして、いの一番に出て行く橋本を見送って、俺は手にした茶封筒を見つめる。
一体、何が入っているんだろう?
茶封筒に入れて持って来いって、よっぽど緊急に必要なものってことだろ? データとかじゃ送れないのか? データに残ると……困るものなのか?
目の前の封筒を見つめながら、色々と考えてしまう。
〝おくだえり〟が〝奥田江莉〟だった事で、どうしたって姉の事が関わっていたりしないか、気になってしまう。
いや、これは仕事だ。私情は関係ない。
この茶封筒の中身は、単なる奥田グループが沖野グループとの何かしらの仕事の書類が入っているだけで、何も関係は無いはずだ。
今は、沖野優志とこれがキッカケで話が出来ればいい。
あの夜、笑顔で出て行ったはずの姉が、どうしてあんな自殺のような事故を起こしてしまったのか、真実を話してほしい。
荷物と上着を手に、足早に沖野ビルへと向かった。
電車に揺られて着いた先のビルの前。一度、落ち着くために胸に手を当てて深呼吸をした。
ネクタイの緩みを直すと、颯爽とビルの中へと足を踏み入れる。
自身の会社よりもシンプルな内装に少し緊張しつつ、どこへ向かえば良いのか、誰にこれを渡せばいいのか、今になって橋本に聞くことを忘れていたことに焦り出した。
自動ドアを潜り抜けたは良いけれど、それ以上進めずにあたふたとしてしまっていると、後ろから声がかかった。
「どうされました?」
優しいトーンの男性の声に、俺は振り返る。
「何かお困りですか?」
「あ、お世話になっております。私奥田グループの永田孝弥と申します。あの、これを届けるように頼まれて来まして……」
深くお辞儀をし、挨拶をしてから持っていた茶封筒をその人に差し出した。
「……僕に、ですか?」
「あ、えっと。申し訳ありません、どこのどなたへ渡せば良いのか聞きそびれてしまいまして……」
「おや、じゃあそれは、自分の仕事を放棄して君に任せた誰かの責任だ。謝ることはない」
「え……あ、いえ。引き受けたからには、もう私の責任です」
「君、永田さんって言いましたか?」
茶封筒を静かに受け取り、優しく微笑むその人に、瞬時に姉の笑顔が浮かんだ。
「……もしかして、沖野、優志さん……ですか?」
質問されているというのに、こちらも質問で返してしまった。ハッとして崩れかけていた姿勢をピシッと真っ直ぐに伸ばすと、ずっと姿勢良く目の前にいた笑顔の男が頷くのを、しっかりと確認した。
この人が、沖野優志。姉の愛した、男。
「君は、もしかして……」
冷静だった表情が一気に崩れていくのを見て、確信する。
「はい。永田キヨミの弟です。あなたに会いたいと思って、今日ここへ来ました」
ビルの静かなロビーで、俺は偶然にも沖野優志と会うことが出来た。
「立ち話では申し訳ないので、良かったら外にでも出ませんか」
そう言って微笑むと、受付の女性に声を掛けに行き、最低限の荷物を持って戻ってくる。
「行きましょうか」と言われて、一緒に外へと出た。
「キヨミとの行きつけの店があるんですが、そこでも構わないですか?」
笑顔でそう言ってくる沖野さんに、俺は戸惑いつつ頷いた。
何も言葉を発しないのは、沖野さんがさっきから終始笑顔でいるからだ。俺が弟だと知った瞬間に、仕事用の顔とはまた違う柔らかい表情を向けてくれている気がする。
姉の事故死から時間は経っているが、もう立ち直ったと言うことだろうか? それとも、姉が死んだことなど別にどうでも良いのだろうか? いや、あの顔はどちらでもないような気がする。
なんとなく、嫌な予感を拭えない。足取りが重たくなるのを感じながら、沖野さんの後をゆっくりとついて行った。
着いた先は、賑やかな通りから一本路地に入った落ち着いた雰囲気のお店が並ぶ中の一つ。
カラカラと音を鳴らす引き戸を開けて暖簾をくぐると、こじんまりとした店内にはすでにお客がたくさんいて、賑やかだ。
「お、優志くんじゃないか。久しぶりだな、今日は美人の彼女と一緒じゃないのかい?」
すぐに声を掛けて来たのはこの店の店主だろう。沖野さんが陽気な店主に挨拶をすると、店の奥の方を見ながら、「関さん、いつもの部屋良いですか?」と、聞いている。
店主の関さんはすぐに頷いて、いつもの部屋という場所へと案内してくれた。
表の賑やかさから一変して、奥の部屋は狭いながらも静かで雰囲気のある和風の個室になっていた。一室へと通されると、腰をおろした沖野さんを確認してから、向かい合うように腰を低くしながら座った。
「キヨミに弟がいる事は聞いていたけど、こんなに近くに居たなんて驚いたよ」
沖野さんは出されていたおしぼりを手にとり、拭きながら笑った。
「……俺……あ、私のことを姉から、聞いていたんですか?」
話してくれていたんだ、俺の存在を。
心の奥の方がじんわりとあたたかくなった。
「小さい頃から元気で素直で、優しい弟がいるって。僕が嫉妬するくらいに、いつも君のことを自慢げに話しているよ、キヨミは。あ、こんな事言ったら怒られるな、きっと。今のは内緒にしておいてくれないか」
苦笑いして、沖野さんは眉を下げつつも嬉しそうに微笑む。
この人は、本当に知らないのか?
目の前の優しい笑顔に、どうしても疑問を持ってしまう。
「キヨミは、元気にしていますか?」
一気に、血の気が引くような寒さが体を駆け巡った。沖野さんのその一言で、俺の疑問が確信に変わる。
「もう、僕の事など忘れてしまったかな、連絡をしてもなかなか通じなくて。僕が優柔不断だった為に、キヨミには辛い思いをさせてしまった。でも、もう全て解決したんだ。もう、僕はキヨミを堂々と受け入れられる事が出来るようになったんだ。だから、君からも伝えてくれないかな、僕が連絡を待っていると」
申し訳なさそうに、しかし真っ直ぐな目で真面目に伝えてくれる言葉に、目の前が真っ白になった。遠くなりかけた意識を懸命に戻した。ガクガクと震えだした顎に、冷や汗が止まらない。
そんな俺の姿に、沖野さんが手を差し伸べる。
「大丈夫ですか?」
ハッとして、胸ポケットから取り出したハンカチで汗を拭った。
「……あ、すみません。姉の彼氏がこんな凄い人だなんて、緊張してしまって……」
俯いたままそう言って、顎を伝って流れた汗をもう一度ハンカチで抑えた。
「いえっ、凄い事なんてなにもないですよ。僕なんて本当に……キヨミに何もしてあげられなくて。だから、早く今まで我慢してきた事全部、キヨミのやりたい事、全部叶えてあげたいんです」
なんの曇りもなく、ただただ澄んだ水の様に綺麗で、穢れのない沖野さんの言葉。膝の上で握りしめていた手に、ますます力を込めて握った。この人に、伝えるべきか。
姉の死に一番に関わっていると思っていた男が、目の前でこんなにも潔白で優しく笑っているというのに、そんな残酷なことを言えるだろうか。
俯いてしばらく、そんな事を考えていた。
知らない方が幸せなことだって、あるのかもしれない。
俺は沖野さんに向かって、うまく笑えているだろうか。
「言っておきますから、任せてください」
そんな俺の苦渋の言葉に、沖野さんは欲しかったものが目の前に差し出された子供の様に、無邪気な笑顔を見せた。
沖野さんとの食事はほとんどが姉の惚気とも言える話が延々と続いた。
正直聞きたくないこともあったけれど、それは仕方がないことで、お酒も勧められて飲んだが、全然酔うことなどできなかった。
「キヨミに、早く会いたい」
切実に、そう溢した沖野さんの一言だけが、耳から離れずにいる。
帰りの電車の中で、何度もその言葉が頭の中をリフレインする。
暗くなった外を眺めて、窓に映る自分の情けなく眉を下げた顔にますます気分が落ち込んだ。
──言っておきますから、任せてください──
「……なにが、任せてください、だ」
ポツリと呟いて、電車はホームへと到着する。ちょうど開いたドアから、人の流れに身をまかせる様に電車から降りた。
結局、あの人からは何も事故に関することは聞き出すことが出来なかった。
それどころか、俺は姉ちゃんが死んでしまった事を伝え損ねた。
……と、言うよりも、言えなかったんだ。
だってそうだろう?
あんな風に嬉しそうに、愛おしそうに姉ちゃんのことを話す男が、姉ちゃんを追い詰めるくらいに酷いことをしたのか?
あの笑顔の裏には、黒い何かを隠しているのか?
いや、それはない。あの人は姉ちゃんのことを心から愛していると感じた。
だったら、どうして側に居てやらなかったんだ?
あの日出て行った時の笑顔は、あの人に会うためにと、喜んでいた笑顔じゃなかったのか?
疑問ばかりが頭の中を駆け巡る。
重たくなっていく頭を片手で押さえて、足取りもゆっくりと歩いていると、胸ポケットに入れていたスマホが震えだした。
着信は〝モヨ〟
「はい」
『あ、孝弥? お疲れ様ーっ、今大丈夫?』
相変わらずの元気いっぱいなモヨの声に、淀んでいた頭の中が少しだけ晴れていくのを感じる。
「ああ、大丈夫だよ」
『あのね、ちょっと急なんだけど、明日詩乃とそっちに行くから、孝弥のとこにお邪魔してもいいかなと思って』
「……え? お邪魔って、俺のうちに来るってことか?」
『そうそう。急遽だったから泊まるとこ探すまで置いてもらえないかなぁって思ったんだけど、大丈夫?』
本当に急な話だ。どうしたものかと、しばらく黙り込んでしまう。
『やっぱ駄目か。急すぎるよね、ごめん。そしたらさ、ちょっとだけでも話せない? キヨミさんのことで話したい事があるの』
モヨから出た姉の名前に、歩みを止めた。
街路樹が風に一瞬だけ強く揺れて、ザワザワと生い茂った緑が何か不安な感じを思わせた。
生ぬるい風に、口元をキュッと締めると、眉を寄せて目を閉じた。
沖野優志と偶然にも会えて話ができた事、モヨから姉の名が出た事、全て、何かが繋がっている様な気がしてきてならなかった。
思わず震える口元に手を当てながら、俺は聞いた。
「モヨは、ねぇちゃんの何かを……知ってるのか?」
スマホの向こう側が、急に静かになった。
俺の質問に、今度はモヨが黙り込んでしまって、しばらくの沈黙の後。
『会ったら話すから』
消えそうな声でモヨが答えるから、締め付けられ続ける胸に手を当てた。真っ黒な空を見上げて、ため息をついた。
周りの煌びやかな街灯で星など一つも見えやしない。だけど、なにか、たどり着くことの出来ない迷宮の中で、一点だけの出口が遠くに見えるような、そんな予感がして、頷いた。
「明日、何時に来るんだ? 仕事の合間でも終わってからでもいい。話が聞きたい」
『お昼には着くように行く。どこかで食べながらでも』
モヨから提案されて、通話は終了した。
たとえ、何が真実だったとしても、ねぇちゃんが死んでしまったのは事実だ。もう戻っては来てくれない。もう、会いたくても、会えないんだ
──キヨミに、早く会いたい──
沖野さんの切願する想いを思い返すと、自分と同じ気持ちである事を感じてしまって、胸から込み上げてくる感情がツーンっと喉と涙腺を刺激する。
なんであんたは、何も知らない?
こんなに悲しくて、辛くて、悔しくて。
大好きだった。
きっと、全てを知ってしまったら、あんたの笑顔もぐちゃぐちゃになってしまうんだろう。
「俺だって、もう我慢の限界だ」
小さく呟いて、フラフラと帰路に着く。
悲しみを溜め込みすぎていた。
伝えたくても伝えてはいけないと、自分の気持ちに蓋をし続けていたからだ。
こんなに涙が出てくるのは、大好きな姉の死に関わっている人間がすぐそばに何人もいたのに、どうしてそれに気がついてやれなかったんだと思ったから。
沖野優志だけを責めることは出来ない。
明日、モヨがどんな話をしてくるのかなんて、想像もつかない。
ただ、少しずつ、事故への真相へ近付いている。そんな気がしてならない。
前回までの話はこちらから↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

