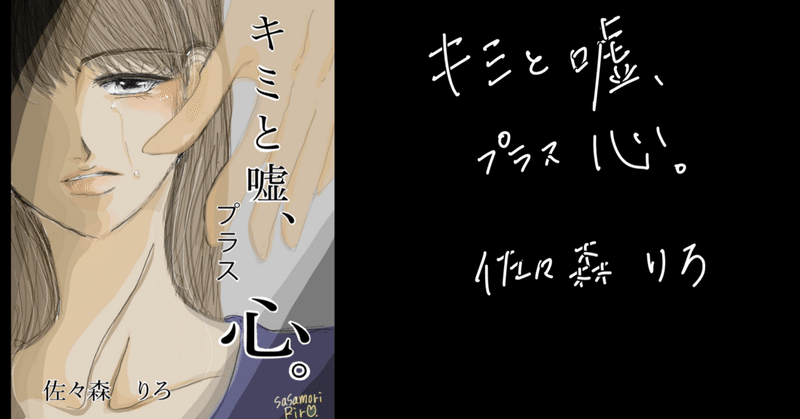
キミと嘘、プラス心。10
第十章 偽り
孝弥の表情が不安の色一色に変わるのを確認して、胸の中がキリキリと痛んだ。だけど、ここまできてしまったら、これはあたしにも責任がある気がしてならなくて。ずっとずっと、悩み抱えてきていた。
一生黙ったまま過ごすのもありだった。
知らないふりをしていれば、高校時代の友人となんて、関わり合おうとしない限りまた仲良くなんてなることはない。
あたしが今繋がっているのは、詩乃と孝弥くらいだ。それだって、自ら連絡を取ったからこうしてまた懐かしい話をできるわけで。
もう奥田の人間ではないと公言はしていても、繋がりは完全には取り払えないし、どうしたってあたしはあの二人から産まれた子供だし、姉は奥田江莉しかいない。憎いし縁だって切りたいのは本当なんだ。
けれど、生まれてこなきゃよかったなんて、思いたくない。
あたしはあたしが好きだし、目指したいこともある。だけど、いつだって邪魔をするのは、そもそもの生まれた環境が付いてくること。
だから、あたしはその事実からは逃げてはいけない。知らないふりなんて、してはいけない。孝弥を救う為だなんて、カッコいい理由で動くんじゃない。あたしという人間が見てきたものを伝えて、それが間違っていることだと、同じように共感してもらいたいだけなのかもしれない。
そんな共感が出来たとしても、それは虚しいだけなのだけれど。言わずには、いられない。
「あたしが喫茶店〝鈴蘭〟を見つけたのは、キヨミさんがきっかけだった」
手元のカップに手を添えて、通りを走り去る車の列を瞳に写しながら、あたしはあの頃を思い出す。
学校からの帰り道、まだ知らない町のことを知りたくて歩き回っていた時に、手にしていたオーディションの落選の文字が書かれた通知を落としてしまった。キヨミさんはそれを拾い上げて、申し訳なさそうに返してくれたんだ。
別に、あたしはどうでもよかった。落ちるのが当たり前だと思って毎回受けていたから。だけどキヨミさんは、あたしに用紙を差し出しながら、笑顔をくれたんだ。「頑張ってね」って。
細くて色白な指先から用紙を受け取った時に、キヨミさんは綺麗だけど、どこか寂しそうな表情をしているような気がした。
「ずっと自分との戦いだったし、誰かに応援してもらったことなんてなくて。オーディションに挑む時はいつだって孤独でいた。誰かに褒めてもらいたいとか、慰めてもらいたいとか、そんなことは思ったこともなかった。だから、あたしにとって、キヨミさんの言葉がすごく胸に響いてしまって、気が付いたら泣いてしまっていた」
そんなあたしに驚いたキヨミさんは、すぐ近くにあった喫茶店『鈴蘭』へと誘ってくれた。不思議と、初めて会った人なのに警戒心はなかった。
『コーヒーは飲める?』と聞かれて、首を振ると、優しく微笑んだキヨミさんはマスターに『紅茶でお願いします』と注文した。
誰も他にお客さんはいなくて、耳を澄まさないと聞こえないくらいに静かな音でクラシック音楽が流れていた。
『オーディションは東京なの?』
『……え、あ、はい』
『そう。また東京へ行くことはある?』
『……出来れば行きたくはないのですが、オーディションを受けるためには行きます。あたしの夢なので』
ブラックのままコーヒーカップを持ち上げて飲むキヨミさんの姿が、なんだかとても大人の女性に見えた。歳上の女性は姉のような大人とばかりしか関わりがなかったから、キヨミさんの存在もこの人だって姉と同じなんだろうと、初めはどこか冷めた目で見てしまっていた。
『私ね、今東京に住んでいるの。ちょっと用事があって帰ってきたんだけれど、もしも向こうで会えることがあれば、嬉しいな』
『……え、あー……はい』
あまりにも淡白なあたしの返事に、目の前でキヨミさんはおかしそうに笑ってくれるから、なんだかその笑顔に安心してしまった。
「気が付いたら、初めてあたしは自分の心のうちを、笑いながら話せていた。キヨミさんに聞いてもらったことで、心の中がすごく、軽くなったんだ。だから、あたしは東京へ行く決心をした」
そこまで話し終えると、「お飲み物のおかわりはいかがですか?」と店員さんが来てくれて、それぞれ頂いた。
「と、ここまではあたしの話。ここからは、キヨミさんと優志さん、そして……」
たっぷりと注がれた紅茶のカップを持つ手が震える。本当のことを話すのが、やっぱり怖い。あの名前をこの口から発することを拒絶するように、胸焼けを起こしたみたいに吐き気が込み上げてくる。
知らないうちに伝っていた冷や汗が額から流れ落ちる。そっと、孝弥があたしの手に触れた。
「……モヨ、そんなに苦しいのなら、言わなくてもいい」
顔をあげると、今にも泣き出してしまいそうな孝弥が目の前にいた。
震える手に力を込める。ここでまた黙ってしまったら、今までと同じ。吐き出すことで楽になるとは思わない。むしろ、吐き出すことで、きっと孝弥を悲しませてしまうのは分かっている。だけど、真実を知って欲しいから、あたしは、この名前を口にする。
「……奥田、江莉……」
「……え?」
明らかに、触れていた孝弥の手がピクリと反応する。そして、泣きそうだった顔色は眉間に皺を作り、鋭い視線へと変わっていった。
「奥田江莉は……あたしの実の姉なの。そして、キヨミさんと優志さんとの交際を物凄く恨んでいた……」
姉がキヨミさんへと募らせた憎悪を知っている。優志さんへの異常なまでの愛着を知っている。影でお金や地位を使って、二人のことを引き裂さこうとしていたのを、あたしは知っている。
見たくない姉の嫌なところは全部見てきてしまった、あの日、あたしを貶めたあの瞬間から、ずっと。
孝弥は瞳の色が変わったような気がするほどに、先ほどまでの穏やかさがなくなって、触れていた手を離すと、イラつくように前髪を掻き乱した。
「……モヨに、聞いたよな? 奥田江莉を、知らないかって……どうしてあの時嘘をついたんだ?」
「大っ嫌いだからよ!」
張り上げたあたしの声は思ったよりも周りに響き渡り、周囲の視線が集中した。
だけど、そんなことは今はどうだって良い。あの人を姉だと認めることが、あたしには何よりも侮辱的だった。だけど、孝弥には知っていてもらいたかったから言ったのに。
あんな姉がいるなんて恥でしかないのに、嘘をつきたいあたしの気持ちまでは、きっと分かってもらえない。
「……俺も、大っ嫌いだよ……っ……」
波紋を揺らす紅茶から、視線を上げた。
小さく震えながら泣いている孝弥の姿に、あたしの瞳も一気に崩壊してしまった。
我慢していたんだ。ずっと。
ひとりぼっちで抱え込んでいた。
誰にも分かってもらえない。分かってももらいたくない。だったら、ひた隠しにしてあたしはあの人は姉なんかじゃないと嘘をつくしかなかった。
「……ごめん、孝弥、あの人、キヨミさんのこと追い詰めていたかもしれない……そういう人だってあたしは知っている。何をしてでも、欲しいものは手に入れる人だから。だから、もし、キヨミさんが江莉に何かされていたんだとしたら、あたしは居ても立っても居られなくなって。本当は関わりたくない。あんなやつの尻拭いなんてごめんだ。だけど、その前に、あたしキヨミさんのことが大好きだったから……あんな素敵な人のことを追い詰めるほどの何かをしたんじゃないかと思うと、江莉のことをどうにかしてしまいそうで……だから、あたしはまた、東京を離れたの……」
ようやく、周りの音が聞こえ始める。
コーヒーの苦い香り、ケーキが香る甘い空気、出入り口の開閉音とその度に聞こえてくるゲリラ豪雨の激しい雨音。
突風が吹き込んできて、アスファルトと車のガソリンの湿った匂いを運ぶ。
これは現実だ。
夢だったら、どれほど良かったのかと、込み上げてくる涙を拭った。
前回までの話はこちらから↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

