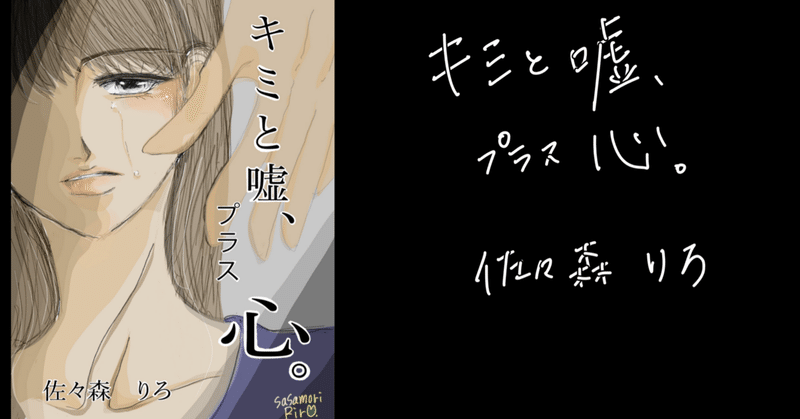
キミと嘘、プラス心。9
第九章 待ち合わせ
空は眩しいほどに太陽が燦々と輝いていて、雲一つない真っ青が目に沁みてくる。荷物は最小限にしたかった。もしかしたらすぐに帰ってくることになるかもしれないし、何日も滞在しなければいけなくなるかもしれないし、どちらになるかなんて、あたしには検討がつかなかった。
少しだけ大きめのトートバッグに必要最小限を詰め込み、必要ならば向こうで買えばいいだろう。そう考えて、貯めていた貯金を確認した。
凌二と別れてから、数ヶ月は仕事に没頭すれば忘れられると思いながら頑張ったけど、結局失敗をする度に、今までは愚痴を聞いてくれたり、励ましてくれたりした凌二の存在があったことを痛感した。
それがもう無くなってしまったことに、ポッカリと穴が空いたように、あたしは寂しさに耐えられなくなってしまった。
だから、仕事を辞めた。
元々向いていなかったのかもしれない。
だけど、いざ辞めるとなると、お店に来てくれていた常連のお客さんがあたしに対して「いつも笑顔がステキだったわよ」「辞めないで欲しいなぁ」「あなたのシャンプーが好きだったわ」「これ、私の名刺よ。覚えててね」たくさんそうやって、あたしが辞める事に残念がってくれているのを見て、ここにいて良かったんだと感じた。
だけど、今更また戻りたいかと聞かれても、あたしはもうあの場所には戻りたくなかった。
凌二との思い出もありすぎるし、続けられる自信もない。
今までのことを思い返していると、電車の到着を告げる合図がなった。
この数年で駅も立派になった。二階建てで見晴らしがいい。
ああ、モヨの部屋から見た僅かな明かりは、きっとこの駅の明かりだったのかもしれない。
視線が遠くに高いマンションを捉えて、あたしはそれがモヨの住むマンションだと認識した。
モヨは用事を済ませてから向かうと言うから、あたしは一人電車に乗り込んだ。
ここから少し、時間がある。
空いている席に座って、窓の外を眺めながら頭を働かせた。
沖野さんと会うこと。
あたしが嘘をついていたこと。
キヨミさんの死を告げること。
順を追って、今日やるべきことを頭の中でシミュレーションする。
大丈夫。ちゃんと伝えられる。
そう思った瞬間に、沖野さんの笑顔が浮かんできてしまって、あたしは目を閉じた。
揺れる車内は平日の学生や仕事へ行く人たちのラッシュが終わった後で、乗り込んでいる人はまばらだ。この車両の長椅子に座っているのは、あたししかいない。だから、思い切り吸い込んだ息を吐き出しながら、額に手を当てた。
あの笑顔を思い出すと、あたしにこんな残酷なことがちゃんと伝えられるのだろうか、と不安が押し寄せてくる。
動き出した電車は、前へと進む。あたしも、もう引き返すことなど出来ない。
*
東京へ到着すると、あたしは駅からようやく外へと出れたことにホッとしたのも束の間。
見上げた空に、向こうではあんなに晴れていた青空はどこにもなかった。灰色に濁った狭い空には、薄暗い雨雲が幾重にも重なり、今にも降り出しそうな気配を漂わせていた。
あいにく傘は持って来ていない。
モヨが来るまで駅の中で待とうか、そう思った瞬間に、スマホが震えた。
トートバッグを肩に掛け直すと、あたしはスマホを開いた。
『あ、詩乃? もう東京着いてた?』
「うん、今駅」
『そっか、あたしもう少し着くまでかかるから、先に今から送るとこで待っててくれないかな?』
「え、あ、うん。分かった」
モヨに言われるまま、あたしは通話が終了すると、モヨから送られてきた場所を確認する。
スマホを頼りに向かった先にあったのは、どう見ても高層すぎるビルディングで、思わず首が直角になるほどに見上げてしまって、キョロキョロと挙動不審になってしまう。
スマホでもう一度場所を確認して見るけど、ここを示しているようにしか見えない。
見る限り、オフィスの入ったビルで関係者以外は出入りできない様な雰囲気だ。行き交う人たちはみんなスーツ姿で、今のあたしの格好ではかなり場違いな気がする。
もちろんお洒落はしてきた。一応美容師見習いまでしてきたんだし、髪も暑さを感じさせない様に上から編み込んで長くなった三つ編みをくるくると纏めるとゴールドのピンで留めた。
ロングのシャツワンピにブルーデニム。肩にかけたトートバックはノーブランド。思い切りカジュアルな姿の自分になんとも居た堪れなくなっていると、横から声がかかった。
「詩乃、無事に着いたんだな」
聞き慣れた声に、現れた人の姿を確認したあたしは、一気に安堵してしまった。
「孝弥!」
スーツ姿で見慣れない営業マン風の孝弥は、いつもの様に優しく笑顔を向けてくれるから、一気にそれに緊張感が緩んでしまった。
「よかったぁー。こんなビジネス街に辿りついちゃって、不安だったんだよー」
「え、詩乃こっちにいたんじゃなかった?」
「……仕事と家の往復で、あんまり外出たりしなかったから」
「あ、そっか、こんなとこ来る用事もないだろうしな」
「うん」
「近くのカフェにランチ予約してたから、先行ってようか。モヨももうすぐだって」
「え! そうなんだ。孝弥が来るって言ってくれればよかったのに、モヨ」
場違いだと狼狽えていたあの不安な時間を返してほしい。
「あれ? 聞いてなかったの?」
「聞いてない」
「モヨってしっかりしてそうで肝心なとこ抜けてるよな。高校の時もじゃなかった?」
思い出して、ははっと笑う孝弥に、あたしは元気そうなことを感じてホッとした。
少し歩いた先、広いテラス席のあるカフェは見覚えのある店名。
「……あれ? これって」
カフェの入り口のドア、足を止めてガラスに書かれた文字に見入っていると、孝弥が微笑む。
「気付いた?」
「……ここ、flavorfulって言うの?」
地元のflavorfulと同じ。
「そうそう。向こうとの関わりとか聞いたことないけど、見つけた瞬間に鳥肌立ったよ。今俺のこっちでの一番のお気に入りカフェ」
嬉しそうに笑う孝弥は、ガラスの扉を引いて「どうぞ」とあたしに微笑む。さりげない紳士的な行動に少し恥ずかしさを感じながらも、あたしは小さく「ありがと」と呟いて店内へと進んだ。
店員さんに案内された席へ、向かい合うようにして座った。お互いにモヨが到着するまでとりあえず、とアイスコーヒーを注文する。
「テラス席も良いんだけどさ、多分今から雨、降ってくるよな」
窓の外に目線を移して空を見上げる孝弥に、あたしも視線をそちらに向けた。駅に着いた時にはすでに、厚い雲が狭い空を覆っていた。だけど、ここへ来るまでは降り出すことはなかった。
相変わらず、空は高いビルとビルの隙間からわずかに見えるだけ。その隙間を縫って降りてくる雨粒さえも間近に見えそうなくらいだ。
「向こうはすっごく天気良かったんだよ。まさに晴天って感じ。入道雲がモコモコしてた」
「そっか、梅雨も明けたし、いよいよ夏だよな」
そう言って孝弥はガムシロップを開けて、アイスコーヒーの縦長のグラスに落とした。濃いめのコーヒーに透明なシロップが混ざることなく落下してゆくのを眺めていると、くるりとストローでそれが混ざり合っていく。
「ミルク、要る?」
あたしの方にミルクの入った小さなミルクカップを向けてくれるから、あたしは迷わずに受け取った。自分のアイスコーヒーへと躊躇なく注ぐ。
「詩乃は甘いの好きだよね」
そう言われて、思わず照れてしまう。
しばらく会わなかったのに、高校の頃のあたしを知っている孝弥は、やっぱりホッと安心させてくれるような雰囲気を纏っている。モヨが優しいと言っている意味も、分かる気がした。
「あ、そうだ、詩乃の連絡先も教えといてよ。俺知らなかったから、モヨとしか連絡出来なくて」
「あ、うん。ぜひぜひ」
孝弥が思い出したように言いながらスマホを取り出すから、あたしもすぐに頷いて交換を済ませた。
「……孝弥はさ、キヨミさんの彼氏さんの事って、知っていたの?」
アイスコーヒーに口を付けようとしていた孝弥の動きが、あたしの質問でピタリと止まった。
「……あたし、向こうでキヨミさんの彼と会ったことがあって」
「……え?」
明らかに、孝弥の表情が曇る。
言うべきかどうかなんて迷わずに、あたしは続けた。
「キヨミさんが亡くなった少し後だった。その人、薔薇の花束を抱えて、明らかに田舎の雰囲気には合っていなかったから、不思議に思って声、かけちゃったんだ」
黙ったままの孝弥をチラリと見て、さらに続ける。
「あたし、キヨミさんが亡くなったこと、言えなかったの……まだ生きているかのような、希望を与えてしまうようなことを言ってしまって……だから、今日、その人に、キヨミさんのことをちゃんと話すために、こっちに来たの」
誰かに聞いてほしくて、それがキヨミさんの弟の孝弥なら尚更だ。
あたしは、ずっと抱えていたあの人への罪悪感を吐き出して、少しスッキリした胸を押さえつつ、小さくため息を吐いた。
あの人へ伝える前に、誰かに話す事でまた、自分の付いた嘘を正当化しようとしてしまう。
そうすることが良かったんだ。
それであの人は救われる。
そうなってほしかった。
単にあたしが付いた嘘への罪悪感が生んだもので、あたしの嘘は正しかったんだと誰かに言ってもらいたいと望む気持ちが渦巻く。
自分もあたしと同じ立場だったらそう言っている。
そう、言って欲しかった。
目の前の孝弥に視線を上げると、泣きそうに瞳が潤んでいた。
必死に我慢しているような、口元をきつく結んで、孝弥は震える声で「そっか」とだけ言った。
気持ちを落ち着かせるためにだろうか、孝弥はまた空へと視線を上げた。
ポツポツと降り始めた雨に、自身が流したい涙を代わりに流してくれているような空に、孝弥は目を細めている。
「どうして、そんな嘘をついたの?」
思ってもいなかった返答を返されて、今度はあたしの動きが止まる。目を空へと向けたまま、孝弥は何かを考えている様な表情をしていて、まだ辛そうに眉を顰めたままだ。
「……あたしにも…分からなくて。だけど、どうしてか、あの時、あの人のことを悲しませたくはないと、思ってしまったから……」
自分でも驚いたんだ。どうして知りもしない他人にこんな嘘を、ついてしまうんだろうと。
あたしが答えると、孝弥の視線があたしを向いた。目が合うと、やっぱり悲しげに、儚げにその目は笑う。
「……そう」
一言漏らすと、孝弥はアイスコーヒーを啜った。
カランっと氷が小さく崩れる音がして、それと同時に孝弥のスマホが震えた。
「あ、モヨだ」
届いたメッセージを確認している孝弥の後ろに、あたしはカフェの扉を開いて入ってくるモヨの姿を捉えた。
「あ、いたいたぁ。ごめんね、遅れて!」
店員さんと会話をしてこちらに気がつくと、モヨはランウェイを歩くファッションモデルの様に足取り良くこちらに歩いてきた。周りにいるお客さんは、みんなモヨの姿を振り返って見ている。
スタイル抜群のモヨは振り返らない人の方がどうかしていると思うほどに容姿端麗だ。本人はそんな美貌も努力の賜物だと言っているが、その振る舞いにはぎこちなさなんて微塵も感じない。きっと産まれながらに培ってきた土台があるんだろうとあたしは思う。
孝弥はそんなモヨに、お好きな方にどうぞとあたしの隣と自分の隣の席をモヨに選ばせた。
一瞬だけ「うーん……」と悩むそぶりを見せつつ、あたしの隣にモヨは座った。
目の前の孝弥の方を見て、モヨは笑顔になる。
「こっちだと孝弥の表情がよく見えるし、やっぱこっちだよね。詩乃の横は落ち着くしっ」
あたしにもそう言って笑顔をくれたモヨは、孝弥の方に視線を戻すと嬉しそうに笑っている。
もう、孝弥のことが好きなのがダダ漏れしている感じがするのはあたしだけ?
孝弥はすぐにメニュー表を手に取り、あたし達に向けて開くと、ランチのメニューをおススメしてくれる。
「どれも美味しいんだけど、結局俺はいつもこれにしてる」
そう言って孝弥が指を指すのは【気まぐれランチ】のケーキセット。カフェの店長が平日限定でランチメニューを考案しているらしい。
「日替わりでなにが出てくるかはその日のお楽しみだけど、どれを食べても美味しいしハズレがない。それを知ってしまってからは、これを頼むのが楽しくてしょうがないんだよ」
ワクワクと子供みたいな笑顔で孝弥が話すと、隣のモヨまで目を輝かせている。
「じゃあ、あたしもそれにする。ケーキも食べたいと思ったの! さっき入り口のショーケースの中見た? キラキラでみんな美味しそうだった!」
「うん、あたしも見た」
オーソドックスなショートケーキから、チョコレートケーキ、チーズケーキ、シフォンケーキにキラキラのフルーツがたくさん乗ったタルトにパイ。種類も豊富でいくらでも眺めていられそうなくらいに、綺麗なショーケースだった。
「あたし、ショートケーキにしよっ」
すぐにそう言って、モヨは孝弥の悩む顔を微笑んで眺めている。
「……あれ? もしかして、モヨ」
そんなモヨに視線を向けて、孝弥は何かを思い出したようにしてから、笑顔になった。
「誕生日?」
「え⁉︎」
モヨよりも先にあたしの方が驚いてしまって、思わず出た声に口に手を当てた。
「モヨ、ショートケーキは誕生日にしか食べないって、前に言っていたよね?」
孝弥がメニュー表を開いたまま言って、店員さんを呼ぶために片手を上げた。
注文を済ませると、ニコニコのモヨが孝弥に頷いている。
「そうそう。誕生日にあたしがショートケーキこっそり買ってる所を見られたことがあってね。それで孝弥には話したことあったけど」
「そうなんだ」
あたしの知らないモヨがまた顔を覗かせる。
「あの時、見られたの孝弥でほんと良かったって思ったよ。絶対他の男子だったら色々聞いてきそうで、面倒くさかったし」
「だよな、俺もすげー気にはなったけど、モヨって変わってたし、なんか理由があるんだろうなって思って深入りしなかったよ」
「んー、なんかあたしになんて全然興味なかったっても取れるけど。まぁ、いっか」
楽観的に笑うモヨに、あたしは突っ込んで聞きたい事が山のように思い浮かぶけれど、それじゃあ面倒な男子と一緒になってしまうと思って、聞くことを諦めた。
「あ、良かったらだけど、夜モヨの誕生会兼ねての飲みに行くか? 同期の奴誘ってみるよ」
「飲み! 行くいくっ!」
飲めると聞いて、行かないわけがないのがモヨだ。
誕生日か。なにも用意してこなかったな。あたしも、モヨになにかしてあげたい。
楽しそうに孝弥と話すモヨの横顔を、あたしは微笑ましく眺めた。
メニュー表のケーキの欄にまた視線を戻すと、悩み始める。
「……孝弥ってば、そういうとこが変わらないよね。よく覚えてるよ」
笑いながらも、モヨは少し寂しげな表情をしていて、あたしは二人の過去に何かあったんじゃないかと頭が働いてしまう。
だけど、それは知らなくても良いのかもしれない。
日替わりランチを食べ終えると、デザートにケーキが運ばれてくる。
隣に置かれた紅茶に、スティックシュガーを流し入れた。モヨはそのままストレートで紅茶を口にすると、ゆっくりとカップを戻した。
「……キヨミさんのこと……」
静かにそう言ったモヨの方へと視線を上げた。
モヨと同じくショートケーキを選んだ孝弥は、途中までフォークを通した手を止めて、食べることなくそっとそれから手を離した。
モヨに向かっていた視線が、窓の外へと外れた。
先ほどまでまだ青色がわずかにあった空は、黒々した雲に覆われてしまっていて、雨粒もより強さを増して打ち付けている。
外を歩く人の足が早足で、ここへ駆け込んでくるのも見えた。
「話しても良い?」
モヨは確認する様に孝弥に尋ねる。
外の雨音と店内の穏やかなクラシックが入り混じって聞こえてくる。
不穏ながらも、なにか期待をしてしまうような雰囲気に、あたしとモヨは孝弥の反応を待った。
孝弥がキヨミさんと沖野さんのことをどこまで知っているのかは分からないし、モヨがキヨミさんとどんな接点があったのかも、あたしは知らない。
でも、それぞれの過去が、きっとキヨミさんの事故の真相に結びついて、沖野さんへと繋がっていくんじゃないかと思うと、不謹慎にも期待をしてしまう。
当事者ではないあたしが、ただ単にそれを楽しんでいると思われてしまえばそれだけだけど、あたしは、やっぱり沖野さんの悲しむ顔を見たくはない。
モヨや孝弥の話を沖野さんへと伝えられたら、もしかしたら、キヨミさんが亡くなったことも、そこまで重く受け止めることなく悲しみも半減してくれたら良いのに、と、そんな安易な考えをしていた。
だけど、そんなのはやっぱりあたしの勝手な自己満足で、現実はどうしたって残酷だった。
空が泣き始めたと思ったら、あっという間に土砂降りになった。アスファルトを強く叩きつけては跳ね返る雨粒が白んでいる。
孝弥がようやくこちらを向いて、微笑んだ。
「教えて欲しい。モヨの知っていること、全部」
落ち着いているように見えるけれど、テーブルの上に置かれた孝弥の手が、わずかに震えているのに気がついた。
「あたしの分かる範囲で全部、話すからね。だから、最初にこれだけは、言わせて」
先ほどまでとは変わって、モヨは背筋を真っ直ぐに伸ばして手を膝の上に置くと、テーブルギリギリまで深く頭を下げた。
「本当に、ごめんなさい」
苦しそうな声が、下を向いているからか余計にくぐもって聞こえてきた。
震えるモヨの肩に、あたしはどうしようもないくらいに息が詰まる。
あたしが考えているよりも、遥かにことの重大さが伝わってくる。
モヨがなにを語るのかが、一気に怖くなった。
前回までの話はこちらから↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

