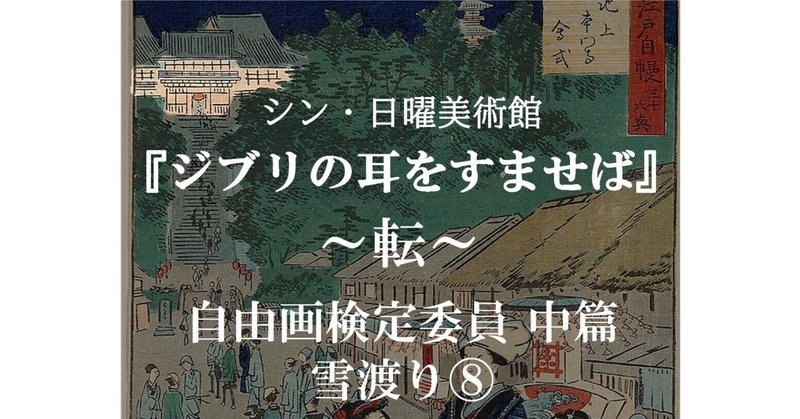
シン・日曜美術館『ジブリの耳をすませば』~転~「自由画検定委員 中篇:雪渡り⑧」
前回はこちら
2019年 7月 フランス
アルザス地方 コルマール
RESTAURANT JAPONAIS NAGOYA
日本料理レストラン ナゴヤ

「紺」の「甘」は何なんだ?
なぜ「イト」が「甘」だと「餅」になるんだよ?

だって聖書にも出て来るじゃないですか。
「甘」の「餅」が。

は? 聖書に甘い餅なんか出て来ないだろ。
そもそもイエスが餅を食ったなんて聞いたことがない。

はっはっは。そうでしょうか?

餅は東アジアの食べ物だ。東地中海沿岸にはない。

何事も決めつけはいけませんよ。
それでは解説しましょう。
イエスが食べた「甘」の「餅」について…

手短に頼むぜ、爺さん。

はい。今回はすぐに終わります。
そもそも「甘」という漢字がどんな意味なのか知っていますか?

「甘」という字が?
甘寧だけに、わかんねい。

「甘」という字は「口の中に平べったい食べ物を入れる」という意味なんです。


ん? これって、もしや…

そう。イエス・キリストの肉体であるパン「聖体」のことですね。
最後の晩餐が過越しの夜(除酵祭)に行われる『ルカによる福音書』では、種入れぬパン、つまりイースト菌を取り除いた無発酵のパン生地で作った、薄くて平べったいものになっています。
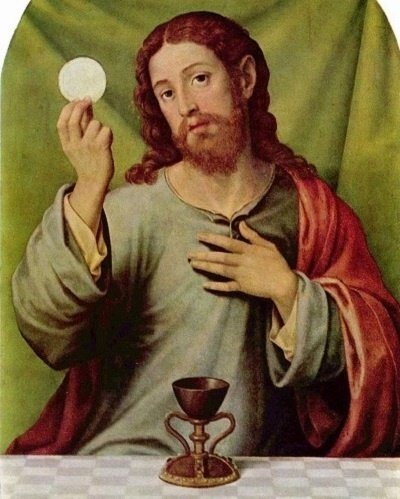

しかしパンは「餅」ではありません。
聖書には「餅」なんて一言も書いてないです。

確かに今は聖書に「餅」なんて出て来ませんが、だからといって賢治の時代もそうだったとは限りません。

え?

『ルカによる福音書』第13章「神の国の宴」と「キツネの例え話」のあと、第14章でイエスはパリサイ人に招かれて安息日の晩餐会へ行きました。
賢治が読んでいたと思われる当時の聖書には、こう書かれています。
ルカ 第十四章
一 イイスス 安息日の一の宰なるファリセイの家に入りて、餅を食ふことありしに、人々 彼を窺へり。

も、餅と書いてパンと読む?
そんなのありなんですか?

さすがに「餅」と書いて「パン」は無理があり過ぎるだろ。
それとも昔の日本人は「春のパンまつり」を「春の餅まつり」と書いていたのか?


はっはっは。
どうやら日本の「おもち」と混同しているようですね。

「餅」とは、月のウサギがぺったんぺったんして作るあの「餅」のことじゃないのか?


そもそも「餅」とは米ではなく麦から作られるものです。
漢字の「餅」という字は「小麦など穀類の粉を練り、焼いたり蒸した食べ物」という意味なんですよ。

麦で作る? もち米じゃなくて?

米文化の日本と違って中国の大部分は小麦文化ですからね。
だから「餅」と書いて「パン」と読ませるのは、漢字本来の正しい使い方であり、昔の人にとっては特に違和感もなかったのです。

なるほど…
確かに中国では、薄く焼いたパン生地の中に餡を入れたものを「月餅」と呼ぶ…
「月の餅」だけど、あの「おもち」ではなく、小麦から作られたパン菓子だ…

そういうことです。
月餅、おいしいですよね。

そういえば賢治が読んでいたと思われる聖書…
イエスのことも変わった表記になってたな…

イイススね~、イエ、イエ、なんてね。

は?

よくないこれ?これよくない?
よくなくなくなくなくなくない?

バウバウッ!バウバウッ!バウバウッ!

うるせえなカール。
なんで三度も鳴くんだよ。

イイススね~って『今夜はブギー・バック』のラップのことを言ってたんですか?

賢治が読んでいたと思われる聖書…
それは1902年(明治35)に出版された日本正教会の翻訳による『我主イイススハリストスの新約』…

なるほど。正教会の聖書だから固有名詞がギリシャ語ベースなのか。

『我主イイススハリストスの新約』の固有名詞は、カトリックやプロテスタントの聖書とは大きく異なっています。
ユダヤはイウデヤ
ヨルダンはイオルダン
イスラエルはイズライリ
ナザレはナゾレイ
ベツレヘムはワィフレエム
エルサレムはイエルサリム
アブラハムはアウラアム
イサクはイサアク
ヤコブはイアコフ
モーセはモイセイ
ダビデはダワィド
ヨハネはイオアン
ヨセフはイオシフ
カエサルはケサリ
ヘロデはイロド
バラバはワラウワ
イスカリオテのユダはイスカリオトのイウダ
などなど…

バラバの「ワラウワ」は草だな。

だけどこれって賢治ワールドのネーミングっぽくないか?
イワテはイーハトーヴ
ハナマキはハームキヤ
モリオカはモリーオ
センダイはセンダード
トウキョウはトキーオ
アタゴはアタゴオル
イバラキはイバラード

ふむ。そう言われてみれば確かにそうだな。

賢治ワールドのユニークなネーミングについては、エスペラント語の影響が有名です。
しかしエスペラント語だけではなく、正教会聖書の影響もあると思われます。
賢治は、トルストイをはじめとしたロシア文学を、好んで読んでいましたからね。

では『雪渡り』の続きを見てみましょう。
「狐こんこん狐の子、狐の団子は兎のくそ。」
すると小狐紺三郎が笑って云いました。
「いいえ、決してそんなことはありません。あなた方のような立派なお方が兎の茶色の団子なんか召しあがるもんですか。私らは全体いままで人をだますなんてあんまりむじつの罪をきせられていたのです。」
四郎がおどろいて尋ねました。
「そいじゃきつねが人をだますなんて偽かしら。」
紺三郎が熱心に云いました。
「偽ですとも。けだし最もひどい偽です。だまされたという人は大抵お酒に酔ったり、臆病でくるくるしたりした人です。面白いですよ。甚兵衛さんがこの前、月夜の晩私たちのお家の前に坐って一晩じょうるりをやりましたよ。私らはみんな出て見たのです。」
四郎が叫びました。
「甚兵衛さんならじょうるりじゃないや。きっと浪花だぜ。」
子狐紺三郎はなるほどという顔をして、
「ええ、そうかもしれません。とにかくお団子をおあがりなさい。私のさしあげるのは、ちゃんと私が畑を作って播いて草をとって刈って叩いて粉にして練ってむしてお砂糖をかけたのです。いかがですか。一皿さしあげましょう。」
と云いました。

紺三郎は世間で信じられている「キツネは人を騙す」という話を「ひどい嘘」で「無実の罪」だと言った…
これは賢治とトシが傾倒していた日蓮宗とキリスト教のこと…
日蓮もイエスも、無実の罪で処刑され、奇跡が起きて死ななかった…

熱心な浄土真宗の信徒だった父政次郎は、両者を断固として認めず、やめさせようとしていた。
もしかしたら賢治とトシは、政次郎から「あれは人を騙す宗教だ」と言われたことがあったのかもしれないな。


この部分には、もう1つ重要なキーワードが出て来ます。
それは、甚兵衛さんの「浪花節(浪曲)」です。

なにわぶし?
あの『浪花節だよ人生は』の浪花節か?

ええ。そうです。

つまり甚兵衛さんは演歌を歌ったということか。

いいえ。甚兵衛さんが歌ったのは浪花節。
演歌は賢治の時代にはまだありませんでした。

演歌って日本の伝統芸能じゃなかったのか?

演歌というジャンルが出来たのは1960年代です。
演歌の代名詞のように言われる「こぶしをまわす」という技術も、そもそもは古典芸能だった浪花節から来たもの。

演歌って、わりかし新しいものなんだな…
和服を着て歌うから、日本伝統のものだと思ってた…

演歌というのは、初めから商業用のポピュラー音楽として作られたもので、シングル・レコードの尺に合わせて1曲が3分~4分程度になっています。
しかし古典芸能である浪花節はそうではない…
1曲が、とても長いのです…

日蓮上人?

これが浪花節か…
なんだか面白い構成だな…
メロディに合わせて歌うパートと、語り口調のパートが、交互に繰り返される…

何かとよく似てませんか?

何かと?

♬ダンスフロアーに華やかな光~♬
と、
「1、2、3、を待たずに二十四小節の旅の始まり」

ああっ!

歌➜ラップ➜歌➜ラップ➜歌… と続く『今夜はブギー・バック』そっくりじゃねえか!

浪花節(浪曲)は、旋律・メロディのある歌唱パート「節」と、語り口調のパート「啖呵」が、交互に繰り返されます…
おそらく小沢健二は、賢治が使った「浪花節」というキーワードから『今夜はブギー・バック』の構成を思いついたのでしょう…


『今夜はブギー・バック』は「浪花節」そのもの…

いや、ちょっと待て。
『今夜はブギー・バック』は Nice & Smooth(ナイス&スムース)の『Cake And Eat It Too』をサンプリングした曲だ。
だからこっちが元ネタだろ。

『雪渡り』の「浪花節」が先でしょう。
まず賢治の『雪渡り』から始まって、そこから「ルカーっと」つながりで Nice & Smooth の『Cake And Eat It Too』が引っ張り出され、「行き渡り」つながりで Roy Ayers Ubiquity の『The Boogie Back』がサビとタイトルになったという流れだと思います。

おいおい。『Cake And Eat It Too』は「ルカー」っと叫ばねえだろ。
勝手にルカつながりにするんじゃねえよ。

やれやれ。何もわかっちゃいない…
まあ、いいでしょう。今は賢治の『雪渡り』の話。
あとで時間があった時に『Cake And Eat It Too』の話をします。
それとついでに『今夜はブギー・バック』のアンサーソング、ECD『Do The Boogie Back』についても。

はあ? なんじゃこりゃァ?

ヒット曲のアンサーソングは数あれど、この歌ほど原曲をリスペクトしているアンサーソングはないと思います…
あまりにも完璧すぎるので、もう公式の『今夜はブギー・バック』続編にしてもいいくらい…
♬チャンスだ ドア開いてるぜ みんな♬
ああ、なんて素晴らしい…

何言ってんだ?
こんな原曲ぶちこわしのふざけた歌を聴いたら、さすがのオザケンもブチ切れるだろうに。
「ふざけんなーっ!」って。

では『雪渡り』に話を戻しましょう。
と四郎が笑って、
「紺三郎さん、僕らは丁度いまね、お餅をたべて来たんだからおなかが減らないんだよ。この次におよばれしようか。」
子狐の紺三郎が嬉しがってみじかい腕をばたばたして云いました。
「そうですか。そんなら今度幻燈会のときさしあげましょう。幻燈会にはきっといらっしゃい。この次の雪の凍った月夜の晩です。八時からはじめますから、入場券をあげて置きましょう。何枚あげましょうか。」
「そんなら五枚お呉れ。」と四郎が云いました。
「五枚ですか。あなた方が二枚にあとの三枚はどなたですか。」と紺三郎が云いました。
「兄さんたちだ。」と四郎が答えますと、
「兄さんたちは十一歳以下ですか。」と紺三郎が又尋ねました。
「いや小兄さんは四年生だからね、八つの四つで十二歳。」と四郎が云いました。
すると紺三郎は尤もらしく又おひげを一つひねって云いました。
「それでは残念ですが兄さんたちはお断わりです。あなた方だけいらっしゃい。

キツネの幻燈会に入れるのは11歳までで、12歳以上の子は入れない…
なぜそんな年齢制限があるんだろう?

11はユダを除いた使徒の数…
12はユダを含めた使徒の数…
これか?
ルカ 第二二章
一 除酵節 即ち 逾越と名づくる節は近づけり。
二 司祭諸長と學士等とは如何にイイススを殺さんと謀れり、蓋 民を畏れたり。
三 時にサタナは十二の一なるイウダ、稱してイスカリオトと云ふ者に入れり。

『Verraad Judas(ユダの裏切り)』
Giotto di Bondone(ジョット・ディ・ボンドーネ)

なるほど。
確かに賢治は「十二」のあとにすぐ「もっともらしく又おひげを一つひねって」と書いている。
これは「十二の一なる」を意識した書き方だ。
つまり「キツネの幻燈会」とは、ユダヤ人の祝祭「除酵節・過越祭」のこと…

『The Last Supper(最後の晩餐)』
Jacopo Tintoretto(ヤコポ・ティントレット)

ですね。
キツネの幻燈会で食される「餅」と「黍団子」には酵母(イースト菌)は入っていません。
そしてキツネの幻燈会とは「お会式」の「お逮夜」のことでもあります。

『江戸自慢三十六興・池上本門寺会式』
歌川広重

おえしき? おたいや?
なんだそれは?

日蓮の命日は10月13日…
その日に向けて11日から行われる日蓮宗最大の祭りが「お会式」です…
そして「お逮夜」とは、命日の前日12日の日没から13日未明にかけての夜に行われる祭りのこと…
大きな幻燈と共に信徒たちが提灯行列を行います…

日蓮の命日は13日…
その前日12日の日没から13日にかけて行われる夜の祭り…
なんだかイエスの命日と前夜の過越し祭のようだ…

「お逮夜」は命日の前夜?
つまり「お逮夜」ってのは、イエスみたいに日蓮が「逮捕された夜」という意味なのか?

『The Arrest of Christ, Kiss of Judas(イエスの逮捕 ユダの接吻)』
Giotto di Bondone(ジョット・ディ・ボンドーネ)

確かに日蓮もイエス同様に逮捕・処刑されましたが、それとは別のこと。
「逮夜」というのは「命日に至るまでの夜」という意味なんです。
つまり「特別な日の前夜」ということですね。

つまり「お逮夜」の「逮」は、クリスマスイブのイブと同じってことか?
じゃあなぜ日本語では悪人を捕まえることを「逮捕」と言うんだ?


なんか、写真とリンクが合ってなくないか?

よくないこれ?これよくない?
よくなくなくなくなくなくない?

「逮」という字の元々の意味は「及ぶ・あとから追いつく」というもの。
そこから「特別な日に至る前夜」とか「捕まえる」という意味で使われるようになりました。
ちなみに「逮」という字の成り立ちは「十字路の真ん中で尻尾の長い獣(キツネ)に追いつく」を象形化したものです。

十字路で尻尾の長い獣(キツネ)に追いつく…
『雪渡り』の英語タイトルは『Snow Crossing』…
「cross」は「渡る」でもあり「十字架」でもある…

その通り。
♬アイアムセ~イリ~ン♬
の「cross/crossing」ですね。

「雪」という字は「あめの下を掃き清める」つまり「地上世界を清浄化する」という意味…
そして「渡り」は「cross」だから「十字架」…
つまり「雪渡り」は「行き渡り・あまねく世界に広がる」という意味であると同時に「人類の救済」という意味にもなっている…

その通りです。
これぞまさに賢治が追い求めた法華文学の神髄といえるでしょう。

デビュー作からこんな風になっているなんて…
おそるべし、宮沢賢治…


では『雪渡り』の続きを見て行きましょう。
次はいよいよ「3枚の幻燈」について言及されます…
à suivre
つ づ く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
