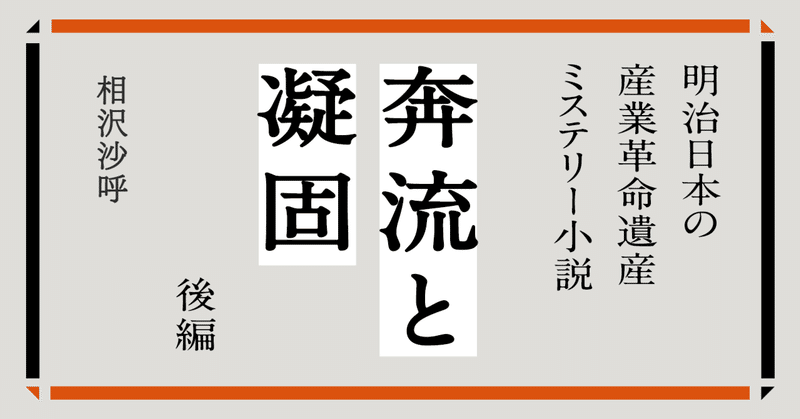
【世界遺産・短編小説】「奔流と凝固」後編
山間の開けた景色に、その施設はあった。
真新しさを感じさせるコンクリートで綺麗に整地されているものの、その綺麗さは逆に、ここもまた激しい奔流に飲まれてしまった土地なのだということをわたしに印象付けた。雰囲気としては、道の駅を連想させる建物だ。何の気なしに駐車場へと車を駐めて、わたしはそこを訪れた。
館内は明るく、近代的で柔らかな印象を持っていたけれど、そこにあったのは東日本大震災の記録だ。震災直後になにがあったのか、津波の被害がもたらしたもの、わたしたちが学ぶべき教訓、そして復興のために人々がどのように尽力してきたのか——。それらが写真やパネルと共に詳細に語られていた。津波による釜石市の死者・行方不明者は約1300人。当時の様子を語る子どもたちの言葉もあり、わたしはどうしてか恥ずかしい気持ちになった。避難場所ですら津波に飲み込まれてしまい、命を落とした人も多かったという。わたしの想像も及ばない恐ろしい出来事がこの世界には確かにあって、そしてそれを生き抜いた人たちがいる。わたしが初日に訪れた狐崎城があった丘陵も、避難場所の一つだったようだ。
わたしの想像よりも遙かに大きなそれは、あらゆるものを飲み込んでいった。となれば、わたしが探しているものもまた流されてしまったのかもしれない。一応、職員の人を訪ねて、この近辺に城跡や神社などがないかを尋ねたが、返って来るのは、どこも訪れたことのある場所ばかりで、満足のいく答えは得られなかった。まぁ、そもそも探し方が悪いのだから、仕方がない。写真さえ持ってきていれば、きっと違っただろうに。
諦めて、建物を出ようとしたときだった。
「すみません」
そう声を掛けられて振り返ると、そこにいたのは眼鏡を掛けた壮年の男性だった。どこか子どもを見守る教師のような眼差しをした人だ、と感じる。彼は笑ってわたしに言う。
「あなたが、お城や神社を探していらっしゃる方ですか?」
「あ、ええ……」
さっきのやり取りを聞かれていたのか、それともそんなことを方々で訊き回っているから、噂になっているのか、わたしは恥ずかしくなって頷く。
「手元にはないのですが、母の写真に写っている場所を探していて。釜石の史跡だと思うのですが、お城か、神社か、お寺か……、お城だと思っていたのですが、どうにも見つけられなくて、たぶん、そういうところだと思うんですけれど」
彼は、しばらく考えこむような間を置いて言う。
「橋野鉄鉱山には、行かれましたか?」
「え?」
鉄鉱山、という言葉に混乱してしまった。当然ながらそんなところはまだ訪ねていない。
「その鉱山に、お城があるんですか?」
「いえ」彼はかぶりを振った。「ですが、ひょっとするとお探しの場所が見つかるかも知れません」
*
彼は市役所の人間で、森さんというらしい。悪い人には見えなかったし、これから、ちょうどそこへ行く用事があるというので、車で先導してもらうことにした。カーナビを確認すると、三十分ほどの距離だ。鉄鉱山というだけあって、ホテルなどがある海沿いの中心地から内陸寄りに向かうことになる。ちょうど、遠野市との間くらいだろうか。

緑に囲まれた山中の開けた場所に、これもやはり道の駅で見かけるようなこぢんまりとした建物と駐車場があった。そこで車を駐めて、案内をしてくれる森さんに続く。山へと向かう方角だったが、道はなだらかで整地されており、ちょっとしたハイキングコースのような心地よい景色が続いていた。鉄鉱山という名称からは程遠い。勝手な印象だが、鉱山というと、山の中の炭鉱とか、そういう暗い場所をイメージしてしまう。そんなところに、わたしの探している石垣があるのだろうか?
不安に襲われた頃、なだらかな緑の向こうに、それが見えた。
「これ……」
一言で表現するなら、それは朽ちた遺跡に見えた。
大きな石を積み重ねて作られた建造物。長い歴史の中で瓦解し、中途半端なかたちを辛うじて保った、堅牢で小さな小屋の名残。それは間違いなく、わたしが記憶の中の写真で見た石垣の壁だった。
「これは……?」
「これは、高炉です。現存する日本最古の洋式高炉跡ですよ」
森さんが、説明をしてくれる。

江戸末期、鎖国状態であった日本へ欧米列強は開国を迫っていた。それらに対抗するため、大砲用の銑鉄を供給する目的で作られたという。その時の日本には、もちろん洋式高炉は存在していなかった。外国の書物に記された設計図を紐解き、日本の伝統的な施工技術を組み合わせて、初めて建設されたのが、この洋式高炉だという。だから、釜石市は近代製鉄業発祥の地でもあるのだ。
「ここで間違いありませんか?」
森さんの言葉に、わたしは呆然と頷く。
間違いない。母の背に写っていたのは、この場所だ。
でも、それがお城の石垣ではなく、製鉄のための高炉跡だったなんて……。
「どうしてわかったんですか?」
森さんによると、橋野鉄鉱山は、『明治日本の産業革命遺産』の構成資産として、世界遺産にも登録されているという。となれば、写真を見せて釜石市の人たちに訊ねれば、すぐに答えは出たことだろう。けれど、わたしは森さんに写真を見せたわけではない。ただ、史跡を探していると訊ねただけだ。それなのに。
まるで、推理小説に出てくる名探偵に問うみたいに、わたしは呆然と訊ねていた。
「なんとなくです」
森さんは言う。誤魔化されたような気持ちになって少し膨れたわたしの気持ちを察したのか、彼は一度笑うと、丁寧に説明してくれた。
「お城か、神社か、お寺か、と仰いましたでしょう。写真に写っている場所を見て、神社かお寺かの判別が付かないというのは、まぁ、まだわかります。けれど、そこにお城が加わると、少し妙だと思いました。その三つの区別が付かないのは少しおかしい。となれば、その三箇所に共通して写りそうな場所……、それは石垣でしょう。それもお城と疑うくらいに大きな石垣に見えるものです。釜石で、大きな城郭の石垣と誤認してしまうものが写りそうな史跡といえば、ここだと思いました」
森さんは、簡単に説明してくれた。
この洋式高炉は海外の設計図通りに造られたわけではなく、日本独特の技術が組み込まれている。そして高炉の外壁の石積は、石垣の技術を用いられて造られているのだ。鉄を製錬するための灼熱を遮る必要があるのだから、堅牢性が求められたのだろう。
わたしは、かつて高炉を形成していたその古い石壁に掌を押し当てた。冷たいが、どこかぬくもりを感じられるような不思議な手触りがあった。
日本の文化や史跡が好きだったという母は、この場所も愛していたのだろうか。彼女は人の歴史からなにを学び取ろうとしていたのだろう。それはわたしや父を捨ててまで追い求めたいものだったのだろうか。
わたしが不思議そうな表情で高炉を見ていたせいだろう。森さんが簡単な仕組みを教えてくれた。
「ここはね、鉱山なんです。採れた鉄鉱石をここまで運んできて、種を砕き、炉に投入して溶かす。それが、銑鉄となって出てくるわけです」
銑鉄はねぇ、固くて脆いんです。
固くて脆い。けれど不純物を取り除いたり、精錬していくと、鋼になる。
「鋼はね。粘り気があって、強靱です。僕はそこが好きですねぇ」
わたしは、その言葉を耳にして、彼を見た。
思わず、笑ってしまう。
「どうしました?」
不思議そうにする森さんに、わたしは言った。
「いえ……、母が、そんな人だったそうです」
*
森さんは、色々と解説をしてくれたあと、鉄の歴史館へという場所へわたしを案内してくれた。そこには高炉を原寸大で再現したちょっとしたシアターがあって、模型に映像とナレーションを組み合わせながら、わたしに歴史と仕組みを教えてくれた。けれど、その小さな映画館めいた暗がりの中で、わたしは別のことを考えていたと思う。
ここに案内されるまでに彼と交わした言葉を思い出す。
「実は釜石を訪れたのは幼い頃以来で、記憶と少し違っていたので戸惑いました」
そうわたしが言うと、森さんはこう答えた。
「そうですか。少しだけで、本当に良かった」
わたしは、その言葉を聞いて、「いのちをつなぐ未来館」で見た写真の光景を思い出す。
きっと、本当はもっと違ってしまっていたのだろう。
それでも、人々はどうにか、復興を成し遂げてきた。
「釜石は、ものづくりの街ですからねぇ」
彼は誇らしげに笑っていた。
小さなシアターの中、暗がりの映像をじっと見つめて、わたしは考える。
すべて洗い流されても、人はまた立ち上がることができるのに、わたしはどうなのだろう。心の中のものを、すべて洗い流したいと思っていた。そのための旅だった。けれど、実際はどうだろう。それはすべてを投げ出そうとしていただけなのではないだろうか。母の愛も得られず、父も亡くし、あらゆることに疲れ果ててしまって、仕事も人間関係も、なにかも捨て去って、どこかへ消えてしまいたいと、そう願っていただけなのではないだろうか。
鉄は、固くて脆い。
それでも、粘り気があって、強靱なものへと変じることができる。
森さんは、この歴史館でも働いているという。それで、もしかしてと訊ねて、わたしは名乗った。そうした仕事なら、母と関わりがあったこともあるのではと考えたのだ。
「僕も彼女には、大変お世話になりました」
わたしは唇を噛んで、母のことを語る彼を見る。
「あなたを見て、面影を感じたんですねぇ。あの推理はうそっぱちです。彼女は高炉が好きでしたから、そこに違いないと、なんとなく思ったんです。小さなお子さんがいると聞いていましたから。いつも写真を見せてくれて、会いたがっておられました」
そんなの。
そんなのは、伝えてくれなければ、わからないじゃないか。
なにも伝えないまま、いなくなってしまうなんて、ずるいよ。
心を流れて行く熱が、かたちを変じながら、溢れ出そうとする。わたしはその奔流を堪えるために、くちびるを噛み締めた。ひょっとすると、すべてを投げ捨てて消えてしまうには、まだ早いのかもしれない、と思いながら。
最後に、森さんは金属鋳造体験を案内してくれた。木枠に鋳物砂を敷き詰めて固め、できた型に溶かした錫を流し込むというものだった。わたしが選んだのは、高炉を模したキーホルダーの型だった。
それを鞄に付けて、わたしは明日には釜石市を去るだろう。
柔らかな金属は、いつかは固まる。それがいつの日なのかはわからないけれど。
でも、きっと大丈夫だよ、と誰かに背中を押してもらえたような気がした。
了
相沢沙呼(あいざわ・さこ)
1983年、埼玉県生まれ。2009年『午前零時のサンドリヨン』で第19回鮎川哲也賞を受賞しデビュー。2020年『medium霊媒探偵城塚翡翠』で第20回本格ミステリ大賞を受賞。
