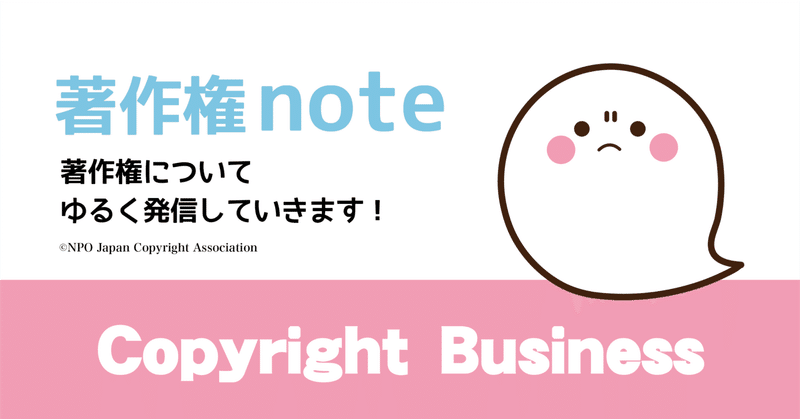
57.人のモノを使用するのが怖い!
前回もお話ししましたが、他人のものを勝手に使用する場合には最低限のルールがあるということをお話ししました。
それは「引用の定義」にあてはめることによって無断でも、許可なく自由に利用できることです。
①必要不可欠であること②人の引用の個所と自分の部分の区別、明確化③必要最低限の範囲であること、④出所明示がされていることです。
1.引用における出所明示の方法
人のものを無断で使用している人も多いのですが、本音を言えばいつも何かしらびくびくと恐れています。
確かに無断で使用するわけですから、訴えられたらどうしょう?と、不安も起こるでしょうが、どうしても必要として利用したい場合もあるはずです。
その場合、公表されているものに関してはしっかりとした「引用条件」を守ることによって堂々と利用することができるわけですから、それを守ることですね。
最近では統計表やグラフなどを自分のブログやnote記事などで掲載したいという人も多く、特に国や公共団体の情報などは必要不可欠なものです。
・統計表・図表を転載する場合の注意点
公表された他人の著作物は「引用」して利用することができる。ただし、この「引用」は公正な慣行に合致するもので、かつ引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。(著三十二条一項)
国または地方公共団体の機関(官公庁)が一般に周知させることを目的とし作成した統計表・図表は、説明の材料として刊行物に転載することができる。(著三十二条二項)
ただし、注意しなければならないことは、「転載を禁止する」旨の表示がある場合は転載することはできません。
2.キャッチフレーズやスローガン
まず、利用しようとするキャッチフレーズやスローガンがどのようなものかという点を調べねばなりません。
キャッチフレーズとは、人の注意を引くための言葉であって、たとえば「この○○は美味しいですよ」といったように商品の広告、宣伝のために商品の品質、効能等を表わす単語を結合して表現し用いられているものです。
では、他社の商品のキャッチフレーズをポスターやカタログ等に使用する場合は、次のことを注意してください。
短い短文、フレーズだからといっても注意が必要です。
3.他社商品のキャッチフレーズやスローガンを使用する場合の注意点
・他社のカタログやパンフレットの一部を使う場合
使用しようとする内容の一部が著作権法で保護されているものかどうかをまず判断します。
著作権法の定義「思想または感情を創作的に表現したもの‥‥‥」であれば保護されているもですが、定義にあてはまらないものであれば何も問題はありません。
カタログやパンフレットには、写真やイラスト、商品説明や文章内容を図解めによく用いられていますね。もちろん、写真やイラストは立派な著作物のため著作権があります。しかし、単なる図形や図解などの創作性のないものは著作物ではありません。
たとえば、★マーク、(^^♪マーク、♪、記号などの簡単でありふれている図形などは自由に利用してもかません。
カタログやパンフレットも引用条件にあてはまり、必要不可欠の場合「引用」として利用することができます。
しかし、自社の広告宣伝物等においては、混同を招く、誤解を招くような使用はできません。あくまでも引用は記事であったり、出版物であったり、自分文章(作品)の内容に対する、文章主体のものだからです。
3.他人のものを使用するのが怖い
他人の著作物を利用すると、すぐお金を取られる…。訴えられてしまう…。そんな考え方をしている人が多くいます。。
たしかに著作物は知的財産権の一部であり、「財産権」と名がつく以上、対価というものは存在していますが、知的財産権侵害のほとんどのトラブルはこのような金銭的なものでなく、「ルールを知らないか」、「めんどうくさいと思うか」、「知って勝手に利用しているか」という共通点のトラブルが多いのです。
知的財産権(著作権含む)等は、無許可でない限り、金銭的なトラブルが少ないのはなぜかといえば、使用許諾を得るために契約をすることによって互いの利益が明確になるためです。
だからトラブルのほとんどは無許可であったりルールを無視して勝手に利用することにあります。
むしろ、両者との話し合いによって、無料で利用できるケースも多大に存在しています。
たとえば「サンリオのキティちゃん」や、まちおこしで活用されている有名キャラクーなど、利用者との話し合いで無料で貸している場合も多くあります。このように大手、有名キャラクターだからといっても、すべて有料ではありません。
これは、特許等の工業所有権も同じことがいえます。
さらに、著作権の発生していないものや、著作権の保護期間が完全に切れているもの(創作者の死後70年以上経過した作品)。特に100年、200年前のものは一切問題はありません。さらに現代でも充分通用する作品が無限にころがっています。
たとえば日本全国各地にある郷土資料館や、美術館。さらに古本屋(古書などを扱っているところ)など。さらにインターネットで世界中の著作権切れ書物(絵画等)なども手に入る時代。さらに図書館などの活用もあります。
このようなことを研究開発してみるのも新しい財産権のひとつです。
4.参考までに著作権切れ作品の一部紹介(パブリック・ドメイン)絵や写真等






著作権が切れたものは誰もが自由に利用できます。
ただし、注意点もあります。それは法律ではまだまだ確率されていませんが「画像権」なる言葉が独り歩きしだし、著作権が切れたものを画像保存した人の労力という点が主張されるようになったことです。
ですから著作権の切れたものでものでも「無断使用禁止」なる文面が記載されている場合があります。
私個人の見解ですが、誰が撮影しても同一の画面に関しては「単なる事実」のために「画像権」なるものは発生しないと考えます。むしろ、それは「画像の所有権」「データ上の所有権」だと思うのです。
しかし、古い著作権の切れた著作物を修正、修整加工したもの、復元したものは新たなる権利が生じていることは事実です。その修整、復元するための労力や時間、費用等が発生するものだからです。(現在、このような半例が少ない)

特非)著作権協会です。みなさまいつも目を通していただいて感謝申し上げます。死後70年経過した作品はすべてパブリック・ドメインとして誰もが自由に利用することができます。
この著作権切れの素晴らしさは誰もが勝手に自分の媒体に使用することができることです。
また、歴史に埋もれたままの素晴らしい作品などを掘り起こして、現代によみがえらせる。これも素晴らしい仕事でしょう。
デジタル時代の今こそ、著作権本来の素晴らしさ、面白さがこのアナログの世界には無限に存在していることがわかります。
※特非)著作権協会おすすめ電子書籍〈~無料・無断で使用できる著作権活用法~「無断OK!著作権」④〉全4巻まで好評発売中!note記事には書ききれない物語満載。お時間がありましたらお読みくださいね。下記で目次内容等を検索して見てください。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
