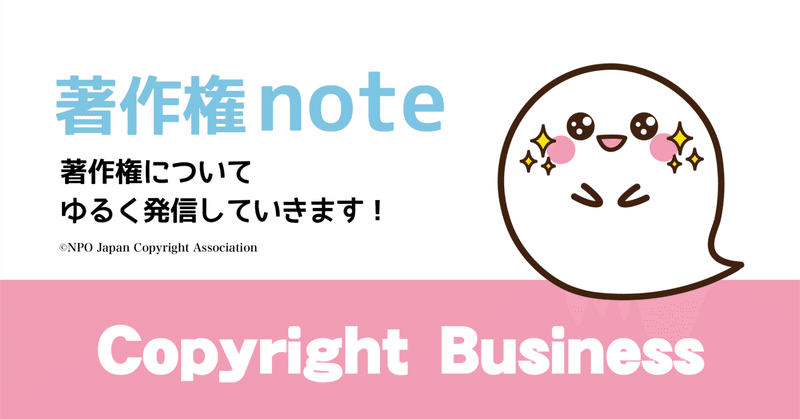
70.公開されている美術の著作物はSNS等の投稿などでも自由に使えるんだよ!
1.公開されている美術の著作物は自由に利用できる
本来、彫刻を写真に撮る行為は複製に該当し(著作権法第二条一項十五号)、彫刻について著作権をもつ権利者の許諾がなければ複製権侵害行為となります。
しかし、著作権法第四十六条(公開の美術の著作物等の利用)では、美術の著作物で屋外に恒常的に設置されているものまたは、建築の著作物については著作権者の許諾なしで自由に認められています。
たとえば、ある公園内に置かれている彫刻を撮影し、その写真を使い、本の表紙にしたり、他の広報物に利用したとしても著作者、著作権者とも許諾を得る必要はありません。
では、著作権法第四十六条を見てみましょう。
(公開の美術の著作物等の利用)
第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に揚げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
どうでしょう。この四十六条の一・二項は、屋外の彫刻を勝手に増製したり、その増製物を譲渡してはならない。三の「屋外の場所」とは、不特定多数の人が見ようとすれば自由に見ることのできる広く開放された街路・公園のある場所と解釈され、また「恒常的に設置する」とは、社会通念上、ある程度の長期にわたり継続して、不特定多数の者の観覧に供する状態に置くことを指しています。
四は、その彫刻写真を使い販売を目的として複製したり、複製物を販売することはできないということです。
2.東京地判平成17年7月25日「まちをはしるはたらくじどうしゃ」事件
こんな事件がありました。
路線バスのボディに描かれた絵画が著作権法第四十六条の美術の著作物に該当するかどうかが争われた事件で、判決は、
「著作物を利用した書籍の体裁及び内容、著作物の利用態様、利用目的などを客観的に考慮して『専ら』美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、またはその複製物を販売する例外的な場合に当たるといえるか否か検討すべき」とした上で、次のように判断しました。

パブリックアートの著作権について考えて
「以上認定した事実によれば、確かに、被告書籍には、原告作品を車体に描いた本件バスの写真が、表紙の中央に大きく、また、本文十四頁の左上に小さく、いずれも、原告作品の特徴が感得されるような態様で掲載されているが、他方、被告の書籍は、幼児向けに、写真を用いて、町を走る各種自動車を解説する目的で作られた書籍であり、合計二十四種類の自動車について、その外観及び役割などが説明されていること、各種自動車の写真を幼児が見ることを通じて、観察力を養い、勉強の基礎になる好奇心を高めるとの幼児教育観点から監修されていると解されること、表紙及び本文十四頁の掲載方法は、右の目的に照らして、格別の不自然な態様とはいえないので、本件書籍を見る者は、本文で紹介されている各自動車の一礼として、本件バスが掲載されているとの印象を受けると考えられること等の事情を総合すると、原告作品が描かれたバスの写真を被告書籍に掲載し、これを販売することは、『専ら』美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する行為には該当しないというべきである」
長くなりましたが、販売の場合においても、本書の目的に照らし、格別不自然な扱いでなければ問題がないことがわかります。
3.公開されている美術の著作物はSNS等の投稿などでも自由に使える!




4.ピカソの絵画とゴッホの絵画を自由利用する場合
自分のホームページや各種の団体がホームページ上に絵画を利用する場合。
ピカソの絵は、著作権法第三十二条(引用)または著作権法第四十一条(時事の事件の報道のための利用)であれば自由に利用できますが、その要件を満たさない場合は、ピカソの相続人の代表から許諾を得る必要があります。
しかし、ゴッホの絵の場合は一切許諾はいりません。
ここで問題は、ピカソ、ゴッホの死後起算です。まず、ピカソは亡くなってから70年を経過していないため、その絵を複製する場合は、現在でも日本の著作権法の適用があります。そのためピカソの場合は「引用」・「時事報道」以外はむずかしい。

5.ピカソの場合、どうすれば許諾を、誰から得ればいいのか
ピカソが1973年4月8日に死亡したことにより、同人の子であるクロード・リュイズ・ピカソ、マヤ・ルイズ・ピカソ、パロマ・ルイズ・ピカソおよびポール・ルイズ・ピカソが、本件絵画の著作権を相続し、ポール・ルイズ・ピカソが1975年6月5日に死亡したことにより、同人の子であるベルナール・ルイズ・ピカソおよびマリナ・ピカソが、ポール・ルイズ・ピカソが有していた本件絵画の著作権を相続しました。
クロード・リュイズ・ピカソほか上記相続人4名は、ピカソの絵画の著作権を不分割共同所有しているところ、クロード・リュイズ・ピカソは、不分割共同所有者の管理者として、フランス民法の規定に従い、不分割共同所有者を代表する権限を有しています。
したがって、許諾が必要な場合、ピカソ絵画の著作権の不分割共同所有権管理者であるクロード・リュイズ・ピカソから許諾を得ることになります。
5.ゴッホの絵は誰もが自由に利用できる
著作権法六条三項は「条約によりわが国が保護の義務を負う著作物」について、日本の著作権法による保護を受ける旨を規定している。この規定に基づき、オランダの画家であるゴッホの作品が日本で利用される場合、日本の著作権法によって保護されることになります。
ところで、著作権法五十一条二項によれば、著作権の保護期間は、著作者の死後七十年とされている。この保護期間の起算は、著作者の死亡した年の翌年から始まります(著作権法五十七条)ので、これによれば、一九四○年の末日をもってゴッホの絵画の著作権は消滅していることになります。
では、ゴッホ作品展をnote記事で開催してみます。
© 2015 ネット美術館「アートまとめん」. All rights reservedより。


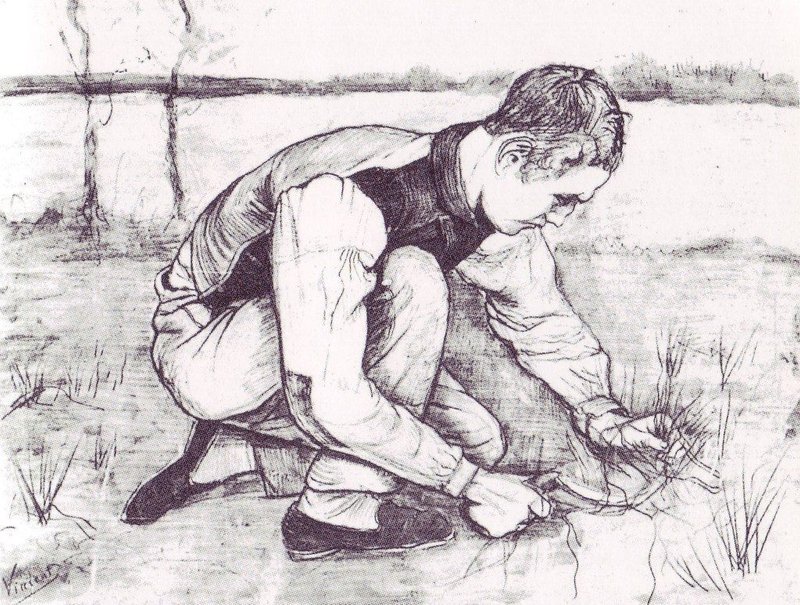











しかし、サンフランシスコ平和条約に調印した旧連合国国民の著作物が日本国内で利用されるときには、著作権法で定められた保護期間に「戦時期間」(大平洋戦争が勃発した日からそれぞれの国が平和条約に批准した日までの期間)という、特別な著作権の保護期間が加算されることになります。これは敗戦国のうち唯一わが国が背負った第二次世界大戦の賠償ともいえます。オランダの場合、この「戦時期間」は三八四四日(約十年半)となっています(宮田昇『学術論文のための著作権Q&A』二〇〇三年、東海大学出版会、100頁)。この戦時期間を加えると、ゴッホの絵画の著作権歩御帰還の終了時期は、およそ一九五一年の六月頃ということになります。
したがって、現在ではゴッホの絵画はすでに著作権が消滅しており、許諾なくして自由に利用することができます。
このように保護期間の終了によって許諾を得ずにその作品を利用できる画家は、ゴッホのほか、ミレー、ゴーギャン、セザンヌなどが挙げられます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
