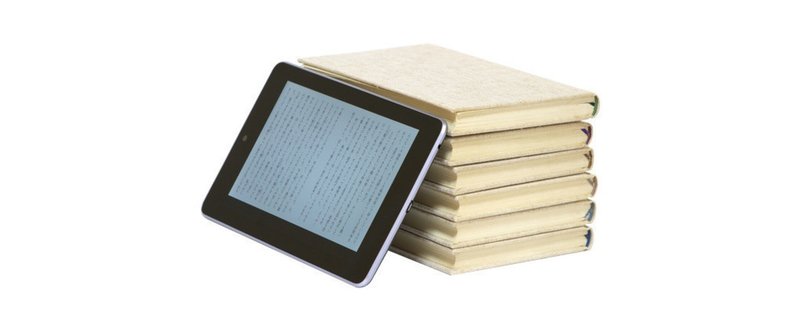- 運営しているクリエイター
2014年10月の記事一覧
ものを考えるとはどういうことなのか、四人の人類の教師たちが今私たちに教えることは数多くあると思います……──和辻哲郎『孔子』
「釈迦、孔子、ソクラテス、イエスの四人をあげて世界の四聖と呼ぶことは、だいぶ前からおこなわれている。たぶん明治時代の我が国の学者が言い出したことであろうと思うが……」
と書き出されたこの本は、『孔子』についてだけの本ではありません。むしろその書名を越えて、この4人がなぜ「人類の教師」と呼ばれるようになったか、その条件とはなんだったのかなどを追求した、知見に満ちた論述、それも推理小説のようなも
『史記』は人はどう生きたか、どう生きるべきかを記したドキュメントでもあるのです──宮城谷昌光『史記の風景』
130巻に渡る大著『史記』、そこには多くの人間たちの生死が描かれています。司馬遷が生んだ紀伝体という記述法は、歴史は人間たちのドラマであるという歴史観を司馬遷自身が持っていたから生まれたものではないでしょうか。そして宮城谷昌光さんもまたこの歴史観を持って、中国古代を舞台に歴史小説の名作を数多く生みだしてきたのだと思います。
この本は『史記』をそのきっかけにはしているものの、『春秋左氏伝』
地方文化の粋は「ものの言い方」の中にある。もう一度、日本のさまざまな声に耳を傾けてみませんか──小林隆・澤村美幸『ものの言いかた西東』
たった2音で会話が成り立つ!? それは
「け」
「く」
です。前者は「食え」で後者は「食う」だというのですが……。
「これについて、筆者(小林さん、澤村さん)は最初、大いに脚色された話だと信じていた。しかし(略)東北人の話し振りを観察してみると、あながちウソとは言えない気がしてきた」
この本は言葉(単語)の違い、イントネーションの違いといったように考えられてきた〈方言〉というものを「もの
私たちは〈肌触り〉というものを失いつつあるのではないでしょうか、ふと立ち止まって周りを見てみるとそんなことが頭に浮かびます──なぎら健壱『町の忘れもの』
下町を語らせたたらこの人の右に出る人はそうそういないのでないでしょうか。下町(と酒場)の帝王、なぎら健壱さんが自らカメラを構え、足の向くまま街を歩き、撮り(しかもモノクロ!)、綴ったエッセイです。
とかくこのような本ですと、ああっ思い出、懐かし話ね、と片付けられがちですが、なぎらさんの語り口と選球眼のよさでしょうか、ついつい引き込まれてしまいます。
取り上げられているものは、ロウ石、コッ
人間的な社会とはなにか、人間にとって必要なものはなんなのか、幾たびも考える必要があるのです──山崎章郎『病院で死ぬということ』
1993年の市川準監督で映画化もされたこの本はターミナルケアというものの重要性を世に問うたもはや古典といってもいいものだと思います。刊行以来、時が経ち、インフォームドコンセント、ガン告知についても、もちろんホスピスについてもいろいろ改善されてきていると思います(そう信じたいです)。
けれどその、一方で
「ガンの告知に関しては、ほぼ一般化したと思われますが、最近では無造作に告げすぎるケースが
読むたびにいつも新たな発見がある物語。夢と希望と純粋さがもたらしたものは……──木下順二『夕鶴』
民話『鶴の恩返し』は、報恩譚と世界中の神話や聖書などにあるように、見てはいけないものを見てしまい、悲劇(終末)をむかえてしまうという“見るなのタブー”をその民話の根幹としています。この戯曲にもその構造は生かされているけれど、この戯曲の悲劇性はそこだけではありません。
つう(鶴の化身)と、なかむつまじく暮らす与ひょうにつうはなにも不満はありませんでした。つうが織り上げた布の代金は二人で暮ら
私たちがいまだに危機の中にあり、新しい道を歩き出さなければならない時に道しるべとなるものがここにある──松井孝典『我関わる、ゆえに我あり』
とても刺激にみちた一冊です。松井秀典さんは「地球システム」という観点から、地球のいとなみというものを総体としてとらえなおそうとしているのです。それはまた新たな文明論(哲学)の提示でもあるのです。
「現代とは、一三七億年の時空で、宇宙、地球、生命、文明をかたることができる時代です。一三七億年の時空という視点に立つことで、我々が知らない領域がどこにあるのか、我々は何を分かっていないのかを、よう
「無知がさかえたためしはない」。だからこそ新たな〈知〉のありようを求め続けなければならないのです──笠井潔・白井聡『日本劣化論』
「敗戦を終戦と言い換えたことを典型として、そこには言葉を変えることでイメージを変えようとする姑息で欺瞞的な作為が歴然としていますね」(笠井さん)
この欺瞞が劣化をもたらした一因であるのは間違いありません。欺瞞は怠惰を生み、自分の都合の良いように世界を解釈してしまいます、いつでも「アメリカが助けてくれる」
といったような。このご都合主義の一例として二人は太平洋戦争末期のソ連を通じた和平工
変化をし続ける日本人の怨霊・霊魂観。それは日本文化の変化でもあり、そこから学べることは多いのです──山田雄司『怨霊とは何か』
物語の世界では『源氏物語』の六条御息所が生霊、死霊として有名ですが、歴史上の怨霊としては、この本の副題になっている菅原道真、平将門、崇徳院が日本三大怨霊としてよく知られています。
「個人の病気や死、さらには天変地異や疫病などが発生した場合、その原因を怨霊に求めようとすることは、日本社会の基層に今でも脈々と流れている。相手側から弾圧されたりしたことにより、追い込まれて非業の死を遂げ、その後十分
さまざまな飾りを取り去った後で〈大いなるもの〉を感じた時にもっとも素直に、謙虚にそして誠実にふるまうこととは──田川建三他『はじめて読む聖書』
全体の三分の一を占める聖書学者・田川建三さんのインタビューを中心に、9人のかたたちに「聖書を、誰が、どのように読んできたのかを問うた」(松家仁之さん)ものを集めています。
やはり圧巻なのは「神を信じないクリスチャン」と自らを称している田川建三さんへのインタビューです。2007年から『新約聖書訳と註』という個人訳を刊行中です。(完結まであと3年くらいかかると田川さん自身が書いていますが)
お月さまや流れ星、ここに描かれた月たちはなかなか一筋縄ではいきません──稲垣足穂『一千一秒物語』
ショート・ショートというジャンルですとすぐに思い浮かぶのは星新一さんの世界ではないかと思います。生涯で1000編を越える星さんのショート・ショートには、星さん独特の乾いたユーモアとウイットに溢れたものでした。
稲垣足穂さんのショート・ショートというものにも、星さんと同様、乾いたユーモアが感じられます。稲垣さんのものは乾いたというよりももっと鉱物質的というか機械的、それも精密機械というより
私たちの希望のひとつともなったNASA、その前史から将来までを見通した時、そこにはなにが見えるのか──佐藤靖『NASA 宇宙開発の60年』
「多くの人がNASAに人類の夢を見、NASAに輝かしい組織であり続けてほしいと願っている(略)そのような人々の希望と信念が、NASAに対する政治的支持の一つの背景となっているように思われる」
と本書の終章に佐藤さんは記しています。政治的支持というものを広義にとらえて政治・文化的支持というようにとればその通りだと思います。
私たちの宇宙というものに対する思い、それは夢であったり、驚異であった
美しさと強さ、優雅さと堅固さ、日本が世界に誇れる城郭の魅力を知ろう!──萩原さちこ『お城へ行こう!』
お城のファンというのは結構いるんじゃないでしょうか? 天守閣を見つけるとつい登りたくなったり、お堀を見ると、おまけに水鳥などがいるとつい気分が和やかになったりする人は多いのではないかと思います。(もちろんお堀は防塁ですから中にはいろいろな防御用の仕掛けがしてあったりします)
萩原さんは小学校2年生の時に松本城に行ったことをきっかけにお城に魅せられたそうです。松本城の登りにくい階段を怪訝に
しなやかで、つよい言葉、「逆転しない正義は献身と愛です」この言葉一筋に生きたやなせさんの見事な一生!──やなせたかし『わたしが正義について語るなら』
ひらがなで〈せいぎ〉という文字が頭に浮かんできました。やなせさんのメッセージはわかりやすく、しなやかで、つよいものです。この〈せいぎ〉に込めた思いをアンパンマンのキャラに託したやなせさんの思いがこの本のいたるところから、ヒシヒシと伝わってきます。そしてそれを生むまでのやなせさんの人生がここにあります。
「正義はある日突然逆転する。逆転しない正義は献身と愛です」
ここにはやなせさんの戦争体