
『史記』は人はどう生きたか、どう生きるべきかを記したドキュメントでもあるのです──宮城谷昌光『史記の風景』
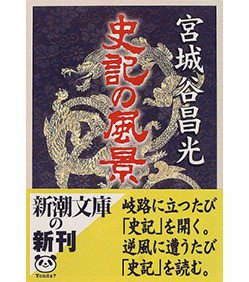
130巻に渡る大著『史記』、そこには多くの人間たちの生死が描かれています。司馬遷が生んだ紀伝体という記述法は、歴史は人間たちのドラマであるという歴史観を司馬遷自身が持っていたから生まれたものではないでしょうか。そして宮城谷昌光さんもまたこの歴史観を持って、中国古代を舞台に歴史小説の名作を数多く生みだしてきたのだと思います。
この本は『史記』をそのきっかけにはしているものの、『春秋左氏伝』『戦国策』『礼記』などの古典だけでなく、碩学・白川静さんの業績を参考にしながら、古代中国に発するさまざまなものに思いを凝らせたエッセイ集です。
織田信長のうつけの元祖(?)は斉の威王の故事によるのではないかとか、大政奉還は周公旦の逸事に発しているのではないかと、時空を越え自在に健筆をふるっています。日本史の思わぬところに『史記』に代表される中国古代の叡智の影響があることを教えてくれています。
その一方で宮城谷昌光さんは『史記』に隠された司馬遷の意図をも明らかにしようとしています。なぜ『史記 列伝』が伯夷叔斉から書き起こされているのか、司馬遷があえて記さなかったものはなにかなど『史記』にはまだまだ未解決な謎があるのだなと感じさせられます。
司馬遷の複眼的な視点も見逃すことはできません。それは呂后の描き方に典型的に現れています。稀代の非常な女性で大量の粛正を行ったとして知られる呂后も人民からみれば決して悪帝ではなかったのです。
「その政治は閨房を出なかったにもかかわらず、天下は晏(やす)らかであった。刑罰がもちいられるのは罕(まれ)で、罪人もめったにでなかった。人民は稼穡(かしょく)につとめ、衣食はいろいろ豊になった」
という呂后本紀にふれて宮城谷昌光さんは
「呂后は人民に愛され、劉邦の遺子と遺臣に忌み嫌われたという、ふしぎな像を歴史の網膜にむすぶ」
と続けています。この複眼的な視点は、時に当時の皇帝・武帝への批判だと思われる論述にもにうかがえます。
司馬遷は時に間違いも犯しているようです。
「司馬遷の杜撰さはしばしば専門家に指摘されるところであるが、それを超えて、歴史と人物の魅力が爍々と放たれている『史記』という書物は、つくづく不思議な歴史書だとおもわれる」
それゆえにこそ、さまざまな小説が書かれて続けているのかもしれません。
「人知の宝庫」という章から書き始められたこの本は、『史記』の大きさを教えるだけでなく、『史記』は一方では人はどう生きたかというあかしを記したドキュメント(!)でもあると私たちに教えてくれているのではないかと思います。
書誌:
書 名 史記の風景
著 者 宮城谷昌光
出版社 新潮社
初 版 2000年4月25日
レビュアー近況:朝からスマホの機種変に来ていますが、銀座のキャリア本店は野中以外、外国のお客様ばかりです。日本語で対応されるのが逆に恥ずかしいアウェイ感と闘ってマス。
[初出]講談社プロジェクトアマテラス「ふくほん(福本)」2014.10.30
http://p-amateras.com/threadview/?pid=207&bbsid=3198
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
