
国語を理系的に攻略したら、新たな学問になるんではないだろうか?
タイトル画像:辞書が開かれてる写真
きしゃこく先生の記事で、国語という学問と学生側の話がありました。
下のリンク:きしゃこく先生のnote記事
この記事の冒頭から、いきなり気になってしまいました。
(中野しょうた@高校生)
きしゃこく先生!
たしかに、うちの国語の先生も同じ感じです。
文学のウンチクばっかりで。
それが興味深かったらいいんですけど、
一方的な時が多くて…
ほとんどの生徒が寝てるか内職してます。
(きしゃこく先生)
しょうた君、これ、きついよね。
色んな学校のリサーチしてますけど、
かなり多くの学校で同様の事態になってるみたいだね。
というか、数十年間変わってないんだけどね。
日本の国語教育、大事です。だからこそ、しっかりした制度設計と成果を上げること、メンテナンスが重要。
同じです、数十年前に実感したこと
自分の高校の現代国語担当教員は、「あんたら日本人だから日本語はできるでしょ」と、その年の最初の授業の冒頭に述べて、「だからこの年の現国の授業はおしまい」と、1年間の休講が宣言されました。
これはこれで一つの真理です。
その先生は逆に古典に関して凄まじく面白い授業をしてくれました。
日本の国語教育で何を伝えて何は伝えなくて良いか、を先生なりに考えたのだと思います。

画像:古今和歌集のイラスト
音声合成を仕事で扱うと
音声合成を仕事にすると、日本語を「技術で扱う要素」で見ていきます。
扱うネタは文系ですが、やってることは理系、それもかなり技術系のアプローチです。
例えば、
データ収集とその手法
パターン分け
目的別データベース化
統計処理
構文解析とルール化
イントネーションと構文状の位置での変化ルール分析
など、色々な定量的な作業が必要。
この定量的な作業は、ある種の国語教育の手法になるのでは?と考えた次第。
それぞれの作業が言ってみればクイズみたいなもんで、面白くもできそうです。また、正解が作りやすい。つまり、納得感もあり、知識の上積みも見えやすい切り口、かつ、面白い時間となるわけです。
文学表現の中身、といったところすら、これらのアプローチで細分化できるかも。
従来の国語という科目に感じた欠点
作者の考えを述べよ、という問題を作者が解いてみたら、不正解だったことがあります。タモリ倶楽部でそんなことやってました。
主観を「正解」として規定した試験。これは一つの例ですが、問題は「主観」。
もちろん数学も、どの単元をどのタイミングでどの程度の理解レベルにするか、など進行設計的には主観は入りますが、問題に解答するプロセスには主観はあまり入りません。
国語は、まずは教育要綱という主観、題材を選ぶ主観、題材を解釈する主観、それをどう教えるかという主観が重なります。
それが、目的や手法や成果に客観的な指標があれば良いのですが、普通に考えてここまで重なると、統一的なポリシーが保たれる確率は下がります。
うじゃうじゃ書きましたが、要するに主観でフラつく危険が多いのが今の状況、と理解してます。
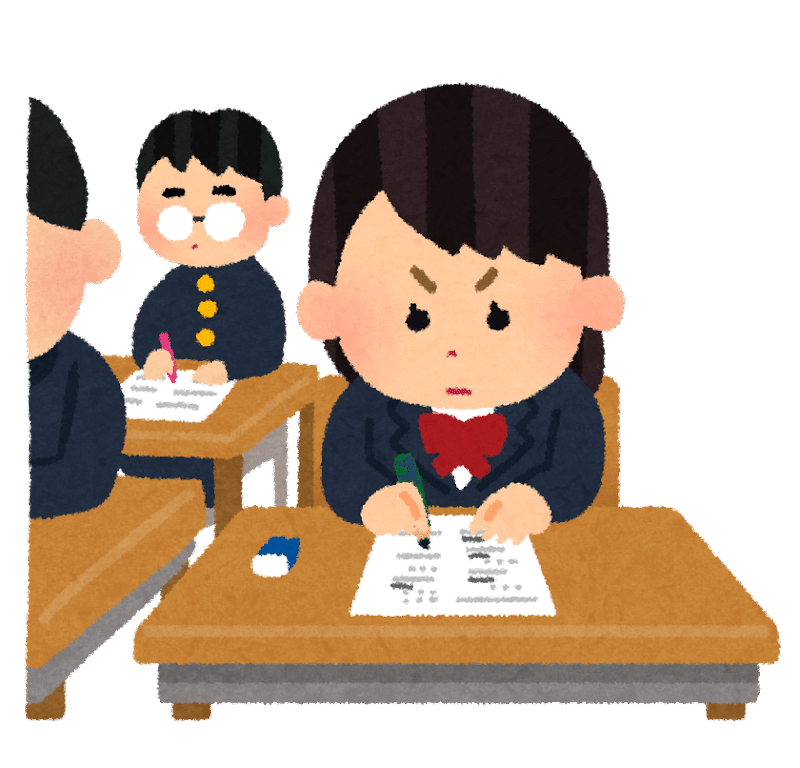
画像:教室で試験を受ける女子のイラスト
理系的アプローチ
仮に国語を理系的なプロセスで教えるとしたら、という思考実験をしてみましょう。
まずは要素の抽出
どういうパラメータで解析できるか、の細分化をします。単語、熟語、基本構文の種類、同音異義語、その反対、など色々な要素が考えられます。
要素と効果の整理
それぞれの要素の習得がどのような効果を与えるか、を見ます。
そんな事知らなくても問題ない、という項目はカットし、これは是非とも伝えたい、役立つというものを優先度高く、でしょう。
与えたい効果のピックアップ
この要素を使い、どのように生徒に何を与えるべきかを設計します。
どのように役立つ、という効果を想定すれば設計しやすくなります。
効果の習得目標とプロセス設計
要素ごとに時系列にさらに細分化設計。
この細分化により、習得単位を小さくし、脱落しそうな場合のリカバリ範囲を小さくします。
実行とメンテナンス
実際に年間を通し履修してもらい、成果を分析、プロセスの改善を行います。これを毎年繰り返します。
永遠のベータ、って奴ですね。しかも、言葉は年々変化していきます。それに追従は必要。今、明治時代の教科書をそのまま使ってないので、既にそうなってますが、もっと頻度は上げる必要があります。
などと考えてみました。
こんな感じにやれば、新しい国語教育はできそうです。
問題はこの要素を選ぶ段階でも、ピックアップという主観が入ること。つまり、国としてどのような国語力を国民に与えるべきか?という設計思想が重要。
どのような国語力を付けさせるべきか
日本語は日本に生まれて育てば、ある程度喋れます。
でも教育をするということは何か、そこに目的があるはず。
社会人としてずーっと人とやりとりしながら、国語に感じた点を考えてみると、何をすべきか?のヒントになりそう。
主にコミュニケーション能力、という点で実際のフィールドで気になっていることが多く、そのような内容になります。

画像:2人がパズルのピースを持ち寄って、ピッタリ合ってるイラスト
論理的組み立て
a=b、b=c、よってa=c、といった論理的な状況を簡潔に述べるなどの、基本構文。
コミュニケーションの基礎になります。
正しい日本語の意味
よく使う言葉の意味は、コミュケーションを行う際には、共通に理解しておかないといけません。
「それを行うのはやぶさかではありません」を、嫌々やりますよ、と取るのか、喜んでさせていただきます、と取るのか、では大きく印象が異なります。こんな言葉、沢山あります。
誰だ、ふいんき、と入力して変換してくれない!と困ってる人は!
正しい外来語のオリジナルと現在の意味
日本に入ってきた時から、外来語の日本での意味は変化しています。また、入ってきた時に既に間違えているものも。アイロン、ホチキス、ファイト、ラムネ、などなど。
これらはかなり古い例ですが、最近使われている言葉でも似たようなことは起こります。
教育全体では英語もやっているので、ではオリジナルはこうだね、日本ではこのように使われるけど、と知ることは両方にとって良いこと。
また、それを日本語で言い換えれば、ということができれば、平易な説明書やマニュアル作成にもつながります。
地名
結構郷土色を入れられる領域です。より教養を深め地域への愛着を身につけるのに良いネタ。
インフラ名
社会と被りますが、社会インフラで使われる言葉は、正確に覚えておいて損はありません。
その中身になると、社会科に任せる必要があるものもあります。しかし、時系列を揃えて、「はい、詳しい内容は次の社会科で説明します」となれば、記憶定着率も上がり良いことばかり。
これらを理系的に。成果を処理する
小テストをやっておしまい、ではもったいない。細分化した成果を可視化して、リカバリ範囲を特定してあげられれば、モチベーションも維持でき、脱落も減ります。
これによって偏差値ではなく習得到達者数で目標設定できます。
さらに授業の形式も
ICTやらGIGAスクールやらなんやら言ってますが、出題→解答→面白解説→結果発表、などをバラエティ番組の進行風に進めれば、飽きる暇などありません。
教科書読んで黒板に書いてそれを写して、というやり方の限界はあります。どうせ改革するならここまでセットで。
何度も書きますが
こんなのすぐ流れ作れます。ご相談ください。初回相談は格安で承ります。
さて。何でこんなことを書いているかと言いますと、ゲーム開発からスタートして、その後、ゲームのお作法でさまざまな一般サービスを立ち上げてきた、ゲーミフィケーションという言葉が一般的になる前からのゲーミフィケーション実践者だからです。
なので、こんな本も出してみました。
もっと自分のスキルを自分を育ててくれた教育に役立てたいな、と思ってます。そうすると、当時の子供たちの貴重な時間と貴重なお小遣いを頂いていた罪悪感が薄れるからです。
#国語
#教育
#ICT
#GIGAスクール
#文科省
#ゲーミフィケーション
#教育改革
#学校
#きしゃこく先生
#学問への愛を語ろう
#国語がすき
#現代文が好き
#古典が好き
#漢文が好き
#ゲームで学んだこと
まだまだ色々と書きたい記事もあります。金銭的なサポートをいただけたら、全額自分の活動に使います!そしたら、もっと面白い記事を書く時間が増えます!全額自分のため!
