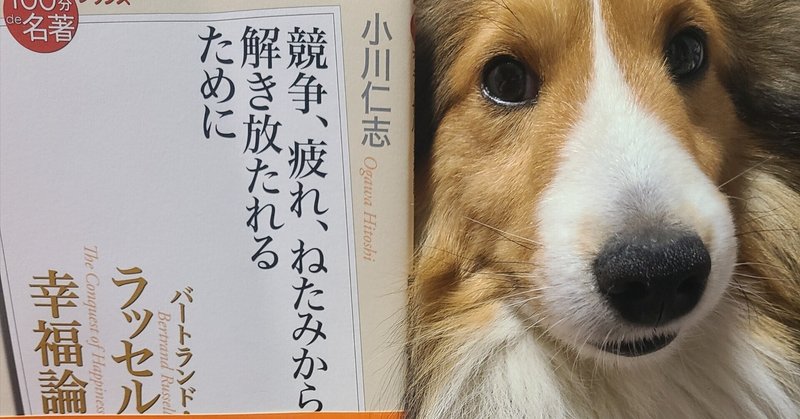
【2024 読了 No.10】小川仁志著『100分で名著・バートランド・ラッセル幸福論』(NHK出版)読了
ラッセル(🇬🇧)の『幸福論』は、アラン(🇫🇷)、ヒルティ(🇨🇭)の『幸福論』と並んで“三大幸福論”と呼ばれているそうだ。
ちなみにミスチルの「PUDDLE 」の歌詞の
「いいことがあった時の笑顔じゃなくて、笑顔でいればいいことあると思えたら、それがいいことの序章です」
というフレーズだが、これはアラン(🇫🇷)の『幸福論』の「幸せだから笑っているのではない、むしろ僕は笑うから幸せなのだ、と言いたい」から来ている。作詞者の桜井和寿本人も認めている。
ラッセル(🇬🇧)に興味を持ったのは、【2024読了No.8】で紹介した國分功一郎著『暇と退屈の倫理学』に出てきたからである。
ラッセルは反戦反核兵器運動でも活躍する「行動する哲学者」であった。特に有名なのが1955年の「ラッセル=アインシュタイン宣言」である。これは前年の1954年のビキニ環礁でのアメリカの水爆実験と第五福竜丸の被曝を受けて出されたものである。
ラッセルは元々は数学者だった。数学者としてホワイトヘッドとの共著で『数学原理』を出版したのち政治に関心を持ち始め、下院議員補欠選挙に立候補したりした(落選したけど😑)
本格的に政治学に転向したのは、1914年に勃発した第一次世界大戦勃発直後。イギリスの参戦決定に、国民が歓喜するのを目の当たりにしたことが契機だった。
「人間とは戦争を好む実に非合理な存在だ。今こそこの問題に取り組まなければならない」と考えて転向したそうだ。
ラッセルの『幸福論』の概要を一言でまとめれば、以下のフレーズになる。(原書は英語だから少しは読めるかなぁ~と思って買ったんで、英文も付けてみた)
「幸福の秘訣とは何か?君の興味をできる限り広げてみることだ。(←私の訳)」
The secret of happiness is this: let your interests be as wide as possible, …
視野を広げる、趣味を持つ、読書をする。広い視野無くして自分を俯瞰する(≒客観視する、メタ認知する)なんてできない。
彼は幸福を論じる序論として、その反対である「不幸」について分析する。
彼は実に沢山の不幸の種類を挙げるのだが、先ずはそれら諸々の不幸の最大の原因として、「自己没頭“self-absorption”」を掲げている。自己没頭とはつまり、興味が自分にだけ向けられている状態。
この「自己没頭」の三つのタイプとして、「罪びと(sinner )」「ナルシスト(narcissist)」「誇大妄想狂(the megalomaniac ※ちなみに原文はmegalomania じゃなくてthe megalomaniac だった。)」を挙げている。
「ナルシスト」や「誇大妄想狂」とかはすぐ分かることだけど、この「罪びと」とはちょっと説明を読まないと意味が分からなかった。
読んでみて驚いた😳。
要するに罪悪感を植え付けられた人とその状態を指すらしい。人が「罪びと」になる要因として、「到達しがたい対象(母親または母親に代わるもの)に対する献身的な愛情」と、「幼年期に植え付けられたばかばかしい道徳律」があるそうだ。ちなみに、これはラッセル自身が叔母に厳格な躾を受けた実体験に基づく分析である。
あらま😳
まさに毒親に育てられたアダルトチルドレンの生きづらさ問題じゃないっすか。
いやぁ~ラッセルの洞察眼の鋭さに改めて驚かされる。まさに今日的な問題を予言しているかのようだよね。
私は1990年代以降に出されたアダルトチルドレン関係の書物によって自分の生きづらさの謎を解くことができた。
それが、既に第二次世界大戦前の1930年に、しかも男性の著作で、“母(またはそれに代わるもの)”のばかばかしい躾に名を借りた精神的虐待について書かれていたことは~😳。学生時代にラッセルに出逢っていたならばなぁ~と悔しく思う。
ラッセルの「今日的な問題を予言しているかのうな」ものとして、「病気の貴婦人」問題の指摘があげられる。
これは、母親が自分の病気を理由に「自分の娘のうちの一人に対し、自分を看護するために完全な自己犠牲を期待する」ことである。
あらま😳
まさにヤングケアラー問題じゃないっすか。
今日本ですごく問題視されてることだよね。
いや、しかしなのだ。
ラッセルの「予言」は予言なのではなく、実は洞察力の鋭さがもたらす「タブー破りの問題提起」なのである。
毒親の虐待問題もヤングケアラー問題も昔っからあったのである。
ただ、それに気がつき、それを発言することは、タブー視されていた。ただ、それだけなのである。
10年程前、私の家の最寄り駅付近で、祖母を車椅子に乗せて押している孫娘らしき16歳前後の若い女性をしばしば見かけた。若い子に似合わず、髪型が一本の三つ編みというかなり古風な髪型をしていた。
老婦人には、青春まっただ中のハズの孫娘(orらしき女性)の時間を奪っているという後ろめたさは微塵も感じられなかった。むしろ、「次はあっち行くのよ❗️」とばかりに指差しながらイケイケ状態だった。対して、若い女性の方は従順でもの寂しげだった。
「あるいは家政婦さん、もしくはヘルパーさんとして雇われているのかな?」とは全然感じられなかった。
その後、その老婦人が亡くなったのか、駅でこの女性がフツーのスーツを着ていたのを見かけた。髪型が古風な三つ編みのままだったので、かなりミスマッチな感じがした。それ以降その女性を見かけたことはない。恐らくこの街を捨てて行ったのだろう。
まだヤングケアラーという言葉も無かった時代であるが、彼女はまさにそのヤングケアラーだった。
ヤングケアラー問題は近年になって発生した問題なのではなく、前からあったものが近年になってやっと“発見”された問題なのである。
「孝行=良いこと」という世間一般の価値観によって覆い隠され、その“発見”が遅れただけなのである。
ラッセルはタブーを気にせずにズバズバ物を言う人だった。だから「世間に叩かれる」人だったそうである。でも、それは「世評をまったく気にしていなかったと」言うより、「それ以上に、信念を貫きたかった」のだろうと、著者の山口氏は分析していた。
最後に私の一番気に入ったフレーズを。
「熟練を要する仕事に就いている人は、その技術を向上させることによっていくらでも仕事を楽しめる」
All skilled work can be pleasurable, provided the required is either variable or capable of indefinite improvement.
その通りで、改善の余地のある仕事は面白い。日々自分の成長を感じられ、喜びに溢れている。
ちなみにこの"Provided"は接続詞で、条件を示す言葉だそうである。文法的には、条件を満たすときに何かが起こることを示しており、この文の場合は「provided」は条件を導入し、その後に条件が続く形なんだそうだ。
私の英文法の質問に答えてくれたのは、なんとChatGTP 先生🤪。役に立つなぁChatGTP 👏
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
