
【医療とアートの学校 オープンキャンパスin浜松】トークゲスト紹介(2日目 6/9)
◾︎5限目 困りごととデザインの時間
6月9日(日)/10:50~11:40
【ゲスト】
ハングオーバー㈱ 代表取締役
いいね㈱ 取締役
㈱ひいらぎ 顧問
岩渕 鉄平(いわふち てっぺい)さん
コミュニティデザインラボ所長
松崎 亮(まつざきあきら)さん
【聞き手】
三重大学医学部3年
医療とアートの学校ディレクター
株式会社ここにあるインターン
佐々木一款(ささきいっかん)
【登壇者紹介】
ハングオーバー㈱ 代表取締役
いいね㈱ 取締役
㈱ひいらぎ 顧問
岩渕 鉄平(いわふち てっぺい)さん
#リンクワーカー
#商福連携
#工賃向上
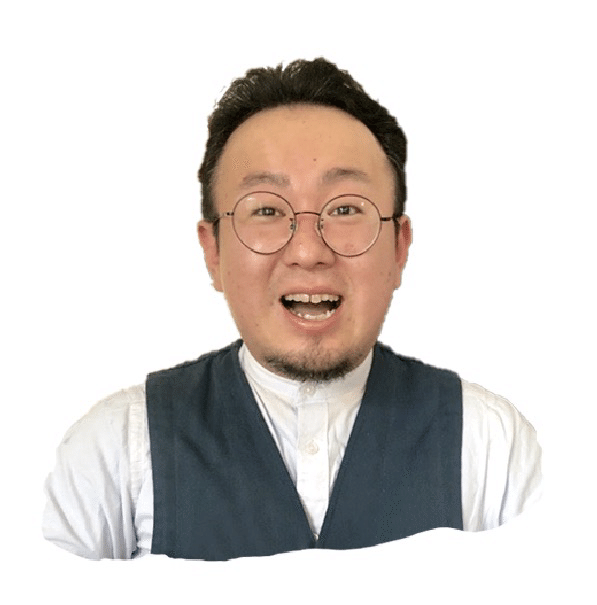
▼自己紹介
新潟県小千谷市生まれ草加市在中。2017年にデザイン、イベント企画の会社して独立。子どもが知的障害を持っている事からを2018年に事業に福祉を取り入れる。現在は草加市で障害福祉事業を展開している会社で顧問。茨城県では高齢福祉、引きこもり支援を行っている会社の取締役を務める。現在では草加市で福祉と街や商業と福祉をまぜている。お酒と新しい事をするのが好き。
▼活動紹介
2023年より、㈱ここにあると一緒に草加市で【ふくらむフクシ研究所】の活動を開始する。ふくフク研はトークイベントや勉強会、ワークショップや地域での実験をしながら、「福」祉の世界に新しい価値を「膨」らませ、また「含」ませていくための研究・活動を行っています。一方的関わりではなく、対話的な関係性づくりをする必要があります。多様な暮らし手が「ともに生きる」を実践していければと考えています。
コミュニティデザインラボ所長
松崎 亮(まつざきあきら)さん
#古着好き
#コミュニティソーシャルワーカー
#収集癖

▼自己紹介
大学卒業後、社会福祉協議会に入職し地域福祉業務を担当。
平成29年こどもの貧困支援に対して、具体的な支援施策を見つけられず悶々としていたところ、東京都文京区がおこなう「こども宅食」を知り、独自にリサーチ。
平成30年4月、商業デザイナー等とチームを組み、こども宅食をローカライズした「みまたん宅食どうぞ便」を立ち上げ、コミュニティデザインによるアウトリーチの可能性を感じる。
平成31年4月より、「自分たちのまちを、自分たちで楽しく」をコンセプトに、社協内に「COMMUNITY DESIGN LAB.(コミュニティデザインラボ)」を立ち上げ、2025年までに200の活動、2025人の地域活動者を生み出し、地域住民の活動で、地域課題の解決を目指すミッションを掲げ、目下活動中。
▼活動紹介
大学卒業後、社会福祉協議会に入職し地域福祉業務を担当。
平成29年こどもの貧困支援に対して、具体的な支援施策を見つけられず悶々としていたところ、東京都文京区がおこなう「こども宅食」を知り、独自にリサーチ。
平成30年4月、商業デザイナー等とチームを組み、こども宅食をローカライズした「みまたん宅食どうぞ便」を立ち上げ、コミュニティデザインによるアウトリーチの可能性を感じる。
平成31年4月より、「自分たちのまちを、自分たちで楽しく」をコンセプトに、社協内に「COMMUNITY DESIGN LAB.(コミュニティデザインラボ)」を立ち上げ、2025年までに200の活動、2025人の地域活動者を生み出し、地域住民の活動で、地域課題の解決を目指すミッションを掲げ、目下活動中。
三重大学医学部3年、医療とアートの学校ディレクター、株式会社ここにあるインターン
佐々木一款(ささきいっかん)
#修行中
#ランドスケープ
#志摩

▼自己紹介
三重大学医学部3年。札幌生まれつくば育ち。早稲田大学卒。1年と少し大学職員として働いたのち、三重大学に入学し今に至る。入院中の「なぜ病院はこんなに暗いのか?」、「友達もできるのに、なぜかわいそうな場所だと思われるのか?」という問いから、ホスピタルアートの世界に出会う。活動に関わる中で、引き受け合うことが重要なのではないかと考え、公共や相互扶助に興味を持つ。「ここで生きたいと思える風景をつくる人」を目指す。
▼活動内容
普段は、80歳の先生がひらく志摩の陶芸工房で色んな人と遊んでます。医療とアートの学校では三重県はしもと総合診療クリニックでのお手伝いをきっかけに、つむぎホームケアクリニックのディレクションやJPCA2024医療とアートの学校ブースの企画・プロデュースとして関わる。現在の興味領域としては、公共、相互扶助、社会参与など。9月から1年間休学して株式会社ここにあるで修行する予定。
◾︎6限目 ケアと表現の時間
6月9日(日)/11:50~12:40
【ゲスト】
アーツカウンシルしずおか
櫛野展正 さん
【聞き手】
株式会社ここにある代表/場を編む人
藤本遼(ふじもとりょう)
【登壇者紹介】
アーツカウンシルしずおか
櫛野展正(くしののぶまさ)さん
#アウトサイダーアート
#超老芸術
#アーツカウンシルしずおか

▼自己紹介
2000年より福祉施設で働きながら、広島県福山市にある鞆の津ミュージアムでキュレーターを担当。2016年、アウトサイダー・アート専門スペース「クシノテラス」開設のため独立。2021年には、アーツカウンシルしずおかチーフプログラム・ディレクターに就任。総務省主催「令和3年度ふるさとづくり大賞」にて総務大臣賞受賞。
▼活動紹介
2000年より福祉施設で働きながら、広島県福山市にある鞆の津ミュージアムでキュレーターを担当。2016年、アウトサイダー・アート専門スペース「クシノテラス」開設のため独立。未だ評価の定まっていない表現者を探し求め、取材を続けている。
2021年には、「アーツカウンシルしずおか」チーフプログラム・ディレクターに就任。総務省主催「令和3年度ふるさとづくり大賞」にて総務大臣賞受賞。
▼あなたにとって医療とアートとは?
アーツカウンシルしずおかでは、高齢者になってから表現活動を始めた人たちを「超老芸術」と名づけ、発掘紹介を続けています。
フィールドワークを続ける中で、人生を回復するための手段として、アートがあると考えています。
株式会社ここにある代表/場を編む人
藤本遼(ふじもとりょう)
#カレー
#場づくり
#ドラクエ

▼自己紹介
1990年4月生まれ。兵庫県尼崎市出身在住。
「余白のデザイン」と「あわいの編集」をキーワードに、さまざまな地域プロジェクトに関わる。代表的なものに「ミーツ・ザ・福祉」「尼崎ぱーちー」「カリー寺」「生き博(旧:生き方見本市)」などがある。多様な地域住民や関係者の巻き込み、プロセスデザインを専門としている。
「場づくりという冒険 いかしあうつながりを編み直す」著。
▼活動紹介
・ここにあるWEB
・ここにあるnote
・株式会社ここにある会社案内冊子
・藤本遼note
◾︎7限目 ライフの時間
6月9日(日)/13:50~14:30
【ゲスト】
社会福祉法人ライフの学校 理事長
田中伸弥(たなかのぶや)さん
【聞き手】
一般社団法人kinari代表理事・桐林館喫茶室【筆談カフェ】代表
コミュニティナース
夏目文絵
【登壇者紹介】
社会福祉法人ライフの学校 理事長
田中伸弥(たなかのぶや)さん
#ライフストーリーブック
#聞き書き

▼自己紹介
1981年 秋田県生まれ。大学卒業後、ケアの現場で介護/支援相談員として働く。
2011年 現法人の特別養護老人ホーム施設長就任。
2013年 同法人常務理事就任。
2019年6月より現職。
・仙台市介護保険審議会委員
・宮城県社会福祉法人経営青年会 会長
・北海道東北ブロック経営青年会 会長
仙台大学 特別講師 / 東北福祉大学大学院 公開講座講師 / 東北大学大学院 ゲスト講師
▼活動紹介
2018年 特養内に駄菓子屋を開設。
2019年「社会福祉HEROs TOKYO 2019」ベストヒーローズ賞を受賞。
2020年「社会福祉法人ライフの学校」に法人名称変更。
特養の庭をリノベーション『嫁入りの庭』開設。
同年9月 特養の屋上を改修『ライフの図書館』開設。
2023年 外国人技能実習生のシェアハウスと障害者の就労支援B型事業所が一体となった「ウェルカム!カフェ』開設。
2024年 特養、看護小規模多機能、放課後デイサービス・児童発達支援センター、保育園併設の多機能施設、六郷キャンパス開設。
一般社団法人kinari代表理事・桐林館喫茶室【筆談カフェ】代表
コミュニティナース
夏目文絵
#筆談カフェ
#福祉とアート
#コミュニティナース

▼自己紹介
三重県いなべ市在住。看護師、教員を経て、2020年に法人設立。コミュニティナースとして、「フクシはオシャレでオモシロイ」をコンセプトに事業を展開している。高校時代に出会った手話をきっかけに、聞こえない世界や障害者福祉に興味を持つ。「聞こえないことが誰かの障害ではなく、ジブンゴトになるきっかけにして欲しい」という思いから、廃校になった木造校舎(桐林館)で音声オフの”筆談カフェ”を運営している。
▼活動紹介
障害のある方の表現活動のサポートとして、アール・ブリュットの展示、福祉プロダクトの開発と販売、「筆談カフェ」などを展開している。
また、医療とアートの学校では、過去の看護師としての経験やコミュニティナースという視点からプロジェクトマネジメントやアドバイザーを担う。
現在、京都芸術大学大学院コミュニティデザイン領域・空間デザイン分野に在籍中。
◾︎8限目 別れとケアの時間
6月9日(日)/14:40~15:30
【ゲスト】
グリサポくわな
矢田俊量(やだしゅんりょう)さん
【聞き手】
一般社団法人Deep Care Lab代表理事・一般社団法人公共とデザイン共同代表
川地真史(かわちまさふみ)
【登壇者紹介】
グリサポくわな
矢田俊量(やだしゅんりょう)
#グリーフケア
#コンパッションコミュニティ
#仏教

▼自己紹介
生命科学の研究者が尊いご仏縁により僧侶に転身。向きあう対象は「生命」から「いのち」へ。専門はグリーフサポート、市民団体・公的機関等のピアサポートに関わり20有余年。浄土真宗本願寺派僧侶で住職。理学博士。
▼活動紹介
「いつも、ともにあった、お寺を いまも、ともにある、お寺へ」
”お寺”は、亡くなった人たちを偲ぶだけではなく、もともと、いまを生きる人たちの救いの場所。生きることの苦しみから解き放たれ、幸せを見いだすために、だれもが、こころ寄せる場所でした。いつも暮らしのそばにあって、ずっと人々に寄り添ってきた”お寺“。「りてらプロジェクト」では、そんな”お寺”本来の姿を取り戻し、ほんとうの“お寺”を新しいカタチで、いまに伝えていきます。
▼あなたにとって医療とアートとは?
元来、医療もアートも宗教から生まれてきたもの。現代においてアートを接点にした医療と宗教の協働の可能性を探ってみたい。
一般社団法人Deep Care Lab代表理事・一般社団法人公共とデザイン共同代表
川地真史(かわちまさふみ)
#想像力
#ケア
#修行

▼自己紹介
Aalto大学CoDesign修士課程卒。フィンランドにて行政との協働やソーシャルイノベーションを研究の後、現在はエコロジーや人類学、未来倫理などを横断し、祖先や山川草木・神仏・未来世代への想像力とケアを探求。論考に『マルチスピーシーズとの協働デザインとケア』(思想2022年10月号)、共著に『クリエイティブデモクラシー』(BNN出版)。畑をやったり、仏様を彫ったり、山に登ったりします。狩猟免許もとりたい。
▼活動紹介
渋谷区のソーシャルイノベーションラボ設立伴走、"産む"を問い直すデザインリサーチと企画展「産まみ(む)めも」、芸術文化・ケア・まなびを軸にあそびから死生観や生き方を見つめ直す地域のお寺・應典院の構想作りと運営、海からプラスチックまで、多種をケアする実験的プログラムの展開などいろんなことをしてます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
