
「ラバーソウル」4|SF短編小説に挑む#4
エピローグ↓(読んでいない方はこちらから)
愛すべき主人公と幸福な社会の隔たり③
群衆のおおよそは広場内に集まりつつあった。
”多世界上映イベント”の上映は間もなくであり、広場内の人々は期待と興奮により、「意子共振器」を大きく振るわせていた。
その中で一人立ち尽くしている男がいる。
高橋である。
彼の周りには言わずもがなある程度のコミュニティが形成されていた。そのコミュニティと彼との間には大きな溝があり、隔絶された彼という個人は、疎外感とともにコミュニティの閉鎖的断絶を受けながらその憂鬱さを受容していた。
コミュニティはそこに組する人々の全てを受け入れ、開放的な繋がりを広げるが、それは感情を持つ者の権利だった。
上映五分前のアナウンスが場内に響き周り、人々の熱気は高潮し、ある程度の騒がしさが会場を包んでいた。
高揚と抑揚、一つの小さな感情の波が大気を震わせ、人々の間を行き交いながら互いに干渉することでそれは大きな波と化していた。
その巨大な振幅を持つ周波数は、莫大なエネルギーを生み出す社会の潤滑油として人々の恵みとなるのだ。
高橋はこの参画的な社会的発電に貢献することはできない。そのための共振器を彼は着けていないのだ。そういう意味では、彼は社会の落ちこぼれである。群衆の異端児である。
彼は広場の後方でスクリーンのただ一点を眺めていた。それは必然的一人を受け入れた者の独特な時間の使い方をだった。傍から見れば胸に着いているはずものが着いておらず、何も映っていないスクリーンをただ見つめている不審な男である。
彼はスクリーンを見つめ、上映五分前のアナウンスからきっかり300秒を数え始めた。それも必然的一人を受け入れた者の独特な時間の使い方だった。
25秒、24秒、23秒…(彼は大きな数字でもカウントダウン方式で数えるのが好きらしい)
あと少しで上映が始まる。
彼は数えながら”ここ”に来た意味を考えていた。
誰かの声を聞きたかったのか? 独りでいることに疲れたのか? 単に外の世界の様子が気になっただけなのか?
おそらく答えは出ない。彼は自分自身のことを全く理解できていないからだ。
彼の無駄な思考を遮るように、上映開始のアナウンスがきっかり10秒前に流れ始めた。
"Saluton ĉiuj.(みなさま、こんにちは)
La filmo baldaŭ komenciĝos.(間もなく上映がはじまります)
Ĝuu!"(楽しんでください!)
会場は静まり返り、群衆は一斉と前方にある巨大なスクリーンに顔を向けた。それはまるで餌を与えられたハトの群れの様に儀式的であった。
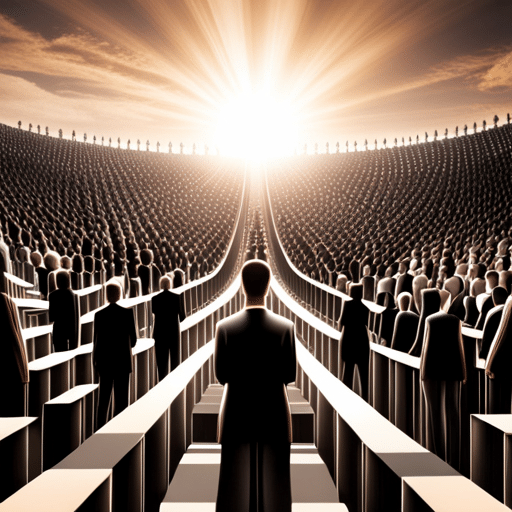
スクリーンが光だし、小さなノイズ音とぼやけた映像が徐々に映り始めている。徐々に鮮明になる映像は、定点カメラで取られたように、固定されてある程度の高さから映し出されていた。
一般的に“多世界上映イベント”では、次の三種類のどれかが映し出される。
①多世界ニュースの映像(多世界でも流されてるテレビのような映像)
②多世界の日常的映像(上空に設置された多数の監視カメラのような映像)
③何も映らない(運が悪い場合のみ)
今回上映されたのは②であった。
スクリーンには多世界で暮らしている人々の様子、街並み、交通技術などの社会的文化が映しだされていた。
画面の向こう側にある世界は分岐番号「1371―11019―293137」と呼ばれているが、実際にそう呼ぶのは政府だけである。分岐番号とは、多世界が分岐し始めたとされる日を基準にして、そこから無数に枝分かれた世界を割り振った番号である。
無数に分岐された世界はそれぞれが異なる発展を遂げている場合が多く、分岐点が過去になればなるほどその差異は明らかであった。
分岐番号「1371―11019―293137」には、可視光に分類されるそれぞれの波長を反射する物質が存在しなかった。その世界の物質はみな、反射された光をある一定の波長のみで返すという特殊な性質を持っていた。
簡単に言うと、色の無い世界が作られるということである。
白と黒だけの世界。
故に別名、“世界モノクロ”と名付けられた。
“世界モノクロ”の文明レベルは低いものだった。衣服はかろうじて陰部を隠す程度のすっきりしたペラペラな何かだけで、ファッション性は皆無である。
住居はコンクリートのような壁に囲まれた簡素な構造に、同じ様な材質のものを切り揃えた空間があるだけで、部屋という概念を満たしていない。
食事は固形物を柔らかくする程度の調理のみで、見た目はひどいものである。
高橋はその光景を見て、おそらく色という認識が無いことで味覚や視覚、触覚レベルの感覚が未発達となっている、という結論に至った。
彼は認知進化学の心得があった。
彼は以前、「生物の感覚的な認知がその進化の形を決定する」という旨を論文として発表しようとしていたことがある。だが落ちこぼれである高橋は、書いても世に公開する勇気が無かった。
スクリーンに映し出されたその光景は、広場の人々を盛大に興奮させた。その興奮は心底の軽蔑によるものだった。そこにいる全ての“人間”は自分たちの世界の優位性の悦に肩まで浸り、高尚な存在であることを実感していた。
高橋はそれをとことん滑稽だと思った。彼は落ちこぼれの異端児ではあるが、多分な知識と広い視野を持っていた。
“世界モノクロ”は文明的な観点からすると未発展な世界かもしれないが、貧困の格差が全く無かった。貧困の格差が無いことは、平等という観点からすると最上の発展であると高橋は考えていた。
それは生物として繁栄レベルの進化を表しており、認知の違いにより進化の方向性が変わっただけの話である。
もう一度言おう。
高橋は認知進化学の心得があった。
その後“世界モノクロ”の映像はきっかり17:17に途切れた。そして、上映終了のアナウンスが流れた。
"La projekcio finiĝis.(上映は以上となります)
Ĉu vi ĝuis ĝin?(お楽しみ頂けましたでしょうか?)
Ni revidos vin!"(また会いましょう!)
愛すべき主人公と幸福な社会の隔たり③(完)
二◯二四一月
Mr.羊
続き↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
