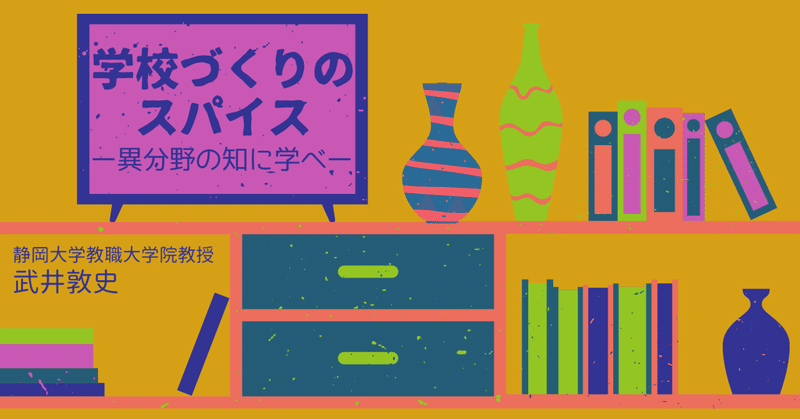
#64「主体性」を疑おう~國分功一郎『中動態の世界 意思と責任の考古学』より~|学校づくりのスパイス
今回のテーマは「主体性」についてです。昨今、学習指導要領をはじめ、さまざまな場面で「主体的な学び」が強調されていますが、私は実はこの「主体性」とはよくわからない概念だと前々から思っていました。今回はその「主体」の根拠について、哲学の観点から論点を掘り下げている國分功一郎『中動態の世界 意思と責任の考古学』(医学書院、2017年)を足がかりに考えたいと思います。

でっち上げられた「自由意志」
私たちが「主体的」という場合、それは自分自身の意志(自由意志)で行った、ということを意味します。自分の意志から出発する行為は「主体的」、そうでなければ「受け身」で「やらされている」、というのが日常(学校現場)での言葉の使い方です。けれども國分氏は、この現代に生きる私たちが当たり前に使っている能動態「○○する」と受動態「○○される」の区別は、古代ギリシャ語等の言語には存在しなかったと論じています。
「能動態と受動態の対立は少しも普遍的なものではなく、それに先だって能動態と中動態の対立があったわけだが、そこからさらに遡ると、動詞は名詞から発展したものであり、またそれは最初、非人称表現という形態を獲得したことがわかった。動詞の原始的な形態は『する』と『される』を対立させるパースペクティヴとは無縁であって、『起こる』こと、すなわち出来事を表現するものである」(198頁)。
筆者なりにわかりやすくたとえてみましょう。私が「今夜はビールが飲みたい」と思ったとします。現代では私に起こったこの衝動が私の意志(能動)であるとされます。ところが職場の飲み会にいやいやつき合っているうちにアルコール依存になってしまった場合には、そこに「ビールを欲する状況にされた」という受動の要素が入ります。
出来事の因果をたどっていくと、このように主体が誰かはわからなくなることがほとんどですが、その根本にはビールというモノ(名詞)があって、それを飲みたい衝動が私の中に「起こった」という、人が主語にならない非人称の経験があったはずです。
このような、ビールを飲みたいという衝動の発生を記述するのが中動態、実際ビールを飲むという行動が能動態であり、この区別を起点に言語は現在のカタチに発達してきたようです。
問題は、これがなぜ能動態―受動態(するか―されるか)という「主体の意志」を問う区別に変化してきたのか、ということです。
本書ではこの点について「意志を有していたから責任を負わされるのではない。責任を負わせて良いと判断された瞬間に、意志の概念が突如出現する」(26頁、傍点は原文ママ)と端的に記されています。つまり「意志」とは、だれかにある行為や出来事の結果について責任を負わせたい場合に利用される、ある種の「でっちあげ」であったというのです。
実際どれほど「自分の意志で行った」と信じていることでも、自分がそのように考えた理由はあるはずで、だとすればそれが「もともと」私の意志であったとはいえません。
「主体性」より「相互作用」を
さて、「自由意志」や、それを基盤とする「主体性」なるものが論理的に成立し得ないことが明らかになり、学習指導要領に失望したとしても、何もいいことはないでしょう。「主体性」という言葉が意味不明であるとしても、「この言葉で表現したかったこと」までがそれによって否定されることにはなりません。
むしろ、「曖昧な言葉を使って表現しなければならなかった何かがそこにはある」という思考を働かせてみることこそ、生産的な教育論のために必要なのではないでしょうか。
筆者の観察によれば、教員が「主体性」という言葉を使うときには、たいてい下記に示す三つの要素が介在しています。
まず、内省の機会が設定されていることです。「これまでで楽しかったことは何か」「日本社会について問題だと感じているのはどんなことか」など、自分や環境に対して目を向けて内省する機会が必要であるという前提が、「主体性」強調の背後にはあります。
次に、学習者からの発信(表現)が行われ、表現や発信をおこなった対象との間に「やりとり」の連鎖が生まれていることです。学習者からの表現が行われ、それに対して受け手の側からも反応があり、表現の連鎖によって児童・生徒自身も変化していくような要素が活動に入っているときに、より「主体的」と見なされます。
最後に、こうした相互作用を通して、学習者の思考と行動の領域が広がっていく余地が確保されていることです。ドリル学習のような正解の固定された問いのなかでの学びだけではなく、自由研究のようにオープンエンドな問いに向き合う場合に「主体的」と表現されることが多いように思います。
自身の思いや考えをふり返り、さまざまなカタチで表現して他者との対話を重ね、それらを起点に思考と行動の範囲を広げていく……これら三つの要素は、今後の学びにとってますます重要になってくるはずです。
一方で「あなたのやりたいことは何ですか」という問いによって児童・生徒の意志を問うことに、どの程度意味があるかは疑問です。もちろん教師が何をしたいかを聞けば子どもは何らかの答えを返そうとするでしょう。しかしこの「自分の意志を持つことを他者に誘導される」構図のなかで、大人に忖度するよう仕向けられているのではないか、と感じる場面に出くわすことが時々あります。
國分氏の表現を借りればそれは「尋問する言語」(182頁)にほかなりません。
子どもは、また大人も、夢中になれる活動では他者や環境との関係の連鎖のなかで、自身に生じた意欲や関心を発展させようとしますが、「何をやりたいか」という質問は、この、より本質的な問いを解体してしまいます。「主体性」という粗雑な表現を括弧に入れて、ともに物事を創っていく相互作用の豊かさを大切にできたら、学びは今よりずっと豊かになると思うのですがいかがでしょうか?
【Tips】
▼コロナ禍の対応に対しても緊迫感のある問題提起をしています。
(本稿は2018年度より雑誌『教職研修』誌上で連載された、同名の連載記事を一部加筆修正したものです。)

【著者経歴】
武井敦史(たけい・あつし) 静岡大学教職大学院教授。仕事では主に現職教員のリーダーシップ開発に取り組む。博士(教育学)。専門は教育経営学。日本学術研究会特別研究員、兵庫教育大学准教授、米国サンディエゴ大学、リッチモンド大学客員研究員等を経て現職。著書に『「ならず者」が学校を変える――場を活かした学校づくりのすすめ』(教育開発研究所、2017年)、『地場教育――此処から未来へ』(静岡新聞社、2021年)ほか多数。月刊『教職研修』では2013年度より連載を継続中。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
