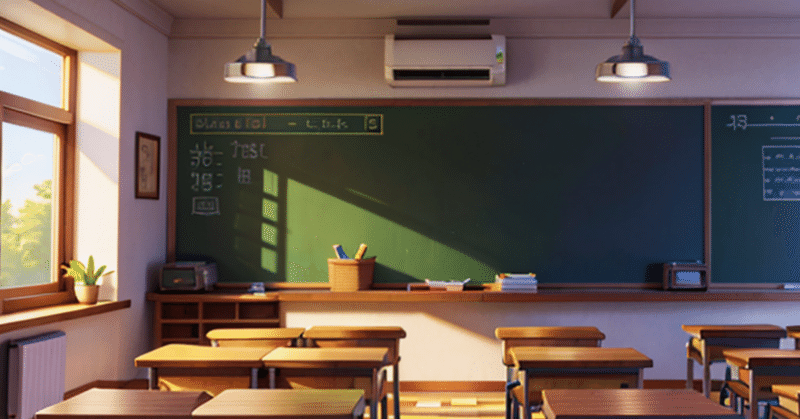
【元小学校教師】学校の先生はなぜ忙しい?日本の学校が抱える問題点
「先生は忙しいって言われるけれど具体的に何をしているの?」「日本の学校って何が問題なんだろう?」子どもをもつ親御さんなら、誰しも一度は思ったことがあるのではないでしょうか。
結論から言うと、学校現場は本当に忙しいです。
筆者は10年教師をしていました。10年という月日の中、「働き方改革」のおかげもあって、業務内容はかなり減ってきています。しかし、1日の密度や精神的に抱えるプレッシャーは高まっているのが現状です。
この記事では、元小学校教師の筆者が、学校現場の実情を赤裸々に語ります。スケジュールの過密さ、事務仕事の種類、学校運営の仕事の負担、そして学校教育が抱える問題点について指摘していきます。
現代は、保護者も大変です。外部の誰からも支援がなく、子育てをする。本当に孤独な立場だと思います。
保護者と教師が、お互いの負担や大変さを共有し、少しでも、よりより方向に教育の在り方が動いていけばよいと思っています。
学校の先生が忙しいのはなぜ?具体的な仕事内容を公開

ここからは、学校の先生が忙しい理由を4つの視点から見ていきます。「会議・行事・提出書類」「校務(学校運営の仕事)」「1日のスケジュール」「子ども・保護者対応」の面からです。
会議・行事・提出書類の多さ
学校は、とにかく毎日何らかの業務があります。それは授業準備、子ども・保護者対応とは別の業務です。これはある月の1か月の行事や会議の予定をまとめたものです。

授業以外にこれだけの特殊業務が入っています。年間を通して、何も入っていない空白は15日程度しかありません。
筆者は6~7年目でようやくこのルーティンに慣れてきましたが、新卒1年目~3年目の若手教師にとっては、怒涛の毎日でしょう。
さらに、ここには提出書類のことは書いてありません。会議の度に新たな提出書類の期限と種類が知らされます。加えて、毎日の連絡事項に「今日行ってほしいこと」がそれぞれの係の先生から周知されるのです。
授業準備に加えて、4月は、教室の設計や年間の計画を様々決め、実行しなくてはいけない時期です。1時間の内に、5~10個の仕事をこなしていかなければ、周りの仕事が遅れて迷惑になってしまいます。
会議の種類
会議には様々な種類のものがあります。学校によって違いますが、どれも重要なものです。以下に種類をあげてみます。
□□□□□□□□□□□□
職員会議・・・スケジュールや行事の内容について検討をする会議
問題行動対策委員会・・・校内のいじめの把握、人間関係の不和を小さなものから共有する会議
校内支援委員会・・・特別に配慮を要する児童に関しての情報を共有し、指導方針を検討する会議
アレルギー対応委員会・・・アレルギーをもつ児童の保護者と共に給食対応を話し合う会議
生徒指導委員会・・・生徒指導の経過報告を共有し、方針の加除修正を行う会議
学校評価委員会・・・学校運営の是非を職員で検討し、今度の運営を改善するための会議
□□□□□□□□□□□□
上記の会議は最低限の種類です。なぜなら、これらの会議は法律に基づいて組織されているからです。
昨今のニュースを見ても「いじめ」や「自殺」といった問題は特にナイーブになっている話題だと思います。その対策として国は法律を定めています。そのため、どの学校もこれらのトピックに関しては、何らかの対策をしているはずです。
そして、学校によって、この会議に+αが付け加えられます。すると、週に1~2回は大きな会議があることが日常化してしまうのです。
行事
毎日の授業に加えて、様々な行事が学校にはあります。具体的にどのようなものがあるのかを列挙してみます。
□□□□□□□□□□□□
①運動会
②学習発表会/作品展(各年)
③授業参観(年4回)
④個人懇談
⑤入学式
⑥卒業式
⑦教育相談
⑧野外学習・野外学習下見・野外学習説明会
⑨修学旅行・修学旅行下見・修学旅行説明会
⑩校外学習・校外学習下見
⑪遠足・遠足下見
⑫家庭訪問
⑬交通安全指導教室
⑭芸術鑑賞会
⑮就学時検診
⑯交通指導員感謝の会
⑰体力テスト
⑱学力調査
⑲幼保小連絡会
⑳身体測定・聴力検査・視力検査・歯科検診・内科検診・腎臓検診
㉑避難訓練
㉒防犯訓練
㉓水泳指導・着衣水泳
㉔小中連絡会
㉕1年生を迎える会
㉖給食参観
㉗校外児童会
㉘学級懇談会
□□□□□□□□□□□□
これがスタンダードレベルです。行事に力を入れている学校は、さらに数が多くなるはずです。そして、大きな行事は2週間も3週間もかけて準備をしていきます。
本来は、授業時間を削らずに、これらの行事をこなさなければいけません。しかし、物理的に無理であるのが現状です。だからこそ、過密スケジュールにならざるを得ません。ギリギリのところで毎日の業務をこなしているのです。
提出書類
「授業に関するもの以外に一体何の書類を作っているの?」と、教師になる前は私も思っていました。
しかし、公務員であるが故に、公の仕事や法律上作らなければならない書類が多く存在します。行事同様、どのような書類があるのかを列挙します。名前を聞いても内容が分からないものがほとんどだと思いますが、ご容赦ください。
□□□□□□□□□□□□
①通知表(評価・所見)
②指導要録
③週案実績簿
④出席簿
⑤給食徴収簿
⑥学年会計簿
⑦個別の支援計画
⑧個別の指導計画
⑨学年だより
⑩教育相談日程表
⑪教育相談反省用紙
⑫個人懇談日程表
⑬個人懇談反省用紙
⑭備品点検
⑮安全点検
⑯校外学習計画書
⑰教科等部会資料
⑱教材採択委員会資料
⑲行事に関するしおり・説明会資料・契約会社への提出書類
⑳職員会議提案文書
㉑問題行動委員会資料
㉒校内支援委員会資料
㉓学校評価委員会資料
㉔授業参観計画書
㉕学校授業研究資料
□□□□□□□□□□□□
思いつく限りザっと書いても、これだけあります。(中には学年主任の仕事も入っています。)これらの書類を定期的に作成しなければならない上に、学校運営の仕事がさらに割り振られるのです。
1日に2~4種類の書類をこなしていかなければ終わらないイメージです。
校務(学校運営の仕事)
次に校務です。この仕事は、中々外側からでは分からない部分が多いです。そして、この校務が場合によってかなりの激務となります。例えばある年の筆者の校務を見てみます。
□□□□□□□□□□□□
◆3年1組担任
→3年1組の学級担任
◆3年生学年主任
→3年生学年全体の主任、学年の責任者
◆6年生外国語専科
→6年生の外国語を週に4時間教える
◆情報機器・情報教育
→タブレットや情報機器の修理・使用に関する方針などの統括
◆校内支援システム
→通知表・要録・学籍などの情報を整理し、操作方法を職員に通達する
◆学校HP
→学校のHPを更新する
◆現職教育(授業研究)
→学校で決まっている研究テーマに沿った年間の計画や推進をする
◆外国語主任
→学校全体の外国語の授業に関係がある書類の整理や教材の購入
◆特別支援コーディネーター
→各学級の配慮を要する児童を見て回り、妥当な支援方法を検討する
◆体育委員
→体育委員会で企画するイベントやその運営の指導
□□□□□□□□□□□□
日常の授業に加え、行事や提出書類が降ってきます。さらに、この校務が乗しかかるのです。
自分の学級をもちながら、学年主任もやりながら、6年生の英語の授業も担当するため、あっちへ行ったり、こっちへ行ったり、という毎日でした。
担任をする自分のクラスがあるのに、1週間のうち5分の2ほどは担任がいないのです。しかしそれ以上に大変なのが、情報関係の仕事です。
特に、昨今のタブレットに関する業務は凄まじいものがありました。
4月1日に勤務が始まり、学年、クラスが発表されます。普通は自分のクラスや学年のクラスの準備を進めるのですが、このタブレットを統括する情報の仕事が信じられない量でした。
全校の名簿を整理し直し、全てのタブレット内にあるアプリケーションにインストールしていくのですが、1週間丸々時間を使っても、全く追いつきません。
何の準備もできず始業式を迎え、学年主任であるのに、同じ学年の先生に「ごめん。自分で進めてて・・・!」としか言えず、周囲からは「早くタブレットを使いたい。」と声があがる。土日も出勤し、丸々1日使っても全く終わらないといった感じでした。
また、GIGAスクール構想(タブレット)のネット環境を整えるため、教室の工事整備をしたこともあります。休日に出勤して5時間作業をしても終わらず、工務に詳しい方に相談をすると・・・「一人でやったら3日徹夜しても終わらないよ。」と言われました。
これは極端な例ですが、実際にあった事実です。それだけ予期せぬ仕事が舞い込んでくるのが校務の仕事であると言えるでしょう。
1日のスケジュール
「朝が早い」「休憩がない」「下校指導後はすぐに定時」。この3点がスケジュールの過密さを物語っていると言えるでしょう。ざっくりとした教師の2日のスケジュールを見てみます。
□□□□□□□□□□□□
【8時~12時】朝の登校指導・朝の会・授業45分×4・休み時間に子どもと遊ぶ・宿題や連絡帳チェック
【12時~13時】給食指導
【13時~15時】授業45分×2・下校指導
【15時~16時】会議
【16時~16時45分】提出書類作成・学級業務
□□□□□□□□□□□□
忙しい日、週か否かによってバラつきがありますが、大体このような流れです。授業を準備する時間はほとんどありません。
筆者が勤めている地域は、かつては部活動もありました。部活動を終えて職員室に戻るのが18時30分。それまでは、8時から一度も職員室に戻ることはありませんでした。
新卒1年目~3年目は終電、始発の生活。授業準備は当然終わるはずがないので、全て土日に行うという日々でした。残業時間は、200~300時間はあったのではないかと思います。
上記に比べると、現在は大分仕事の量が楽になったかと思いますが、それでも忙しさをぬぐい切れない実情があります。
子ども・保護者対応
子どもや保護者へのかかわりを大事にすることが教師の本業です。これらのことにエネルギーが必要となることは、教師になる前からある程度は、分かっていると思われます。
ただ、子ども・保護者対応は突発的に起こることが多く、それが重なってしまうと、疲労となって表れてしまうことがあります。
子どもたちは、危ない行動をしたり、友達と揉めてしまうことがあります。子どもなのですから当然です。だからこそ、休み時間や給食の最中も、常に注意して見ている必要があります。
ただ、授業準備やその他の業務をこなしながら、子どもを観察する必要がありますし、一人で全ての場所を見ることは物理的に無理です。教師が見ていないところでトラブルが起こってしまう可能性は十分あります。
また、授業中に教室の外に出て行ってしまったり、突然パニックを起こしてしまったりする子どもに対応しなければなりません。
授業を中断するわけにはいかないので、時間がかかりそうな場合は、職員室にいる他の教員の手を借りることになります。職員がいればよいのですが、他のクラスの子どもへの対応や出張などで駆り出されていたら、担任一人で何とかしなければなりません。
他にも、不登校の子どもがいるときもあります。定期的に家庭訪問に行ったり、学校の別室で勉強を見てもらったりと、様々な調整を行う必要があります。
保護者に対しては、子どもが学校に過ごしている最中に起こったことを報告する必要があります。怪我をしたことや、友達と揉めて情緒が不安定になっていることを、連絡帳や電話で伝えるのです。
担任が気付いていなかったことを保護者から教えてもらうこともあります。自分で悩みを直接先生に打ち明けることに抵抗がある子どももいるので、保護者が教えてくれることは有難いことでもあります。
上記のようなことに慣れてくると、「今日も2~3件の突発的なことがあったとしても余裕でいられるようなスケジュールや仕事量を調整しよう。」という心構えで仕事をするようになります。
ただ、教師も人間ですから、自分が感じている以上に疲れが出てしまうこともあるでしょう。
元教師だからこそ感じる「学校教育の問題点」

教員採用試験の倍率が低くなり、「教師になりたくない。」と考えている若者が増えている現代。「教師がキラキラと輝いて働ける職場」になっていないのが現状なのでしょう。そこで、日本の学校教育の問題点を考えてみます。
慢性的な人手不足
筆者は現在、療育の分野で働いています。今の職場で働くようになって驚いたことが、体制です。子ども10人前後に対し、大人が最低でも4人はいます。これは学校教育ではあり得ません。
学校では、基本的に担任が学級の全ての業務を行うことになります。朝から子どもが帰るまで、担任以外の先生が一切入ることがないという日は、往々にしてあります。
学級には、様々な子どもがいます。発達の特性に対して配慮を要する子どもは、学級の中に1~2割いるのが実情です。30人学級であれば、3~6人です。その子たちに、それぞれ個別に対応しなければなりません。
「3人は完全に教師の支援がなくては、分からないかもしれないから最前列に席を置いて、あの子は情緒的に不安定だから手が止まっていたら後押ししてあげて、この子は落ち着くことが得意ではないから授業中に適度に指名や刺激を与えて集中を持続させて・・・」といったことを常に考えながら授業を行うのです。
また、出張や授業見学、行事の係、突発的なトラブル対応などで授業を抜け出さなくてはならないときが頻繁にあります。問題なのが、「代わりに教室に入って子どもを見る先生がいないときがよくある。」ということです。
子どもの安全を最優先に預かっているはずなのに、誰も子どもを見ている人がいないのです。家族や自身が、感染症で休んでしまうという職員が多発すると、全く業務が回りません。しかし、子どもは登校してきます。
学校の職員は、そのようなトラブル対応や補欠要員のようなポジションの枠がない。最低限の人数だけで仕事を回しています。だからこそ、先生方も疲れてしまう。ここが学校教育の大問題だと思います。
学級担任は常に孤独
学校では、「担任の先生にそのクラスのことを全て任せる。」という文化があります。自分の担任以外の教室に入ることは滅多にありません。
だからこそ、子どもの指導に関しても、誰も口出ししてこないことが多いです。よその家庭の子どもに対して厳しく注意しないのと同じですね。そうなると、起こったトラブルや子どものメンタルの問題は、全て担任の先生の「自己責任」になります。
名目上は「校長が全ての責任をとる」ことになっています。しかし、実際に対応をするのは担任です。自分のクラスのことは自分で責任をとる形となっています。
教務主任や学年主任が一緒に相談に乗り、間に入ってくれますが、精神的な負担を抱えるのは結局担任なのです。そのため、小学校の教師は、常に孤独との戦いであることは否めないと思います。
授業準備や一人一人を支援する時間がない
学校の先生には授業以外にも様々な仕事があることを既に述べました。子どもが下校後、勤務終了時間までに残された時間は、平均1~2時間でしょう。
その間に書類を作成し、学校運営の仕事をこなし、テストの丸付けをし、成績を付けなければいけません。どこに授業準備をする時間があるというのでしょうか。
10年間も勤めると授業準備もほとんど時間がかからなくなります。しかし、それまでが大変過ぎるのです。
筆者が新卒1年目~2年目の頃は、1時間の授業に対し、2~3時間の授業準備時間を要していました。1日5~6時間授業だとすると、準備時間は10~18時間です。土日を使わざるを得ませんでした。
本業であるはずの授業や子どもへの支援を考える時間が最も後回しになっているのが現実です。
6年生の担任や学年主任になるとさらに大変です。6年生は最終学年。どの行事でもフィナーレを飾るので、クオリティを追求する必要が出てきます。その結果、通常の1.5倍ほどの労力を指導に注ぐことになります。
その上、6年生特有の過密スケジュールがあります。以下のようなスケジュールです。
□□□□□□□□□□□□
①9月始めに学習発表会の準備を始める
②9月中頃には修学旅行の準備も少しずつ進める
③10月に修学旅行の保護者説明会を行うため資料を作る
④10月中頃学習発表会の本番を終える
⑤終了後、すぐに、卒業文集に取り掛かかり、文集指導をする
⑥修学旅行の時期が近づき、細心の注意を払い、打ち合わせを何度も重ねる
⑦修学旅行から帰ってくると、文集の締め切りが迫っているので、それを仕上げる
⑧担任たちで卒業アルバムに載せる写真を選定する
⑨冬休み中に、卒業式や3学期行事のことを決めておく
⑩3学期は、卒業式の練習、6年生を送る会に対する感謝の出し物の指導、成績の処理、中学校に渡す児童の配慮事項をまとめら書類の作成などの業務を連続的に行っていく
□□□□□□□□□□□□
上記のスケジュール+公務員としての書類作成+学校運営の校務です。一体どこに授業に時間を注ぐゆとりがあるのでしょうか。
他にも、8時15分が職員の出勤時間なのに、8時に子どもが登校していたり、給食指導がある関係で基本的に休憩そのものがなかったりと、制度上の問題点もあります。
とにかく怒涛のように日々が過ぎていくのです。
まとめ

筆者はこの10年の間で、学校教育の質が大きく変化してきたことを感じています。
かつては粗暴な行動をする児童がいたり、教室を飛び出していってしまう児童がいたりという問題が多発していました。学級崩壊というワードも、その実情を表しています。
その代わり、「成長したい。」という児童が多く存在しました。良くも悪くもエネルギーがある状態だったのです。
しかし今は、その時代と相対的に見て平和です。(もちろん、荒れている学校は今も多くあります。)
「平和でいいじゃないか。」と思うかもしれませんが、それは表面的に感じるものであると思っています。良くも悪くも目立つことを嫌う傾向が強く表れているのです。
だから、成長していくことに対して、あまりエネルギーを感じることがありません。良い意味でも浮きたくないのです。
また、不登校、うつ、といった内向的に自分を傷つける児童が急増しています。今の教師は、目には見えないストレスを内面に抱える子どもを、ケアする目を持っていなければ難しいとも言えるでしょう。
働き方改革の推進もあり、学校業務はどんどん縮小・簡略化されていきます。授業に使う時間もさらに減っていくでしょう。
かつては、家庭をひっくるめて関わってくれる先生もいましたが、今は学校と家庭が完全に切り離されていっています。そして、この流れは止まりません。
筆者は今後は、公教育ではなく、民間の特色ある教育事業が増えてくるのではないかと思っています。塾のようなテストのための勉強ではなく、本当に生きる力を育むための事業です。少しでも早くその時代が来てほしいと思います。
しかし、ただ指を加えて待っているのではなく、今できることは何かを筆者も考えていきます。そして、いずれ、子どもの「生きる力」を本当に育む事業や取り組みを自分自身ができるように、日々学んでいきます。
このブログを発信しているのも、その一つです。読者の皆さんも、教育について知りたい内容があれば、このブログを読んだり、質問をしたりしてくれると有難いです。
記事の内容が「よかった」「ためになった」と思われた方は、「スキ」や「フォロー」をしてくださるとうれしいです!最後まで読んでいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
