
思考の再構築②
こんばんは。海月です。
書いているのがたいてい夜なのでこんばんはとしておきます。
普段はXでデュエプレに関する情報発信を主に行っています。
質問箱の再読2回目です。
記事の頻度と書くことについて
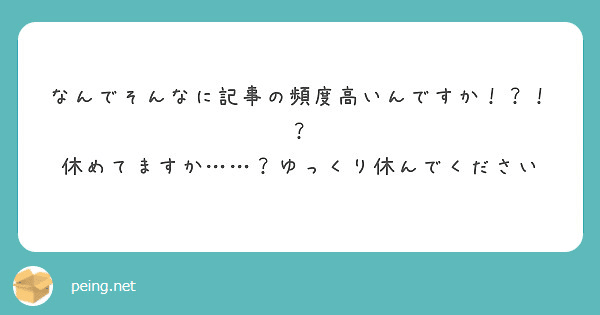
始めた頃は週3とかだったので、新弾前以外週1の今はかなりゆっくりです 笑
わざわざ言って頂けるのは本当に嬉しいですよ、ありがとうございます。
もうめちゃくちゃに書いてた頃でしたね。
数日に一度レベルで投稿していました。
文章を書く経験はこの頃でももう15年くらいあったのですが、こと娯楽事について語るのは初めての経験だったんです。
自分の知識や考えをまとめるのが楽しくて、人に読んで反響がもらえるのが嬉しくて、次から次へと手を染めていました。
こうして心配して下さる方が出たのも、それだけ自分の成果を認めてくれる証左と思えてありがたかった気持ちを覚えています。
一方で、書く欲を満たしながらも、その質が落ちていくことは実感しながら目を背けていました。(前回の記事で挙げた「良いものだけを発表する」に反している…)
ついに書く満足感が限界を迎えた頃に、書く頻度はガクッと落としていきます。
9弾が実装された6月くらいからは
・2カ月に1本(初めの頃はALLも書いていたので2本)の環境考察記事
・2カ月に10本程度の新弾事前公開カード解説記事(19弾~21弾は動画)
・時たま気が向いた時に書くデッキ解説記事
に絞るようになりましたね。
方針を定めたことで、身を入れて書けるようになり、質もある程度の水準は保てるようになりました。
この頃にはもう他者評価も効用が限界に達していて、「かけた時間に対して高い質の記事になっているか」「自分の納得する記事が書けているか」という2点に価値意識が集約されていきます。
そのため、閲覧数、スキの数、Twitterでの伸び等がほとんど意識の外になっていきました。
ストイック過ぎると思いますが、創作に向き合うコンディションとしては悪くないと感じます。
これに没入しすぎると第三者視点の欠けた独りよがりの文章になっていってしまうので、そこは肝に銘じるようにしています。
とは言っても、これでも月で割れば5本、週1本くらい書いている状態なので相当な量です。
特に新弾カード解説は、多ければ2週間程度で書く10本の記事の総文字数が7万字くらいになることもあったので、単純に書くエネルギーの消耗がすごかったです。
一般的な文庫本の1ページ文字数が600字くらいなので、100ページ分くらい毎回書いていた計算なんですよね。
数字にすると気が遠くなりそうな文字をインターネットに残してきたのだなと、改めて思います。
先日Xでは発表しましたが、8弾からずっと続けたこの解説記事の週間も、25弾を最後にすることとしました。
ちょうど今26弾の事前公開を横目にこれを書いているのですが、やはり解放感の中で気楽に書けていることを実感します。
今後は2カ月に1本の環境考察記事のみをノルマにしていこうと思います。
3年前から心配をして下さった質問者さん、ありがとう。
※新カードの紹介について、後継を担ってくださる方が現れました。
方針は違えど、意志を継いでもらえることがこんなに嬉しいことだとは思いませんでした。
こんなことを言ってなんですが、非常に大変なことは身を以て知っているので、どうか無理をせず、やめたい時は気楽にやめていただきたいです。
続ける限りは心からエールを送りたいと思います。
面白かった記事について

書き手が少ないと感じて始めたので、note・ブログが昨今増えているのは嬉しいことですね。
私が引用RTして紹介しているものは特筆すべきものがある記事です。
ただ、だいたいどの記事も面白いと思って記憶に残していますが、突出して印象に残っているものはありません。
「これはすごい、負けた!」って手放しに思える記事に会えたら、その時は喜んで書くのをやめると思います。
具体的な解答ができなくてごめんなさい。
3年活動を続けてきて、正直なところ、強く印象に残るデュエプレのnote記事に出会った経験はそこまで多くないです。
投稿している人の多くは普段「伝える」という行為をしていない人たちで、その技術が圧倒的に不足している場合がほとんどだからだと思っています。
(一応補足しておくと、そうした現実を受け止めているというだけで、非難する意図はないです。)
そのため、記事を評価する指標としては
・斬新な視点があるか
・自分の知らなかったことが書いてあるか
・記録としての価値があるか
・読み物として楽しめるか
の内のどれかに当てはまれば「面白かった」と分類しています。
せっかくなので、今まで読んできた数百の記事からいくつか紹介しておきます。
以下、掲載順は私のnoteアカウントの「スキした記事」を古い順に見た時のもの(デュエプレのnoteは読んだら出来に関係なくスキを押しています)であり、特に意味はありません。
また、挙げるものは各書き手1記事までとしています。
デッキ解説系はその内容の伝わりやすさや緻密さを損ねないために、淡々と情報を絞って書くのが基本だと思います。
その例外になる要素に「情熱」や「愛」があることを知った記事でした。(この言葉もだいぶ多義的に見えます)
こじぃさんは私が活動を始めてすぐの頃から目を付けて下さった方で、彼の静かな応援が今まで支えになってきたことは間違いないと思います。
後半の「初動の話」のところ、特にそこまでほぼ触れている人を見なかった色事故の部分について述べている点に感動しました。
「こういう書き方をすればいいんだな」と方法を盗んだ意識のある記事です。
今読み返すと特筆するほどではなく感じるのは、この3年間で方法が浸透してきたからかなと思います。
デュエプレのゲーム性においても、記事文化の発達という面においても、発展途上なことを感じ取れる記事です。
当時を知らない人が見ても伝わらないと思いますが、何と言うか、この頃は未開拓な要素が点在していて夢があったように感じます。
「コラボカードを使いたい」という純粋な思いから始まって、右往左往しながら模索していく過程が読み物としての楽しさを感じさせます。
ブログってこういう文化だよなあとしみじみ思ったりするものです。
愛と歴史と思い出はすべて一本の糸で繋がっているのだなと感じます。
このニッチなテーマに対してのスキの数が、それを裏付けていますね。
こうしたプレイヤーは、実績等に関係なく常に尊敬の対象です。
体験記録は他者にとっての「非日常」となりやすく、誰でも面白いものを書ける可能性を持ったテーマです。
これは内容の詳細さもさることながら、軽快な論調で笑顔と涙をもらえる力を持った言葉群だと思いました。
クアルトさんはその後私の所属するチームに加わってくれ、今ではデュエプレ以外のことまで含めた人生の良き仲間の一人です。
デュエプレが歴史を刻み、同時に我々の時間も流れていることを強く感じた記事です。
この記事の中で「今後どう転ぶかわからない」と言う囲碁さんは、今でもデュエプレを続けてくれています。
今なおブリザードを追う老人(誉め言葉)の姿を見ると、いつも少し嬉しいです。
オタクが書き殴った記事(誉め言葉)。
読みにくいことこの上ないですが、文字からにじみ出る熱量をたしかに感じます。
こうした遊びが出てくると、文化としての成熟を感じてくるところです。
今読み返しても、根柢の部分は変わらないなあとあたたかく笑えてきますね。
当時「第2のメカオー」と呼ばれるほどに長い期間の活躍と、それに見合う練度を要求されたデッキ【デイガナイト】。
それをディアボロスZカップで1位経験のある実力者が解説したナレッジの塊みたいな記事で、今も昔も貴重な情報量のある記事です。
彼もまた現在のチームメイトなのですが、トップクラスの実力に必ず自身の思考・思想がオリジナリティとして反映されているのがすごいと2年経っても思います。
またなんか書いてくれん?
禁忌に真摯に向き合う紳士の記事。
大真面目な遊びとブログ文化の融合が素晴らしいです。
私も終盤名前をぼやかされて登場しますが、これは少し嬉しかったことを覚えています。
カードデザイン・フレイバーから物語を考察する記事。
デュエプレである記事を読み、そこから遡って他記事を読んだ書き手は今までD.白雪さんだけです。
いつでも新作を楽しみにしています。
デュエプレの確率に関する考察をnoteに書いて下さっている方は、これまでに5人ほどいました。
どなたのも非常に参考になって助かっています。
これは自分じゃ到底計算できなさそうなヴォルグの効果について、クリーチャー採用枚数に応じた指標を簡潔に書いて下さっていて印象付いています。
「自分だけのオリジナルデッキで勝つ」は、カードゲームを遊ぶ人たちの少年の頃から失われない憧れではないでしょうか。
大人になってものを知るほどに難しくなることを、大人だからの知恵を使って達成する。
そんな夢を、言葉と背中で語ってくれる海の幸さんは本当にすごいプレイヤーだと尊敬しています。
誰でも書ける記事の一つ、それが「体験記」です。
要はデュエプレを遊んでの日記なわけですが、これは初心者から熟練者まで、幅広く需要があるカテゴリーだと思っています。
どんなことを書いたら読んでくれる人が面白く感じてくれるだろう?共感してくれるだろう?と考えながら書いてみるのは、上達に向けての一歩です。
先に挙げたクアルトさんの記事と比べても、色んな意味でまったくの別物に仕上がっていて面白いです。
先ほどのくろまくさんの記事同様、最終1位経験のあるparaさんが調整の記録として書いて下さったものです。
解説濃度は当然として、個人的にはリプレイを動画で載せているのが印象的でした。
paraさんは過去にもリプレイを振り返る記事を書いていたのを知っていたので、それが洗練された記事になって来たことに感動しました。
友人とのデッキ調整、いいですよね。
私は今も昔も誰かと真剣に調整をするという経験があまりないので、純粋な思いで憧れてしまいます。
泥臭さは思い出と成長の足跡です。
BA2024Winterにて優勝を飾った、がのととととす選手の自伝です。
デュエプレで人生が変わったという話は、多量の時間を注いでいる身からするとわが身のように嬉しく感じます。
事実は小説よりも、という言葉を多くの人が浮かべたことでしょう。
比較的簡潔な内容に明快なタイトルですが、「嫌い」という誰もが持つ負の感情に向き合うのは大切なことだと改めて感じた記事です。
私もよく黒いものを胸の内に感じた時、なぜそう思うのかを考えることがあります。
論理的に考えていくと、実は自分の中に言い訳している部分を見つけることができて面白いです。
あまり勧められることではないですが、考えることが好きな人には一度文字起こししてもらいたいテーマの一つだと思います。
確率の記事は先ほどふ~りんさんのヴォルグのものを挙げましたが、iroさんもまた確率に関することを度々書いて下さっています。
これを書く2024/5現在では、唯一定期的に投稿して下さっている書き手ですかね。(プレッシャーかける気はないです)
表もたくさん作ってくれており、抜粋して覚えておくだけでも普遍的に実践で役立ちます。
ランクマッチの最前線で戦うプレイヤーの一人シーズン反省会。
書き殴ったような文章で率直に読みづらさもありますが、それがいいんだと思わせます。
ここまでの紹介文に「愛」や「熱」などの言葉を使ってきましたが、それらと近いようで遠いような、それでもはっきり質量のあるものが伝わってきます。
ポッターさんはこの記事のあとがきで「同じことを書いている人をほとんど見ない。もっと他の人にも書いて欲しい。」と綴っていますが、強く共感します。
赤青UKのまさに教科書と言うような、基本を解説している記事です。
「解説」という言葉を充てるにあたって、お手本のような記事構成と内容に感じます。
先ほどのMRCの記事のparaさんとは調整仲間のようで、直近でYoutubeのライブ配信活動を始めています。
今後に期待を込めて、こちらも紹介させていただきます。
noteのスキ欄を4年分遡るのは少し骨の折れる作業でしたが、同時に色々な記憶を取り出す契機となりました。
この記事の目的は「再読による再構築」ですが、その中に更なる奥行きが見つかりましたね。
ネットの広大さと、デュエプレというコンテンツが積み重ねてきたものを感じるところです。
また、記事を通じて懐かしい人たちを思い出すこともできました。
アカウントが消えている人もたくさんですが…元気でやっていてくれたらと思います。
また数年したら、noteのスキ欄を掘り起こす作業をまたやってみたいです。
長生きしような、デュエプレ。
