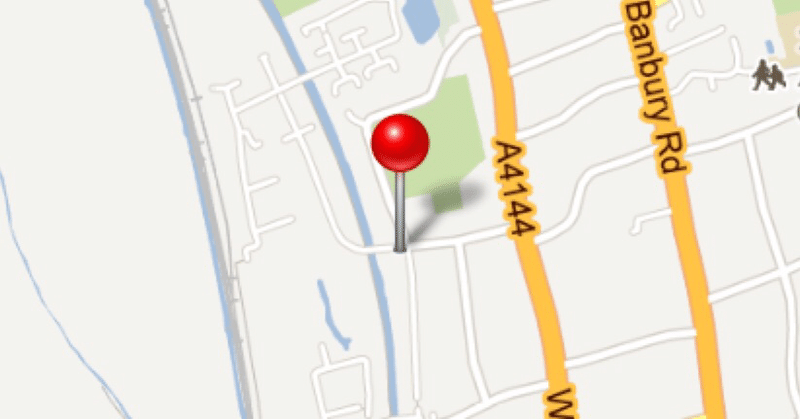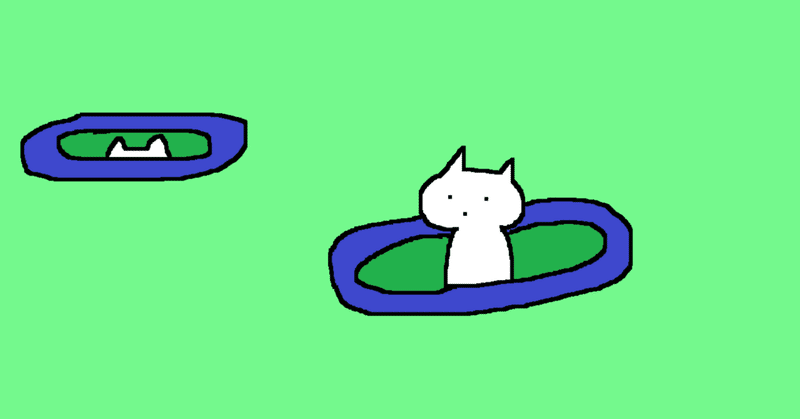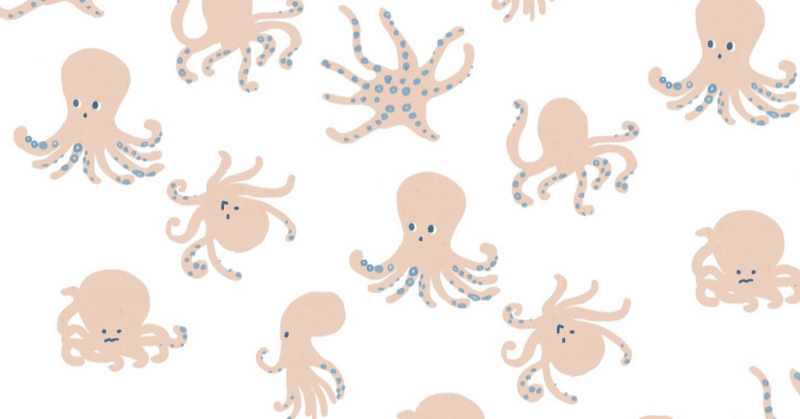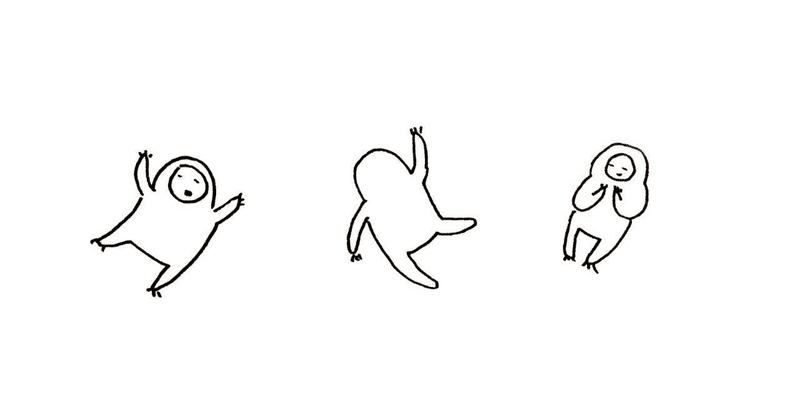#感覚
どこでもない、ここ。
ここではないどこかへ、ではなく、
他でもない、ここ、にいること。
身体のこと、自分のことを知りたいと思うようになって
あれやこれやと調べたり実際に習いに行ったりしましたが、
もうほとんど全部と言っていいくらい、忘れました。
実感から言いますと、わたしにはいらない。
まだアレクサンダーの学校に通っている時
学校の先生に言われたことあるんですよ。
「いろいろあるけどアレクサンダーだけでいい」って
「つもり」ってわからない。
ほんとにやる、と
やっているつもり。
これは文字で読むと
そりゃーそうでしょ!となるんですが、
実際何かをやっている時には
ほんとうに、わかりずらいんです。
私は師匠のレッスンに通い始めた頃
「アップは?」と言われていました。
私としては、
「いやいや、ずっと思ってますよ。」と。
何回か目いや、何十回か目のレッスンで、また
「アップは?」と言われた時、
「ん?思っていました。」と答えたのですが