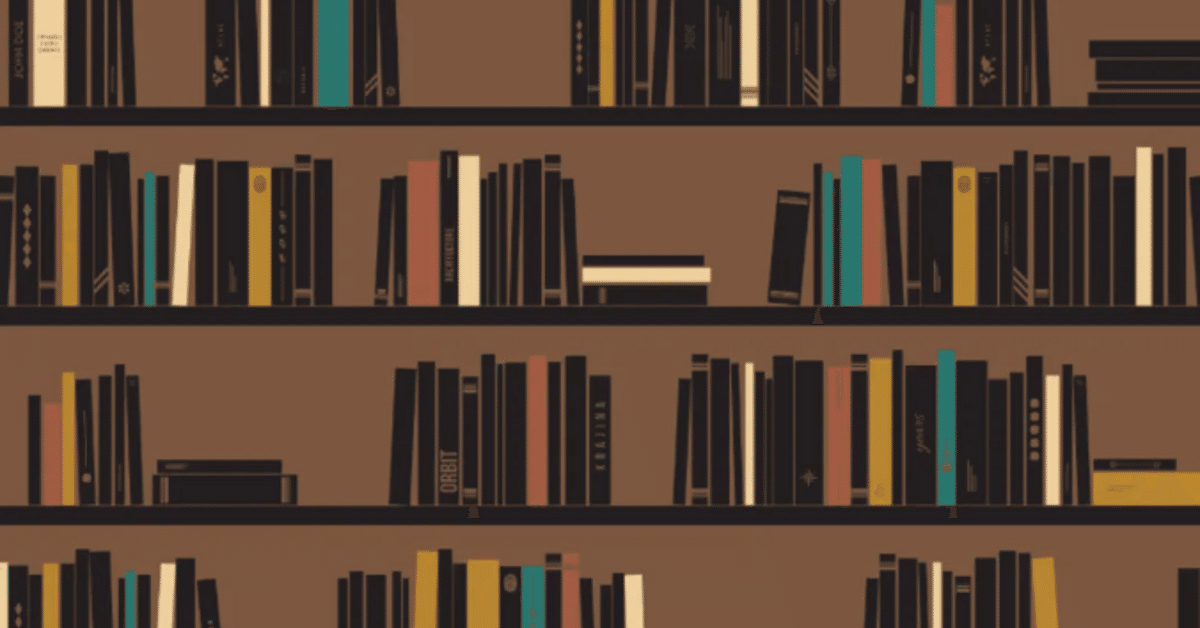
【文学を学ぶことは創作に役立つのか】文学は形式・技術のアーカイブスである(2013年4月号特集)
※本記事は2013年4月号に掲載した渡部直己教授のインタビュー記事です。
学ぶべきは形式の歴史
――文学史を学ぶ意義は?
通常の文学史は内容中心の文学史ですよね。内容だけを読み取り、その変化を歴史的な展望の中で記述する。洋の東西を問わず、それが文学史と言われているものですが、小説を書きたいという人間がそれを学んだって意味がない。内容の大半はすでに死んでいることだから。
――では、何を学べば?
形式の歴史を学ぶ。まず形式をおさえて、かりに内容が重要であるとみなす場合、形式との絡み方の中でその内容を問題にする。そういう立場から文学史を考えた場合には、個々の小説を構成する個々の技術、形式的な技術に着目して、たとえば回想の入り方はどの小説が一番うまくて、どの小説が最初にそれを円滑にやって、他の小説はどのようにそれを展開していったかとか、場合によってはそこから後退していったかとか、そういう小説を構成する技術的なポイントをしっかり把握したうえでそれぞれの歴史性を見ていかなければいけない。そういう形で文学史を学ぶというのはとても大切なことだね。
――その形式とは具体的に言うと?
たとえば、どういう視点から書くか。
三人称で書くのか、一人称で書くのか。
三人称でも、すべてを見渡すことのできる三人称多元(ここで言う三人称多元はいわゆる「神の視点」に同じ)という視点があるのに対し、主人公を三人称に置くものの、その人物が見たものや聞いたものしか書けない、ほとんどその人物と一体化している三人称一元描写もある。
それから、夢からどうやって覚めるかとか、どうやって夢を見るのかとか、それだっていろんなパターンがある。あるいは時間処理の問題。どういうタイミングで回想するかとか。
日本の小説で話の流れの中に回想場面が入ってくるというのは、新しい技術なんですよ。明治時代になってからじゃないと、そういう技術はない。その技術が、どの小説で一番効果的に使われていて、それがどう変化したかを見る。
今までの文学史はみんな内容中心主義だから、そういう意味では僕の『日本小説技術史』は画期的であると自負しているけど、これを読んでいただければ、どんな作家によって、どんな技術が、どんなふうに書かれ始め、あるいは書きかえられたかというのがわかります。
明治期に技術が輸入される
――近代文学以前の文学は時系列で書かれていたのでしょうか。
ほとんどが出来事が起こった順に書かれている。これは日本と西洋の一番の違いで、西洋の小説だと、ホメロスのときから時間がひっくり返っている。ホメロスの『イリアス』はアガメムノンが怒っているところから始まる。いきなりね。
それで、あとになぜ怒っているかというのがフラッシュバックになっている。西洋ではいわゆる時間をひっくり返すというのは、叙事詩の一番古い段階からあるわけ。
――日本の場合はいつから?
日本の場合、時間を転倒させるということができるようになったのは、西洋文学を学んでから。明治20年の二葉亭の時代です。そのときに、ずっと前に起こったことを今語るという形ができた。日本人がいわゆる回想場面というのを小説の中に取り入れられるようになってからまだ120~130年しか経っていない。
そういう大きな違いがある。明治期の日本の場合、回想場面は非常に新しい技術だったわけです。
――ほか明治期に輸入された技術は?
あと面白いのは、江戸時代までは一人称小説っていうのもない。これもやっぱり西洋との大きな違いで、西洋小説の場合は18世紀に書簡体小説っていうのが流行り、複数の手紙で一つの作品が構成されるという形式が1世紀くらい続くんですよ。そうすると書簡体の書き手だから「私」ですね。欧米の場合、一人称でフィクションを語るというのは18世紀に成立する。それへの否定として、三人称多元の、「神の視点」の小説が19世紀に発達する。それが西洋小説の歴史です。しかし、日本の場合は一人称とフィクションの結びつきが極めて希薄だった。
一人称主体がウソの話をするというのはなく、どちらかというと一人称で書くのは随筆だったわけ。日本の場合は、一人称を使ったフィクションは森鷗外の『舞姫』までない。
――鷗外が最初だったんですね。
一番うまく成功したのはね。時間的には明治20年代、一人称小説というのは、小説の新技術としてこの時代に盛んに吹聴された。自分で自分を語る「自叙体の小説」はこれからの小説の可能性だと評されるくらいに、一番新しい手法だった。
しかし、日本の小説はずっと三人称多元小説しか知らなかったから、一人称小説を書くのは難しかったんですよ。
<語る私>と<語られる私>との距離の調整とかね。
大正期に三人称一元が誕生
――明治期の私小説は一元視点ではないんですか。
明治39年に『破戒』が出て、明治40年に『蒲団』が出る。そこから自然主義文学、それから私小説となるというのは文学史の常識だけど、『破戒』も『蒲団』も私小説的だから主人公の視点でずっと書かれていると思うでしょ。ところがあれはやっぱり三人称多元小説で、主人公以外の人物、たとえばヒロインの心も書かれている。日本の小説においては、三人称多元小説という根強い伝統があって、それがやがて、三人称でありながら一人称的に書く三人称一元視点に発展するわけです。
――それはいつ定着するんですか。
私小説と言いながらも、あれは一人称よりも三人称が多いんだけど、三人称で一元の視点を使う、それが定着するのは大正時代です。
――三人称一元視点というのは、なぜ生まれたんですか。
三人称一元小説は、言ってみれば一人称小説と三人称多元小説の折衷みたいなものだよね。日本の場合、一人称小説は主流じゃないわけ。だから、三人称多元小説の中に一人称的なものを求めようとした場合、どうしても三人称を残したまま一元になっていく、一人称的になっていくという流れになるわけ。
――一人称と三人称のいいとこ取り?
そうそう。ただ、いいとこ取りと言っても、実態はほとんど一人称、つまりそこで書かれている主人公を「彼」と言わず「私」って言ったらほとんどそのままなんだよ。でも、それもまた一種の新技術だったわけ。岩野泡鳴が「一元描写」っていうのを大正時代に言うんだけど、
それはまた当時の新技術でもあった。
――一人称と三人称はどう使い分ける?
たとえば二人の人物がいて、相手の気持ちがものすごく謎で、相手が何を考えているかわからない、そういう人物に主人公が振りまわされる話があるとする。
これ三人称多元で書いたら台なしなんだよ。相手の気持ちも書けちゃうから。相手の気持ちを書いちゃうと、読者は相手のことをもうわかっちゃっているわけだよ。主人公だけがわからなくて。これはものすごくアンバランスなのね。
だから、相手の気持ちが謎だというような小説を書くときは、三人称でも一元視点にしなければいけない。『蒲団』の未熟さはそこなんだよ。あれは、女弟子の内面描写もしちゃっている。
――一元描写でない部分がある?
『蒲団』の主人公(時雄)は、女弟子の芳子が何を考えているのかとか、田中という若い青年とできてるんじゃないかとか、二人の秘密についていろいろ考えるわけ。ところが、ある場面でその芳子のほうに焦点移動(芳子の視点で書くということ)しちゃって、芳子が田中と逢い引きした夜のことを芳子が回想している。これはね、やっぱりテクストの技術としては未熟だったんだね。
『蒲団』みたいな小説を書くときは絶対に一元視点じゃなきゃいけないんだよ。そういうような不都合があるから、三人称多元をとらずに一元にしようと岩野泡鳴は主張したわけだね。
これ以降、主人公と作者の気持ちが一致して、世界を限定して見るという形の小説の場合は、三人称一元がオーソドックスになる。一人称だと作者と主人公がビタッとくっついたまま書かれちゃうから相対ができなくなるわけよ。しかし、三人称にすると、自分をモデルにしていながら距離を持って「彼は」と言うことができる。人物に対する作者側の距離感というものを出せるのね。そのうえで、主人公が見たことと感じたことしか書かないという一人称の書き方をするわけ。
渡部直己(わたなべ・なおみ)
1952 年東京生まれ。早稲田大学文学学術院教授。文芸批評家。
著書に『日本小説技術史』(新潮社)、『幻影の杼機』(国文社)、『不敬文学論序説』(ちくま学芸文庫)、『私学的、あまりに私学的な』(ひつじ書房)など多数。
特集「書くために学ぶ文学史」
公開全文はこちらから!
※本記事は「公募ガイド2013年4月号」の記事を再掲載したものです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
