#読書感想文
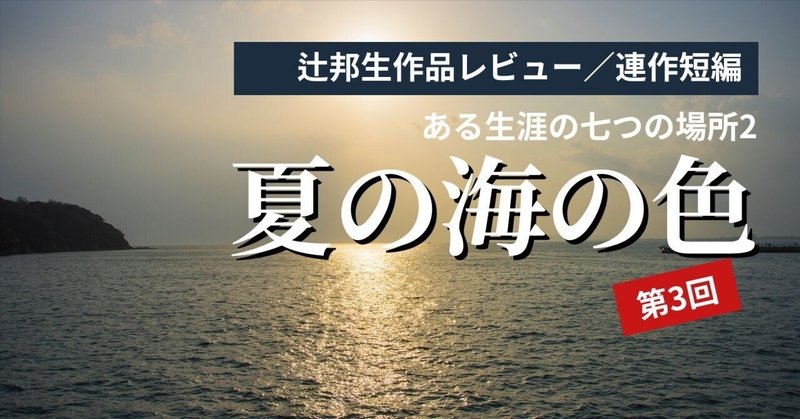
noterさんにぜひお贈りしたい二つの言葉 『ある生涯の七つの場所2』100の短編が 織り成す人生絵巻/夏の海の色 第三回
連作短編『ある生涯の七つの場所2/夏の海の色』第三回。これで『夏の海の色』は完結です。 上記は「黄いろい場所からの挿話」のラストで、アメリカへ留学する恋人エマニュエルとの別れを決めていた「私」が、考えを翻す場面です。 それは、やはり、いつかくるはずの、より完成された形までの、準備にすぎなかった。 お読みくださるみなさんにお贈りしたいのがまずこの言葉です。今自分がやっていることは、いつか手に入れるであろう成功や幸福の準備にすぎないのだ、そんなふうに考えてはいないでしょうか?





















