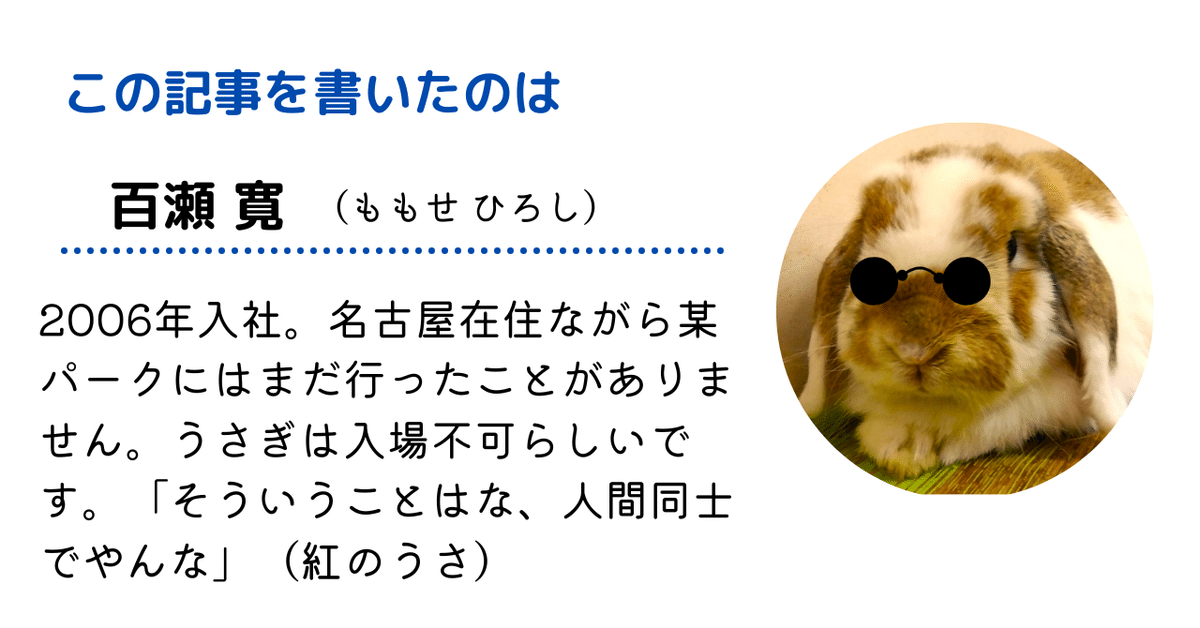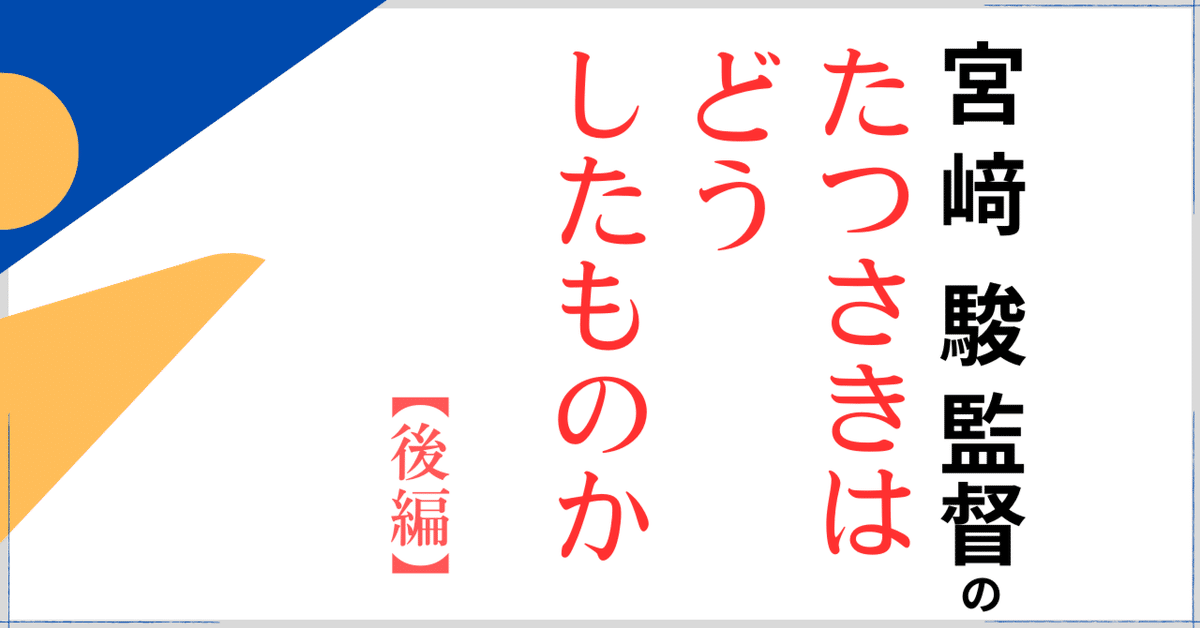
【後編】校閲記者がうだうだ考える「宮崎駿」と「宮﨑駿」
【前編のあらすじ】
・「君たちはどう生きるか」で監督名表記が宮崎→宮﨑駿になった
・広く世間が追従したのは初めて
・前から使ってはいるけど直近では「アーヤと魔女」から
・「君たち~」が「自伝的ファンタジー」だから「宮﨑」なのかも
・新聞表記と個人のアイデンティティーの衝突
前編はこちら▼
【以下後編】
字体統一のメリットとデメリット
新聞のルールで名前の字体を変えた結果、その人が普段使っている表記や他のメディアでの表記と異なることで、「同じ人物」を指すことが分かりにくくなってしまうとすればデメリットと言わざるをえません。
新聞は「分かりやすい」記事を旨とします。普段「臺」を使っている人の名前を「台」にすると、字体は「分かりやす」くなりますが、「臺」と「台」が〈字体が異なる同じ字種である〉という知識を読者に要求する、という点では「分かりにく」くなってしまう(ちなみに「君たち~」という映画は「分かりにくい」。であれば「宮﨑」「眞人」はむしろふさわしい)。
同音同義の異体字でも使い分けるものもあるとはいっても、「浜」と「濱」、「当」と「當」などは字体差が大きくても使い分けず、「富」と「冨」を使い分けて「崎」と「﨑」はなぜだめかという疑問に説得力のある答えはあるのか。
本人がそう名乗っているのだからそれが「正しい」のであり、別の字にしていいか意向を確認したり書き換えたり、一体なぜわざわざそんな面倒なことをするのか。
字体統一のメリットはないわけではありません。
たとえば渡辺さんの「辺」には「邊」「邉」をはじめ異体字が何十種類もあるとかないとか。それを全て区別するとなると、使う字体が増えれば「間違い」のリスクも増す。同音同義であるこの字種は一律でこれを使う、と決めてしまえばそれぞれの「正しい」異体字を書き分ける必要はなくなります。
多くの人間が関わる新聞紙面には交通整理の意味でも一定の表記ルールは必要であり、それが一つの媒体の中での統一性を維持することにもなります。
また、同じことを書こうとしても、ある表記ルールの体系を通すと出力結果が変わる、ということ自体は言語というものの興味深いところだとも思うのです。それは校閲記者という生き物が煩瑣な規則を駆使することに嗜癖する変態だからだ、と言われればそうなのかもしれません。お前と一緒にするな、の声が聞こえますがそれはおいといて。

認識のずれ
問題は、この「見た目は違っても系統上同じ字は自動的に書き換えてよい」という新聞表記の考え方がどこまで世間に共有されているか、ではないでしょうか。ある字体を新聞が「使える/使えない」基準が世間一般の感覚よりおそらくかなり狭いのではないか。字体統一の結果「漢字が違う」と読者からご意見を頂くことがあります。これは「置き換え可能な字体である」という認識があった上での「置き換えるな」なのか、「別の字だから間違いだ」という認識でのことなのか。
雫「やっぱり変えちゃうの? 私たつさきの方が好き」
父「僕もそうだけどね」
字体制限の実際的な動機の一つは漢字の印刷や電子化に技術的制約があったことですが、現在ではほぼ克服された観があります。新聞が異体字を使えなくても昔なら「活字がないなら仕方ないか」と思ってもらえたのかもしれません。しかし今や誰でも手元で簡単にキー変換で出せる漢字を、なぜ新聞で使わないのかと思われても無理はありません。
日本の漢字制限
メリットはあるのだとしても、なぜ新聞は字体をそんなに統一するのか。その「そもそも」を考えてみると、この国の漢字制限の歴史の流れをくんでいるから、だろうと思います。
明治の「漢字なんか使ってたら近代国家になれない!」から始まり、戦後は「漢字なんか使ってたら民主国家になれない!」といった考えの下、漢字制限は行われてきました。技術的制約が大きかった時代は漢字が少なく簡単な方が紙面を作りやすいので、新聞業界もその主要プレーヤーの一角を占めていました。昔から賛否両論かまびすしい漢字制限ではありますが、膨大な数がある漢字を何でも使うとなると大変なので、便宜上ある程度制限を設けておいた方がいい、というのはひとまず妥当でしょう。
日本語における漢字使用量が明治や戦前に比べれば減少し、字体も簡潔になったことは事実でしょうから、漢字制限はある程度は成功し、定着したといえます。しかしそれ以上のこと(さらなる簡略化や漢字廃止)に進もうという気配はありません。当用・常用漢字や人名用漢字はむしろ増加してきました。いわゆるキラキラネームの隆盛(字体というより読ませ方の問題ですが)にしても、漢字によって個性を表現しようという心性は高まっているように見えます。
そういう心性にとっては漢字制限など自由の敵、個性の敵、多様性の敵で、「漢字使用は少ない方がいいし字体も簡潔な方がいい」という大前提が共有されなくなったのだとすれば、その流れをくむ新聞の漢字表記が違和感を持たれるのも致し方ないことかもしれません。
前編で紹介した今野真二さんは、漢字の「私性」の前面化が「わるいわけではない」としつつこうも述べています。
言語は共有されていて初めて言語として成り立つ。「私性」への過度の傾斜は、言語情報の共有を脅かす可能性がある。
現代は漢字の公と私をめぐって新聞表記と時代が対立している、といえば大げさでしょうか。
ジコ坊「いやぁまいったまいった、時代には勝てん」 …?
なお、字体(崎か﨑か)ではなく字種(犬か太か)の点でいえば、今世紀に入ってから新聞業界は常用漢字外の使用漢字を増やしてきています。まぜ書きをやめる(破たん→破綻)、代用表記をやめてルビをふる(棄損→毀損)など、漢字制限はすでに緩和の傾向にあります。字体の制限はまだ比較的厳しいといえますが、時代とのせめぎ合いの中で、今後ははたして…。
もし中日新聞が「たつさき」にしたら
本稿執筆時現在、中日新聞では「宮崎駿の字体は宮﨑駿にせよ」というお達しは下っていません。もしご本人やジブリ側から要望があればそれに従うことになるでしょう。その場合、校閲のゲンバではどのようなことが起きるのか。
まず考えられるのは「たつさき」にし忘れて単純に従来の「宮崎」のままにしてしまうこと。「崎」と「﨑」は字体差が小さいのでうっかり見逃しそうです。逆に、「宮﨑」を多用することによるキー変換の癖で、「宮崎県」などを「﨑」としてしまうこともありえます。テニスの大坂なおみ選手が活躍しだした頃に、地名の「大阪」であるべき所が「大坂」になっていたミスを数回防いだことがありますが、あれはたぶんそういうことだったろうと。
パソコンなどでは「﨑」の表示が完璧というわけでもないようです。検索結果画面で「﨑」が表示できずに空白になっていることがあります。放送局の公式サイトで動画・画像に記事が付いている場合、画像内は「宮﨑」でも記事中は「宮崎」といった食い違いが見受けられます。同一記事でも紙面とネットで「崎」の扱いが違う、見出しと本文で違う、同じ雑誌の中でも記事によって違うなど、どこまで徹底するのかも気に留める必要があります。
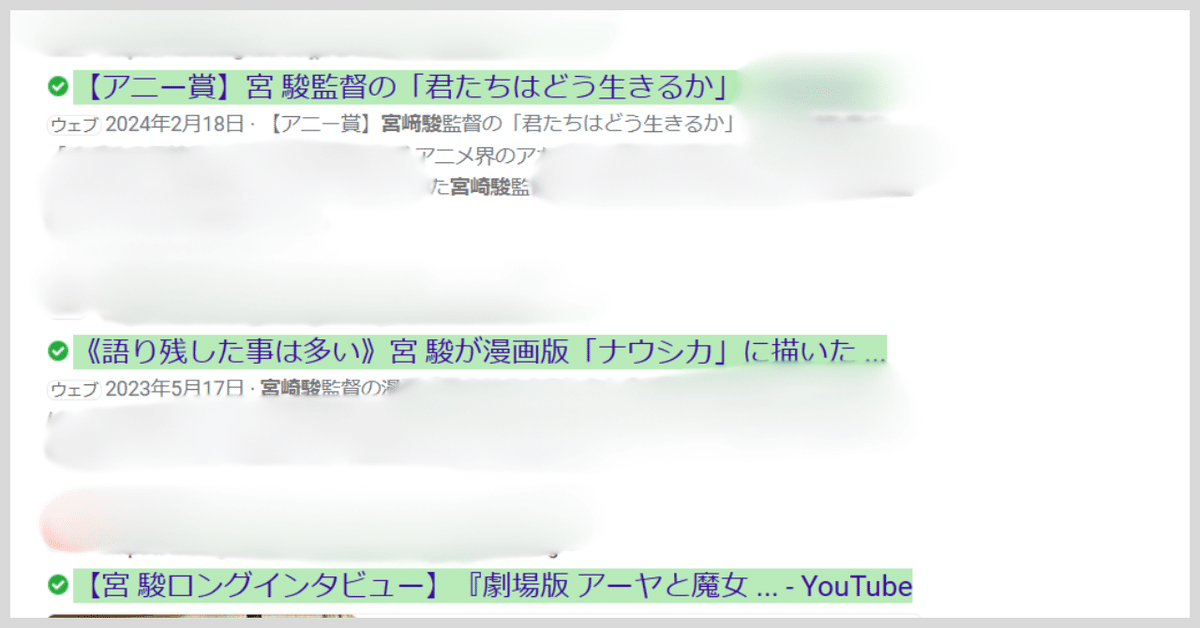
雑誌「現代思想」の「君たちはどう生きるか」特集臨時増刊号(青土社)では、学術系の書き手が多いこともあってか各執筆者が「本文では宮『﨑』駿を用いるが、書籍の表記など必要に応じて『崎』も併用」「宮﨑駿(もしくは宮崎駿)」「以下、宮崎と統一して表記」など律儀に逐一断りを入れていて、表記に関心を持つ者にはちょっとした眺めです。その中で研究者の小松祐美さんが末尾注でこう述べています。
この映画の公開後、この作品を作った監督について語ろうとする時に名前をどのように表記すればよいのかという厄介な問題が生じている。(略)この映画について語るだけであれば宮﨑駿の表記を用いればそれでよいのだが、(略)「宮﨑駿作品」だとか「宮﨑駿的な」といった言い回しが必要になる場合に、これまでの「宮崎駿」表記の作品を含んだものとして伝わるのかどうかという問題が生じているように思う。
研究者らしい厳密さです。「宮崎」と「宮﨑」の意味するところが多少なりとも違う、というのであれば紙面での「宮崎アニメ」「宮崎ファン」などの扱いもちょっと考えてしまいそうです。
著者名ではなく書名に従来通りの「宮崎駿」と入っている関連書籍は多くあります。それを記事で扱うとき書名の内外で崎・﨑を書き分けることになるでしょう(「風の谷のナウシカ 宮崎駿水彩画集」の書名を「宮﨑」にしてしまっているのを某通販サイトで発見)。
もっとも、「ロープウェイ」(世間一般で優勢な表記、または固有名詞中の表記)と「ロープウエー」(普通名詞の場合の新聞表記)のように、「固有名詞ではその表記を尊重するが、普通名詞なら表記ルールで書き分けるのでなんか変な感じになる」というのは新聞特有の「癖」です。一種の味わいでもあると身内としては思いますけれど。
例:「A市の「○○ロープウェイ」は世界最長のロープウエーとされる」
2人の「ミヤザキ監督」
子息の宮崎吾朗監督は今のところ従来の「崎」を維持しています(そもそも戸籍上どうかは部外者には知りえませんが)。当然「宮﨑駿」と「宮崎吾朗」でサキを書き分けることが必須になります。また、現状では同じ記事の中でこの2人が登場する場合、最初に「宮崎駿監督」とあれば次に出てきた「吾朗」監督に必ずしも「宮崎」を付けないこともありましたが、「宮崎」と「宮﨑」が別だとするなら、文脈によっては省かない方がいいのかも。
同じ記事の中で同じ名字の人物が複数登場する場合、特に家族であれば下の名前で区別するのが普通です。しかし(家族ではない)「滝澤」さんと「瀧沢」さんが登場する場合(新聞表記では両方「滝沢」になる)、「滝」と「瀧」、「澤」と「沢」が有意の識別子として機能するという考え方に立つならば、名字のみで両人を区別できる、ということにならなくはない。「宮崎監督について宮﨑監督は」…なんて書き方は常識的にまずやらないはずですが、「宮﨑」と「宮崎」があくまで別だというならそれも不可能ではない、ということにもなりかねない…少々屁理屈が過ぎましたか。
「語り残した事は多いが ひとまずここで、物語を終ることにする」(漫画版ナウシカ)
そういう細かいことを遺漏なく処理するのがお前らの仕事だろ、と言われれば全くその通りで、きたるべき時がくれば我々は粛々とそれを遂行するでしょう。
そもそも表記のルールの多くは、「書きようは様々あるが、いちいち迷わないようにとりあえずこう決めておけば話が早い」という性質のもので、正しいからそう決まっていて、間違っているから直す、というのとはちょっと違います。異体字についても一概にそれがいいとか悪いとか言うつもりはありません。
もとより「たつさき」表記をやめてほしいと言うつもりもなく、「崎」と「﨑」の違いで長々と駄文を書き散らすくらいですから、私はこの「たつさき」をめぐる諸相を「やはり言葉は面白い」と思ってしみじみ眺めているのみです。新聞表記の理非も含めて。
「宮崎駿」であれ「宮﨑駿」であれ、どっちがいいとか悪いとかいうことはないのです。たぶん。(トトロ風)
長文にお付き合いいただきありがとうございました。
おわり