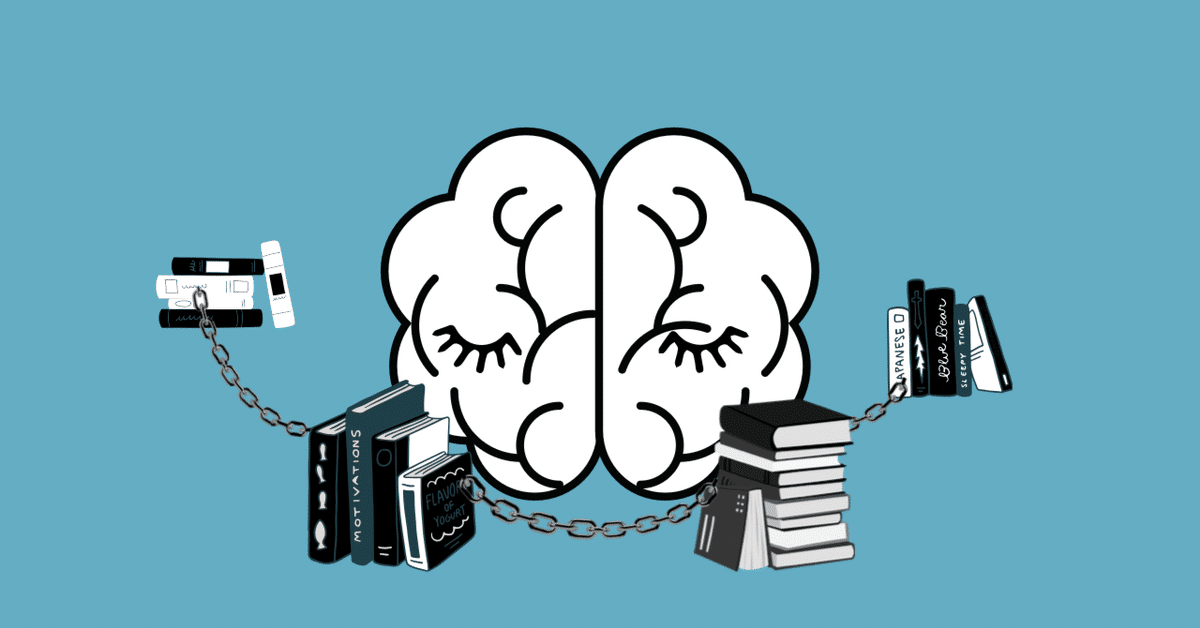
脳は失敗を織り込んで設計されている
前回の「知能ネタ」の続きです。
ようは、
AIが人間の知能(脳)から学ぶ際には不確定性が鍵になりそう、
という話です。
そして不確定性を学ぶのは、脳内の動きをみればよいのでは?という締め(逃げ?)でくくりました。
例えば、最近紹介したように部分的に生物の脳細胞を埋め込んだコンピュータの開発も行われています。
と、人工脳の期待がたかまるわけですが、そもそも、なぜ人類の脳は曖昧性をもっているのでしょう?
そんな疑問をもっていたら、とても面白い書籍を見つけました。
なかなか逆説的に聞こえる刺激的なタイトルです。
この書籍と関連情報も添えながら、疑問への回答に充てたいと思います。
まず、書籍のメッセージを凝縮すると、
「脳は間違えるからこそ高度な知的能力を獲得した」
ということです。
その証拠を最新研究を交えながら個別論点に分けて紹介しています。
なかでも私が一番印象的だったのは、
「神経間の伝達は決定論的でなく確率的である」
という話でした。
脳内の基本素子ニューロン(神経細胞)の動作については、過去の類似投稿に委ねます。

ニューロン間をシナプスという関節に相当する接合部で電気信号を授受した偉大なるバトンリレーなわけです。
これだけかくと、コンピュータ的な動きにみえますが、このバトンリレーが「確率的」というわけです。結構びっくりしませんか?
個人的には、アインシュタインが量子力学を否定するときに使った名言、「神はサイコロを振らない」と連想しました。
書籍内ではそのバトンリレー貢献度が割合で数値化されており、0.01〰0.1です。
つまり、常時微弱な電気信号は発火していて、そのうち最大でも10回に1回(しかもその予測は困難)しか次のニューロン発火には役立たない、ということです。
脳は超エコなコンピュータ、というイメージがありましたが、それを大きく覆しかねない結果です。
しかも、その伝播速度が時速150〰600kmです。
「早い」と思った方のために添えておくと、我々が使っているデジタルコンピュータの伝達素子である電子の速度は光の速さに近い、つまり時速10億km程度です。桁違いも甚だしいです。
我々の精神活動の根っこにある基本所作がこんなに曖昧かつのんびりと動いているのは、結構衝撃的です。
もちろん上記は統計的なマクロ数値ですので、例えば集中しているときはよりニューロン群が同期的に動く現象を起こすことも指摘しています。
ちょっとネガティブな書き方が続いたので、もう少しフォローしておきます。
ニューロン間で正しいデータを受けても間違った処理をする、逆もまた叱りで、間違ったデータから創造的な発想を生む、可能性も秘めているということです。
こんな脳ですが、さて、これをしてコンピュータで再現できるか?
おそらく二極化するかもしれません。
まずは一見難しいのでやはりコンピュータの汎用知能化(人間の脳の再現)は難しい、と感じる方々。
逆に、こういった機能を実装しようとする野心的な方々。例えば、確率的と書きましたが、確率的なモデルを実装すればよい、とも取れます。
ということで、まだまだ脳とAIはランデブーが続き、融合するのはもう少し先になりそうですが、こういった成果がみえてくると、いつかは・・・と期待が高まります。
最後になりますが、誤解したり誤記したりするのは私のせいではなく「脳のせい」ですよ〰、と添えて締めにしておきます☺
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
