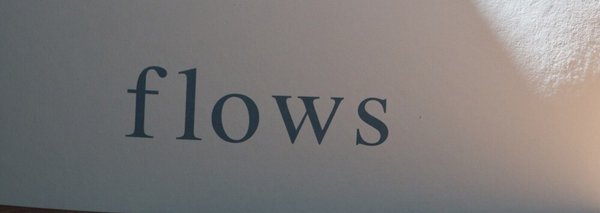最近の記事

「美術大学で、絵を描くことをはじめ美術を学ぶということは、どういうことだろうか?」ということを、学生から教えてもらった4年間の終わり
この3月で山形に越してきてから4年が経ち、いよいよ、4月から5年目になる。大学に勤めての4年間とは、入職当初入学した1年生が4年生になって卒業していく、その時間にあたっていて、先日の卒業式でも、そのような話をした。 あの頃、僕たち(と、あえて「たち」と言わせてもらうけれども)は、大学1年目であったにも関わらず、パンデミックによって、直接会うことはかなわず、前期の授業はリモートで行われた。パソコンのモニタ越しで、zoomで初めて出会い、行われた僕たちの大学生活について、あの苦
マガジン
記事

「つくる」ことをめぐる覚え書き(2024)——「そうすることしかできなかった」物事から生まれたものと、ともに生きることを選ぶこと
明日、2024年2月7日(水)から12日(月)までの6日間、勤務先では「2023年度東北芸術工科大学 卒業/修了研究・制作展」が開催される。今日はその内覧会だった。 学生たちに対して顔には出さないけれども、とても、とても感慨深く、嬉しく思うことは、卒業制作を発表する学部の学生たちは、2020年4月入学のため、私とは言わば「同期」になるのだが、残念ながら、COVID-19の感染防止のため、ともに「入学式」を迎えることができなかったけれども、それから数年が経って、状況が変わり(

[2023/10/26更新・追記]ポジティブなエネルギー(室井悠輔《車輪の下》「中之条ビエンナーレ2023」野反ライン山口)
ここ2年弱、「生きることと芸術は、絶対に結びついている」という確信があり、「だから芸術は大事である」と、一足飛びに結論づけてしまうのは、雑なので、もう少し補足してみると、「生きることと芸術は、絶対に結びついている。なぜなら、僕はそこ(芸術)から、ポジティブなエネルギーを日々もらっているからだ」ということになる。「芸術」という言葉を使ってしまったが、これは便宜的なもので、制度としてのそれではなく、もっと原初的な「つくること」と結びついたそれだ。制度以前の「つくること」、それは、