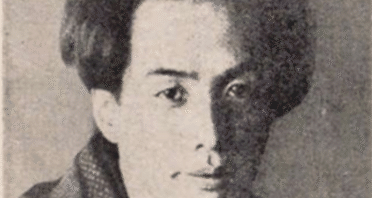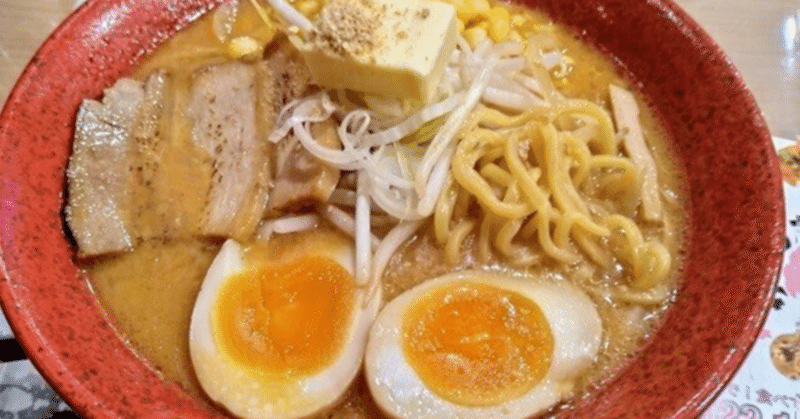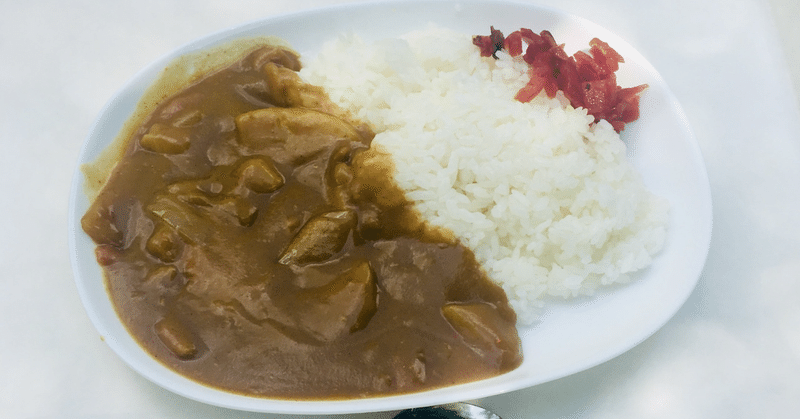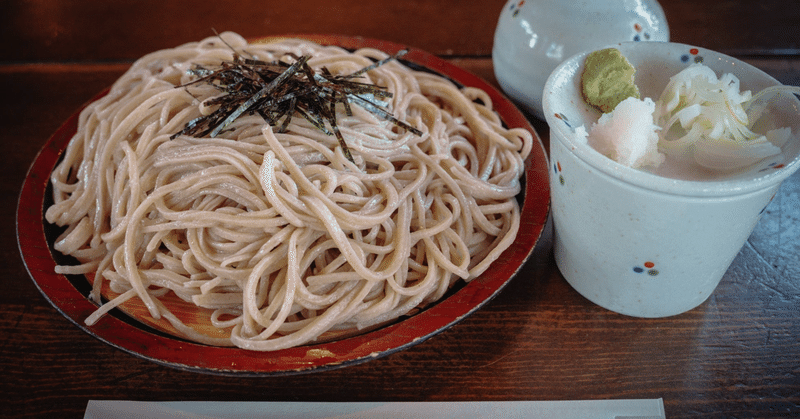2023年4月の記事一覧
芥川龍之介の『報恩記』をどう読むか② そんなことで傷つかなくてもいい
二百貫とは……
夏目漱石の『こころ』で、先生の手紙は長すぎてとても懐に入らないだろうと言われる。
この二百貫も銭貫二百本だと考えると千文が二百束、つまり二十万文の銭となる。
一文の重さが3.75グラムだとすると、阿媽港甚内の胴巻きには750,000グラム、つまり750キログラムの銭が入っていたことになる。雌の水牛かセイウチをぶら下げるようなもので、こんなものを胴巻きに入れるとなると阿媽
芥川龍之介の『報恩記』をどう読むか① 野暮を書いてすみません
一応切支丹ものとは呼ばれていて、切支丹らしき者も出て來るとは言え、どうも切支丹ものとしての『報恩記』というものが真面目に論じられた気配がない。
勿論『報恩記』は保温器の洒落であり、ジューではなくジャーの話だと言った面白い話も見つからない。
むしろみな積極的に切支丹ものではないところに引っかかって、『報恩記』を読んでいるようだ。そんなことだからつい昨日まで『西方の人』という意味が解しかねてい
芥川龍之介の『鼻』をどう読むか① 揺れてこそ
これまで『鼻』に関しては、
①落し噺を換骨奪胎した構成が面白い
②文章が上手い
という程度のことは書いてきたが、きっちり一つの作品として論ってはこなかった。しかしここにはまだ語るべきことがたくさんある。
③題名が簡素で良い
夏目漱石作品も同じく題名は簡素、二文字が多い。『吾輩は猫である』も元は『猫傳』。芥川の場合一文字のものが二十作品以上ある。中身が一番短いものは『私が好きな作家』の
芥川龍之介の『南京の基督』をどう読むか② そういう意味だったのね
芥川龍之介の切支丹ものと呼ばれている作品を立て続けに読んできて、そろそろ核心的な事を書いておかないと、最後に引っくり返す落ちが付かないので、特に『南京の基督』に関して明確に言えるところを書いておこう。
これまで芥川がまるで阿呆にものを教えるように書いてきたところをなぞれば、日本へのキリスト教の伝搬は1549年カトリック教イエスズ会の宣教師フランシスコ・ザビエルに始まる。芥川はそのキリスト教が
芥川龍之介の『南京の基督』をどう読むか① 商女不知亡國恨
何日か続けて『続西方の人』から最初の方に戻って芥川の切支丹ものと呼ばれている作品を何作が読み続けてきて、
①何故芥川は切支丹ものに拘り続けてきたのか?
②何故私は切支丹ものを避けてきたのか?
という問いが頭の中をただぐるぐる回り続けている。切支丹ものを避けてきた理由の一つには解り難さというものが確かにある。たとえば「きりしとほろ」の「ほろ」の意味、これなんか調べないで何となく感覚的に「ホロ
芥川龍之介の主要作品に関する基本的な考え方について
筑摩版『芥川龍之介全集』の解説者・吉田精一がそもそもかなりの偏見の持ち主であることから、多くの読者が芥川作品を読み誤っていることはとても残念なことだ。小説に正しい読み方などないという主張もあるにはあるが、それならば何故「解説」などが可能なのかと問われないことも空しい。
仮に芥川作品の魅力の一つに「知的なひねり」があると認められるのならば、その「引っ掛かりポイント」を指摘し、解釈を示すことは可能
『きりしとほろ上人伝』をどう読むか③ そうやすやすと担がれはしない
つまり「きりしとほろ」の往生にこそ芥川らしい知的なひねりが見出されねばならないのだ。鎌倉の雑貨屋が関東大震災の津波で流されるような、そうした仕掛けがなくてはおかしい。仕掛けはただ山の男が河で死ぬというレベルの落ちではなく、おそらくはキリストやキリスト教そのものを覆すものでなくてはならない。「呪うキリスト」は既に『さまよえる猶太人』に現れていたものだし、「十歳未満のキリスト」も種本から借りたに過ぎ
もっとみる芥川龍之介の『さまよえる猶太人』をどう読むか⑦兼『奉教人の死』をどう読むか③兼『きりしとほろ上人伝』をどう読むか② 逆にこうも言える
昨日、『きりしとほろ上人伝』において平安時代のエジプトに現れる少年「えす・きりしと」は『トマスによるイエスの幼児物語』に現れる幼いイエスのように残酷であり、『さまよえる猶太人』に現れる「呪うキリスト」に似た雰囲気を持っており、形式的には「えす・きりしと」こそが「さまよえる猶太人」になってしまっていると書いた。
では、十歳にもならない「えす・きりしと」を描くことは、十二歳以降のキリストしか登場
芥川龍之介の『さまよえる猶太人』をどう読むか⑥兼『奉教人の死』をどう読むか②兼『きりしとほろ上人伝』をどう読むか① 中身のない話を書くな
私が「芥川龍之介の作品は誰にも読まれていない」と書くのは冗談でも何でもない。例えばこの『きりしとほろ上人伝』に関してネットで検索すると一番上に恐ろしく中身のない論文のようなものが上がってくる。結論は、「『奉教人の死』を含めて考察する必要があると考えている」……それは前置きではないのか。
何故考察しない?
端的に言えば『奉教人の死』は「死んで見たらば始めて女であつたことがわかつたといふ筋」
芥川龍之介の『奉教人の死』をどう読むか① トイレは別の方がいい
まだまだ『さまよえる猶太人』に関しては書きたらないところがあるけれど、他の作品との関連付けで語るべきところもあり、一先ずペンを止める事にしようと思う。
村上春樹のデビュー作『風の歌を聴け』でデレク・ハートフィールドという架空の作家の作品の一部が紹介され、多くの人がその実在を信じた、という話は有名であろう。
そのデレク・ハートフィールドに関して柄谷行人が「アメリカ人も殆ど知らない、又知る必
『さまよえる猶太人』をどう読むか⑤ 即座にやり返す男はいなかった
それにしても芥川の意地の悪いのは、よくぞというネタを拾ってくることだ。「さまよえる猶太人」伝説は格好のキリスト攻撃のネタである。
これまで見てきたように「やがて御主の救抜を蒙るのも、それがしひとりにきわまりました」という「さまよえる猶太人」の主張を拾えば、キリスト自身は救いの御子でもなんでもなくなる。さらにキリスト教を信じても誰も救われないことになる。
そればかりかよくよく考えてみれば、
『さまよえる猶太人』をどう読むか④ 養父への復讐? いえいえ。
ここが解らないで『さまよえる猶太人』に関して何か書いている人は駄目だという話を書いてしまおう。
それにしても④になっていまさら、つまり①~③までこのことに触れずにいるとは、こいつは何か根本的におかしいのではないかと思わないで貰いたい。いや、この『さまよえる猶太人』はややこしい話なのだ。①~③でその話をしてしまうと、こんがらがることが目に見えていたので、①「十四世紀の後半」、②「それがしひとり
『さまよえる猶太人』をどう読むか③ 文禄年間のマスストレージシステム?
夏目漱石の小説には時々物凄く未来感のある文句が飛び出す。「プログラム」という言葉の使い方、「五色の金」のアイデア、そして清子を飛行機に乗せてしまうところなど。
弟子の芥川もその点では負けていない。『さまよえる猶太人』には、こんな表現が出て來る。
現代のエンジニアなら、なるほど「文禄年間の MSS. 中から」見つけたのか、と何のこだわりもなく読むだろう。MSSをマスストレージシステムと読む
芥川龍之介の『歯車』をどう読むか52『さまよえる猶太人』をどう読むか②
これは飽くまで芥川の小説の読みの問題だとしながら「悪魔とさまよえる猶太人はキリスト教徒が日本に連れてきた」「悪魔と猶太人がセットになっている」などと書いてしまえば、何か酷く剣呑なことを書いてしまっているような気分になる。それがたとえ「十四世紀の後半において、日本の西南部は、大抵天主教を奉じていた」といった意味不明な出鱈目が仕掛けられた小説の解釈だからと云って、何を書いてもいいわけではなかろう。