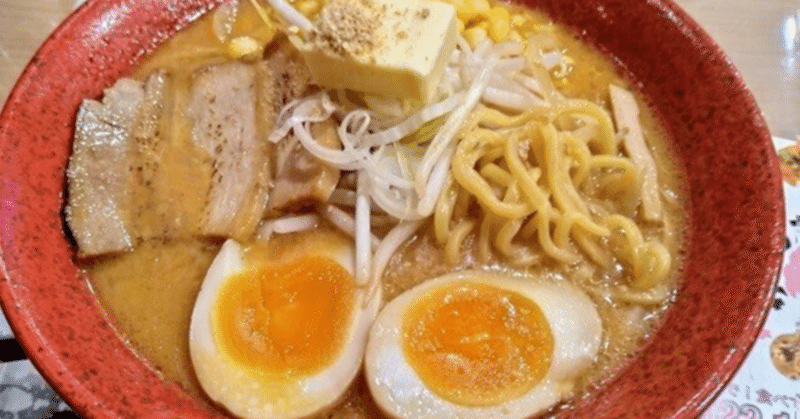
芥川龍之介の『報恩記』をどう読むか① 野暮を書いてすみません
一応切支丹ものとは呼ばれていて、切支丹らしき者も出て來るとは言え、どうも切支丹ものとしての『報恩記』というものが真面目に論じられた気配がない。
勿論『報恩記』は保温器の洒落であり、ジューではなくジャーの話だと言った面白い話も見つからない。
むしろみな積極的に切支丹ものではないところに引っかかって、『報恩記』を読んでいるようだ。そんなことだからつい昨日まで『西方の人』という意味が解しかねていたのではないか。
それにしても『報恩記』は確かに「そこ」に眼がいかないように様々な目くらましが仕掛けられた作品だ。
阿媽港甚内とはどういう意味か?
まず「阿媽港甚内(あまかわじんない)」という意味ありげな名前。「阿媽」とは、
中国・インドなどの東アジア圏において、外国人の家庭に使役された現地人の召使を指す語。乳母またはメイドに相当する。
などと説明されている言葉だが、谷崎潤一郎の『肉塊』にも登場していて、日本においても輸入されていた言葉だと解る。しかし桃山時代にはない言葉だろう。と思えば、
ただ阿媽港にいた時分、葡萄牙の船の医者に、究理の学問を教わりました。それを実地に役立てさえすれば、大きい錠前をねじ切ったり、重い閂を外したりするのは、格別むずかしい事ではありません。(微笑)今までにない盗みの仕方、――それも日本と云う未開の土地は、十字架や鉄砲の渡来と同様、やはり西洋に教わったのです。
とある通り、東アジアにキリスト教を広める起点となったマカオの異名が「阿媽港」であり「天川」と呼ばれていたこと、いずれにしてもキリスト教と因縁深い苗字であることが解る。
解る?
いや、全然解っていない。
わたしは甚内(じんない)と云うものです。苗字は――さあ、世間ではずっと前から、阿媽港甚内(あまかわじんない)と云っているようです。阿媽港甚内、――あなたもこの名は知っていますか? いや、驚くには及びません。わたしはあなたの知っている通り、評判の高い盗人です。しかし今夜参ったのは、盗みにはいったのではありません。どうかそれだけは安心して下さい。
この「阿媽港甚内」は飽くまで通り名のようなもの、つまりアントニオ猪木や「ぽうろ」弥三郎やジョン万次郎と同じで戸籍上の本名ではないのだ。
そして「ぽうろ」や「ジョン」は姓ではなく、「ぽうろ」弥三郎という名前は(個人名)プラス(個人名)ではなく、(洗礼名)プラス(個人名)と捉えるべきなのだろう。だとすると「阿媽港甚内」と呼ばれている男には、別の洗礼名があるのかもしれない。
阿媽港甚内は何者なのか?
あなたは日本にいる伴天連の中でも、道徳の高い人だと聞いています。して見れば盗人と名のついたものと、しばらくでも一しょにいると云う事は、愉快ではないかも知れません。が、わたしも思いのほか、盗みばかりしてもいないのです。いつぞや聚楽の御殿へ召された呂宋助左衛門の手代の一人も、確か甚内と名乗っていました。また利休居士の珍重していた「赤がしら」と称える水さしも、それを贈った連歌師の本名は、甚内とか云ったと聞いています。そう云えばつい二三年以前、阿媽港日記と云う本を書いた、大村あたりの通辞の名前も、甚内と云うのではなかったでしょうか? そのほか三条河原の喧嘩に、甲比丹「まるどなど」を救った虚無僧、堺の妙国寺門前に、南蛮の薬を売っていた商人、……そう云うものも名前を明かせば、何がし甚内だったのに違いありません。いや、それよりも大事なのは、去年この「さん・ふらんしすこ」の御寺へ、おん母「まりや」の爪を収めた、黄金の舎利塔を献じているのも、やはり甚内と云う信徒だった筈です。
それにしてもいささか情報量が多すぎる。「が、わたしも思いのほか、盗みばかりしてもいないのです」という言葉を真に受けると、呂宋助左衛門の手代、連歌師、大村あたりの通辞、甲比丹「まるどなど」を救った虚無僧、南蛮の薬を売っていた商人、黄金の舎利塔を献じた信徒、これらがみんな阿媽港甚内だということになる。
この阿媽港甚内の正体の解らないところは後に、
わたしが遇った贋雲水は四十前後の小男です。が、柳町の廓にいたのは、まだ三十を越えていない、赧ら顔に鬚の生えた、浪人だと云うではありませんか? 歌舞伎の小屋を擾がしたと云う、腰の曲った紅毛人、妙国寺の財宝を掠めたと云う、前髪の垂れた若侍、――そう云うのを皆甚内とすれば、あの男の正体を見分ける事さえ、到底人力には及ばない筈です。
このように「ぽうろ」弥三郎の話で念を得される。これでは鼠小僧でも石川五右衛門でもなく、まるで江戸川乱歩の怪人二十面相ではないか。
あるいはこのnotを三回以上読んだ人の中には、一日に二つの記事が書かれているところに気がついて、小林十之助というのは何人かの共同ペンネームではないかと疑った人もいるかもしれない。
その発想で言えば阿媽港甚内を一人に限るわけにもいかない。
さらに最後に結果として阿媽港甚内という名は「ぽうろ」弥三郎に乗っ取られてしまうので、阿媽港甚内は一人だったと言い切るわけにはいかない。少なくとも野村証券の創始者・野村徳七に初代と二代目が存在したように、阿媽港甚内に二代目がいてもおかしくない。呂宋助左衛門の手代、連歌師、大村あたりの通辞、甲比丹「まるどなど」を救った虚無僧、南蛮の薬を売っていた商人、黄金の舎利塔を献じた信徒、……これらのうちどれかは先代であったかもしれないのだ。
そして逆接の接続詞「が、」に注目してみれば阿媽港甚内は伴天連に対して「私は盗人と名のついたものではありますが、実は切支丹なのですよ」と言っているように読める。
御力を御恵み下さったのは阿媽港甚内
「おん主、『えす・きりすと』様。何とぞ我々夫婦の心に、あなた様の御力を御恵み下さい。……」
弥三右衛門は眼を閉じたまま、御祈りの言葉を呟き始めました。老女もやはり夫のように天帝の加護を乞うているようです。
弥三右衛門の窮地を救ったのは結果として『えす・きりすと』様ではなく阿媽港甚内だったということになる。この『報恩記』でもキリストは「だし」に過ぎず、キリスト無きまま耶蘇教徒が救われている。つまり阿媽港甚内は実質的にキリスト樣?
恩が仇になる話?
どうか恨みを返してやりたい、――わたしは日毎に痩せ細りながら、その事ばかりを考えていました。するとある夜わたしの心に、突然閃めいた一策があります。「まりや」様! 「まりや」様! この一策を御教え下すったのは、あなたの御恵みに違いありません。ただわたしの体を捨てる、吐血の病に衰え果てた、骨と皮ばかりの体を捨てる、――それだけの覚悟をしさえすれば、わたしの本望は遂げられるのです。わたしはその夜嬉しさの余り、いつまでも独り笑いながら、同じ言葉を繰返していました。――「甚内の身代りに首を打たれる。甚内の身代りに首を打たれる。………」
甚内の身代りに首を打たれる――何とすばらしい事ではありませんか? そうすれば勿論わたしと一しょに、甚内の罪も亡んでしまう。――甚内は広い日本国中、どこでも大威張りに歩けるのです。その代り(再び笑う)――その代りわたしは一夜の内に、稀代の大賊になれるのです。
この話は『報恩記』というタイトルなのにいつの間にか恨みを返す話になっている。しかし阿媽港甚内という名前に集められた数多くの罪を代わりに背負って斬首される「ぽうろ」弥三郎こそが偽キリストのようではなかろうか。そしてここで「無理やりにでも恩を受けさせること」が敵討ちになるという捻じれたところがまた芥川らしい訳の分からないところだ。恩に報いているようで報いていない。
それは阿媽港甚内が弥三右衛門にしたことも同じで、
ゴリゴリのキリスト教徒で日本に布教に行きたい旦那について行きたい米人女性、なぜ日本で布教したい?との質問に対し、良い国にしたいって言ってから、しまったと言う顔してた。
— 梓弓 (@Ma_R8) April 26, 2023
彼女は日本留学経験があって日本の実態を知ってたが、旦那の上から目線が問題だと分かってた。
昨今のLGBTQもコレ。
泥棒のテクニックにもなりうる究理の学問を阿媽港甚内に教えた葡萄牙の船の医者にも別に悪意はなかろう。善かれと思ってやったことが仇になっている。「ぽうろ」弥三郎が無理やり着せた恩は少しは阿媽港甚内の為になっただろうか。

いかに「読まないか」競争しているの?
阿媽港甚内と弥三右衛門の話だけ聞かされた伴天連は果して何を想うのか。これは私なんぞが訳知り顔で書く話ではないが『報恩記』の味噌は、最後の「ぽうろ」弥三郎の真意というものを伴天連が知らず、弥三右衛門の幻聴のまま受け取ったとしたら、というところにある。
適当なことを書いている人がいて、『藪の中』では互いの話が食い違うが、『報恩記』の場合にはそうした食い違いは見られない、なんてやっているが、どうしたものか。
弥三右衛門の幻聴に関わらず「ぽうろ」弥三郎は阿媽港甚内の手下になれなかった悔しさから、その仇討ちに阿媽港甚内に無理やり恩を着せたのであり、そこには何者にもなれない吐血の病に罹った「莫迦」な「白癩」が日本一の大泥棒の名前を奪って愉快がっている姿がある。
「甚内は貴様なぞの恩にはならぬ。」――あの男はこう云いました。しかしわたしは夜の明け次第、甚内の代りに殺されるのです。何と云う気味の好い面当てでしょう。わたしは首を曝されたまま、あの男の来るのを待ってやります。甚内はきっとわたしの首に、声のない哄笑を感ずるでしょう。「どうだ、弥三郎の恩返しは?」――その哄笑はこう云うのです。「お前はもう甚内では無い。阿媽港甚内はこの首なのだ、あの天下に噂の高い、日本にっぽん第一の大盗人は!」(笑う)ああ、わたしは愉快です。このくらい愉快に思った事は、一生にただ一度です。が、もし父の弥三右衛門に、わたしの曝らし首を見られた時には、――(苦しそうに)勘忍して下さい。お父さん! 吐血の病に罹かかったわたしは、たとい首を打たれずとも、三年とは命は続かないのです。どうか不孝は勘忍して下さい、わたしは極道に生まれましたが、とにかく一家の恩だけは返す事が出来たのですから、………
この「ぽうろ」弥三郎の哄笑を伴天連は知らない。そして残念なことに日々真面目に勉強して何とか学会やなんとか研究会に所属して、掲載料を払って書いた論文に、『藪の中』では互いの話が食い違うが、『報恩記』の場合にはそうした食い違いは見られないなんて書いていたとしたら、その人にも「ぽうろ」弥三郎の哄笑が届いていないことになる。
・いきなり誰か後から、言葉もかけずに組つきました。
・いきなり誰か言葉もかけず、わたしの襟上を捉えたものがあります。
これは食い違いではなかろうか。
それだけではない。
ある凩の烈しい夜でございましたが、わたし共夫婦は御存知の囲いに、夜の更けるのも知らず話して居りました。
例えば「御存知の」とあることの指摘がない。「囲い」とは茶室のこと。つまり伴天連は北条屋弥三右衛門の茶室に招かれたことがあるということになるが、そこを掘る人はいない。
人も二三人は殺して見ました。
『さん・ふらんしすこ』の寺の鐘楼も、焼けと云えば焼いて来ます。
そんな切支丹がいるものだろうか。この「見ました」って、お試しみたいな言い方はなんなのだろう。その親も親で切支丹ながら泥棒に金の工面をさせている。そして切支丹らしき阿媽港甚内は唐人を殺め日本一の大泥棒になっている。
兎に角切支丹はどいつもこいつも碌でもない、と芥川は書いていないだろうか。それなのにどういうわけかこの『報恩記』は切支丹ものとして論じられない。
あるいは、「親孝行でもしろ」と言われて親不孝をしていることや、凩がやんだ途端どっさり雪が降ることやなんかもほったらかしだ。「雪の深い茶室の前には」なんてことある?
そんなことある?
みんなどれだけ芥川を「読まないか」という大人の遊びをしているのであって、野暮な私がつい禁を冒している?
今私は少しも笑っていない。
[余談]

呂宋もお盛んなところだったようだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
