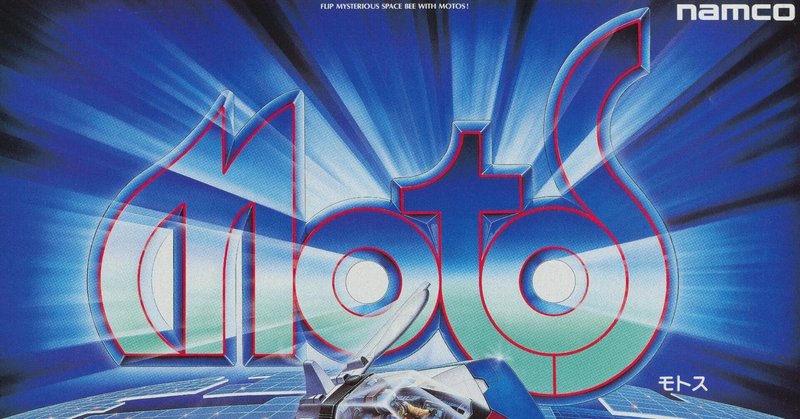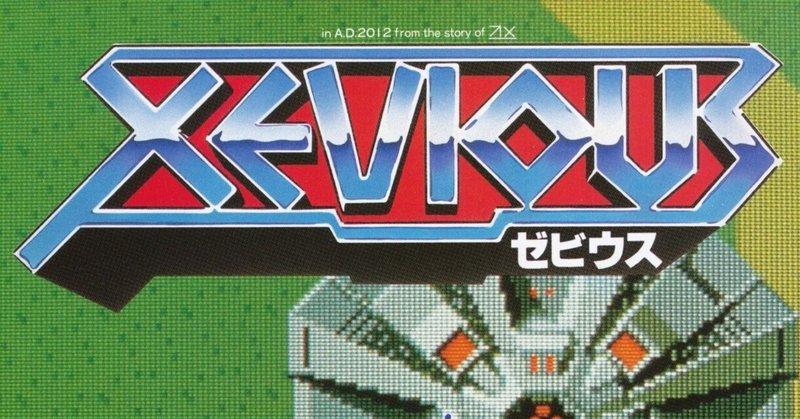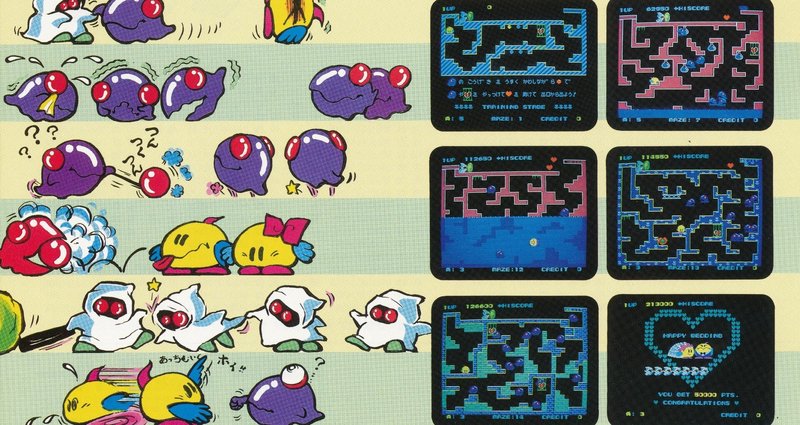
- 運営しているクリエイター
2017年6月の記事一覧
『アはアーケードのア』 第14回『ゼビウス』(1983年/ナムコ)
ゲーム史において時計の針を大きく進めた作品 地上と空中を撃ち分けて進んでいくゲームシステム、無彩色のグラデーションで表現されたメカニック、絵巻物のように進んでいく背景、神秘的なSE、バックストーリーを感じさせる謎めいた世界観と数々の隠し要素……『ゼビウス』はその後のビデオゲームに大きな影響を与えた黎明期の傑作です。
『ゼビウス』を初めてプレイしたとき、じつに不思議な気持ちになったことをよく覚え
『アはアーケードのア』 第13回『スペースインベーダー』(1978年タイトー)
衝撃的だった『スペースインベーダー』との出会い
『スペースインベーダー』は西角友宏氏がAtariの『Breakout』(ブロック崩し)をヒントに作り出したといわれています。『Breakout』のブロックを動かし、弾を撃たせ、より能動的な遊びに進化させたのが『スペースインベーダー』です。
社会現象にもなった『スペースインベーダー』という作品があったからこそ、多くの人々が「テレビゲーム」というもの