
太宰治と火野葦平 転向と自殺
火野葦平(1907年生まれ)と太宰治(1909年生まれ)は、同世代の作家だ。
どちらも昭和2(1927)年前後、大学生のころに、左翼思想にそまった。(火野は早稲田大学文学部、太宰は東京帝国大学文学部)
そして、どちらも大学を中退、どちらも昭和7年ごろに転向し、小説家を志した。
太宰は昭和10年と11年、「道化の華」などで芥川賞候補となるが、落選。昭和12年に自殺未遂事件を起こす。
火野は昭和12年の日華事変で応召、昭和13年に「糞尿譚」で芥川賞を受賞し、戦場の杭州で小林秀雄より賞を受け取る。
火野は戦中「兵隊作家」として人気となり、文学報国会の中心メンバーとして戦意高揚に努めた。昭和18、19年には芥川賞選考委員。いっぽう太宰は、肺浸潤のため徴兵免除されていた。
戦後、どちらも自殺した。太宰は昭和23年、38歳で。火野は昭和35年、53歳で。
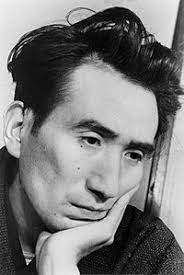

*
奥野健男は、太宰の自殺の遠因は、左翼運動からの転向だと論じた。
思想を、組織を、同志を、そして自己の倫理観を、裏切ったということが、彼の心にいやすことのできない傷を与えました。この時から、彼は一生、裏切り者としての罪の意識を背負うことになったのです。自己の一切を賭けて、信じた思想、立場を、自分の弱さから放棄し、脱落した、というどうすることもできない罪の意識を抱いたのです。
(奥野健男「太宰治論」)
*
田中艸太郎は、火野葦平の場合、転向が太宰のような「傷」にならなかった、と論じた。
火野は「オプティミズム(楽天主義)の作家」であり、「踏み絵の痛痕が存在しない」「『転び』の劣等感を抱かずに済んだ」と。
火野には、状況と人生がはげしく交錯したあと、おのれのくだらなさに後悔のほぞをかみながらも、誤謬をふくめてまるごとそのおのれを容認し、頭をひと振りすると、再びそこから生き直してゆく庶民の無意識のバイタリティがあり、時流に奔弄されるかにみえながら、容易に崩壊しない向日性の自己信頼が火野を激流の中でしっかと支えていたのである。
(田中艸太郎「火野葦平論」)
田中の「火野葦平論」が昭和46年に出版されたことが重要だ。火野は昭和35年に死んでいたが、それが自殺だと発表されたのは昭和47年だった。田中は、火野が自殺したことを知らずに、火野の「庶民のバイタリティ」を論じている。
(おもしろいのは、本書の出版をあっせんしたのが、火野の文学的同志だった劉寒吉だったことだ。劉は、火野の死が自殺だったことを知っている数少ない近親者の一人だった。だが、そのことを田中に言わなかったわけである。劉は、この時点で、火野が自殺だったことは永遠に発表されないと思っていたのかもしれない)
*
実際には、火野は転向で悩んでいた。
しかも、火野は2度「転向」している。
火野は、昭和2~7年は左翼であり、昭和13~20年は右翼だった。
かれは、昭和7年に、左翼から転向し(公安に逮捕連行された)、昭和20年に、右翼から転向した(日本の敗戦で転向を強いられた)。
太宰が自殺したころ、火野は「戦犯」疑いで公職追放されていた。
太宰の死後、公職追放が解除された昭和25年から作家活動を再開した。
だが、作家として活動しつつも、過去に「左翼」であったこと、そして「右翼」であったことは、かれの評価について回った。
戦後の左翼は、火野の「右翼」の経歴を許さなかった。だが、中野重治のような左翼は、火野の「左翼」の経歴を重視して、火野を擁護した。
いずれにせよ、かれは、戦前は「左翼」であったこと、戦中は「右翼」であったこと、そして戦後の自分は何者であるかについて、説明を求められていた。
*
火野葦平は一般に、太宰治のような「ひ弱なインテリ」ではなく、「たくましい庶民」であるとイメージされる。
火野自身が、そのようなイメージを自分で作っていった面がある。
しかし、戦中の「兵隊作家」時代から、かれにはある種の自殺性向があった。
かれは、戦場におもむいて作品を書く「兵隊作家」として重宝された。ほかの作家や新聞記者が行かない前線にも行きたがった。
「インパール作戦従軍記」などを読むと、自分はいつ死んでもいい、むしろ自分が戦場で死ぬことが日本のためだ、という意識がある。
そのころからすでに、過去の転向体験からくる自罰意識があったのかもしれない。
*
火野は、昭和33年、52歳のとき、「世界」に、左翼時代を振り返る「青春の岐路」を執筆した。
昭和34年、53歳のとき、「中央公論」に、右翼時代を振り返る「革命前後」を執筆した。
そして、昭和35年1月、自殺した。
(遺書)
「死にます、芥川龍之介とは違うかもしれないが、或る漠然とした不安のために。すみません。おゆるしください、さようなら」
かれはついに、転向の言い訳をするのに疲れたのかもしれない。
<参考>
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
