
四季詩集(5)
四季詩集とは
詩誌「四季」の同人の作品を収録した詩集です。「四季」は昭和8年創刊の詩誌で、萩原朔太郎、室生犀星、井伏鱒二、中原中也、伊東静雄、立原道造らが同人として参加し、風立ちぬで知られる堀辰雄が編集に携わっていました。
四季詩集概要
タイトル:四季詩集
著者:丸山薫 編
出版社:山雅房 昭和16年(1941年)
価格:3円50銭
発行部数:限定800部
参加詩人:
井伏鱒二、乾直恵、内木豊子、大木実、木村宙平、阪本越郎、神保光太郎、杉山平一、竹村俊郎、竹中郁、田中冬二、立原道造、高森文夫、津村信夫、塚山勇三、萩原朔太郎、福原清、丸山薫、眞壁仁、槇田帆呂路郎、三好達治、室生犀星、村中測太郎、薬師寺衛 (50音順)
竹中郁『首里少女』
光る枝、
光る木の葉、
光る赤屋根。
かなた
白い波さわぐ珊瑚礁、
豚の血に染められた帆、帆。
とほく慶良間群島。
首里陽春。
髪ゆたかな娘の項に
うごくともない天とう蟲。
一見して、ほのぼのとした印象を覚える10行の叙景詩です。光を強調した書き出しは、雲一つない快晴の空を想像させ、平和な日常を思わせます。「豚の血に染められた帆、帆。」とは真っ赤な”何か”がたくさん揺れている様子を表現しているとしたら、私はデイゴの花が思い浮かびました。珊瑚礁の海に白波が立ち、陸では真っ赤な花々が揺れている。美しい色の対比がされています。「首里陽春。」の4文字でピシャリと言い切る形は、その美しい景色が、春の首里から望む不変的、恒久的なもので、常に日常のなかにある親密さを思わせます。そして少女の項に止まる天道虫が、おそらく太陽のメタファであるとすれば、燦々と降る陽光が彼女を見守り続けるような、神秘的な情景として切り取られているのかもしれません。
しかし、どこか心が騒ぎ立つのは、歴史を知っているからでしょうか。四季詩集が出版される2年前には第二次世界大戦が勃発しており、出版された年には太平洋戦争が勃発、さらに4年後には沖縄戦に突入していきます。それを踏まえて読み返すと、言語化できない虚しさのような感情が込み上げてきます。
田中冬二『湖水のほとり』
湖水の一処 湖水へ渓流の注ぐ処に
水車はさびしい音をさせて廻っていた
湖水の鱒が渓流へ遡るのを阻止して
水車のさびしい音が木枯を呼んだ
この湖水には「水車」と「鱒」と「私」しかいません。風さえ吹かず、水車の軋むような音は寂しさを思わせます。「水車」はその寂しい世界を創るものであり、「鱒」はその世界でしか泳ぐことのできない弱々しい存在です。そしてそれは、どこか人間社会の写しているようにも思えてきます。「鱒」が「私、あなた」ならば、「水車」は何でしょうか。そして水車が呼んだ木枯らしは、世界の寂しさを強めるのか、それとも寂しい世界を壊してくれるのか、たった4行の詩からも想像が膨らみます。
「湖水」「水車」「さびしい音」という言葉が文章を主導していて、ひとつの視覚的リズムを作っているのと、それらに拘束されたひとつの世界というものが表現されているようです。
立原道造『村ぐらし』
作者は四季詩集が出版される2年前に亡くなっていて、唯一故人として詩が掲載されています。未刊詩集『田舎歌』に収録されている一編がこの『村ぐらし』ですが、『立原道造詩集』と『四季詩集』とで、実はこの詩の内容が異なっていたりします。
郵便函は荒物店の軒にいた
手紙をいれに 真昼の日傘をさして
別荘のお嬢さんが来ると 彼は無精者らしく口をひらき
お嬢さんは急にかなしくなり ひっそりとした街道を帰っていく
まるで何か物語の始まりを思わせるようです。そして、ここから4回も場面が切り替わり「僕」と「村人」の生活の一部が切り取られています。
「お嬢さん」は街道を帰っていき、その道は落葉松の林に繋がっている。「僕」はその落葉松の林から見据えた山脈の向こうに、雨を降らせて帰っていく雲を見つめている。雨上がりの虹に見惚れている村の「娘たち」は、洗濯物を干し忘れて空を眺めている。
あの人は日が暮れると黄いろな帯を締め
村外れの追分け道で 村は落葉松の林に消え
あの人はそのまま黄いろなゆふすげの花となり
夏は過ぎ……
やがて日が暮れると、「あの人」は黄色の帯を締めて何処かへいきます。季節柄、夏祭りなどを想像させますが、「ゆふすげの花となり」「夏は過ぎ……」という言葉の連なりから、佳人薄命というような儚さを感じさせます。このように4つの場面が直線的に繋がっていて、朝から夜にかけて「夏の一日」が物語のように語られています。
さらに場面が切り替わり、「僕」と崩れかかった「水車小屋」の描写がされています。歌うように、緩やかに廻る水車のことを村人たちは忘れ、「僕」だけがその存在を認めています。そこには人に対する愛情のようなものさえ感じさせます。
ああ、傷のような僕、目をつむれ。風が林をとおりすぎる。お前はまたうそをついて、お前のものではない物語を盗む、それが詩だといいながら。
この詩の最後は散文詩で締められています。そしてそれは『立原道造詩集』には無い一文です。(その他も内容の違いはありますが。)作者の、物語詩を書くということの迷いや葛藤が感じられます。詩はフィクションなのかノンフィクションなのか、本人の体験なのか、他人の体験なのか、詩人は色々と悩むところでもあります。それにしても、この詩の物語はさながら無声映画のように、綺麗な映像が思い浮かぶようでした。短文で読者に想像力を働かせる文章は、小説とは明確に区別された物語として魅力的です。
高森文夫『少年』
空は原始林の焚火のようだった
病院帰りの馬車にゆられて
わたしは父親の肩にもたれていた
轍のひびきは楽しく物悲しかった
病院帰りの最中に見る景色というものは、健康体であるときよりも暗い印象に映ります。轍のひびきはリズムを感じさせるように心地良いものですが、当人の気分次第で楽しくも悲しくもなります。
ぼんやりと遠くを眺めていると、農民が牛を曳いている姿が見えます。すると一羽の鴉が空低く翔び降りてきて、牛の頭にとまって不気味に鳴きだします。鴉は不吉の象徴として描かれているのでしょう。農民の顔に当惑と戦慄が現れたかと思うと、それは「少年」にも押し寄せてきます。
馬車は落日に長い影を曳いて走り
轣轆(れきろく)の音は重々しく野末につたわった
空は大火事のような夕焼だった
轍のひびきから「楽しさ」は消えて、鴉の鳴き声が不気味に響き渡ります。そして、空はいつの間にか大火事のように怖ろしい様相を示していて、子供の不安定な心情が表現されています。景色の見え方を変えることによって、それを感じさせる誘導が上手くなされています。
終わりに
『首里少女』のように、歴史を知ったうえで読むと受け取り方が変わるような詩があります。それは叙景詩が叙事詩に繋がっていくような印象ですが、昨今のコロナ禍でも同様に、ひとつの詩の見え方が変わってくることもあるでしょう。戦前・戦中・戦後で詩の作風が変わった詩人は多くいるでしょうが、アフターコロナの詩人もそのように影響されてくるのかもしれません。
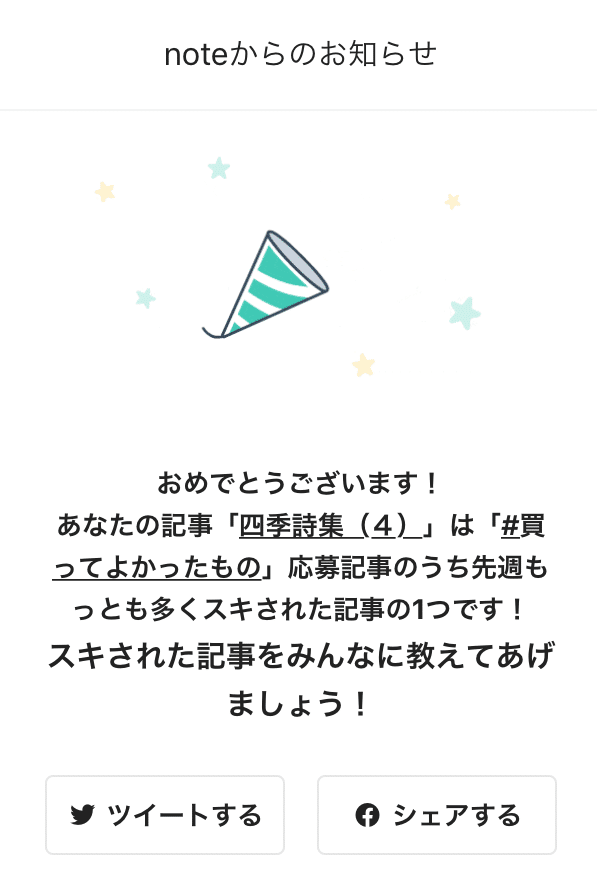
『四季詩集』の折り返し地点にきましたが、やはり様々な表現に驚かされています。私は自分の詩的表現の糧にするため、詩を読み、分析していますが、「書くために読む」ということの大切さが日に日に理解されてきます。改めて良い本に出会ったと思います。
余談
詩を寄稿しています。興味のある方は是非。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
