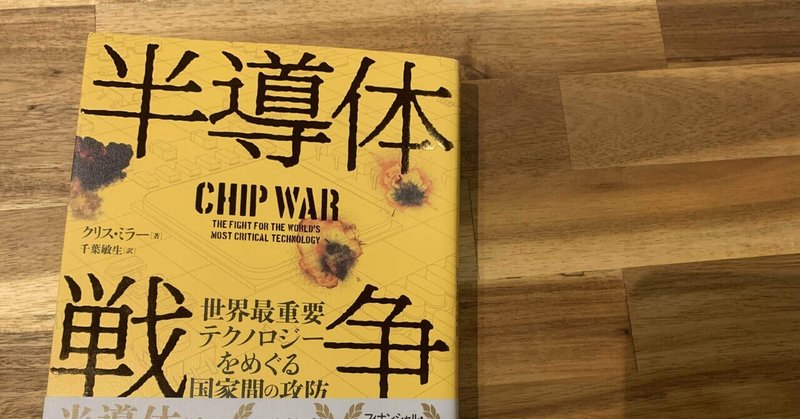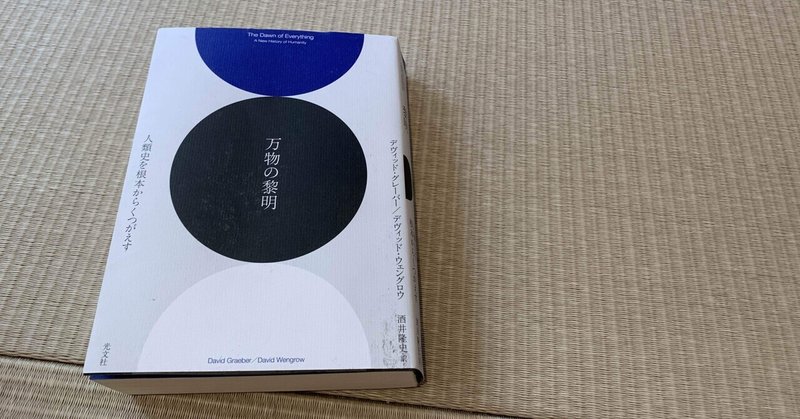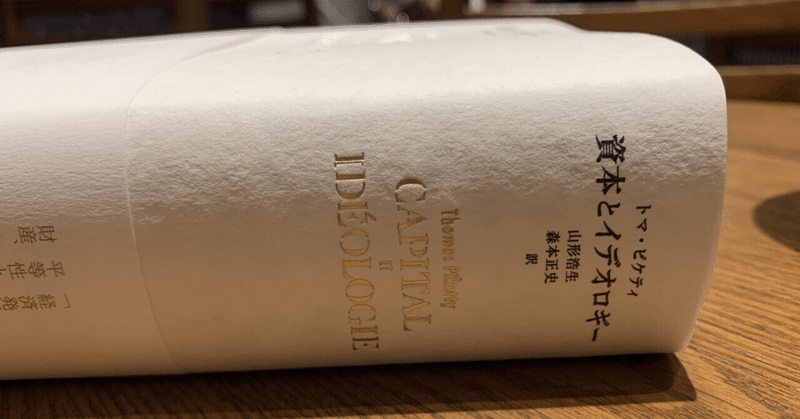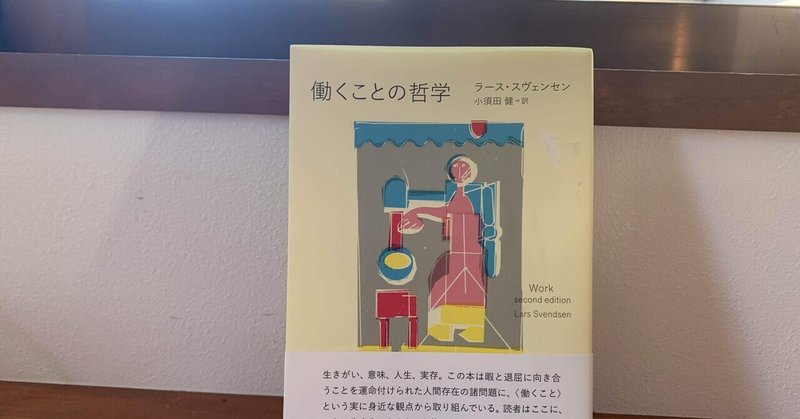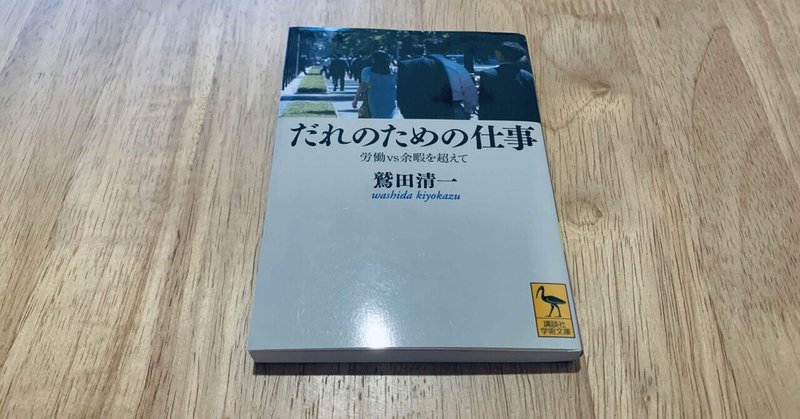- 運営しているクリエイター
#読書感想文
グレーバー&ウェングロウ『万物の黎明』を読んで
「この本は、瞬く間に世論を席巻し、歴史を変えるに違いない」と確信する本に、これまで何度か出会ってきた。例えば『ブルシット・ジョブ』『Humankind』『ティール組織』などである。実際にこれらの本は、僕のようなごく一部の人々を勇気づけ、知的興奮に誘った。しかし、残念ながら瞬く間に歴史を変えるような事態にはならなかった。例えば、僕が自称読書家が集まる読書会で『ブルシット・ジョブ』を紹介しようものなら
もっとみるトマ・ピケティ『資本とイデオロギー』を読んで
索引と注を除いても931ページ。税込価格で6930円。ピケティが想定する読者層である「市民」の大半は、この本を読むくらいならアニメONE PIECEを全話(約1000話)観る方を選ぶだろう。
しかし、その選択は賢明とは言えないかもしれない。ピケティの文体は読みやすく、グラフでの図解も多いため、想像以上にさくさく読み進められる。それに、知的好奇心を刺激するような描写も多く、アニメONE PIECE
ラース・スヴェンセン『働くことの哲学』を読んで
そう言って、埃まみれの積読エリアにピケティ『資本とイデオロギー』がやってきた。自分がリアルタイムで興味関心のあるテーマと、新発売された本が噛み合わないことはよくある(と、言い訳しておこう)。
代わりに読んだのが『働くことの哲学』である。
この本は、以下の書評でいただいたコメントの中でタイトルが上がっていたので、読んでみたのだ。
(そろそろ、労働哲学者でも名乗ろうかと思ってきた。宗教の教祖とか
鷲田清一『だれのための仕事 労働vs余暇を超えて』を読んで
自分と似たような主張を発見したときは、複雑な感情が込み上げてくる。
特にその主張が、自分独自の考察であると確信していた場合には、自分だけの秘密基地に誰かが土足で上がり込んできたような、そういう感覚を覚える。
それでもなお、自分の考えが第三者によって裏付けられたという心強さを感じられるし、自分の考えとの微妙な相違点に気づき自分の独自性に対する確信を強める結果に着地することもある。
要するに、自
中山元『労働の思想史』を読んで
■この本を読むきっかけ教養の幅広さ至上主義(もうちょっといい名前がつけられそうだが、まぁとりあえずこう呼ばせてほしい)みたいなものが、近ごろ自称インテリ界隈の中で跋扈している気がする。僕はこういうマウント合戦には極力参加しないつもりでいたのだが、知らず知らずのうちに参加していたらしい。最近、そのことに気付かされた。
僕は「労働」というテーマについて本を書いたし、次もこのテーマをさらに発展させて
ハンナ・アレント『人間の条件』を読んで
コロナで1日中書斎に篭っていられる今、積読消化週間を開催中。2冊目はハンナ・アレント『人間の条件』だ。
最近、新訳出てたから買ったはいいけど、たぶん読んでもつまらんだろうなぁと思って放置していた。人間の行為を「労働」「仕事」「活動」に分けてウンタラカンタラ的な内容ということは知っていたが、そういう分け方が恣意的であまり意味がないような気がしていたし、尚且つ「人間の条件」というタイトルが押し付けが
来たれ、どんぶり勘定革命
あまり大きな声では言えないが、最近、柄谷行人の『世界史の構造』を読んだ(オードリー・タンに触発されて読んだというのも、ナイショの話だ)。マルクスが生産様式で歴史を語ったことの問題点を指摘しつつ、その代わりに交換様式を導きの糸として歴史を語り、その上で申し訳程度に資本主義を乗り越えるための展望が描かれている本だった。
資本=ネーション=ステートという構図で歴史を語る手法は鮮やかで「天晴れ」の一言に