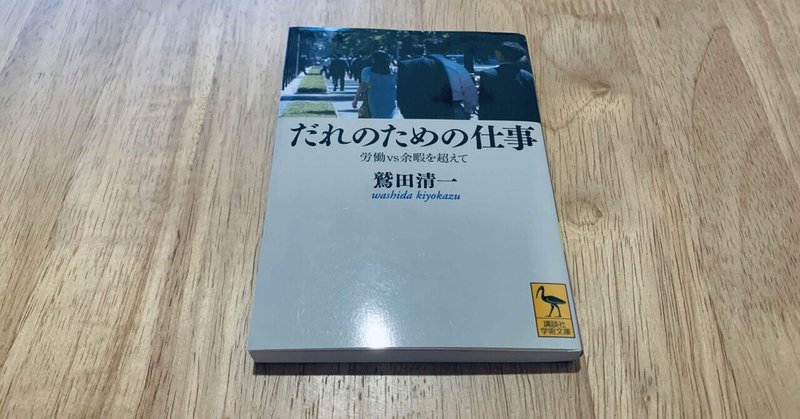
鷲田清一『だれのための仕事 労働vs余暇を超えて』を読んで
自分と似たような主張を発見したときは、複雑な感情が込み上げてくる。
特にその主張が、自分独自の考察であると確信していた場合には、自分だけの秘密基地に誰かが土足で上がり込んできたような、そういう感覚を覚える。
それでもなお、自分の考えが第三者によって裏付けられたという心強さを感じられるし、自分の考えとの微妙な相違点に気づき自分の独自性に対する確信を強める結果に着地することもある。
要するに、自分と似たような主張を発見することは、複雑な感情によるマイナス効果を補って余りある、プラスの効果をもたらしてくれる。
そして僕は今回、似たような主張をしている本をたまたま発見して、読んでみた。
サブタイトルにもあるように、人々の心理にインストールされている「労働vs余暇」という対立構造の成立過程を考察しつつ、それを超える労働観を提示しようとしている本だ。看板に偽りはなく、昨日、書評を上げた中山元『労働の思想史』の教科書的成分を弱めて、切れ味を強めたような内容である。
やっぱ似たようなことを考える人の本を読むのは気持ちがいいものだ。「わかるー」という気持ちになれるからだ。だが、もちろん細かい不満点や相違点はいくつかあった。それに、僕のスタンスのようににラディカルな社会変革につなげて論じるような本ではなく、むしろやや昔ながらの職人気質や根性論に後退するような記述もみられたため、そういう点でも諸手を挙げて同意するような本ではなかった。だが、そこに至るまでの現代の労働観への分析は鋭く、納得感を持ちながら読み進められた。
賛成点、不満点、その他諸々もふくめて、何はともあれ書評を書き始めてみよう。
■まず、この本の前提
僕のnoteを読んでくれている人なら、一般的な意味で使用される「労働」と「余暇」という2つの概念の対立構造が、いかに曖昧なものかを知っていると思うが、改めて鷲田の言葉で復習しておこう。
鷲田は、「仕事=苦労、遊び=安楽」という世間一般に概ね流通しているように見えるイメージを「ステレオタイプ」として批判している。
このような考え方を純粋に適用できるような場面というのは、わたしたちの生活にはほとんど例外的にしか存在しない。働くか、さもなくば遊ぶか、といったオール・オア・ナッスィングの選択は、むしろ抽象的である。現に仕事を生きがいとするひとがいる以上、仕事にはよろこびがあるはずであり、またゲームのように遊びにもルールがある以上、そこには訓練がつきものである。スポーツを職業にしている人たちにとっては、それは深い快楽を生み出すものであっても、少なくとも安楽な遊びではない。
もちろんこの指摘を見たとき、人は「金がもらえたら仕事で、そうじゃなかったら遊びでしょ?」という素朴な疑問を投げかけることになるが、この本を読み進めていくにあたっては、一旦その疑問は脇に置いた方がいい。金を抜きにして、両者の性質を考察していくのが、この本の目的である。いずれにせよ人は、仕事=苦労、遊び=安楽というのイメージを持っていることはほぼ疑いようがない。それに「金」という基準で両者を区別するのは、この記事を読んでいるときのように改めて思考を巡らせているときであり、日常的にそう感じているわけではないと思われる。そして、そもそも「なぜ、金以外で両者を区別できないのか?」という疑問も生まれてくる。つまり、「金でしょ?」と一蹴せずに、じっくり考えてみることで、何か新しい洞察が生まれてくる可能性に期待した方がいいと、僕は言いたいわけだ。
では、鷲田と共に考えてみよう。なぜ人は「仕事=苦労、遊び=安楽」の二項対立に囚われているのか?
■二項対立の背景にある人生観と資本主義
学生の頃にもどりたい
でも 社畜の貯蓄はロマンチック
全ては老後のために
僕たちの人生観は概ね岡崎体育が歌詞にしてくれている通りだ。僕たちは学生という自由から追い出され、社畜という地獄の期間を豊かな老後のために働くのである。
鷲田の言葉で説明するとこうなる。
なぜ働くのかという問いがもしじぶんのなかからいやおうもなく頸をもたげてきたら、わたしたちは、生活するため、じぶんや家族の豊かで安らいだ将来の生活のためといった理由を挙げるにちがいない。
就職とは〈死〉であるという意識が根底にある。そうだとすれば、勉強という「仕事」からやっと解放された大学生たちが、残された束の間の期間をとにかく楽しんでおこうとするのも無理はない。
このような価値観は、すべて「現在というものが別の時間のためにあるという価値観(p21)」であると鷲田は指摘する。つまり、常に楽しみを先送りにしながら、気づけば死んでいくスタンスだ(もちろん、「土日祝日にそれ自体が楽しみである余暇があるのだ」という反論も生じるかもしれないが、その点に関しては後述)。
このスタンス自体は、普遍的なものでもなんでもなく、おそらく近代社会を象徴する「進歩史観」や「資本主義」といった発想から形成されたものであると、鷲田は考える。
進歩史観とは要するに「明日はもっとテクノロジーが発展し、生産力が向上し、知識が増大し、人類は良くなっていく」という発想だ。資本主義も同様の前提を基に、投資、複式簿記、約束手形といったメカニズム形成し、それらのメカニズムが前提をさらに強化してきた。そうしているうちに「未来に大きな価値を生み出すために、今を生きる」という価値観が人々にインストールされていったのだろう。
これは必然的に強迫症的な発想にたどり着く。それはつまり…
人間の活動というものは価値を生みだすべきものであるから、より多くのものをより速く、より効率的に算出していかねばならないという、資本主義のエートスの基底にある思考法であり、ベンジャミン・フランクリンが強調していたように、たんに価値を生みだすだけではなく、より生産的な未来に備えるという、目的性のある生産をしなければならないという思考である。
わたしたちの日々の行為が、何らかの価値を生産する活動として規定され、その合理性が効率性を基準として規定される。
時間を無駄に使用することをひとつの損失として意識させるような一種脅迫的な心性が発生する。
つまり、価値を生み出す時間=善、価値を生み出さない時間=悪という価値観が生まれてくるのである。
では、これがなぜ、「仕事=苦労、遊び=安楽」というイメージに発展していくのか? そこには一度、「価値観の強烈な揺り戻し(p43)」が必要だったと鷲田は指摘する。
■仕事中毒の沼と、離脱と
二世紀前は時間をすきまなしに効率よく使うために、そしてこんどは時間をのびのびと味わうために。「仕事中毒」というクリティカルなことばが生み出され、「仕事」や「労働」ということばが急に色褪せてみえるようになった。
いわゆるモーレツ社員的な人生に対する反撃である。ここで注目しなければならないことは、「余暇」の魅力に注目が集まるのと同時に、その対立項にある仕事が、全く魅力のないものとして人々の目に映るようになったことである。これまでなら仕事に多少は存在すると思われていた魅力が、不可視化され、労働と余暇が全く別物であるとする二項対立が確立されたのだ。
もともと人は「労働」に対してポジティブな感情とネガティブな感情の相反する感情を抱いていた。それはアダム・スミスの「労働価値説」とマルクスの「疎外論」から見てとることができる。
まず、鷲田が引用するアダム・スミスの「労働価値説」についての文章を見てみよう。
およそ商品の価値は、それを所有していても自分では使用または消費しようと思っている人にとっては、その商品でかれが購買または支配することのできる労働の量に等しい。
あらゆる物が、それを獲得した人にとって、またはそれを売りさばいたり他のなにかと交換したりしようと思う人にとって、真にどれほどの価値があるかといえば、それによってかれ自信がはぶくことのできる苦労と骨折りであり、また、それによって他の人々に課することができる苦労と骨折りである。
ここで注目しなければならないのは、「労働=価値」という労働価値説の発想ではない。「労働=苦労と骨折り」と前提されていることである。この発想自体は、古代ギリシアの自由人による労働蔑視に由来していると思われるが、何はともあれ、そのような発想自体は存在していた。
(ギリシアの話は、このあたりでも書いておいたので適宜参照してほしい)
だがこれが、実際に畑を耕し、パンを焼くような人々の実感と合致するかどうかは常に疑問である。ギリシアの自由人も、恐らくアダム・スミスも労働者ではない。彼らがある種、見下していたであろう人々こそが労働を担っていたのである。ならば、「それはきっと苦痛なのだろう」というイメージを抱くであろうことは、想像に難くない。間違っても「創造的で楽しいことをしている」というイメージを抱くことはないだろう(それは自らが楽しく意義深い労働という活動を放棄しているという事実と、心理的不協和を起こしてしまうからだ)。
一方で、労働そのものには本来喜びが存在すると考えていたのがマルクスであった。
マルクスにとって労働が人間にとってかけがえのないポジティブな意味をもつのは、それがみずから設定した目的の実現の過程としてあるからである。人間の労働過程は、計画と構想にもとづいて設計される。たとえば蜘蛛は巣作りにおいて、ミツバチは蝋房作りにおいて、人間の建築士顔負けの精緻な作業をする。が、人間の建築士の労働はそれよりも格段優れている。
わかりにくいが、要するに、自分で計画し、構想し、何かを実現していくというプロセスこそが、労働の優れた点であり、労働の魅力であるとマルクスは考えている(逆にミツバチや蜘蛛の行動は本能に支配されていて、計画や構想とは無縁であるとマルクスは考える。そう単純な話でもないことは近年の生物学の研究で明らかになっているようだが、本筋から逸れるのでスルーする)。
しかし、生産手段が資本家に所有され、労働者が単なる歯車となってしまった労働現場では、労働本来の魅力が失われていると、マルクスは考えた。裏を返せば、マルクスは、生産手段と計画と構想を取り戻せば、労働は楽しいと考えていたわけである。
アダム・スミスのように労働とはそもそもつまらないものと考えるにせよ、マルクスのように資本家のせいで労働がつまらなくなってしまったと考えるにせよ、いずれにせよ資本主義社会における「勤勉に労働せよ」という道徳的な命令は、「つまらないことをやり続けろ」という命令であり、自然とそれに対する反発が生まれてきた。そしてその反発自体が「つまらない労働ではなく、楽しい余暇をよこせ」になり、決して「楽しい労働をよこせ」ではなかったのは必然だった。「楽しい労働」とは存在し得ない空想へと転落していった。
だが、楽しいはずの余暇すらも、時間を効率的に使わなければならないという資本主義のエートスに支配されてしまっていると、鷲田は指摘する。
余暇(自由時間)そのものが消費の制度のなかに組み込まれ、たえず新たな欲望で埋められるだけでなく、さらには何か実のあること、たとえば自己学習や家庭奉仕、ヴォランティアなどといった別の意味で価値生産的な活動で充填しなければ……という脅迫的な意識がわたしたちのなかで芽生えてくる。あるいは、ゲーム、リゾート、観光旅行などといったレジャー産業の興隆。そこでは労働からの免除という余暇活動のディレクションとマネージメントこそが、もっとも大きなビジネス・チャンスとして浮上してくる。快楽までもが、まるで義務のように脅迫的に感じられるようになるのだ。
鷲田は無意識だろうが、ここでは現代の労働観における2つの潮流を、ごちゃ混ぜにして語っているようだ。
前者は余暇を仕事に役立つスキルアップなどに充てているのに対し、後者は仕事を徹底的に忘れて効率的に娯楽に邁進することを目的化している。
そして恐らく、前者は仕事に意義を見出そうとする労働至上主義であり「意識高い系」とも言い換えられる。後者は仕事の意義をとことん否定する娯楽至上主義であり「意識低い系」と言い換えられる。
さて、ここでこの本の前提条件が揺らぎ始めていることにお気づきだろうか。娯楽による快楽を至上目的とする「意識低い系」はともかくとして、「意識高い系」は「労働と余暇」という二項対立に囚われていないような印象を受ける。果たして休日に自己啓発セミナーへ参加したり、旅行や食事を「投資」と呼ぶような意識高い系は、仕事中毒からの離脱を望んでいるのだろうか? 仕事を忌むべき労働として軽蔑しているのだろうか?
恐らくそうではない。彼の仕事は、マルクスのいう計画や構想に溢れていて、やりがいに満ち溢れているに違いない。
とは言え、この本が出版されたのは1996年である。当時は意識高い系という現象が見られたのかは明らかではないし、恐らく見られなかった。この時点では鷲田は、現代では意識高い系と呼べるような姿勢を「エグゼクティブ」と呼んでいる。
仕事が遊びとなり、遊びが仕事となっている「やり手」たち、エグゼクティブたちが、かつての有閑階級の地位を占めているといえる。
まだこの当時はエグゼクティブ的なマインドセットで働く人は少数派だったのだろう。だが、エグゼクティブへの憧れを募らせている意識高い系がどこかのタイミングでマジョリティになっていった。
※人々がなぜ有閑階級ではなくワーカホリックなエグゼクティブに憧れるようになったのかは、以下で分析した。
彼らが台頭してきたことは、ある意味で歴史の必然であった。資本家たちは、労働者を徹底的に歯車扱いするテーラー主義やフォーディズムが実は非効率であることに気づいたのである。
より効率的な生産のために考案されたこの単純な反復労働の組み合わせは、生産工程としては合理的であったが、労働意欲を殺ぐというかたちで、逆にその効率を低下させていく。
そこでまた「いかにやる気を出させるか」という工夫を、管理職の人たちは考えださねばならないことになる。
この先のプロセスも二段回に分けられるだろう(鷲田はそのように分類しているわけではなく、あくまで僕個人の見解であるが)。
まず一段目はフーコー的な意味での「規格化(p65)」であり「自己監視の視線をノーマライズ(p66)」することであった。だがこれはあくまで学級委員的に黙々と刺身にたんぽぽを乗せるような姿勢は育んでも、それ以上の活躍は期待できない。そこで二段目として導入されたのが意識高い系的なモチベーションである。人々はスティーブンコヴィーや稲盛和夫、ロバートキヨサキのような人の自己啓発書を読んで、経営者目線とか、自分の市場価値とか、そういう観点をインストールして(されて)いったのだ。
この辺りのプロセスについては鷲田はほとんど記述していない。が、現代において労働を論ずるにあたっては見逃せない要素だろう。
さらに僕の意見を付け加えると、「労働効率を殺ぎ、非効率であることが発見された」のではなく、「非効率ではなかったが非効率になっていった」という側面が強いと思われる。あえて単純化すれば初期資本主義においてはモノを作れば作るだけ売れていて資本を増殖させられたが、市場が飽和していった中期から後期にかけては単に流れ作業でモノを作ってもゴミになる。市場となる地理上のフロンティアは消滅して、フロンティア‥言い換えれば欲望を作らねばならないフェーズに資本主義が突入したのだろう。
さて、それではニーズを生み出さねばならなくなり、社会はどうなったのかと言えば‥
豊かな物があたえる快適さではなく、記号やイメージを消費する快適さをターゲットにしたビジネスの急速な伸びである。旅行、娯楽、スポーツ、テーマパーク、教育、健康、ギャンブル、投機、出版、ファッション、美術・音楽・映画を対象とした、いわゆるレジャー行動(=自由時間消費)の巨大産業化である。
ここでは、意識低い系が消費する娯楽やテーマパークだけではなく、意識高い系が消費する出版、教育、美術なども含めまれる(ビジネス芸人のビジネス書やイベントなども、現代においては含まれる)。仕事以外を娯楽と捉える場合であれ、仕事のための投資と捉える場合であれ、あらゆるニーズが産業化されているのである。これはフロンティアを失った資本主義によるフロンティアの捏造以外の何物でもない。
フロンティアにニーズを捏造していくプロセスは、僕のような左翼にとってはブルシット・ジョブだと感じられるが、意識高い系にとっては「マーケティング」や「ブランディング」といったキラキラした概念に置き換えられる。つまりそれ自体が情熱を持って乗り越えるに値する難問であると解釈されていったのである。
(繰り返すが、これは鷲田の本が出版された後に起きたプロセスであり、僕の独自解釈である。)
■お膳立てされた遊びとプロ思考
一方で、意識低い系の人々が人生の醍醐味だと考えていたレジャーや余暇は、どのように変遷していったのだろうか?
まじめかふまじめか、仕事か遊びか、労働か余暇か、生産か消費かという、紋切り型の二者択一のなかで、遊びからしだいに<まじめさ>が欠落していった。
要するにあらゆる遊びが食材からコンロまで業者が用意してくれるグランピングのようなものに成り下がり、趣味人のアマチュア化が進んでしまったと、鷲田は考える。
これはフロンティアの中のフロンティアをマーケティングによって開拓しようと創意工夫した意識高い系と、「娯楽は楽であればあるほどいい」という余暇効率に支配された意識低い系の相互作用が発展していった結果であると思われる。
だが、ここでも現代の視点から見れば、鷲田の論点は不十分であると言わざるを得ない。この傾向も現代においては新しいフェーズに入ったと考えられる。近年では、余暇におけるプロ志向という新しいベクトルが人々を焚き付けている。
グランピングのような娯楽が溢れかえっている反面、本格的なキャンプグッズを揃えて手作り感のあるキャンプを追求するクラスタや、それを礼賛する傾向も存在する。
ここ10年ほどのオタク礼賛の傾向は、その象徴的な出来事と言える。ゼロ年代において、オタクは蔑称であった。しかし、アニメやゲームについて豊富な知識を有し、熱く語るオタクが、次第に憧れの対象になり始めたのだ。同様に、あらゆる趣味においてそれを突き詰めた人を称賛する文化が徐々に強まっていった。恐らくアマチュアリズムの飽和から、アマチュアリズムの脱却が起きているのだ。
この傾向により、趣味は再び意識高い系的な「生産性」の論理へと接近していった。どんな趣味であっても「それ、YouTubeで配信すればええやん?」と言われる現代では、趣味すらも広告収入に繋げることが最適解だとみなされる。
※プロ志向とYouTubeの関係については、こちらでも書いた。
まとめれば、とことんラグジュアリーな余暇を追求する態度と、趣味すらも文字通りの生産性へと変えてしまうプロ志向の、2つのベクトルが存在しているのだ。
鷲田の語り口からして「アマチュアリズムはくだらないから、もっと本気で趣味に取り組めよ」というスタンスが透けて見えた。そういう意味では、片方で、脱アマチュア傾向の強い現代は鷲田の理想通りの社会なのかもしれない。
このようなプロ志向すらも、資本にお膳立てされた趣味であるとみなすこともできる。「プロにならねば」という強迫観念を煽るために教則本があり、YouTube動画があり、習い事化し、ユーキャンが資格化する。それに本気の趣味というものも、資本主義の倫理に支配されてしまっている。全国の公演を観て回るジャニオタや、1人用の炊飯器や燻製器を揃えるキャンパー、自宅に音楽スタジオを作ってしまうアマチュアギタリストの消費額は、受け身のアマチュアとは訳が違う。
だが、鷲田は、あまり「資本がどうのこうの」という話はしない。あくまで彼が重視するのは、仕事の意味を取り戻し、趣味の意味を取り戻すことだからである。鷲田はアレントの有用性と有意味性という概念を比較し、有意味性の重要性を主張している。
有用性とは、とある目的のための手段として有用であることを意味し、これは快感の先送り的な発想であり、それ自体は意味を持たない(ゆえに労働であろうが、余暇であろうが、豊かな体験とはなり得ない)。本当に必要なのは、有意味性、つまり「達成されようとされまいと、発見されようとされまいと、関係なく存立しうるような意味(p117〜118)」が必要であると、鷲田は考えている。
考えようによっては、フロンティアのフロンティアを開拓しようとする創造性と、プロ志向の趣味人は、相互作用によって鷲田の理想を叶えかけているのかもしれない。どちらもそれ自体が目的化して、行為そのものに意味が付与されているように見えるからだ。
では、ここでいう「意味」とはどのように獲得されるのか? 鷲田の家事労働の解説からみていけば、そのプロセスがわかりやすい。
■家事労働からみる「意味」とは
家事労働も労働と同様、解放の論調の中で「退屈な行為」として烙印を押されているのだと、鷲田は考える。
労働と余暇を対置し、家事という「隷属的」な苦労から解放することがそのまま女性の解放につながると考えることによって、家事そのものがとてもネガティブな規定をあたえられることになった。
とは言っても、家族に貢献することは意味ではないのか? 貢献の喜びを噛み締めれば家事も楽しめるのではないだろうか?という疑問が頭に浮かぶ。だが、そう簡単ではないと、鷲田は説明する。
彼女が姑の世話をしていてしんどいのは、それがやってあたりまえのことだからである。
これは主婦ならば誰しもが経験する体験だろう。掃除をしようが洗濯をしようが、それは当たり前であり、誰からの感謝もない。故に誰かに貢献しているという意味を感じることなく、嫌々やらされる義務のようになる。そこには喜びはない(もちろん、そうでない人もいる)。姑はまるで自然現象のように世話を受け入れることになる。「昨日もやってくれたんだから、当然今日もやってくれるよね?」というわけだ(これはデヴィッド・グレーバーが『負債論』で展開した「ヒエラルキー」の概念に一致する)。
一方で、同じ主婦が姑の世話をすっぽかして、熱心にボランティアに取り組んだりすると、鷲田は言う。
家に病気で寝ている姑がいるのに、その看病をほっぽりだして、遠くの体育館へ毎日遅くまでヴォランティアに出かけている主婦がいるというひとがいる。
「単に姑が嫌いなだけやろ?」というツッコミは置いておこう。ボランティアは、他者への貢献という確かな意味を感じ取ることができる。これこそが人の活動を有意義なものに仕立て上げる意味の1つだろう。
ヴォランティアという活動が浮き彫りにしたのは、他者の前でだれかとしてその他者にかかわるという、ひさしく労働というものが失っている契機である。物ではなくて、記号でもなくて、他のひとにたいするものとしての労働、人びとのあいだでの活動としての労働である。
「ヴォランティアってなんやねんw」というツッコミも置いておこう。
繰り返すが、意識高い系の労働においては、個人としては他者へ貢献するという側面が一部復活しているように思われる。だが、鷲田による執筆当初においては、会社の歯車の一員として命令に従うという側面の方が強く、それは自己の意味として認識できなかったのだろう。
さてここまでの記述を読めば、鷲田の考える「意味」が他者との関係性のネットワークの中でしか形成されないものであるかのような印象を受けることになる。
だが、自己など存在せず、他者との関係性の中にしか人格は存在しないといった極端な立場を鷲田は取らない。自己としてのアイデンティティも、意味の形成には役立つ。結局のところ、そのせめぎ合いで意味が生み出されると、鷲田は言う。
<わたし>はだれかという問いは、したがって、わたしの自己理解のなかにあるのではなく、他者がじぶんを理解するそのしかたのなかにあるのでもなく、その二つが交錯し、せめぎあうその現場にこそあるといわねばならない。
他者との関係のなかで編まれていくこのような<わたし>のストーリーが、仕事のよろこびに欠かすことのできない達成感というものを裏打ちしているのだし、また仕事がたんに必要に迫られておこなうものである以上に、それ自体において楽しいとのだという感情をはぐくみもするものである。
こうした論点を踏まえて、鷲田は「ホモ・ヴィアトール(旅する人間)」という概念を紹介する。他者との関係を次々に網変えながら、旅をしていくこと。それが人が人らしく生きるための鍵なのだと鷲田は言う。
筒井康隆の『旅のラゴス』も、まさしくそのような物語であった。主人公ラゴスは、他者と関係を結び貢献しては、それが当たり前の習慣になる前にまだ旅に出て新たに関係を結ぶ。『ラゴスの旅』ではなく『旅のラゴス』というタイトルなのは、ラゴスという人間の本質が旅そのものにあるからだと僕は考えたが、それはそもそも人間というものの本質でもあったのかもしれない。
この本の結論は一言では言い表しにくい。ともかくとして僕たちは意味を求める。そして、意味とは他者との関係性の中で自分のアイデンティティを開いて更新していくプロセスの中にある、ということになるだろうか。
■まとめると…
「だからなに?」という感想が脳裏をよぎるかもしれない。僕はよぎった。いろんな労働に関する価値観を脱構築してくれたという実感はあるものの、その先には何らかの結論を下してくれるわけではなかった。
僕の言いたいことはいつも通りである。人間は労働とされる作業に強制されずとも取り組むだろうし、むしろその方が効率的であるという発想があって、その素朴な観点を阻害しているのが、労働vs余暇の二分論だと考えている。つまり、労働観と人間観を更新することで現在の非効率な経済システムを更新すべきだと考えている。
鷲田はそこまで僕の共鳴していたわけではないとはいえ、僕の理屈を補強してくれる材料をいくつも提供してくれた。1996年に書かれた本ということもあって、現時点の社会との齟齬も感じたわけだが、それでも十分役に立ったと感じる。
薄い本なので、労働を考えている人には、お勧めしてもいいのかもしれない。鷲田さんは革命家ではないが、哲学者だった。
1回でもサポートしてくれれば「ホモ・ネーモはワシが育てた」って言っていいよ!
