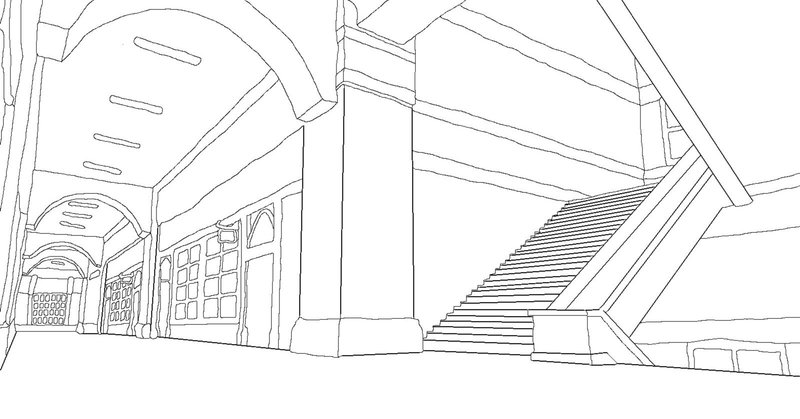
なんとなく vol.8
十月
文化祭真っ只中。
生徒の家族や友人、他校の生徒や近所の人たちで校内は賑やかだ。軽快な音楽が流れ、誰もがウキウキと足取り軽く、文化祭という名の通りみんなお祭り気分。
だがしかし、そのウキウキの中にドキドキも混じっている。なぜなら文化祭というのは出会いの場でもあるからだ!とほとんどの生徒が思っているに違いない。俺の隣にも確実にそう思っている奴がいる。
「ラストチャンスだあ!」
「がんばれ」
「おい凌。なんでそんなに乗り気じゃねえんだ。なっちゃんがいるとはいえお前だって今彼女いねえだろ」
「だって見てみろよ」
花壇の端っこに腰かけて、行きかう人たちを眺める。目の前に広がる光景がサバンナに見えるのは俺だけだろうか。
我が校の肉食動物たちと他校の肉食動物たち。男も女も、あわよくば臭がぷんぷんしている。暇さえあれば鏡を眺め、獲物探知センサーを張り巡らし、それに引っかかれば巧みに近づいていく。うまくいくいかないは別として、今日の肉食動物たちは血気盛んである。すっぽんでも食ってきたんだろうかと思ってしまうほどだ。
「あんなんに興味はない」
「お前はいいよな、モテるから」
「だからモテないって」
「凌、俺はさっき見てたぞ。チェックのスカートの女の子らと、セーラー服の女の子らに声掛けられてただろ」
「ああ……」見られてたのか。
「でもって冷たく袖にしただろ」
「冷たくはお前の想像だろ」
「なかなか可愛かったのに。わかってるのか、お前は俺のチャンスまでもを潰したんだぞ」
「知るか。俺の好みじゃなかったんだよ」
「なにを贅沢なことを言ってるんだ。そこから広がる輪があるだろが」
「べつに広げたくない」
そこに将太が便所から戻ってきた。
「どうしたの」
「将太、凌が俺の恋路の邪魔をする」
「は?」
「声を掛けてきた女の子を全員冷たくあしらいやがった」
「さっきよりひどくなってるぞ」
「凌ちゃんが断ったことがなんで裕ちゃんの恋路を邪魔することになんの」
「将太、よく言った」
「凌がその子たちと仲良くなれば俺にも輪が広がるだろうが」
「人任せはよくないよ」
「将太、よく言った」
「それに、今凌ちゃん元気ないからどっちにしろ無理だよ」
「なんで」
「先生がいないから」
そう、そうなのだ。文化祭がつまんないわけじゃない。この賑やかな感じはやっぱりわくわくするし、クラスのみんなで焼きそばを作って売るのも楽しい。だけどやっぱり、先生がこの場にいないことが寂しい。店番をしてるときも、先生来ないかな、なんてここに居もしない人を待ってしまう。花びらを千切って「来る、来ない、来る、来ない」と、「来る」で終わるまでやりたくなる。
自分でもやばいなって思ってるよ。大丈夫、ちゃんとわかってる。でもね、俺の脳みそは完全に龍河ウイルスに侵されちゃってるんだよ。望んで侵されてるんだけど。
ああ、先生は今なにしてるんだろう。デートだろうか。あのとんでもなく可愛い恋人とデートだろうか。いいなあ、先生も彼女さんも。
ごめんね、と思いながら、俺は後ろに咲く名前もわからない花を摘んだ。花びらがたくさんあるから占いにはもってこい。一枚一枚千切っていく。
来る、来ない、来る、来ない、来る、来ない、来る、来ない……。
「ねえ、裕ちゃん。凌ちゃんなにしてんの」
「こりゃバグったな」
「止めたほうがよくない?これやってる人はじめて見たよ」
来る、来ない、来る、来ない……うん?来る、来ない、く……る、こ……ない――。
「来るううううううう!」
めしべだけになった可哀想な花を天高く突き上げ、俺は声高らかに喜びの感情を爆発させた。
マジか、来るのか!どこだ、どこから来るんだ!
きょろきょろしてると、裕吾に腕を掴まれた。
「凌、俺が悪かった」
「凌ちゃん、一旦落ちつこ」
「なにが。俺は至って冷静だ」
「そう思ってる時点で冷静じゃないよ」
「凌、俺が悪かった」
「なにが。なんで謝る?」
「凌ちゃん、そろそろお店戻ろ。俺たちが当番する時間だよ」
おいおいなんなんだ、と思いながら、将太に手を引かれ、裕吾に背中を押され、俺は食欲そそるソースの香りが立ち上るテント内へと移動した。
肉、キャベツ、にんじんを鉄板で炒め、麺を入れてソースをかける。混ぜ合わせるように炒めたあと、透明のパックに詰めて出来上がり。
俺と裕吾は会計係、将太は炒め係。と言っても、三人並んでるから作業しててもぺちゃくちゃ喋ることに変わりはない。
「腹減ったな」
「フランクフルトがいい」
「終わったら行くか」
「二人は月曜なにすんの。振替で休みでしょ」
「うーん、勉強?」
「とくに予定はねえな。集まって勉強するか?」
「それもいいね」
「そうするか」
「お前らバイトいつまでやんの」
「俺は今月いっぱい。って言ってももうほとんど入れてないけど。おじちゃんとおばちゃんが入れるときだけでいいよって言ってくれてさ」
「俺も親からそう言われた。手伝えるときだけでいいよって」
「ってことは全員職なしか。となるとやっぱりマックだな」
「じゃあうち来る?裕ちゃんは遠くなっちゃうけど、昼飯はうちの親が作ってくれるよ」
「それはありがたいけど、いいの?」
「うん、うちの親がどういう人か知ってるでしょ。喜んで作っちゃうよ」
「たしかに。じゃあ甘えさせてもらおう」
「あ、その前におばさん見舞わない?」
「ああ、そうか。それいいな。行っても問題なさそうか?」
「うん、大丈夫。二人が会いたがってるって話したら喜んでたよ。裕吾とは初対面だからドキドキしちゃうって言ってた」
「俺もドキドキしちゃう」
「それじゃあ午前中お邪魔して、それからうちで勉強しよう」
「充実した一日にな――あっ!」
「うん?」
「あの可愛い子と目が合った」
「今誰もいないから行ってきていいぞ」
「勘違いだったら恥ずかしいじゃん」
「凌ちゃんを見てたかもしれないしね」
「将太、そういうこと言わないで」
「将太、俺を巻き込まないで」
「おい、こっちに来るぞ」
裕吾の声で前を向くと、他校の制服を着た女が二人、こっちに向かって歩いてきていた。裕吾はそわそわしはじめて、むやみやたらと手元にある小銭やらビニール袋やらをいじっている。俺らの前に二人が立った。
「焼きそば一つください」
「お箸二膳入れたほうがいいですか?」
「あ、はい。お願いします」
「四百円です」
俺が金を受け取り、裕吾が焼きそばのパックを袋に入れて手渡した。
終了。
「焼きそば食べたかっただけじゃん」
「将太、そういうこと言わないで」
あはは!と俺と将太が笑ってるところに、多田さんがやってきた。今度は俺がそわそわしてしまう。
「暇そうだね」と将太に話しかける多田さん。「さっきまでは忙しかったんだけどね」と答える将太。二人とも笑顔である。
うんうん、文化祭からはじまる恋ってのもいいじゃないか。でもなあ、将太は好きな人いるっていうし、多田さんの恋は実らず終わっちゃうのかなあ。多田さんいい子だし可愛いし、将太と並んでるとお似合いなんだけどなあ。恋って難しいなあ。
しみじみそう感じていると、食材を入れてあるクーラーボックスを覗いた多田さんが俺らに向かって言った。
「材料なくなりそうだから取ってくるね」
すると将太がすぐに言う。
「俺も行くよ。一人じゃ大変でしょ」
「大丈夫。重いものじゃないし」
俺はハッとした。
ここは俺の出番だろ!おせっかいかもしれないし、将太からしたら迷惑になるかもしんないけど、ここは黙っちゃいられない!
「けっこうかさばるし、重くなくても大変だよ。将太を使ってやってくれ」
「そうそう。多田さん、行こう」
「うん、ありがとう」
並んだ二人の背中を見送る。
少し距離をとって歩く感じがいいじゃないか。多田さんも嬉しそうだ。心なしか多田さんがふわふわ浮いているように見えるのは俺だけだろうか。
恋っていいなあ。ま、多田さんが将太を好きってのは俺が勝手に思ってるだけだけど。
十分ぐらいで将太と多田さんは笑顔を湛えたまま戻ってきた。やっぱり楽しそうだ。「おかえり」と二人を迎えた俺は、あたたかい目で二人を見守ることにした。
「ありがとう、助かった」
「こんくらい大したことじゃないよ。っていうか多田さん、ちゃんと見て回れてる?」
「うん、ちょこちょこ見てるよ。でもそろそろお腹減ってきた」
「焼きそば食べる?」
「いいかな、食べちゃって」
「いいよいいよ。実行委員の特権だよ」
ふふふ、と笑って、多田さんは作り置きの焼きそばを手に取ろうとした。それを将太が止める。
「作りたて食べなよ。作り置き減ってきたから今から作るし」
「ほんと?やった!」
ジュージュー音を立てながら、焼きそばが出来上がっていく。その間も、「手際いいね」だとか「油跳ねるから気を付けて」だとか「いい匂~い」だとか「どのくらい食べる?」だとか、微笑ましいやりとりが二人の間にある。
将太の気持ちは一旦置いといて、多田さん今嬉しいだろうなあ、楽しいだろうなあと、俺は孫を見守るお祖父ちゃんの気持ちで若い二人を眺めていた。そこに裕吾の声。
「なあ、凌」
「うん?」
「あの二人がきらきらしてるように見えるのは俺だけか」
「いや、裕吾だけじゃない」
「そうか、やっぱりそうか」
「見守ろうじゃないの、若い二人を」
「でも将太は好きな人いるんだよな?」
「想われてはじまる恋もあるんだよ」
「……なるほど」
「しばらくはそっとしておこうじゃないの」
裕吾がどっしり重いため息を吐き出した。
「ついに将太も……」
「裕吾、チャンスはまだまだある。大学に行けばもっとある」
「そうだな。うん、その通りだ!俺は諦めないぞ!」
「すいません、焼きそば一つくださーい」
「ああはいはい。四百円です」
店番してることを忘れてた。
当番の時間があと十分ぐらいで終わるころ、広場にいる幾人かの人たちから喜びと戸惑いを混ぜ合わせたような声が漏れてきて、誰もが同じ方向に視線を向けはじめた。なんだろうと首を伸ばし、その原因となってるものを見つけたとき、俺の目は釘付けになった。
え?えええええっ!
先生?なんで?休みって言ってたじゃん!なんでいんの?嘘だろ、マジかよ、花びら占い当たったああああああ!ありがとう!お花さんたち!
校内をざわつかせている龍河先生は、チャコールグレーのスラックスに白シャツを着て、首には黒いネクタイが緩められた状態でぶら下がっている。さらになんと、龍河先生の整った顔には眼鏡があった。
なんだあれ、あれは反則だろ。あんなんかっこよすぎだろ。いつもラフな格好してるくせに、なんで今日はそんな格好なの!なんで眼鏡掛けてんの!そんな先生知らないんですけど!かっこよすぎてどうしたらいいかわかんないんですけど!
龍河先生は周りの反応など気にも留めず、足早に校舎へと向かっている。誰もが龍河先生に道を譲るようにさささあっと退いていき、肉食動物たちはもちろん、すれ違った人すべてが龍河先生を振り返ってその足を止めてしまう。
ああ、バラが見える。先生が通った道にバラが咲き乱れている。今日はいつも以上にきらきらと輝きを撒き散らしている。それとも今見た先生の姿は幻なんだろうか。会いたい気持ちが強すぎて俺に幻を見せたんだろうか。だってあんなにかっこいい先生、現実なわけがない。ついに幻覚を見るようになってしまったんだな、俺は。
「凌ちゃん!」と背中を叩かれて目が覚めた。
「なに?」
「先生戻ってきた!早く行っておいで!」
将太に言われて、頭で考えるより先に身体が動き出していた。人混みをすり抜けてバラの花びらを追いかける。校門を出たところでやっと追いついた。
「先生!」
車のドアノブに手を掛けた龍河先生が俺を見た。え?車?と驚きながら龍河先生に駆け寄る。車は詳しくないけど、たしかSUVというやつだ。黒みがかったオリーブ色のその車は少しレトロ感があって、お尻のほうが四角い形をしている。
先生、車もやっぱりおしゃれなんですね。なんて感心してる場合じゃない。
「どうした」
「どうしたって、先生がどうしたんですか」
「ああ、忘れ物取りに来た」
「そうなんですか」
「焼きそば売れてるか?」
「あ、はい。ぼちぼち」
「そうか。楽しめよ」
「はい」
俺の返事を聞くと、龍河先生はさっさと車に乗り込んでしまった。エンジンを掛けて、俺を見て小さく微笑んで、慣れた手つきでハンドルを操作して、走り去った。
車を運転する姿が好きって女の人が言ってるのをよく聞くけど、俺は今、それを全身で感じてます。これでもかってぐらい感じてます。女の人は間違ってなかった、その通りです。ものすんごいかっこいい。立ち尽くしちゃうぐらいかっこいい。
ああ、ネクタイなんかしちゃって、どこに行くんだろう。まさか、ご両親への挨拶か?ついに結婚か?いやいや、それはないな。結婚はまだまだ先っていうか、先生自身は結婚に興味なさそうだったもんな。でもだとしたら、どうしてネクタイなんて。ああ気になる。今すぐ先生と話したい。
我に力を!ばりに天を仰いでいたら、将太と裕吾がいつの間にか俺の隣にいた。
「先生と話せた?」
「うん、ちょびっとだけ」
「よかったな」
「うん、ありがとう。先生、車で来てたよ。かっこよくておしゃれな車で、颯爽と走り去っていったよ」
「それはまた……たまらんな」
「それにネクタイに眼鏡ってのもたまらないよね」
「でもあんな格好でどこ行くんだろうな」
「そう、そこなんだよ」
「気になるねえ」
「火曜だな」
うん、と将太と裕吾が力強く頷き、俺らの文化祭は幕を閉じた。
将太と裕吾の訪問を母さんはすごく喜んだ。将太は久しぶり、裕吾は初対面ということもあって、二人ともはじめはぎこちなかった。だけど将太と母さんは親子みたいなもんだし、裕吾は誰とでも仲良くなれる愉快な奴だ。あっという間にぎこちなさはなくなり、俺ら三人はいつもの調子でくだらない話をして、龍河先生の話をして、将来の話をして、またくだらない話をして、俺らの話を聞く母さんはずっと笑っていた。
昼前に母さんとこを出て、そのまま将太んちへ。俺と裕吾が揃って来ることがあんまりないからか、おじさんとおばさんは大歓迎ムード。たらふく食わせてもらい、学校の話、龍河先生の話、母さんの話、進路の話、お客さんそっちのけで俺らの話を聞いて笑って涙ぐんで、最後はやっぱり笑っていた。そのあとちゃんと三人で机を囲み、途中息抜きしながら勉強を――いや嘘、くだらない話と龍河先生の話をしてたらもう外は暗かった。夕飯食ってけ!と言うおじさんの言葉に甘えてまたたらふく食わせてもらい、充実した一日はお開きとなった。
そんな月曜日を経て、火曜日。
今日の龍河先生は、薄いモカ色のバンドカラーシャツに濃紺のチノパンを、相も変わらず完璧なバランスで着こなしている。そういえば、その形のシャツ前にも着てたな。ふむふむ、よし、俺も買おう。
それにしても、数日前のあの姿もかっこよかったけど、いつものラフな格好の先生もやっぱりかっこいいなあ。たとえぼろぼろに破れた服だろうと、きらきらした衣装だろうと、ガチガチの甲冑だろうと、なんでも着こなして、似合わないものなんてないんでしょうね。と数日前の目撃者全員がため息を零したに違いない。
龍河先生のわかりやすくて丁寧な授業は残念ながらあっという間に終わってしまい、次の授業の終わりを告げるチャイムがやっと鳴って、昼休み。
四限目が終わると自然と俺らは集まり、昼飯を食いに行くか買いに行くかがいつもの流れ。今日も後ろの席から裕吾が俺の席までやって来て、二人で将太の席に行こうとするも、俺と裕吾の足が止まった。
多田さんが将太になにか話しかけている。
なんの話かはわからないけど、やっぱり楽しそうだ。あんなに眩しい笑顔を向けられて、将太は気付かないんだろうか。俺だったら気付いてしまう。気付いてドキドキして、俺も好きかもって思っちゃう。将太自身に好きな人がいるから想われていることに気付けないんだろうか。ああもどかしい!
多田さんとの話を終えた将太が俺らのとこに駆けてくる。
「ごめんごめん」
「いや、大丈夫」
「多田さん、よかったのか?」
「なにが?」
「楽しそうに話してたから」
「そう?普通だけど」
「そうか」
「どうしたの?」
「いや、なんでもない。飯行こう」
この感じだと将太は気付いてないし、なんとも想ってないな。こうなったら多田さん、もう告っちまえ!と身勝手に思う俺であった。
そして待ちに待った放課後。
三人で龍河先生に会いに行くと、いつものごとく視聴覚室へ移動することになった。そしていつものごとく指定席とも言える席に腰かけてすぐ、ブーブーと振動音が鳴り、龍河先生がポケットに手を突っ込んだ。取り出したスマホは震え続けていて、あのときのような恐ろしい電話だろうかと俺らは身構えてしまう。
「悪い、出る」
「どうぞ」
「龍河です」
お、なんか違うぞ。
「先日はありがとうございました。はい、はい、そうですね、そのつもりです」
敬語である。俺はなぜかこういうときの先生が好きだ。
「はい、スケジュール通りで構いません、こちらもそれで動いてるので。はい、はい、はい、お願いします。ん?ああ、いえ、冴島には俺のほうから伝えておきます。わかりました、はい、こちらこそよろしくお願いします」
なんか、大人だなあ。当たり前なんだけど。
「はい、溝口さんにもよろしくお伝えください。はい、失礼します」
ああ、見惚れてしまう。
「悪い」
「いえいえ。音楽のほう忙しいんですか?」
「いや、まだそうでもねえかな。来年スムーズに動き出せるように準備してるだけで、まだのんびりしてるよ」
来年スムーズに動き出せるように、か。日本からいなくなるって言ってたもんな。どのくらい日本を離れるんだろう。いつ日本に帰ってくるんだろう。帰ってきたら会えるのかな。会ってくれるかな。俺に会いたいって思ってくれるかな。日本に帰ってきても――。
「凌」
少し叱るような口調で呼ばれてハッとする。
「はい」
「ぶっ飛ばすっつったよな」
あ、バレてる。
「違います!寂しいなって思っただけです!それ以外のことは思ってません!」
「うまく逃げたな」
「ところで先生」話を変えてやる。
「ん?」
「文化祭のとき、なんでネクタイしてたんですか?」
「しちゃいけねえのかよ」
「そういうことじゃないんですけど、珍しいなあと思って」
「学校での先生しか知らないから驚いちゃったんです」
「すげえかっこよかったっす」
「なんでネクタイしてたんですか」
「しつけえな」と龍河先生は笑う。「べつに大したことじゃねえよ。世話になってる人に呼ばれて、ちょっとした集まりに参加させられたってだけ。マシな格好してこいって言われたからそうしただけだ」
「なんだ、そうだったのか」
「なんだってなんだ」
「いや、もしかして彼女さんのご両親に挨拶とか、結婚とか……」
あっはは!と笑われた。
え、だってふつうそう思わない?思わないの?イケメンは思わないの?
「俺があんな格好で行ったら腰抜かすだろうな」
「え、もう相手のご両親と会われてるんですか?」
「ああ、もちろん」
「へえ。さっきの感じだと、彼女さんのご両親と仲いいんですか?」
「十年以上の付き合いだからな。可愛がってもらってるよ。俺もあいつの家族のことは、あいつを想うのと同じぐらい大切に想ってる」
またそうやってさらっと言っちゃうんだから。かっこよすぎるんだから!
ああ、いいなあ、羨ましいなあ。
「いいなあ、羨ましいなあ」
「ん?」
「凌ちゃん、心の声がダダ漏れだよ」
「はっ!すいません」
「でもそうやって想ってくれたら嬉しいっすよね。自分の家族もちゃんと大切に想ってくれるって、幸せだよなあ」
「一概にそうとは言えねえんじゃねえか?」
「どういうことですか」
「好きな相手の家族がどうしようもねえ人間ってこともあるからな。虐待してたり依存してたり、好きな相手が家族を大切に想えねえ事情があるなら、相手の家族を大切に想うことは難しいだろ」
「そっか」
「その分、その相手を大切に想えばいい」
「そうっすね。でも、まずそんな相手に出会えるのかなあ」
「今日は随分と弱気だな」
「文化祭でまったくなんもなかったから落ち込んでるんです」
「うるせえ。お前はいいよな、いっぱい声掛けられて、いっぱいすげなくあしらって」
「へえ」
「違いますよ先生、こいつの勝手な想像です」
「でも凌ちゃん、三、四人には声掛けられてたよね」
「へえ」
「違いますよ先生、いや、声掛けられたのはほんとですけど、すげなくあしらってもないし、みんなちょっと試しに声掛けてみたって感じでしたから」
「凌ちゃんモテるんです。俺と裕ちゃんとは違って」
「ふうん。なんか妬けるな」
「え?」今、なんて?
「将太、それはちょっと違うぞ」
「なにが?」
「お前だっていい感じじゃねえか」
おいいいっ!裕吾!ちょっと待て!今それ言うのか?見守ろうって話したじゃないか!
「は?」
「多田さんといい感じじゃねえか」
「はあ?」
「俺だけじゃない、凌もそう思ってるぞ」
「はあ?」
「いや、将太、なんて言うか、多田さんが将太に好意を抱いてるのかなあってちろっと思っただけだよ」
「なんでそうなるの。どこ見たらそうなるの」
「……どこからどう見ても」俺と裕吾の声が揃う。
「ええ?ないない、あるわけない」
「やっぱ気付いてないな、こいつは」
だと思いました、と小さく息を吐き、そういえばと思って龍河先生に補足する。
「多田さんて子がうちのクラスにいるんです。明るくて可愛くて、頑張り屋さんでいい子なんですよ」
「へえ」
こちらもやっぱり知らなかったようですね。名前覚えられてんの俺らだけなんじゃないかって、俺は本気で思ってる。
「裕ちゃん、もし万が一そうだったとしても言わないでよ。これから多田さんと接しづらくなるじゃん」
「俺は見守ろうって言ったんだよ?もう、なんで言っちゃうかなあ」
「我慢できませんでした。でも、多田さんいいと思うけどなあ。可愛いし、いい子だし、将太と並んでてお似合いだったし」
「…………」
「裕吾」
「無理に付き合えって言ってんじゃなくてさ、それも選択肢にあってもいいんじゃねえのかなって話」
「…………」
「想う人がいるんだろ」龍河先生がぽつりと言った。「裕吾の言うこともわからなくはねえが、人の想いってのはそんなに都合よく変えられねえよ。ちょっとしたきっかけで、たった一つの出会いで、それまでの想いが、ずっと想い続けてきた強い想いが変わっちまうってこともあるがな」
「……そっか、そうっすよね。将太、すまん」
「いいのいいの、気にしてないよ」
「いや、怒ったほうがいいぞ。こいつのせいで多田さんと喋りづらくなったんだから」
「それはたしかに」キッと裕吾を睨む。
「だってさあ、羨ましかったんだもん。俺だけ誰にも相手にされなくて」
「あわよくば臭がぷんぷんしてたからな、お前は」
「そりゃそうだろ!俺は卒業までに童貞を卒業したいんだ!」
「だったらあの逆ナンしてきた子でよかったじゃん」
「俺は心も身体も満たされたいんだよ」
「贅沢だな」
「……贅沢か」とちょっと思案してから顔を輝かせる。「わかった!」
「凌ちゃん、訊かなきゃダメ?」
「訊かなくても勝手に言うよ」
「卒業までにキスをしたい!あわよくば、童貞卒業!」
呆れるしかない。俺も将太もなにも言いたくなくてただ裕吾を見る。龍河先生は「なに言ってんだ?」と言いたげな顔に、小さな笑みを浮かべている。
「なんだその顔は。余裕があっていいよな、お前らは」
「どこが」
「将太は多田さんがいるだろ?好きとか関係なしに、しようと思えばできるじゃねえか」
「そんな最低な男じゃない」
「凌はいつでもできるだろ?」
「できないよ。誰とすんだよ」
「よりどりみどりじゃねえか」
「そういう誤解を生む発言はやめましょう」
「なっちゃんもいるし」
「なっちゃんは関係ないだろ。俺が勝手に好きだなあって想ってるだけ」
「ってことはもうできるじゃねえか」
「お前な――」
「誰?なっちゃんって」
龍河先生の声が静かに割って入った。
「うちのクラスの大石ななちゃんです。すげえ可愛いんすよ。凌の次の彼女です」
「ふうん」と俺を見つめながら、龍河先生はなにか言いたそうにする。
なんですかその目は。ちょっと、怖いんですけど。え、なに。
「裕ちゃん、まだ決まったわけじゃないよ。ほぼ決定だけど」
「おい、将太」
「ずりいなあ、凌は。モテモテだもんなあ。お前あれだろ、俺の知らないとこで実はちゅっちゅしてんだろ。お前に愛の告白をした子ととりあえずちゅっちゅするだけして、さっさとサヨナラしてんだろ」
「どんだけ悪い奴なんだよ俺は」
「お前だけキスしやがって」
「だからしてないって。しばらくしてないって」
「ほんとかよ?」
「ほんとだって。嘘ついてどうすんだよ」
「じゃあ凌は俺と同じなのか」
「そう言われるとなんか嫌だけど、そういうこと。お前と同じで、俺だってキスしたいんだよ」
「俺がしてやろうか」
……………………は?
えっと、少々お待ちください。
今の、先生の声だよな?将太も裕吾もぽかんとしてるな。そうだよね、その反応が正しいよね?
え?今、先生なんて言った?
「……は?」
「キスしたいなら俺がしてやるよ」
……は?は?はあああああああ?
この人は、な、なに、なにを言ってるんだ。なにを言っちゃってるんだこの人は。
「な、なに、言ってるんですか」
「ん?キスしてやろうかって言った」
ははあ~ん、これは俺の反応を見て楽しんでるだけだな。
「先生、さすがにその冗談は笑えませんよ」
「冗談じゃねえよ」
「え?」ええ?「またまたあ~」
冗談を受け流すような反応に龍河先生は少し首を傾げ、すっと立ち上がって俺に近寄ってきた。え、なに?と戸惑う俺に手を伸ばし、耳から頬のあたりに右手を添えると、身を屈めて、そのまま顔を近づけて、俺にキスをした。
ゆっくりと瞼を閉じた龍河先生の顔はとても美しく、思わず見惚れてしまう。唇が離れ、すぐそこに龍河先生の茶色がかった瞳があって、その瞳がわずかに微笑む。龍河先生は身体を起こすとすぐ横の机に尻を乗せ、俺の顔を覗き込むように身体を傾けた。
ふたたび、少々お待ちください。
三秒ほどですべてを思い出した俺は叫ぶしかない。
「えええええええええっっ!え?……え?えええええええええええええっ!」
「冗談じゃなかっただろ?」
「え、ちょ、な、ど、な、ちょ、は、ええええええええ?」
ちょっとさ、俺今、頭爆発してない?漫画とかでよく見る感じで爆発してない?だって、だって、俺、キスしたよ?先生とキスしたよ?しかも、可愛らしいちゅってやつじゃなくて、小鳥のキッスみたいなやつじゃなくて、あの、唇で唇を挟むような、ちょっと本気のやつだよ?しかも五秒ぐらいくっついてたよ?しかもしかも、なんか離れるときに余韻があったよ?いたずらでちゅってやつじゃないよ?ちょっと本気のやつだよ?
おいいいいっ!たつかわああああ!どういうことじゃあああああああ!
「……あの、先生」
「ん?」
「冗談にならないですし、俺男ですし、さすがにまずいんじゃ」
「なんで?男が男にキスしちゃいけねえって誰が決めた」
「そうなんですけど。もちろん、そこはご自由になんですけど……」
「ん?足りなかったか?もう一回してやろうか」
「なっ!に言ってるんですか!やめてください!もう十分です!」
「なんで。いいじゃん」
あららあらら、あの笑顔が見えますね。これはもう俺の反応を楽しむやつに変わりましたね。なんなんだこの人は。なにがしたいんだこの人は!
くそっ、転がされてる。コロコロコロコロ、コロコロコロコロ、やりたい放題だなこんちくしょう!
ああもうほら、将太と裕吾は魂抜けて時間が止まっちゃってるよ。お~い、帰ってこい!俺を助けてくれえ!
そう心の内で叫んでいる間にも、龍河先生は俺を弄んで楽しんでいる。
「ちょっと先生!ほんとに、もうやめてください!」
「そう言われるとしたくなる」
「えええ?ちょっと、ダメですってほんとに!先生恋人いるじゃないですか!それにもう一回しちゃったら俺、本気で好きになっちゃいますから!」
はうっ!しまった!
「ふうん」と笑顔満開。
「いや、違います。今のは言葉の綾というか、勢いというか、とにかくもう十分です!」
「本気で好きにさせたくなった」
「ええええええ?」
真剣みを帯びた目で言われ、俺はもうどうしていいのかわからない。
にやりと笑う龍河先生が恐ろしい。背もたれに目一杯背中をくっつけて身体をのけ反らせてみるが、逃げ場なし。それでも逃れようとがんばったけど頬に手が添えられちゃって、もうほんとに逃げ場なし。
横に倒した顔が近づいてきて唇が重なった。同じキス。だけど、さっきよりも長い。ようやく離れた唇は今にも触れ合いそうな距離で止まり、龍河先生は俺を瞳に映しながら低い声で訊いた。
「本気になった?」
「……はい」と言うしかない。
嬉しそうに頬を緩めて「よかった」と言う龍河先生。俺から離れてまた机に尻を乗せると、いたずら大成功!と言わんばかりの、満足げな笑みを俺に向けてきた。
マジで洒落にならない。俺をからかってるだけだってわかってるからまだなんとか持ちこたえてるけど……いや嘘、持ちこたえられてない。
だって無理だよそんなの~。こんなことされて平気でいられるわけないじゃないか~。これから事あるごとに思い出しちゃうよ~。その度に頬染めちゃうよ~。ばか~。あほ~。まぬけ~。おたんこなす~。
恨みを込めて睨んでみるけど、そんなのが通じるわけがない。龍河先生は何事もなかったかのような顔で首を傾げる。
「ん?怒った?」
ぷいっと下を向く。今は龍河先生の顔を長く直視できない。
「……怒ってはないですけど」
「けど?」
「……なんでもないです」
「なんだよ、言えよ。マジで怒ったんなら謝る」
「怒ってません」
「じゃあなに」
「…………て……す」
「ん?」
少しだけ俺に身体を寄せた龍河先生をいじけた顔で見上げる。
「……先生のことが好きすぎてやばいです」
俺の言葉を受け、龍河先生はいたずら大成功!じゃなくて、自然と湧き上がった満足げな笑みを浮かべた。
「可愛いなあ、凌は」
「じゃああんまりいじめないでください。今回のはマジで洒落にならないです」
「やだ。おかげで俺のこと本気で好きになってくれただろ?」
「こんなことしなくても大好きですよ」
「足りねえ」
「ええ?」
「俺とおんなじぐらい好きになってもらわなきゃ気に食わねえ。俺がどんだけ凌のこと好きかわかってねえだろ」
どふわばああああああんっ!
もう壊れるものがありません。俺自身が壊れるしかありません。なんてことを言うんだこの人は。俺をどうしたいんだ。
「せ、先生こそ、俺がどんだけ先生のこと好きなのか全然わかってないですよ」
「伝わんねえ。もっとくれ」
「恐怖を感じるかもしれませんよ?」
「構わねえよ。俺は好きな子のことはすげえ愛するし、好きな子にはすげえ愛されたいの」
「言いましたね?」
「ああ、言った」
どうしようかなって考えてたら、ふっと頭に浮かんだ。
「……じゃあ、母さんに会ってもらえますか?」
「ん?」
「先生の話をしたら、会ってみたいって。一度ちゃんとお礼を言いたいって」
無理を承知で言った。だから言ってすぐに視線を下げてしまった。でも、少しでも母さんの望みを叶えてあげたかった。
龍河先生の手が俺の頭に乗っかった。
「いつにする?」
まさかの答えに勢いよく顔を上げると、いつもの龍河先生が俺を見ていた。
「いつでも。先生の都合のいいときで大丈夫です」とは言ったものの、あっと思う。「でも、週末は父さんと姉ちゃんがいるから、平日のほうがゆっくりできると思うんですけど、先生仕事あるし、平日は難しいですよね」
「いや、いくらでも言いようはある」
「え、それは大丈夫なんですか?」
「校長に言えば問題ねえ」
「おお、さすが校長」
「中間終わって少し落ち着いたら伺わせてもらうよ」
「はい、ありがとうございます」
「だが凌」
「はい」
「こんなんじゃ全然足りねえ」
「え?」
「もう一回キスさせろ」
「えええ!ちょっと、無理です!」
あははは!と、今度はいたずら大成功!のやつ。
「冗談」
「手のひらで転がされてる……」
「可愛いなあ、凌は」
そう言って、龍河先生は俺の頬をつまむ。
ああ、俺は一体どこまで先生を好きになるんだろう。俺のほうが絶対好きなのにな。ああ、それにしても幸せだ。俺は今、生きとし生けるものすべてにありがとうと言いたい。
そういえば、自分のことに精一杯で将太と裕吾のことをすっかり忘れてた。でもごめん、今は二人を気にかける余裕がない。だって俺、先生とキスしちゃったんだもん。
……てへ。
土曜日、いつものマックにて。
龍河先生とキスした日から、将太と裕吾がうるさい。魂ぶっ飛んでたくせにいろいろ訊いてくるし言ってくる。はいはいうるさい、はいはいそうだね、と適当にあしらっていたが、ついに今日捕らえられ、こうしてマックで尋問と拷問を受けている。
「いいなあ、先生とちゅう」
「まさかちゅうするとはね」
「どうだったんだよ、先生とのちゅうは」
「先生とちゅうしてどうだった?」
「先生の唇もやっぱ最高だったか?」
「どんな感じなの、先生の唇は」
「っていうか、どんなちゅうだったんだよ」
「なんかさ、ちゅって感じじゃなかったよね」
「おい、俺に再現してみろ」
「ちゅううううって感じだったよね」
「おい、どのくらいのちゅううううなのか俺でやってみろ」
「いつもの戯れだと思ってたらほんとにちゅうするんだもんなあ」
「俺の勘違いじゃなきゃ二回してたよな?」
「してた。しかも二回目のほうが長かった。ちゅううううううううって感じ」
「おい、なんで二回したんだ?」
「先生すごい楽しそうだったし、嬉しそうだったよね」
「彼女いるのに、浮気だな」
「先生にとってはキスは挨拶みたいなもんなんじゃない?」
「海外での生活長かったみたいだしな」
「でもあれは挨拶って感じじゃなかったよね」
ポテトを一本口に入れようとしてる俺を、将太と裕吾が見る。
「なに」
「なにじゃねえよ。吐け」
「そうだよ、ずるいよ。自分だけ」
「うるさいな、ほっといてくれ」
「ほっとけるか!」
「だってちゅうだよ?」
「あのな、俺だってまだ混乱してんだよ。ふとした瞬間に思い出してやばいんだよ」
「その思い出すやつを俺らに話してくれって言ってんだよ」
「なんで話さなきゃなんないんだよ」
「からかいたいから」将太と裕吾の声が揃う。
「絶対言わない」
「そんなこと言うなよ~」
「言いたくない気持ちもわかるけど」
「そ、言いたくないの。俺の胸にしまっておきたいの」
「なんだよなんだよ~」
「裕ちゃん、諦めよ。しょうがないよ」
「そうしてくれ。俺のためにも」
裕吾は諦めのため息をつき、拗ねたように唇を尖らせた。
「そんなに知りたいならお前もしてもらえ」
「それは無理。死んじゃう」
「俺も無理」
「それにしても、先生って自由だよなあ」
「そうだね」
「凌にキスしたのだってさ、からかいもあるだろうけど、凌にキスしたいって純粋に思ったからしたんだろ?」
「そうだと思う」
「からかいしかないよ、あれは。俺の反応を楽しんでた」
「いくらからかいたいからってふつうキスはしねえよ」
「凌ちゃんに対する愛情があるよね、変な意味じゃなくて」
「男だろうと女だろうと、好きになった相手には自分の想いを隠さず伝えちゃうんだよなあ、先生って。それってすごくね?」
「すごい。俺だったら余計なこと考えちゃう」
たしかにって思う。からかうためのキスだったとしても、先生が俺に言った言葉に――。
――本気で好きにさせたくなった。
――本気になった?
――おかげで俺のこと本気で好きになってくれただろ?
――俺とおんなじぐらい好きになってもらわなきゃ気に食わねえ。俺がどんだけ凌のこと好きかわかってねえだろ。
――俺は好きな子のことはすげえ愛するし、好きな子にはすげえ愛されたいの。
嘘はなかった、と思う。あのキスだって、ちゃんと気持ちがこもってた。
うああああっ!思い出してしまった!
「凌ちゃんが思い出してる」
「しばらくは拷問だな」
「先生に好かれるってある意味大変だね」
「だな。でも、好かれた人は幸せだろうな」
「それは絶対だね」
「ほんとかっけえなあ!」
「非の打ち所がないって先生のためにある言葉だよ」
「夏休みにさ、先生と凌のバイト先行ったじゃん」
「うん」
「あんとき先生が言ってたこと、忘れらんねえんだよな」
――自分に正直になんなきゃなんもはじまんねえなとは思ってる。
――自分の欲を満たすためだけに、自分を偽ることほどみっともねえことはねえよ。
――自分に嘘つくってことは、周りの人間にも嘘ついてるってことになる。
――たとえ自分の本当が周りに笑われようが蔑まれようが、俺は自分に嘘はつきたくねえ。なりたい自分になるためには、まずは自分が自分自身を受け入れなきゃはじまんねえだろ。
「先生はちゃんとそれができてるんだよな」
「……うん」
「自分に素直になるって意外とできねえじゃん。それができるってマジでかっこいいよ。他人にどう思われようが自分には絶対嘘つかない感じ、マジでかっこいい。俺もそういう人間になりたいし、ならなきゃなって思う」
将太が裕吾をじっと見つめて、つと視線を下げた。視線を下げたまま「そうだね、すごいよね」と呟いた声に自嘲するような響きがあり、俺は過去から戻って思わず将太の顔を覗き込んでしまう。
まただ。最近ちょこちょこ見せるこの感じ。
「どうした?」
「うん?」
「急に元気がなくなった。それに、最近よくそんな顔するからさ。なんかしんどい?」
「ううん、なんもないよ。なんか自分が情けなくなっちゃって。先生がすごすぎて」
将太のこの感じはまだダメなやつだな。もう少し、かな。
「そっか」
「将太、気にすんな。俺のほうが落ち込んでる!」
「そうだよ将太。裕吾を見れば自分はまだましだって思えるぞ」
「それはどういう意味かな、凌君」
「そのまんまの意味だ」
あはは!と笑う将太の表情は、やっぱりどこか硬かった。
中間テストが終わり、答案用紙も全教科返ってきて数日が経った。
将太、裕吾、俺の中で、だいたい俺が一番早く登校して教室に入る。その少しあとに将太、もう少しあとに裕吾がやってくる。将太とは同じ駅なんだから一緒に来ればいいじゃん、って思われるが、朝は自分のペースで行動したい俺なのだ。将太もそれをわかっているから、駅で鉢合わせしない限りは俺を放っといてくれる。
この日も俺が一番乗りで登校し、案の定、その少しあとに将太が教室に入ってきて「おはよう」と挨拶を交わした。いつもならそのまま自分の席に行くはずの将太が、俺の席まで足早に近づいてくる。その顔には最近よく見せる硬い表情が貼り付いていて、俺は少しだけ身構えてしまう。
「凌ちゃん、今日なんか予定ある?」
「いや、なんも」
「話したいことがあるんだ」
ついにきた。深刻な顔する将太には申し訳ないが、俺は少しだけほっとした。
「うん、わかった」
「できれば、先生にも聞いてもらいたいんだけど」
「じゃあ放課後お邪魔しよう。裕吾もそろそろ来るだろうし――」
「裕ちゃんには言わないでほしいんだ」
「え?」
「裕ちゃんを仲間外れにするつもりはないんだけど……」
表情の硬さといい、縋るような声といい、将太から切羽詰まった感じが伝わってくる。幼馴染みの俺から見ても、将太は裕吾に心底気を許してるし、今までも裕吾に隠し事なんてしたことない。だからこのお願いにはなにか切実な理由があるんだろう。俺は安心させるように将太の肩を叩いた。
「わかった。なんとかして裕吾には一人で帰ってもらおう。うまい手考えとくよ」
「うん、ありがとう」
少しだけ表情を和らげ、将太は自分の席に戻っていった。
将太の話がなんなのか、どうして裕吾には聞かせられないのか。気になるけど考えたってわかるはずもないし、放課後になればわかる。それよりも裕吾を納得させる理由を考えないと。こりゃ厄介だ。
あれやこれやと考えてみたものの結局ありきたりな理由しか思い浮かばず、二限目の休み時間に「二組の水口に誘われたから帰り行ってくる」と、暗に今日は一緒に帰らないぞと伝えてみる。そして昼休みに「将太今日図書館行くんだろ?」と合図を送り、合図を受け取った将太は「そう、放課後寄ろうと思って」と、これも暗に先に帰ってねと伝えてみる。こういう勘は鋭いようで、裕吾は「なんだ、俺を一人ぽっちで帰らせるつもりか」と拗ねたが、用があるなら仕方がねえと諦めてくれて、なんとか誤魔化し成功。
そして放課後。
裕吾とは教室で別れ、将太とは英語準備室の前で待ち合わせた。将太と二人で龍河先生を訪れるというのも奇妙な感じだったけど、あんな顔をするほどの事情があるようだし、少しでも将太の力になってやりたい。
ドアから顔を覗かせた俺と将太を見て、龍河先生は「裕吾は?」と訊いた。
「ちょっといろいろと事情がありまして」
ちらっと龍河先生の視線が将太に向く。なにかを察したのだろうか、龍河先生は「あそう」と言って手元にあるマグカップを持って立ち上がり、部屋の隅でコーヒーを淹れてから廊下に出てきた。三人で視聴覚室に向かう。
「そういえば先生、今さらですけど、ほかの先生って準備室使ってないんですか?いつもいないですけど、まさか嫌われてるんですか?」
軽く尻を蹴られる。
「部活受け持ってんだよ。お前らが来るときにたまたまいねえだけだ」
「そうなんですか、よかったです」
心から安堵して言うと、龍河先生は頬を緩めて歩きながらコーヒーを一口啜った。
三人がいつもの席に腰かける。一人いないことにやっぱり違和感を覚えながら、どうしたもんかと考える。将太のタイミングがあるだろうし、かと言って言い出しづらい雰囲気になっちゃうのもあれだし、でも沈黙ってのも息苦しいし、さて、困った。
将太を窺うと、相変わらず硬い表情のまま視線を落としている。どんなことなのかはまったく想像つかないけど、将太が今覚悟を決めようとしているのは伝わってきて、だから俺はもう少しだけ将太を見守ることにした。そうなると沈黙が視聴覚室を覆ってしまう。将太が唾を飲み込むのを何度か見て、口を開きかけては閉じるのを見て、そろそろ俺からなんか言ったほうがいいかなと思っていると、龍河先生がふっと小さく笑った。バカにするような笑いじゃなく、労わるようなあったかい笑い。
「将太、どうした?」
その声に、将太は顔を上げた。その目が真っ赤になっていて俺はハッとする。膝に置いた両手は強く拳を握り、骨が白く浮き出すほどだ。
……将太?
「決心しても決意が揺らぐこともある。将太の心がまだ話せねえと言うなら、その心を捻じ曲げる必要はねえよ」
首を振る将太。その痛々しいとも感じる姿に、俺は自分を殴りたくなった。
こんなになるまでどうして俺は気付かなかったんだ。将太がこんなに苦しんでたのに、俺は今までなにやってんだ。
ごくりともう一度、唾を喉に押しやってから顔を上げた将太は、龍河先生を見て、俺を見た。俺は見つめ返すことしかできない。
「……俺」唇を震わせ、息を吸う。「俺、裕ちゃんのことが好きなんだ」
将太が口にした言葉の意味を考えるが、よく意味が分からない。
「……うん?」
「友達としてはもちろんだけど、それだけじゃなくて、みんなが女の子に抱くような、恋愛感情がある。そういう意味で、裕ちゃんのことが好きなんだ」
また将太の喉が動き、覚悟を決めるように大きく息を吸った。
「俺はゲイなんだ」
俺を見つめる将太の瞳を、俺は固まって見つめる。
ちょっと待て。裕吾のことが好き?
うん?うんんんんんん?
おいおいおいおい!
「凌ちゃんが引くの――」
「ちょっと待て」将太に手のひらを見せて口を閉ざさせる。「……なんで俺じゃないの?」
今度は将太が俺の瞳を見つめたまま固まっている。
「……は?」
「いや、だってここは俺だろ!幼稚園ときから一緒にいんだよ?なのになんで裕吾なんだよ!おかしいだろ!」
「え?」
ぽかんとする将太。そこに「あっはははは!」と可笑しそうに明るく笑う龍河先生の声が響いた。
「将太、不安に思う必要どこにもなかったな」
龍河先生にそう言われた将太は気が抜けた顔で笑い、「はい」と頷いた。顔の強張りが取れ、代わりに心底安堵した表情がそこにはある。いつもの将太が戻ってきた。
「うん?どういうことですか?」
「裕吾のことを好きだって伝えたら、それが恋愛感情だって伝えたら、凌にどう思われるのか将太は不安だったんだよ」
「だってふつう驚くし、人によっては気味悪がるでしょ。男が男を好きになるなんて。なのに、なんで俺じゃないのって返ってくるから」
「はあ?まあ、そりゃあ驚いたけど、将太が誰を好きになるかは将太が決めることだろ。男だろうと女だろうとそんなの関係ないし、それを周りがとやかく言うのはおかしいし、いいじゃんべつに、男を好きになったって。え、ダメなの?」
「ダメじゃねえよ。なんもおかしくねえ。ただ、偏見を持つ人間がいるのはたしかだ。だから将太は今まで言えなかったんだろうし、ダチである凌に距離を置かれたらどうしようかと不安だったんだよ。将太の気持ちもわかってやれ」
思い詰めた表情と、真っ赤な目と、強く握った拳と、震える声。
「……そうか、そうですよね。俺がもしそういう偏見持ってたらって思うと、そりゃ不安ですよね」
将太に目を向ければ、不安な想いを思い出したからなのか、安堵からなのか、うっすら涙を浮かべている。ちゃんと俺の想いが伝わるよう、身体ごと将太に向き直った。
「将太、話してくれてありがとう。でも将太、俺は将太をおかしいなんてこれっぽっちも思わないよ。そりゃあ、なんで俺じゃないのとは思ったけど、でも将太は将太じゃん。裕吾を好きな将太も、うまい飯屋の息子の将太も、俺の友達の将太も、全部将太じゃん。だからもう、不安に思わなくていいよ」
ぷしゅっと空気が抜けるような音がして、それは将太が堪えていたものを吐き出した音で、将太は顔を覆って泣き出した。
「俺、ずっと怖くて。ちっちゃい頃から、自分は周りの男の子と違うって、なんとなく感じてて、そのなんとなくがはっきりわかったとき、それが変な目で見られる、おかしいって思われることなんだってわかって、ずっと怖かった。バレたら、みんな離れてっちゃうんじゃ、ないかって。凌ちゃんも、凌ちゃんの俺を見る目が、変わっちゃったらどうしようって。でも、苦しかった。大切な人に、ほんとの自分を隠し続けて、嘘ついて、それが苦しくて……ずっと言いたかったんだ。先生が、飲み屋で言ってたことが、すごく胸に響いて、自分がすごく恥ずかしくなって、だから――」
「将太」
将太が顔を上げて俺を見るのを待つ。涙で濡れた真っ赤な目が俺を見た。
「もう大丈夫。俺が本当の将太を知ってる。将太が教えてくれた。だからもう大丈夫」
顔を歪めて将太は大きく一つ頷き、「ありがとう」と震えた声で言ってくれた。俺はほっと胸を撫で下ろす。
あんなに深刻な顔して何事かと思ったけど、将太にとっては深刻なことだったけど、病気とか、命に関わるようなことじゃなくてほんとによかった。
手のひらと手の甲で涙を拭った将太は、龍河先生に頭を下げた。
「先生、ありがとうございました。先生にも聞いてほしかったんです。俺が決心できたのは、先生のおかげだから。それに、これは俺の勝手な願望ですけど、先生ならこんな俺を否定しないでくれると思ったんです。受け止めてくれて、ありがとうございました」
「礼を言われるようなことはしてねえが、俺も凌とまったく同じ想いだ。自分を恥じる必要なんてねえ。むしろ誇るべきだ。将太は今、自分で自分を受け入れて、自分を認めることができた。誰にでもできることじゃねえよ。俺は将太を尊敬する」
「……ありがとうございます」
将太はぐいっと涙を拭い、もう一度頭を下げた。
俺はなんだかすっきりして嬉しくて、にこにこ将太に話しかける。
「たしかにこれは裕吾にいられちゃあ困るな。俺と先生の前で告ることになっちゃうもんね」
「うん」
「好きなら言えばいいだろ」
「え?いや、それにはまた別の決心が必要です」
「なんで」
「先生、先生と違って将太は初心なんです」
「あ?」と睨まれる。「俺だって初心だよ」
「どこがですか!初心な人はからかってキスなんてできないですよ!」
「からかってねえよ。凌とキスしたかったからキスしただけ。なに、俺の本気のキス伝わってねえの?もっと本気で伝えてやろうか?」
「いいいいえっ!じゅうううううううぶん、伝わってます!」
「凌は嘘が下手だな」
「ええ?」
「まだ足りねえって顔に書いてある」
「書いてません」
あははは!と将太の明るい笑い声が俺と龍河先生の耳に届く。その笑い声は俺を、きっと龍河先生のことも明るい気持ちにさせてくれた。
将太はいつもそうだ。俺と裕吾が言い合いしてると間に入って和ませてくれて、将太が笑えば俺らも笑ってしまう。思いやりがあって優しくて、将太がそこにいるだけで不思議と柔らかい雰囲気に包まれる。もしこれから先、そんな将太をバカにして傷つけるような奴がいたら、俺は絶対にそいつを許さない。
「明日からどんな顔すればいいかわかんないなあ」
「え、ふつうにしててよ」
「俺だけが知ってるって、なんかそわそわしちゃうじゃん」
「堪えてよ」
「うーん、やっぱ言っちゃえば?」
「そんな軽いノリで言わないで」
「裕吾なら大丈夫だよ。もし将太の気持ちに応えられないとしても、あいつは変わんないよ」
「それはわかってる。でもそういう問題じゃないんだよ。好きだって伝えるのってとんでもなく緊張するんだから。凌ちゃんは伝えられるばっかり――」
急に言葉を切り、将太はなにかを思い出したような、思い出すような表情を浮かべている。
「うん?」
「そんなことないか。凌ちゃんはちょっとズレてるから」
「どこが。なにが」
「先生、聞いてください」
「ん?」
「中三のときなんですけど、俺たち部活終わってコートの隅で――」
「しょーーーた!」
「凌、うるせえ。で?」
口を噤むしかない。
あああああ、恥ずかしい。あああああ、やめてくれ。
将太が嬉しそうに楽しそうに口を開いた。
「部活終わってコートの隅で休憩してたんです。そんとき凌ちゃん陸上部の子が好きだったんですけど、蒼野さんっていうすごい可愛い子で、すごい明るい子で――」
「将太!余計なこと言わ――」
「凌、黙れ」
「うううう」
「それで?」
「とにかく蒼野さんは外見も性格も凌ちゃんの好みどんぴしゃだったんです。実際すごい気が合って仲良かったですし。で、その蒼野さんが休憩してる俺たちのそばに偶然いて、そしたら凌ちゃんいきなり立ち上がって、急にどうしたんだろうって思ったら、『俺蒼ちゃんのこと好きだ』って告白したんです」
「へえ」とあの笑顔で俺を見る。
ああ、なんて楽しそうなんだろう。俺は全然楽しくないけど。
「でもさすがは凌ちゃんで、OK貰ってました」
「へえ」とあの笑顔がさらに広がる。
将太、やめてくれ。俺の若気の至りを堂々と話さないでくれ。
「そのあとで『なんで今?』って訊いたら、『なんとなく』って。俺はそんときに凌ちゃんは只者じゃないなって確信しました」
「へえ」と満面の笑み。
「いや、俺も若かったんです。今言えるなあって思ったら勝手に身体が」
「凌のその感じもわからなくはねえが、やるなあ、凌」
「え、わかるんですか?」きょとんと将太が訊く。
「どっちかと言うと俺は凌の感じに近いな」
「もしかしてそれがモテる男のやり方なんですか?」
「先生はそうだけど、俺は違うよ」と釘を刺してから、気になったことを訊く。「先生は彼女さんにどうやって伝えたんですか?」
「好きだって」
「どういう状況で」
「ダチ何人かで集まってるときに、笑ってるあいつ見てたら言いたくなって言った」
「同じ!」目を見開く将太。
「同じじゃないよ将太。かっこよさが全然違うから」
「やっぱりそれがモテる男のやり方か」
「伝えたいときに伝えるのが一番伝わるからな」
「なるほど……」
「将太にもあるよ。伝えなきゃってときが」
「……そうですね。もしそういうときが来たら、迷わず伝えます」
龍河先生は将太を励ますように笑いかけ、冷めてしまったコーヒーを口に含んだ。
「ところで将太。俺の質問に答えてないぞ」
「なんか訊かれたっけ?」
「なんで俺じゃないんだ」
「そこ気になる?」
「気になるだろ。将太と俺は幼稚園からだぞ?あいつはたったの二年!」
「年月の長さじゃないじゃん、こういうのは」
「そうだけどさ~。えええ、俺、裕吾の負けたの?」
「勝ち負けじゃないって。凌ちゃんのことも大好きだよ」
「わかってるけど、なんか悔しいなあ」
「正直言うと、惹かれてた時期はあったよ」
「お、マジか」
「でもなんて言うのかな、べつに自分を下げて言うつもりはないんだけど、凌ちゃんと一緒にいたら、なんか自分にはもったいない人だなって思ったんだよね。凌ちゃんとはそういう関係じゃなくて、友達としてずっと、一生一緒にいたいなって」
「将太……」
「裕ちゃんとも友達として一生一緒にいたいって思うけど、なんだろう、裕ちゃんってバカでしょ、いい意味で。あの底抜けにバカな感じが気安いっていうか、安心っていうか、なんか落ち着くんだよね。あ、凌ちゃんと一緒にいるときも同じ感覚はあるよ。ただ、裕ちゃんの場合はそこに……うーん、なんて言うの?」
「将太の言いたいことわかるよ。まあでも、ってことはある意味俺のほうが褒められてるな。もったいないだもん」
「そういうことになるのかな?」
「そういうことにしといて。なんか寂しいから」
「ふふ、わかった」
「でもほら、将太が好きな人いるって教えてくれたとき、俺てっきりマジで先生のことかと思った。俺らがどうこうできるような人じゃないって言うし、好きってだけでいいとか言うし」
「俺も裕吾に負けたのか」
「違います先生、それは断固違います。先生は畏れ多くてそんなこと、神様に恋するようなもんですよ」
「じゃあ凌より上だな」
「もちろんです」
「将太くーん。即答しないで~」
「あはは!うそうそ、みんな同じぐらい大好きだよ。優劣なんてない。凌ちゃんも裕ちゃんも、先生も同じぐらい大切に想ってるよ」
「なんか照れるなあ」
「でも凌ちゃんの一番は先生だけどね」
「なんでそこ突っかかんの。俺もみんな同じぐらい大好きだよ」
「なんだよ、同じかよ」
「ええ?」なんだこの挟み撃ちは。
「大丈夫です、先生。これは嘘ですから」
「おい、なんでだよ」
「だって先生、文化祭のときの凌ちゃんの元気のなさと言ったらもう、ひどかったんですよ」
「しょーーーた!」
「凌、うるせえ」
すいません。でも照れくさいじゃないか。
「先生に会いたすぎて、花びら千切って『来る、来ない』ってやってましたから。ついにイカれたと思いました」
「へえ」
ほらまたあの笑顔の登場じゃん。楽しそうに俺のこと見てんじゃん。
「先生見つけたときの凌ちゃんの顔見せてあげたかったです。この世の終わりかってぐらい沈んでたのに、一瞬にして生命が漲りましたから」
「へえ」
ほらほら、どんどん広がってくよ。もう止めないと。
「将太、それは言い過ぎだろ。たしかに会いたいなあとは思ってたし、『来る来ない』もやったけど、そこまでの浮き沈みはなかったよ」
「なんだよ、ねえのかよ」
「いえ先生、ありました」
「なんなんだよさっきから二人して!二対一は卑怯だぞ!」
「凌ちゃんにとって先生は神様じゃないもんね。ただの特別な人だから、そりゃ恋もしちゃうよ」
「いや、うん、特別ってのは間違ってないけど、べつに恋してるってわけじゃ――」
「なに、俺に恋してねえの?」
はうっ!しまった!
そろ~り龍河先生に目を向けると、不満げな顔で頬杖ついて、俺をロックオンしていた。
「え?いやあ、その~」
将太~!と睨むと、将太は楽しそうににこにこしてる。
くそっ、こいつも楽しんでいやがる。
「俺のこと本気で好きになったんじゃねえの?」
「好きです!すっごい好きです!でも、それと恋とは違うじゃないですか」
「ふうん」とちょっと口を尖らせてる龍河先生が可愛い。
もう、そんな顔しないでください。可愛すぎて俺の好きが止まらなくなりますから。ああ、俺はあの唇にキスされたんだな。なんて恥ずかしいことを思い出してる場合じゃない。
「いや、その、恋みたいなもんです。だけど、将太が裕吾を好きっていうのとはまた違う好きであって、恋だけど恋じゃないんですよ」
「つまりは恋じゃねえってことだろ。本気になってねえじゃん」
「なってます!ぞっこんです!」
「つまんねえなあ」
「ええ?先生は俺にどうしてほしいんですか」
「惚れてほしい」
「俺さっきぞっこんだって言いましたよね?」
「凌の嘘はすぐわかんだよ」
「ええええ?いやでもだって、もしもですよ?もしも俺が本当に先生に惚れたとしても、俺の想いが実ることないじゃないですか。先生恋人いるし」
「だな」
「……先生、じゃあ俺が惚れる意味なくないですか?」
「俺が嬉しい」
「俺の気持ちは!」
「あははは!」
「あはははじゃないですよ。最近からかい方がえげつないですよ」
「凌が可愛いだもん」
だもん。くそっ、可愛い。かっこいい。どういうことだよ。ずるいよ、卑怯だよ。からかってるだけだってわかってるけど、惚れてないわけないじゃないか。本気で好きに決まってるじゃないか。恋愛感情とは違うけど、俺は龍河大という一人の人間に心底惚れてんだよ。ああもうこんちくしょう!弄びやがって!こうなったらマジのトーンで言ってみるか。そうだよ、たまには俺が弄んだっていいじゃないか!
行け、風丘凌!反撃開始だ!俺の雄姿を見てろよ将太!
俺は椅子をコロコロ転がして龍河先生の目の前まで持っていくと、お互いの膝がくっつくぐらい近寄って座った。将太は「なにしてんの?」って顔で成り行きを見守り、龍河先生は「ん?」って顔で俺を見た。その目をまっすぐ見返して、心を込める。
「先生、本気で伝えます。俺は、先生のことがほんとに大好きです。この感情がなんなのか、正直わかりません。恋に似てるけど、恋とは違うんです。こうやってからかわれながらも一緒にいたいって思うし、欲を言うなら、先生の時間が許す限り、毎日毎日ずっと一緒にいたいんです。先生のこともっと知りたいって思うし、俺のことももっと知ってもらいたいって思うし、俺は、先生を独占したい。ただそばにいてほしくて、そばにいたい。死ぬまでずっと、死んでもずっと、そばにいたい。そう想うぐらい、先生は俺にとって特別で、すごく大好きな人なんです」
嘘はない。全部ほんとのこと。だから伝わるはず。
「先生、大好きです」
よし、最後の仕上げた。がんばれ、奮い立て、風丘凌!
俺は龍河先生の両膝に両手を乗せて身を乗り出し、顔を近づけてキスをした。ちゅっじゃなくて、ちゅううぐらい。
唇を離し、目の前にある龍河先生の瞳を見つめて俺は訊いた。
「伝わりましたか?」
俺が見つめる瞳も、俺の瞳をじっと見つめて言った。
「足りねえ」
そう言うや否や、龍河先生は俺の後頭部を大きな手で包んで引き寄せて、俺の唇を塞いだ。
え?ええええええええっ!
ちょっとちょっと!ええええええええっ!
なんか、この前よりちょっと濃厚な気がするのは俺の気のせいだろうか。あれよ、ディープってことじゃなくて、なんか熱っぽい感じがするっていうか、なんか長いし、なんかマジで、俺がやばい。
ゆっくりと唇が離れて、少し茶色がかった瞳が俺を捕らえて、俺に聞こえるぐらいの低い声で囁いた。
「俺もすげえ好き」
どふわばああああああああああああああああんっっっ!
即死。
なにも考えられない。すいません、ちょと時間をください。
やっと解放された俺は龍河先生の膝の間に立ち、呆然と龍河先生を見下ろした。俺を見上げる龍河先生はそれはもう満足げに笑っておりますとも。
「もっと好きになった?」
「はい、もう止まりません」
ふふん、と嬉しそうに笑う龍河先生は、俺の手を取りそっと握った。その笑顔はあの笑顔じゃなくて、見惚れてしまうほどの優しい微笑み。気付くと俺は、同じようにそっと握り返していた。
「凌、すげえ嬉しかった。ありがとな」
「ほんとのことを言っただけです。伝わってよかった」
「すげえ伝わった」
「なので、もうえげつないからかいはやめてください」
「やだ」
「なんでですか。伝わったんじゃないんですか」
「凌が可愛いから」
「俺の勇気を返してください」
そこに窺うような、申し訳なさそうにする声が間に入った。
「あの、俺のこと忘れてません?」大ダメージを受けた様子の将太が言う。
はっ!俺の雄姿を見せるはずが!
「忘れてない!」嘘、忘れてた!
「まあいいけどさ、いちゃいちゃを見せられるこっちの身にもなってよね」
「いちゃいちゃって……」
「想い合ってるからしょうがねえよ、なあ?」
はっ!いつの間にか笑顔がすり替わってるじゃないか。今俺は防衛能力ゼロなんだからやめてくれ。
「……そう、ですね」
「なんだよ、冷てえな」
あ、いじけてる。可愛い。そんな風にされると俺のほっぺは緩んじゃう。
「いえ、ラブラブです」
「そういうことだ」
あ、嬉しそう。可愛い、かっこいい。ああ、たまらん。
なんて悶絶してたら、俺はもう一人忘れてる人を思い出してハッとした。
多田さん!なんてことだ、多田さん失恋しちゃったじゃないか。ああ、なんて切ない。ああ、なんて世知辛い。多田さん、どうか幸せになってくれ。男は将太だけじゃない!腐るほどいる!だから多田さん、泣かないで。俺は多田さんの幸せを願ってるよ。
今多田さんがどこにいるのか知らないが、テレパシーを送るように俺は天に向かって語りかけた。
「凌ちゃん、なにしてんの」
「メッセージを送ってる」
「誰に」
「泣いてる誰かに」
「凌ちゃんってたまにイカれるよね」
「俺今一生懸命だから」
「はいはい、邪魔してごめん」
届け!多田さん!
テレパシーをきっと成功させた俺と、なんだかご満悦な様子の龍河先生と、すっかり元通りになった将太。将太の顔は心なしか晴れ晴れしてるように見えて、俺も嬉しかった。
五時になって三人並んで帰る。龍河先生と駅で別れて、俺と将太は一緒に電車に揺られて、駅に着いて分かれ道までのんびり歩く。俺はまっすぐ、将太は左へ。「凌ちゃん」と将太が足を止めた。
「うん?」
「ありがとう」
「やめろよ、礼を言われることなんてなんもないだろ」
「ううん。俺は凌ちゃんにまた救われたから」
「また?」
「いつも助けてもらってる」
「それはお互い様。友達なんだから当たり前だろ」
「うん、そうだね」
「先生が言ってたみたいにさ、裕吾に伝えたくなったら余計なこと考えないで、まっすぐ伝えてやれよ」
「うん、そうする」
「またなんかあれば言って。話聞くことしかできないけど、俺は絶対に将太の味方だから」
「うん、わかった」
「じゃあまた明日な」
「うん、また明日」
お互い軽く手を上げて、家までの道のりを歩き出す。
将太の恋がどうなるのかなんてわからない。裕吾が応えてくれたら嬉しいなとも思うけど、裕吾には裕吾の想いがあるし、こればっかしは見守ることしかできない。
でも、どっちに転んだとしても俺らは変わらない。それだけは断言できる。
恋か、と思う。本気で誰かを好きになる。誰かを好きになったことはあるけど、本気でとなるとあるとは言えない。歳を重ねて、いつかそう想える人と出会えるだろうか。
もし出会えたとしても、先生に抱く想いを超えることはないんだろうなって、なんとなくそう思った。
≫≫ 十一月へつづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
