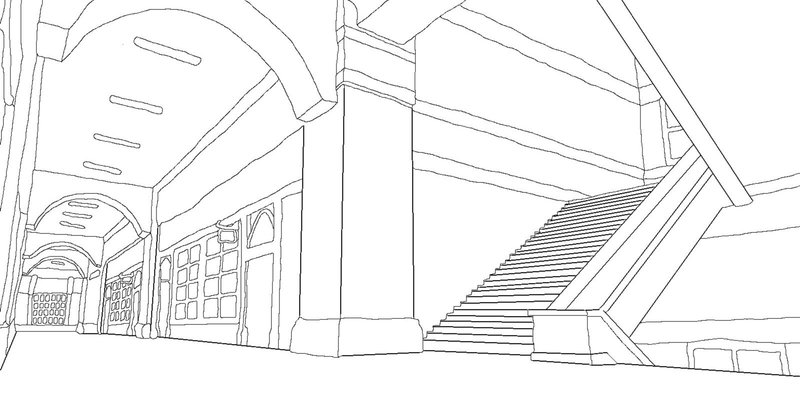
なんとなく vol.6
八月
八月十八日、夜六時三十分。
「うわ……」
「すげえ人だな」
「人酔いしそう」
ライブハウスの前は平日の夜にも拘らず、多くの人が集まり、自分の番号が呼ばれるのを今か今かと待っている。
はじめて訪れた街はすごく賑やかで、飲み屋、古着屋、コンビニ、雑貨屋、喫茶店、八百屋、色んな店が新旧問わず軒を連ね、歩いてるだけで楽しい場所だった。きょろきょろしながら約五分の道のりを歩き、道に迷うことなく無事ライブハウスまで辿り着いたのはいいものの、ライブハウス前に集まる人の多さに俺らは呆気に取られ、完全に尻込みしてしまっていた。
龍河先生からは「スタッフに言えば入れるようにしとくから」と言われているが、ライブハウスの前にいるスタッフさんは一人だけで、その人は整理番号を大声で叫んでいるから話しかけるのも気が引ける。将太と裕吾と話し合い、もう少し人が減ってからにしようという結論に達した俺らは、しばらくその場でライブハウスに入っていく人たちを眺めていた。誰も彼もが待ちわびたような顔をしていて、これから起こることを思って胸躍らせていることがひしひしと伝わってくる。
入口前に並ぶ人がほとんどいなくなり、俺らは入口に立つスタッフさんに声を掛けた。
「あの、龍河さんに誘ってもらって来たんですけど」
「ああ、はい。下の受付でお名前仰ってください」
「わかりました。ありがとうございます」
軽く頭を下げ、地下に伸びる階段を下りる。下りきったところに受付があり、そこにいたスタッフさんに同じように声を掛ける。
「あの、龍河さんに誘ってもらって来たんですけど」
「お名前よろしいですか?」
「風丘と渡真利と相沢です」
「ああ、はい」とスタッフさんの表情が明るくなる。「伺ってます。そこの扉からどうぞ。あとこちらワンドリンクチケットです」
「ありがとございます」
あああああ、緊張した。
そのスタッフさんにも軽く頭を下げ、ステッカーとサインで埋め尽くされた重い扉を開けた。
「おおお」と思わず声が漏れる。
人、人、人。教室二つ分ぐらいの広さに人が詰め込まれている。洋楽が流れるフロアは、人が蠢く音と囁く声と、隠し切れない興奮と熱気で、異様な空間に思えた。
圧倒されるばかりの俺らは、後ろから来た人と少しぶつかって我に返り、とにかく移動しようと人の合間を縫って前に進んだ。バーカウンターが見えてなんとか辿り着き、ドリンクチケットと飲み物を交換する。苦戦しながらさらに前に進むが、少し行ったところでこりゃ無理だと諦めた。
「すげえな」と呆れたように裕吾が言う。
「こんなに人気あるライブに誘ってくれたの?」と怯えるように将太が言う。
俺はもう呆然とするしかなくて、ただただステージのほうを眺めていた。すると裕吾が「こっち」と腕を掴んで俺の身体を引っ張った。どうやら誰かが移動して場所が空いたらしい。すいません、と思いながら身体を押し込み、三人で横に並ぶ。俺らが立つ場所は前方より少し高くなっているようで、さらに前に並んでいるのが女性だったからステージがよく見えた。ドラムが左後ろにセットされ、ベースが右後ろ、エレキギターが前方左右に置かれている。アンプなどの音響機材があちこちと置かれ、マイクスタンドが右前方に一本ある。
「ステージよく見えるね」
「裕吾ナイス」
「だろ、俺天才」
「今日だけは認めてあげよう」
「いつも認めてよ」
「今何時だろ」
「六時五十五分」
「あと五分か。なんかすげえ緊張してきた」
「俺も」
「俺たちが演奏するわけじゃないのにね」
「大丈夫かな、俺らの心臓もつかな」
「俺はもう今日は壊れるつもりで来たから」
「覚悟はできてる」
「そうだな。みんなでぶっ壊れよう」
ドキドキしながら七時を待つ。開演時間が近づくにつれ、周りの人たちもそわそわと落ち着きをなくしてきた。だけど七時を過ぎてもステージには誰も現れない。どうしたどうしたと一人焦るが、たぶん将太と裕吾もなんで?と思ってるだろうが、周りの人たちにそんな素振りはない。今か今かとただ待ちわびている。なるほど、これはふつうのことなのか、と思ったとき、フロアのライトがふっと消えた。それと同時に観客の蠢きが止まり、囁き合っていた声も消える。だがその静寂はすぐに歓声と拍手で打ち消された。照らされたステージに男の人が一人現れて、ドラムセットの後ろに座る。続いてもう一人、すぐに龍河先生ともう一人も現れた。
胸が鳴る。俺の心臓はもうはち切れそうだった。
白Tにカーキ色のハーフパンツを履き、いつもの落ち着き払った表情でステージに現れた龍河先生は、左前方に置かれたエレキギターを手に取って肩にかけた。エレキギターのネックに手を掛け、首をぐるっと回す。四人がそれぞれと視線を交わすと、龍河先生は不敵に小さく笑った。
それを合図に、フロアはまた静寂に包まれる。
心臓が暴れる。暴れまくってる。
そして、爆発した。
ステージ上の四人も、観客も、熱が一気に上がって、破裂した。
ドラムは流れるようにいくつもの音を生み出し、ベースは軽やかに重みのある音を刻み、エレキギターは力強くも美しい音を疾走させる。それらが重なり一つの音となって、俺らの感情も、俺らの思考も、俺らの欲望も、この空間に存在するすべてのものを吹っ飛ばす。音の衝撃が身体にぶつかって、放たれる熱が身体を覆って、俺は立ち尽くした。
これが龍河先生。これが龍河先生の音。
身体を揺らし、己が持つすべての力を使って音を奏でる。自分の魂をぶつけるように、それを音に変えて叫んでいる。その姿は美しくてかっこよかった。だけどなぜか胸が締め付けられて、俺は爪が食い込むほどに拳を強く握りしめていた。
いくつか曲が終わり、龍河先生が袖にいる誰かに目顔で合図する。その誰かがちらっと姿を見せると、龍河先生はその人と一言二言喋って、最後に可笑しそうに笑った。あれは親しい人にしか見せないやつだ、と思うのと同時に、フロアの至るところから喜びの声が上がる。
ここにもいるのか肉食動物たちが。先生、どこにいてもやっぱり狙われちゃいますね。
ステージの四人は水を飲んだり、チューニングしたりと、ちょっとした小休憩に入っている。龍河先生は水を飲みながらドラムの人となにやら言葉を交わしていて、その顔にも笑顔が浮かぶ。そうするとまた喜びの声。俺らの後ろにいる女の人も思わず出ちゃったって感じで、「ああ、かっこいい」と零していた。わかるわかる、と周りにいる全員が頷いたに違いない。
龍河先生たちは観客に向けてほとんど、いや、まったく喋らなかった。最初の数曲が終わったときに、右側にいるもう一人のエレキギターの人が「今日は来ていただいてありがとうございます。最後まで楽しんでってください」と、愛想笑いをするでもなく淡々と言ったきり喋ってない。あのマイクスタンドが可哀そうに思えてしまう。
そんなこんなで演奏は続き、また一曲が終わった。拍手が続く中、もう一人のエレキギターの人がマイクスタンドを引き寄せた。
「今日はありがとうございました」
またも淡々と言って、もうお役御免だよ、とでも言うようにマイクスタンドを遠ざけてエレキギターを持ち直す。二回しか使われなかったマイクスタンドが哀れに見えてしまう。
四人の表情がすっと変わり、龍河先生が弦を弾いて次の曲がはじまった。
エレキギターの音だけではじまった曲は静かにそっと流れ、心地よく耳に残る。そこにドラムとベースが重なり、さらに美しく音を紡いでいく。そのどこか物悲しいメロディは溶けていくように消えていき、ついに無音となった。
フロアが静まり返る。
静寂の数秒。
そして――。
ドラムの叩き付けた一音からすべてを破壊してしまうほどの音の衝撃。これまでの音とは真逆の、まるでなにかと戦っているような激しさ。四人の音がぶつかって弾けて、音の威力を上げていく。それに合わせて彼らの音はさらに強くなり、全力で、なりふりかまわず音を生む。暴力的とも言えるぐらいに、自らも叫びながら、自分たちの音を見えないなにかにぶつけていく。
断ち切るように音が消え、四人もステージから消えた。
雄叫びと歓声、はち切れんばかりの拍手が誰もいなくなったステージに送られる。その拍手は少しずつ形を成し、一定のリズムを作りだした。俺らもそれに合わせて手を叩く。どのくらいだろう、二、三分ぐらいだろうか。四人がまたステージに現れ、一定のリズムは拍手に変わって、フロアはまた指笛や歓声で満たされた。
もう一人のエレキギターの人が、脇に追いやったマイクスタンドに顔を近づける。
「今日はほんとにありがとうございました。また会いましょう」
ほんとに思ってますか?と訊きたくなるほど、声に感情がこもってない。
ファンだろうとなんだろうと、親しくない人には愛想を使わない感じ、さすが先生のお友達です。
最後の曲、エレキギターは二本ともアコースティックギターに変わった。二人はなにかに腰かけている。穏やかにはじまった曲は、途中強弱をつけながらも最後まで穏やかで、俺らを覆っていた熱をそっと冷ましてくれた。
曲が終わるとともに四人は観客に向けて一礼し、袖へと消えて行く。フロアにライトが灯って、ライブの終わりを告げた。
ライブ中、俺も将太も裕吾も、一言も喋れなかった。そんな余裕がなかった。目の前にある圧倒的なパワーを受け止めるのに精一杯で、次々に奏でられる音に夢中で、正直俺は、二人の存在を忘れてしまっていた。
学校での習慣が身に沁みついているのか、大渋滞になっている出口がある程度空くまで俺らはフロアに残り、出口が空いたところで出口へと歩き出した。
感じたことはたくさんあって、それを二人に伝えたいのに俺はまだ言葉が見つからない。将太も裕吾も同じなんだろう、無言のまま出口を通って階段を上る。外の空気に触れたとき、なんだか夢から覚めたような気分になった。
「すごかったね」ぽつりと将太が言う。
「すごかった」ぽつりと裕吾も言う。
俺はやっぱりまだ言葉が見つからない。そんな自分に戸惑ってるとスマホが震えて、画面を見ると龍河先生からだった。心臓が一気に跳ね上がり、慌てて出る。
「はい!」
『今どこいんの』
「えっと、ライブハウスの前です」
それに対する反応がなく、電話切れたかなと思って画面を見てもまだ通話中。なんだこれは、と将太と裕吾に困惑した目を向けたとき、背後から「凌」と名前を呼ばれた。振り向くと龍河先生がそこにいて、こっちに向かって歩いてくる。
突然の龍河先生登場に、出待ちなのか、それともただ偶然いただけなのか、その場にいた人たちから歓喜の声が漏れてざわざわと騒ぎだした。だけど迷いなく俺らのとこに歩いてくる龍河先生に話しかけられる猛者はおらず、明らかに肉食動物も混じっていたが、どうやら諦めて、龍河先生に呼び止められた俺らに羨望とも敵意ともとれる視線を送ってきた。
だんだんと近づいてくる龍河先生。その姿を目に映しながら、さっきからずっと俺の中にあるよくわからない感情がどんどん膨れ上がっていく。ごくりと唾を飲み込んだ。なんか言わなきゃと思うのにやっぱり言葉は出てこないし、会えて嬉しいから笑いたいのに笑えない。そんな俺を見て、龍河先生は首を傾げた。
「どうした?気分悪くなったか?」
少し俯き、首を振って否定する。喋らない俺に、将太と裕吾も心配するような目を向けている。
違う、喋りたいんだ。でも言葉が出ないんだ。なんかが込み上げてきて、それを呑み下さないと、みっともないことになりそうなんだ。
「どうした?」
俯く俺の顔を覗き込むようにして龍河先生の顔が近づく。その途端、勝手に涙が零れ落ちた。泣くつもりなんてなかったし、泣くようなこともなかったのに、なぜか涙が止まらない。ちょっとやそっとでは動じないはずの龍河先生がわずかに目を瞠り、ぽたぽた落ちる涙を見ている。涙の分だけ、声が戻った。
「すいません。なんか、勝手に」
慌てて涙を拭って顔を上げようとすると、その前に龍河先生の腕が伸びてきて、俺の後頭部を手のひらで包むとそのまま胸に抱き寄せた。え、と思うのと同時に、耳元で優しく笑う声。
「ありがとな」
え?ん?なにが?
それにしても、ライブ終わったばっかなのにいい匂いするなあ、Tシャツ乾いてるから着替えたのか。なんて呑気なことを考えてる場合じゃない。
こんなにくっついたら心臓の暴れ具合がバレてしまう。嬉しいけど、もうご勘弁を。ああでも、このままでもいたい。
身体がそっと離され、龍河先生は俺の顔をまた覗き込んだ。
「落ち着いたか?」
「……はい。すいません」いえ、心拍数が爆上がりです。
「裕吾、将太。ありがとな、来てくれて」
「いえ!あの、すっっっげえかっこよかったっす!」
「はい!あの、かっこよすぎてもうよくわかんないです!」
相当なダメージを食らってるはずの二人がしどろもどろに答える。龍河先生は少し呆れるようにして、嬉しそうに微笑んだ。
「気を付けて帰れよ」
「はい!」将太と裕吾の声が揃う。
訳わからず泣いたこと、急に抱きしめられたこと、それが恥ずかしかったのもある。でもまだやっぱりどうもうまく言葉が出ない俺は、こくんと頷いて返事した。
「凌」
呼ばれて顔を上げる。いつもならあの笑みがあるはずなのに、今は見惚れてしまうほどの優しい笑みがあった。龍河先生の腕がまた伸び、その手は頭じゃなくて、俺の頬にそっと触れる。
「またな」
返事をする間もなく、龍河先生はライブハウスに戻っていってしまった。
頬が熱い、いや、熱い視線を感じる。そう思って周りを見渡すと、肉食動物たちの光る目が俺を捕らえていた。喰われる前に逃げなければ、俺らはその本能に従ってその場からそそくさと立ち去った。
帰りの電車の中。一時間の道のりだから喋る時間はたっぷりある。
「いきなり泣くとは」
「びっくりしたね」
さっきからこればっか。
「うるさいな。俺だって驚いてんだよ」
俺は完全復活を果たしました。
「それにしてもさ……はあああ」
「なんだよ」
「俺も抱きしめられたい」
「あんなのドラマでしか見たことないよ」
「かっけえなあ」
「どこまでもかっこいいよね」
「先生たちの音楽もすげえかっこよかったし」
「だね。インストってちゃんと聴いたのはじめてだったけど、すごいかっこよかった」
「そりゃ凌も泣いちゃうよな」
「え?」
「感極まって泣いちゃったんでしょ?」
「……そうなのかな」
「え?違うの?」
「俺はてっきりそうだと思ったんだけど」
「いや、すごいかっこよかったし、感動したのはたしかなんだけど、なんで涙が出たのかはよくわかんない」
「ふうん」
「お前らの言う通りなのかもしんないけど、なんだろう、なんか少し違う気もする」
時間を置いて考えると少しずつ見えてくる。自分の中に湧き上がった感情がなんなのか、明確な答えはまだ見えないけど、ぼんやりと形ができてくる。
「先生たちの音楽はすごいかっこよかったし、かっこよすぎて鳥肌立ったし、俺は先生たちの音楽すごい好きだし、先生たちが演奏する姿に圧倒されたし、マジですごい感動した。だからそれもあるんだろうけど、なんか、先生たちの音を聴いてたら、先生たちの音楽に対する想いがこれでもかってぐらい伝わってきたんだ。好きなことをやれてる嬉しさとか楽しさだけじゃなくて、なんて言うんだろう、好きだから苦しいっていうか、なんかそういうのも伝わってきて、あのステージに立つ四人の覚悟みたいなのを感じたんだよね。生半可なもんじゃなくて、絶対的な覚悟みたいな」
自分の感情を整理しながらぽつぽつ続け、俺はそうか、と思う。
「だから、もちろん感極まってってのもあるけど、俺はあの人たちのそういう想いに心打たれたんだと思う。先生の全力の本気を目の当たりにして、嬉しかったんだと思う。あの時間、俺はすごい幸せだった」
一人で頷く俺を見て、将太がちょっと寂しそうな声で言った。
「凌ちゃんと先生が親しくなるの、わかるな」
「え?」
「ずっと思ってたんだよね。俺たち三人と先生で喋ること増えたけど、凌ちゃんと先生が話してるの見ると、ああ、やっぱ違うなって」
「俺もそれは感じてた」
「え、二人とも?でもそれはあれだろ、俺のほうが先生と一緒にいる時間が少し長いから」
「そういうんじゃねえんだよ。もし俺が先に先生と関わることになってたとしても、今と同じ感じになってたと思う」
「うん、そう思う。たぶんさ、凌ちゃんの感性が先生と合うんだろうね」
「……感性?」
「物事に対する考え方とか捉え方とかさ、価値観とはまた違う、モノへの想いが合うんだと思う。あと、凌ちゃんって自分の想ってることをちゃんと伝えるでしょ?」
「嘘?そんなことないけど」
「そんなことあるよ。自分がどう想ってるのか、自分の言葉でちゃんと伝えようとしてくれるからさ、聞いててすごいなって思うけど、すごく素直なんだよね、伝え方が。まっすぐっていうか」
「先生に対する気持ちもなんだかんだちゃんと伝えてるもんな。俺だったら照れちゃって誤魔化しちゃいそうなのに、凌は伝えようと努力してる」
「え、なに。そんなことないって。最近なんかおかしいよお前ら。どうしちゃったの」
「どうもしないよ。俺たちも想ってることはちゃんと伝えようって思ってるだけ」
「そうそう。さっきの話も俺感心しちゃったし。俺はただかっけえなあ、すげえなあって思うだけで、そこに先生たちの想いを感じようとはしなかったし、気付かなかった」
「先生はさ、凌ちゃんがそこまで想ってくれてることにあの一瞬で気付いたんだよ。だからああやって受け止めてくれたんだと思うよ。俺たちは感動して泣いてんだなって思うだけだけど、先生はちゃんと凌ちゃんのそういう想いに気付いてくれる。それもたぶん、感性が合うからなんだと思う。だから自然と二人は惹かれ合うんじゃないかな」
「惹かれ合うって……」なんか照れちゃう。「まあ、俺が先生のこと大好きなのはたしかだけど、先生の態度は俺ら三人なんも変わんないよ」
「目に見えることじゃねえんだって」
訳わかんないと眉をひそめた俺を見て、あははは!と将太が楽しげに笑う。
「凌ちゃんごめん。俺が言ったこと忘れていいよ。凌ちゃんは今まで通り先生と仲良くしてください。俺らはその恩恵に預かるから」
「ま、そういうこった」
「どういうことだよ」乱暴な締め方に笑ってしまう。「まあいいや、悪い意味じゃなさそうだし」
そう言った俺に将太は笑顔を向けて、その笑顔のまま前に向き直る。なにかを思い描くように、瞳を明るくして言った。
「楽しみだな、これからも」
「うん」と俺も笑顔で頷く。
「だな」と裕吾も笑顔で頷くが、すぐにため息を零した。「あ~あ」
「なんだよ」
「いいなあと思って」
「なにが」
「ああやって自分のやりたいことをちゃんと見つけられて、それに夢中になれて、それで飯が食っていけるって最高に幸せだよな。そりゃ大変なこともしんどいぐらいあるんだろうけど、それだって羨ましいって思っちまうよ。やりたいこともわかんなくて、ただなんとなく生きるよりかは」
「うん、なんとなく生きるのは楽かもしんないけど、つまんないもんな、そんな生き方。俺も見つけたいなあ、夢中になれること。それが仕事じゃなくてもさ、生きる糧になるようなもの」
「見つかるよきっと。俺らまだ十七だよ?八十で死ぬとしても、あと六十年近くも時間はあるんだから」
「それもそうだな」
「早く見つかるに越したことはないけど」
「あ~あ、やっぱすげえな、先生は」
「これから先生はどんな未来を生きるんだろうね」
将太の疑問に、俺と裕吾はちょっと考えて諦めた。
「俺らの想像をはるかに超えてくることだけはたしかだよ」
「だな」
「だね」
電車はガタゴト揺れて夜の街を走る。窓から見える夜の街は真っ暗だ。でもその中にもちゃんと灯りはあって、時折大きな灯りが暗闇を照らし出したりする。
未来に不安はあるけど怖くはない。俺には将太と裕吾のような最高の友達がいて、追いかけたい背中がある。それだけで今は十分だ。
夏休みがはじまってから今日まで、自分がなにをして過ごしてきたのか。
よく覚えていない。記憶に残っているのは、龍河先生のライブで大興奮したことと、将太と裕吾の三人で日帰り旅行的な遠出をして腹が痛くなるほど大笑いしたことぐらい。あとは勉強したり、将太と裕吾とその辺で集まったり。そんなほぼ単調な日々を過ごしていたら、あっという間に新学期まであと一週間になってしまった。時間の流れが絶対に早くなっている。そうに決まってる。
九時ぐらいに起き、一階に下りると誰もいなかった。
平日だし当たり前か、と思って顔を洗って歯を磨いて、食パンをトースターに突っ込んでから冷蔵庫で冷やされた牛乳を飲む。チン、と鳴ってトースターから食パンを取り出して、バターを塗って苺ジャムを塗って、コップに牛乳を注ぎ足してからテーブルへ移動する。無音の中むしゃむしゃ食べて牛乳をたまに飲んで、ふと手が止まってハッとして、またむしゃむしゃ食べて牛乳を飲む。皿とコップを洗って、ソファに移動してテレビをつけて、ぼんやりと見る。
情報番組がただ流れてる。誰かが喋って誰かが笑う。俺しかいないリビングにその笑い声が虚しく響く。自然と視線はキッチンに向いた。何度目になるかわからないため息を吐き出し、俺はソファに寄りかかった。
気付いたら時計の針は十一時を指そうとしていて、いかんいかんと我に返り、今日はなにをすべきか頭を回転させる。
参考書でも買いに行こうかな、一応受験生だし。昼飯どうするかな、隣駅のでかい本屋に行くか。そこで飯食って、帰りに立ち寄ろうかな。せっかくの夏休みだし、行けるときに行かなきゃな。どうしようかな。
また無意識にぼんやりしていると、テーブルに置いたスマホが震えて身体がビクッとなった。びっくりしたあ、と思いながらスマホを手に取り、今度は身体が跳ね上がる。
え、え、え、え?
震える指でスマホ画面をタップする。
「はい!」
『今なにしてんの』
間違いなく龍河先生の声が耳に聞こえる。
嘘だろ、え、なんで。
「え、あの、家にいます」
『なんか予定ある?』
「全然ないです」これはまさか。
『じゃあ二時間後にそっちの駅集合。裕吾と将太にも連絡しといて』
「あ、はい!」わおわお!マジか!
『じゃあな』
電話が切れた。
しばらくその場でじっとする。じわじわと沁み込んで、俺の顔は緩みに緩みまくって笑いが止まらないけど笑ってる場合じゃない。
えっと、どうすればいいんだ。そうだ、まずはあいつらに電話して、ああっ!どうしよう、なに着てこう。いやいや、まずは電話!
裕吾にかけてみる。暇してたのだろう、すぐに出た。
『はいはーい』
「裕吾!今日なにしてる!」
『なになにその切羽詰まった感じ』
「今先生から電話があったんだよ!二時間後に駅集合だって!」
『ええええっ!ちょと待て……』五秒ほどの沈黙のあと、沈んだ声が聞こえてきた。『ダメだ、なんとかできないか頭フル回転させたけど、どうしても外せねえ用事がある』
「マジかあ……」
『でも夜は空いてるぞ!四時以降なら!』
「その時間までいてくれるかな。ただ集合って言われただけだし」
『でもこれはあれだろ?この前話してた将太んとこと凌のバイト先に行くってやつなんじゃねえの?』
「そうか。ってことは夜まで一緒にいてくれるのかな」
『そうであってほしい』
「わかった。じゃあ夜までだってわかった時点で連絡する」
『頼む!必ずそうしてくれ!ああああっ!』
「なんだよ」
『なに着てこう』
「俺も思った」
『でも悩むほど服持ってねえや』
「たしかに」
『まあいいや。とにかく夜までだったら連絡くれ』
「了解!」
電話を切り、すぐ将太に電話するも出ず。
ああ、これは店手伝ってるな。いや、待てよ。突撃訪問ってのもアリだな。ふふふ、将太の驚いた顔が楽しみだぜ。
あれよあれよと時間は過ぎ、約束の二時間後。
待たせてはいけないと思って、俺は二時間後だと思われる一時の二十分前、十二時四十分ごろから駅の改札前で今か今かと龍河先生の到着を待っている。
そしてついにやって来た。神々しい光を纏って、龍河先生が歩いてくる。
眩しい、ああ眩しい。なんだこの光は、お前は一体何者だ!と駅にいる全員が目を細めたに違いない。
今日の龍河先生は、大きな葉っぱがプリントされた紺色のアロハシャツに紺色のハーフパンツ、足元は白いスニーカー。閉じたアロハシャツの首元からくすんだ青色のTシャツが見えている。俺にとってアロハシャツと言えば、ウクレレ持った陽気な人が着ている派手なシャツというイメージしかなかった。
なるほど、こうやって落ち着いた雰囲気で着ることもできるのか。それにしても先生、今日もかっこいいです。
「お待たせ」
「いえ」
「なんか変わったな、この駅」
「そうですか?」
「俺が住んでたときはもっとしょぼかった」
「そうか。工事してたの五年前ぐらいですもん」
「へえ」
「あ、そうだ。裕吾はどうしても外せない用事があるとかで、将太は電話に出ませんでした」
「そっか」
「でも裕吾は四時以降ならがら空きだそうです」
「なら夜来ればいいじゃん」
「じゃあ連絡しときます!将太はたぶん店手伝ってると思うんですよね」
「じゃあちょうどいいな。道案内よろしく」
「はい!」
将太の家は駅から歩いて十分ぐらい。一階の半分が店舗、店の奥と二階が居住スペースになっている店舗兼用住宅というやつである。店舗面積はそれほど広くないものの、飯がうまいからいつもお客さんで賑わってる人気店で、俺も俺の家族も昔からお世話になっている。だから将太とは家族ぐるみの付き合いだ。
おじさんが作る飯はマジでうまい。どれだけうまいのか、先生に早く食ってもらいたいし、自慢したい。ああ、楽しみだ。
「そういえば今日平日ですけど、学校行かなくていいんですか?」
「今日は代休。この前の休みんとき校長に付き合わされたから」
「ゴルフですか?」
「なんでゴルフなんだよ」
「いや、なんか休日の付き合いっていったらゴルフかなと」
「ゴルフだったらぜってえ行かねえ。そもそもやったこともねえよ」
「じゃあなにに付き合ったんですか」
「通訳」
「え?」
「よくわかんねえ集まりがあって、そこに外国からのお客さんが来るからって呼び出された」
「校長も大変なんですね」
「俺を労えよ」
「あ、ご苦労様です」
「凌、これっぽっちも思ってねえだろ」
「思ってます。心底思ってます」尻を軽く蹴られて、俺も龍河先生も笑う。「でもほんとに来てくれるとは思ってませんでした」
「ん?」
「先生忙しいですし、遠いじゃないですか」
「関係ねえよ。約束しただろ」
「……はい、そうですね」
「なんで笑ってんの」
「嬉しいなと思って」
なんか照れてしまって前を向いて歩くけど、たぶん今、すごい見られてる。あの笑みを浮かべた龍河先生が絶対横にいる。と思ったら、歩きながら寄りかかられて、俺はおととととと、と体勢を崩しかけて踏ん張って、龍河先生が転ばないように肩で支えた。
「ちょっと、危ないですよ」
「可愛いなあ、凌は」
「どこがですか。ちょっと危ないですって」
ふふんと笑って、龍河先生はまっすぐ歩き出す。
この人はどうしてこうもやることなすこと可愛くてかっこいんだ。ほんとずるい。ずるいよ先生。
「そうだ先生。俺、先生たちのアルバム全部買いました」
「マジか。毎度」
「裕吾も将太も買いましたよ」
「気に入ってくれたんならよかった」
「気に入ったなんてもんじゃないですよ。べた惚れです」
「そりゃ嬉しいな。ほかのメンバーにも言っとく。泣いて喜ぶよ」
あの愛想の欠片もない人も泣いて喜んでくれるんですか、と咄嗟に訊きそうになったがぐっと呑み込む。
「来年の今頃は、先生たちは音楽漬けなんですね」
「だな。待ち遠しいよ」
そう言って微笑む龍河先生。なぜか突然、猛烈な不安に襲われた。前を向いて歩く龍河先生の目がすごく遠いところを見ていて、このまま手の届かない遠い場所へ行ってしまうんじゃないかって。
「どうした?」
歩みが遅くなった俺を振り返って龍河先生が訊く。
縋りたくなった。どこにも行かないですよねって、これからも俺たちと一緒にいてくれますよねって、縋って訊きたくなった。でもそれは俺の勝手な望みだとわかってる。だから言えない。
「いえ」と笑って龍河先生の隣に並ぶ。
こうやってずっと隣を歩けたら、どれだけ幸せだろう。先生が隣にいてくれたら、どれだけ心強いだろう。
そう願いながらも、まったく違う道を歩みはじめる日が訪れることはちゃんとわかってる。それでも今は、どうか、と願わずにはいられなかった。
てくてく歩き、将太んちに到着した。「とまり」とひらがなで書かれた白い暖簾をくぐって店に入ると、おじさんとおばさんの元気な声に迎えられた。
「いらっしゃい!」と言って、二人が笑顔になる。「あら、凌君」
「こんちは。昼食いに来たんだけど、将太いる?」
「いるいる。トイレ行ってるだけだからすぐ戻ってくるわよ」
おばさんがそう答えたタイミングで、扉を閉めていた龍河先生が俺の隣に立った。
「あ、おじさんおばさん。うちの高校の先生で龍河先生です」
「はじめまして、龍河です」と会釈する。
おばさんの頬が染まり、乙女のごとく照れているように見えるのは俺だけだろうか。なぜかおじさんまでもがはにかんでいるように見えるのは俺の気のせいだろうか。
「あら、やだ」と言いながら髪を手で撫でる。「まあこんな汚いとこに、まあまあどうしましょ。どうぞお掛けください」
おばさんに案内されて奥の四人席に腰かけた。お客さんはまだいるものの、昼のピークを過ぎて席は所々空いている。おばさんが水を二つ運んできたところでエプロンをつけた将太が現れた。で、固まった。
「よお」にやける顔を隠し切れない。ああ、楽しい。
口をぱくぱくさせる将太の顔がみるみる赤くなっていく。
「な、な、な、な、な」
なんでいんのと言いたいんだろう。
「将太、おすすめなんだっけ」
将太の動揺なんて気に留めず、メニューを眺めながら龍河先生が将太に訊く。俺は可笑しくて可笑しくて、ついに笑い出した。
「ごめん将太。電話したんだけど出なかったから直接来ちゃった」
「ちょ、ちょっと待って」呼吸を一つ、二つ、三つして、テーブルに近づいてきた。「えっと、え?どうされたんですか?」
「飯食いに来た」
「そう、ですよね。そりゃそうですよね」
ああ面白い!ああ楽しい!裕吾にも見せたい!
おばさんは息子の隣で、おじさんはカウンターの中から、見目麗しい龍河先生をぽうっと見つめている。動揺しまくりの息子は眼中にないようだ。
「えっと、おすすめですよね。えええええと、あ!カツカレーとレバニラが人気です」
「凌はいつもなに食ってんの」
「決まったもんはないですけど、レバニラ好きですね」
「じゃあレバニラにする」
「俺はどうしようかな」メニューをざっと眺め、目が留まる。「あ、今日はアジフライ定食にしよ」
「うわ、それもうまそうだな」と悩む顔になってメニューを覗く。「アジフライ単品ってありますか?」
龍河先生がおばさんを見る。おばさんの頬はさらに染まって満面の笑みになる。
「ありますよ」
いや、ないだろ。ここ定食しか出してないだろ。
俺も将太も突っ込みたい気持ちをぐっと堪えておばさんの相好崩れた顔を見るが、おばさんは龍河先生に夢中である。
「じゃあそれもお願いします」
「はい!ちょっと待ってくださいね、すぐ作りますから」
「お願いします」
おばさんがカウンターの中に入り、将太が俺の隣に座る。カウンターからはなにやらきゃっきゃと興奮気味の楽しそうな声が聞こえてきた。
「いやあ、驚いた」
「すまんすまん」
「あの、たぶんいろいろ出てくると思うんですけど、無理して食べなくていいですし、食べ切れなかったら残してもらって構わないんで」
想像できるわ。だってアジフライ単品で出しちゃうぐらいだもん。俺が一人で食いに来たときだってなんかしら出してくれるもん。
龍河先生は将太が言ったことを聞いているのか聞いていないのか、店内をぐるりと眺めている。
「俺こういう家庭的な店好き」
「あ、ありがとうございます」頭を下げる将太はまだどこかぎこちない。「凌ちゃん、水ちょうだい」
「どうぞ」
一口だと思ったら、将太はごくごくコップの水を飲みほした。それで少し落ち着いたのか、将太の顔がふっと綻ぶ。
「まさかほんとに来てくれるとは思ってませんでした」
「それ俺もさっき言った」
「信用ゼロだな」
「違います違います」顔の前で高速で手を振る。「先生、いろいろ忙しいでしょうし、ここまで遠いですし」
「それも言った」
「約束したんだから来るに決まってるだろ」
あのときの俺と同じように、将太は嬉しそうに笑って頷いた。
「はい、ありがとうございます」と言った将太の目が入口に向く。「すいません、ちょっと行ってきます」
立ち上がって入口に駆けて行った将太はお客さんのお会計をし、「ありがとうございました」とお客さんを見送った。将太はそのまま今お会計をしたお客さんの席に向かい、テーブルを片付け、食器類をカウンター内の流しに置き、布巾を持ち出してテーブルを拭きはじめた。
ずっとその様子を眺めていた龍河先生の顔が俺に向き直る。その顔は柔らかく微笑んでいて、それを見た俺はほっこりとあったかい気持ちになった。
「お待ちどうさまあ!」
元気な声とともに、レバニラ定食とアジフライ定食と単品アジフライが運ばれてきた。今度はおじさん登場。定食は白飯、味噌汁、おかず、お新香のセットである。お客さんに出す白飯は誰もが思う一膳分だが、今おじさんの手にあある白飯は漫画の世界かな?って思うぐらいてんこ盛り。でもこれはいつものことで、俺が食いに来たときもてんこ盛り。優しさのてんこ盛り。
茶碗と皿をテーブルに並べながら、おじさんはしげしげと龍河先生の整った顔を凝視する。
おじさん、見すぎだよ。
「うまそ」
龍河先生はそう言って、テーブル脇にまとめてある箸に手を伸ばした。俺も手を伸ばしたとき、今度はおばさんがやってきた。一人ではない、手に持つお盆には小皿がいっぱい。定食を運んできたおじさんも、いつの間にかお盆に小皿をいっぱい乗せていた。その小皿たちが次々とテーブルに置かれていく。
肉じゃが、コロッケ、からあげ、ほうれん草の胡麻和え、かぼちゃの煮つけ、いかの煮つけ、いり豆腐、蓮根のきんぴら、おくらとささみの中華和え、シュウマイ。どれも少しずつ、ちょっと食べてみてよ、ぐらいの量が小皿に盛られている。明らかにメニューにないものもあり、これは渡真利家の食卓に並ぶはずだったんじゃないかと心配になってしまう。
そんなこんなで、四人掛けのテーブルはあっという間に埋め尽くされた。将太が頭を抱えてる。
「お父さんお母さん、こんなに食べれないって」
「なに言ってるの。せっかくいらしてくださったんだからこのぐらいはお出ししないと」
「出しすぎだよ」
息子の小言なんてどこ吹く風。おばさんはにっこり笑う。
「先生、遠慮せず召し上がってくださいね。ほかにも食べたいものあれば仰ってください。あ、あとごはんおかわりできますから」
いや、できないだろ。ここそんなサービスしてないだろ。
申し訳なさそうにする将太と、笑いを堪える俺。テーブルに並んだいくつものおかずを嬉しそうに楽しそうに眺めていた龍河先生が、その笑顔のままおじさんとおばさんを見上げた。
「ありがとうございます。遠慮なくいただきます」
おじさんとおばさんは見えない波動を受けてちょっとよろめいた。
わかるわかる、どんっと鳩尾あたりにくるよね。年齢問わずなんだな、やっぱり。
ふわふわした足取りでおじさんとおばさんはカウンター内に戻り、将太は疲れた顔でぺこっと頭を下げた。
「すいません、押し付けるようにこんなにいっぱい」
そんな将太を見て、箸を割る龍河先生の手が止まる。
「なんで謝んだよ。これはご両親のご厚意だろ?お前を大切に想うからこそ、俺をこうやってもてなしてくれてる。お前は喜ぶべきだし、俺はすげえ嬉しいよ」
「……はい、そうですね」将太は照れたように笑い、テーブルに広がった皿に手のひらを向ける。「どうぞ、どんどん召し上がってください。俺は手伝いに戻ります」
そう言って将太はカウンターの中に消えてしまった。きっと気恥ずかしかったんだろうし、龍河先生の言葉が嬉しかったんだろう。俺も嬉しかった。
龍河先生は箸を割って「いただきます」と手を合わせ、レバニラを口に運ぶ。「うまっ」と声を漏らして白飯も口に入れる。
ああ、相変わらずいい食べっぷりですね。可愛いのにかっこいい、かっこいいのに可愛い。ほんと、反則ですよ。
俺もいただきますと手を合わせてからアジフライにかぶりつく。衣はさくさく中はふわふわ、そして熱々。
「うんまあ」
「あ、俺も食いたい」と龍河先生は言って、べつに盛られたアジフライを箸で取ってかぶりつく。サクっと音が鳴った。「うまっ」
箸が止まらずひたすら食べる。うまいから食べられる。並べられた皿に箸をつけるたび、龍河先生は「うまっ」と感激のご様子。それを眺める渡真利家も感激のご様子。よかったよかった。
「どれもうまいっすね」
「すげえうまい」
その言葉に俺は嬉しさ全開で笑ってしまう。
「よかったです。気に入ってもらえて」
「自分が褒めてもらったみたいな顔だな」
「はい。ここの味が褒められるのはほんと嬉しいですから」
何度か小さく頷いて小さく笑い、龍河先生は「そっか」と言った。そしていかの煮つけを口に入れる。
「渡真利家とうちは家族ぐるみの付き合いなんです。幼稚園で将太と仲良くなって、いつからかは覚えてないですけど、いつの間にか家族で飯食いに来るようになってました。それからずっとお世話になってるし――」
過去に意識が飛び、自然と箸を持つ手が止まる。
「うちがいろいろあったときも、ここで将太と一緒に飯食わせてくれて、笑わせてくれて、励ましてくれて、おじさんとおばさんには、もちろん将太にも、いっぱい助けてもらいました。だから俺にとって渡真利家は、もう一つの家族みたいなもんなんです」
べらべら喋ったところで我に返る。俺はなにを喋ってしまってるんだろう。
視線を上げると、龍河先生は右手に箸を持ったまま俺をじっと見つめていた。俺はなにかを誤魔化すように慌てて口を開く。
「えっと、なので、ここの味を褒められると嬉しいって話です」
なにか訊かれるかな、とわずかに身構えたが、龍河先生は俺を見つめる目をつと下げ、「そうか」とだけ言って箸を動かしはじめた。俺はどこか安堵していて、でもそれが情けなく思えて、龍河先生にバレないよう小さく息を吐き出した。
先生に話せないわけじゃない。きっと先生に話したら止まらなくなる。全部吐き出したくなる。そうやって弱い自分が剥き出しになるのが怖いんだ。
少しして昼飯がまだだった将太が加わり、おかげでぎこちない空気はなくなった。三人で賑やかに話しながら笑いながら、おじさんが作ってくれた料理を全部平らげた。腹いっぱいである。
「おなかいっぱいになりました?まだ食べれるならお持ちしますけど」
皿が空になった頃を見計らってやってきたおばさんはそう言った。本気で言ってるんだろうか、と疑うようにおばさんを見上げるが、おばさんは至って本気。こうなると笑うしかない。
「おばさん、さすがにもう食えない」
「あらそう?先生もおなかいっぱいになりました?」
「はい、十分いただきました」龍河先生も笑ってる。「ものすごくおいしかったです。ご馳走様でした」
「こんなものでよければいくらでもお出ししますよ」
「こんなものじゃないですよ。俺にとってはご馳走です」
「まあ」
おばさんは瞳をきらきらと輝かせて感動し、手近にあった椅子を引き寄せるとその場に座った。いつの間に来ていたのか、ちゃっかりおじさんも椅子を持ってきておばさんの隣に腰かけると、龍河先生に訊ねた。
「うちの息子がご迷惑おかけしていませんか?」
「はい。と言っても、俺は英語を受け持ってるだけですので、将太の様子を常に見守ることはできていないんですが、授業中はいつも熱心に聴いてくれてますし、わからないことは自ら学ぼうとしてますし、それをしっかりと結果に繋げることができています。すごく一生懸命です、将太は」
「そうですか」
ほっとした様子でおじさんは表情を緩めた。隣にいるおばさんも。そんな二人に笑いかけ、龍河先生は将太に視線を移して言った。
「将太は、心根がすごく優しい子です」
「え?」と渡真利家の声が揃い、龍河先生の視線がおじさんとおばさんに戻る。
「俺は赴任してまだ半年も経たないんですが、その短い間に何度も将太の優しさを感じました。人に対する思いやりが強いんです。それがなんでなのか、お二人を見て納得しました。お二人に大切に育てられたからこそ、将太はこんなにも人を想うことができるんだって、今日それがわかって俺はすごく嬉しいです」
おじさんもおばさんも俯いてしまった。おじさんは唇を噛み、おばさんは指で目元を押さえている。将太は顔を赤くしながら、嬉しさ半分恥ずかしさ半分で居心地悪そうにしている。俯いたまま頭を下げたおじさんとおばさんの顔は、頭を上げたときにはもう笑顔に変わっていた。
「ありがとうございます。自慢の息子ですから、先生にそう仰っていただけて本当に嬉しいです。今後ともよろしくお願い致します」
おじさんとおばさん、遅れて将太も深く頭を下げ、龍河先生も「こちらこそよろしくお願い致します」と丁寧に頭を下げた。俺は一人取り残された気分で頭を下げ合う四人を見ていたが、心はほかほか。お腹もいっぱい、心もいっぱい、なんて呑気に思っていた。
姿勢を戻したおじさんが龍河先生と向き合う。
「うちのもう一人の息子、凌君のこともどうぞよろしくお願いします」
え?
「凌君も可愛い自慢の息子ですから」
え?
「よろしくお願いします」とおじさんとおばさんはもう一度言って、俺のために頭を下げてくれた。俺も慌てて下げる。なぜか将太も頭を下げてくれて、俺は喉が熱かった。
気恥ずかしい空気を残して、おじさんとおばさんはほったらかしにしていた仕事に戻り、俺と将太は照れ笑いを浮かべて顔を見合わせ、どちらともなく声を上げて笑い合った。笑い合う俺らを見つめる龍河先生の目は優しい。
「あ、そうだ。将太、夜も手伝い?」
「ううん、夜は坂口さん来てくれるから」
「じゃあ将太も来てよ。夜は俺んとこのバイト先に行くからさ。裕吾もそこから合流する」
「行く行く」
「裕吾とは五時に駅前で待ち合わせてるんだけど、将太はどうする?もっと早く来れるなら来れる時間で待ち合わせようよ」
「いや、裕ちゃんと一緒でいいよ」
「そっか、わかった」
「よし、じゃあ俺は手伝いに戻るね」
「うん、ありがとう」
「先生、ゆっくりしてってくださいね」
「ああ」
立ち去る将太の背中を見送って時計を見ると、もうすぐ三時になろうとしていた。さて。
「五時までどうしますか?」
「どうすっか」
「久しぶりでしょうし、どっか行きたい場所ありますか?」
「ない」
即答。
でもそっか、暮らしてたって言っても十五歳からの数年だもんな。とくに思い入れとかはないか。
「じゃあ、とりあえず腹ごなしに駅前ぷらぷらしますか?」
「だな。凌は行きたいとこねえの?」
「うーん……あ、本屋に行こうかなとは朝思ってましたけど」
「なら本屋行くか」
「え、いいんですか?」
「なんで」
「いやなんか、付き合わせちゃう感じでいいのかなって」
龍河先生が頬杖ついてじいいいっと見てくる。
え、なに?俺なんか変なこと言った?え、ドキドキしちゃうんですけど。
「凌のそういうとこ好きじゃねえ」
「ええええ!」ショーーーック!
「なんで遠慮すんの」
「なんでって」そりゃあ……ん?なんでだ?
「凌からしたら気遣ってるつもりなんだろうが、それはただ自分が傷つきたくねえだけだろ。付き合わせたら申し訳ねえ、付き合ってもらうことに気が引ける、相手が負の感情を抱くと勝手に決めつけてるからそう思う。そうやって勝手に決めつけんのは、自分の価値を下げたくねえからだ。気の利かねえ奴だと思われたくねえ、嫌われたくねえ。そういう保守的な気持ちを、気を遣ってるように見せて誤魔化してるだけだ」
「……」泣きそうだ。
「今俺は凌と同じ時間を過ごしてる。凌と飯を食いたいと思ったから、凌に会いたいと思ったから、俺は凌に電話した。だから俺は今楽しいよ、すげえ楽しい。そう思ってる奴が、凌の行きたい場所に行くことをなんで嫌がる?」
「……」今そういうこと言わないで。
「それとも、凌は今楽しくねえの?」
「……楽しいです、嬉しいです、ものすごく」当たり前じゃないか。
「じゃあなんで遠慮してんの。そんなん邪魔じゃん。だろ?」
「……はい」うう、喉が詰まる。
「凌」
「はい」
「こっち見て」
「やです」
「泣き虫凌ちゃん」
「泣いてません」
「ふふん」
「泣いてませんってば」
「じゃあこっち見て」
「……先生のそういうとこ好きじゃないです」
「マジか、嫌われちった」
「……嘘です。好きです」
「ふふん」
ああ、完全に弄ばれてる。
今どんな顔してんのか想像つくわあ、と思って半分泣き顔のまま顔を上げると、案の定、龍河先生は満足げに嬉しそうに笑っていた。俺のいじけた顔を見て、あははは!と可笑しそうに笑う。
「悪い、言い方がきつかったな」
「いえ、嬉しかっただけです」
龍河先生は小さく笑い、コップに残った水を飲み干して立ち上がった。
「行くか」
「はい!」
席を立った俺らに気付き、渡真利家がカウンターからぞろぞろと出てくる。
「あら、もうお帰りですか」
「はい、ご馳走様でした」
「なんのお構いもしませんで」
「いえ、十分すぎるぐらいもてなしていただきました。ありがとうございました。とってもおいしかったです」
「先生にそう言ってもらえて嬉しいなあ」
「お父さん張り切った甲斐がありましたね」
「俺もやればできる」
「おじさんの料理はいつもおいしいよ」
「なんだよ、そんな嬉しいこと言ってくれちゃって」
「ほんとのことだもん。な?将太」
「うん、うちのごはんはおいしい」
「お父さん、今の録音しておくべきでしたね」
「くああ!失敗した!」
ぺちん!と自分の額を叩くおじさんを中心にみんなで笑って、龍河先生がポケットに手を入れる。
「会計をお願いします」
「なに言ってんですか、いいですいいです!」
「いや、そういうわけには――」
「わざわざ来ていただいた上にお代まで頂くなんてできませんから」
「俺が来たくて来たんです。あんなにうまいもん食わせていただいて、代金払わないなんてできません」
「いやいやいやいや」
こうなるだろうなとは思ってたけど、想像以上にわちゃわちゃしてるな。それにおばさん、財布を持つ龍河先生の手ちゃっかり握ってるし。さすがだな。
「お気持ちはすごく嬉しいんですが、生徒の親御さんからなにかをいただくようなことはできないですから」
この一言には、おじさんもおばさんも引き下がるを得なかった。不承不承に「そうですか」と呟いておばさんがレジに入る。
「凌の分も一緒で」
「え!それはダメですって」
「ライブに来てくれた礼だ」
「ええ?お礼しなきゃならないのはこっちですよ」
「いや」と言って、ふっと微笑んだ。「凌の気持ちが嬉しかったから」
くうぅぅぅぅぅ!鳩尾にソフトアタック!
そんな風に言われたら、そんな優しい顔で言われたら、もうなにも言えないじゃないかこんちくしょう!
「それじゃあ、またお言葉に甘えます。ありがとうございます」
「どういたしまして」
「二人合わせて千四百円ね」
「単品分入ってますか?」
「あれはうちのサービスですから。ゼロ円です」
しれっと言うおばさん。うんうんと頷くおじさんと将太。龍河先生はちょっと困ったように、でも可笑しそうに笑って、「ありがとうございます」と言われた代金を支払った。
渡真利家は外まで見送りに来てくれた。
「先生、来てくれてありがとうございました」
「またぜひいらしてくださいね」
「今日以上に張り切って作りますから」
「ありがとうございます。楽しみにしてます」
「将太、またあとでな」
「うん」
「おじさんおばさん、ご馳走様でした。今日もすごいうまかった」
「ふふ、ありがとう。いつでもおいでね」
「うん、また来る。家族でも」
「うん、待ってるよ」
おじさんとおばさんの優しい笑顔に胸があったかくなる。
「おじさん、おばさん」
「なあに」「どうした」
「ありがとう」
きょとんとする二人と、二人とそっくりな顔をしている将太に「それじゃ」と俺は片手を上げ、龍河先生は渡真利家に一礼する。俺と龍河先生は並んで歩き出した。
光陰矢の如し。俺はたった二時間でそれを嫌というほど痛感した。
五時までの約二時間、本屋に行って参考書を選んだり音楽雑誌を読んだり。CDショップに寄って龍河先生が好きなミュージシャンを教えてもらったり視聴したり。靴屋に入って欲しがったり試着したり。そんなことしてたら、ぴゅうん!と時間は過ぎていった。矢の如しじゃない。光の如しだ。
駅の改札に将太と裕吾がいる。龍河先生と二人で歩いてきた俺を見て、裕吾が感心するように言った。
「すげえなお前」
「なにが」
「いや、なんでもない」
「先生、さっきはありがとうございました。父も母もとんでもなく喜んでました」
「こっちが礼を言わなきゃだろ。あんなにいろいろ食わせてもらって」
「いいなあ、俺も食いたかった」
「いつでもおいでよ。二人とも裕ちゃんに会いたがってるよ」
「明日行こうかな」
「うん、おいで」
「将太が店の手伝いしなくても大丈夫な日にまた行きましょうよ。四人であのうまい飯食いたいです」
龍河先生に向かってそう言うと、龍河先生は「そうだな」と答えてくれた。少しほっとする。不確かな約束でも、俺らの未来に龍河先生がいるという希望が欲しかった。そんな未来が来ると思いたかった。
俺のバイト先である飲み屋『かねや』は、夫婦で営んでいる飲み屋である。だいぶ前から駅前に店を構えているらしく、店を訪れるお客さんの大半が昔からの常連さん。年齢をなぜか教えてくれないおじちゃんとおばちゃんは、俺の見立てだとたぶん六十後半から七十前半。からっとした性格でお人好し、俺のことも孫のように可愛がってくれて、だからなのか、それともこの店に集まる人がみんな陽気な性格だからなのか、俺は常連のお客さんからも可愛がってもらっている。愉快で楽しいバイト先だ。
店のドアを開けると、おじちゃんとおばちゃんと常連客が目を丸くした。
「凌ちゃん、どうしたの。今日バイトだっけ?」とおばちゃん。
「どうした。暑さでやられたか」とおじちゃん。
「凌ちゃんいなくて寂しかったんだよお」と常連さんその一。
「凌ちゃん、ビール追加ね」と常連さんその二。
「凌ちゃんは俺に会いに来たんだよなあ」と常連さんその三。
まだ五時だってのにだいぶ出来上がっている。
「今日は店員じゃなくて、お客としてきました」
「それはそれは、いらっしゃいませ」
「奥いいですか?」
「いいよ、好きなとこ座って」
奥の壁際に俺、その隣に龍河先生、俺の前に裕吾、その隣に将太。龍河先生を奥にと思ったけど、こっちがいいと言われてしまったから仕方がない。将太んちでのやり取りもあったから、俺は遠慮せず奥に座らせてもらった。
俺らが席に着くと、おばちゃんがすぐにお通しの松前漬けとおしぼりを持ってやってきた。すると、龍河先生を見て一言。
「いい男だねえ」
余計な感情を省き、ただ見たものの感想を言いました、というド直球な言い草に俺らは笑ってしまう。いい男と言われた龍河先生も戸惑うように笑って、「ありがとうございます」と会釈するしかないようだ。
「凌ちゃんのお友達?」
「あ、はい。でもこのいい男は高校の先生です」
ああ?と龍河先生は無言で俺を牽制する。
すいません、調子に乗りました。
「へえ。こんないい男が学校にいちゃ大騒ぎだわよ。大変だねえ」
「先生も昔この辺住んでて、この店来てたんですよ」
「あら!そうなの?」
「はい、だいぶ前ですが、お世話になってました」
「あそう……」と言って、記憶を探るようにおばちゃんの顔が険しくなる。その顔がパッと明るくなった。「もしかして、五、六年前じゃない?」
龍河先生が目を瞬いた。
「そうです」
「やっぱり!その頃いい男がよく店に来るってんで話題になってたのよ。そのせいか女の人のお客さんも増えてね」
「へええええ」俺と将太と裕吾の声が揃い、思わず龍河先生を見てしまう。
「いやあ、なんだか嬉しいわ。またこうして来てくれて」
「ここの出汁巻きが食べたいって来てくれたんです」
「あそう、じゃあさっそく作らなきゃ。ほかはなににする?」
「俺らはウーロン茶で。先生なに飲みますか」
「俺はビールを」
「はいよ。なんか食べる?」
うーん、と言いながら龍河先生は店内に貼られたメニューを見渡す。将太と裕吾もきょろきょろと壁を見る。
「じゃあ、ししゃもと、板わさを」
「はいよ。凌ちゃんたちはお腹減ってるの?」
「俺はそこまでですけど、お前ら減ってるだろ」
「うん、ほどほどに」
「俺は腹ペコ」
「うちおつまみしかないから、なんか適当に作ってあげる」
「わ!ありがとうございます!」
「すいません、ありがとうございます」
「おばちゃん、俺揚げ出しともつ煮食べたいです」
「はいよ。ちょっと待っててね」
少しして頼んだものがテーブルに並んだ。将太と裕吾のためにおじちゃんが唐揚げと野菜炒めを作ってくれたようだ。白飯と味噌汁もつけてくれている。おじちゃんの作る飯もうまい。バイトのときは俺もここで晩飯を食わせてもらってるから知っている。いいなあ、と腹は空いていないが思ってしまう。
「先生、出汁巻きどうぞ」
「いただきます」と出汁巻きを箸で割り口に入れる。その顔が綻び、「うまっ」と言ってさらに笑みを広げる。
「やっぱうめえ。健在だな」
「はい、お客さんみんな頼みますから」
作ってくれた料理をもぐもぐ食べながら、話はやっぱり自然とライブの話になった。将太と裕吾が勢い込んでどれだけ感動したか、どれだけ龍河先生がかっこよかったかを熱弁する。将太は熱くなりすぎてむせ、裕吾は興奮しすぎてご飯粒を飛ばし、もちろん将太に「裕ちゃん汚いよ」と注意されていたが、とにかく熱く語り尽す。ライブにまた行きたいと言う二人に、龍河先生は「いつかな」と、ここでもまた遠い目をしていた。
テーブルにはおつまみ類だけが並び、龍河先生はすでにビールを一瓶空けて、今二本目が空になった。お酒強いんですね、とそれさえも不思議とかっこよく思えてしまう。ああ、これが龍河マジック。
話の切れ間で、裕吾が「はい!」と手を上げて居住まいを正した。
「どうぞ」
「父親と話しました」
「おお」
「お父さん聞いてくれた?」
「まあ、納得はしてねえけど、話は最後まで聞いてくれた」
「親父さんなんか言ってた?」
「勝手にしろ、だとさ」
「……そうか」
「でもだいぶ進歩したんじゃない?絶対許さないって言ってたんだから」
「たしかに。まあ、すぐには無理だろうけど、いつかさ、裕吾が選んだ道を認めてくれる日が来たらいいな」
「うん」
「殴られなかった?」
「一瞬来るかなって思ったけど、なかった」
ちっと龍河先生から舌打ちが漏れる。ええ?と俺らは苦笑い。さらに「家庭訪問と称して殴りに行くか」なんて言うもんだから、俺らは大笑いした。
「でも、先生が言ってた区切りってのがつきました。今はもう、自分の考えに迷いはないっす」
「そうか」と微笑んで、龍河先生はビールを一口飲んだ。
「そういえば、先生ってなんで教員免許取ったんですか?音楽にまっしぐらって感じがするんですけど」
「あ、俺も気になる」
「俺も」
「校長に言われたから」
「え?」
「それだけですか?」
「ああ」
「じゃあ、取りたくて取ったわけじゃないんですか?」
「ああ、そもそも大学に行くつもりもなかった」
「え、じゃあなんで」
「それも校長に言われたからってなるな」
「はあ……」
どういうことだと間抜けな顔をする俺ら三人。龍河先生は小さく笑い、背もたれに寄りかかって腕を組んだ。
「凌には話したが、校長は俺が高一んときの担任なんだよ」
「へえ」将太と裕吾の声が揃う。
「日本に慣れねえ俺が高校卒業できたのは校長のおかげなんだ。音楽をはじめたきっかけも校長だしな」
「へえ」今度は俺と将太と裕吾の声が揃う。
「高一の冬休み前に、校長が急に音楽やったらどうだって言い出して、自分が持ってるギター寄越してきたんだよ。俺が音楽は好きだって一度だけ話したこと覚えてたらしくてな。たしかに音楽は好きだったが、楽器に触れたことはなかった。だが、一音鳴らしたとき、身体が痺れた。身体が熱くなって、なんとも言えねえ感情が湧き上がってきた。俺は音楽で生きてくんだって直感的に感じたんだ。それからは音を鳴らすことに夢中になってのめり込んで、だから高校卒業したら凌の言う通り、音楽だけの生活に浸ろうと思ってた」
「それがなんで大学に」
「ちょうどお前らぐらいの頃かな、校長から大学に行けって言われたんだよ。俺は行くつもりねえって断ったんだが、校長に――」
――お前が音楽の道に進むことは賛成だし応援してる。だけど、大はもっと外の世界を知らなきゃダメだ。自分が今いる場所がちっぽけな世界なんだってことを知らなきゃダメだ。外ではもっとたくさんの面白いことが起きていて、たくさんの面白い奴らがいる。外の世界に目を向けて学ぼうとする気持ちがなきゃ、人を魅了する音楽は作れない。俺はそう思う。
「たしかになって思ったよ。いろんな国で暮らしてはいたが、それはあくまで守られた外の世界であって、俺自身の外の世界ではねえ。こんなちっぽけな世界じゃちっぽけな音楽しか作れねえなって思ったから、大学に行った」
「校長いいこと言いますね」
「言っとくよ」
「やめてください」
「でも、どうして教育学部だったんですか?」
「教員免許持っとけばいざというとき役に立つぞって」
「え?」
「お前は語学が堪能だから英語教師にでもなっとけって」
「え?」
「校長が言うならそれでいいかって」
「校長適当ですね、先生も」
「言っとくよ」
「やめてください」
「でも教員免許取るのってすごい難しいですよね?音楽と両立するの大変じゃなかったんですか?」
「すげえめんどくさかった。教育実習が一番面倒だったな」
「先生、生徒の前で言わないでください」
「今は思ってねえよ」
「安心しました」
「でもよかったって思ってるよ。一日二十四時間じゃ足りねえって思うぐらい時間に追われてたが、あの時間がなきゃ、俺は今の俺になれてなかった。面白え奴、気に食わねえ奴、すげえ奴、ほんとにいろんな奴がいて、そいつら一人一人が別もんで、そんな奴らからすげえ刺激を受けて、喜怒哀楽が爆発するようなことが何度もあって、その度に自分が変わってった。新しい自分に気付いたし、自分の間違いにも気が付いた。外の世界はでかいんだって気付かされた。だから、これまで出会った奴ら全員に感謝してるが、外の世界に引っ張り出してくれた校長にはほんとに感謝してる」
「俺も校長に感謝してます」
「ん?」
「だって、校長が別の学部勧めてたら、俺らは先生とこうやって飯食えてないですもん」
「校長万歳」
「あっぱれ校長」
「だな。そういう意味でも感謝してるよ、俺は」
くううぅぅぅぅぅ!
それって先生も俺らと出会えてよかったってことですよね?そういうことですよね?ああもう、抱きつきたい。ぎゅっとしてぎゅっとされたい。先生、大好きです!
「すいません」と龍河先生がおばちゃんを呼ぶ。
「はいはい」
「日本酒を冷で」
「銘柄は?」
「さっぱりするやつならなんでも。お任せします」
「はいよ。あ、そら豆食べる?頂いたやつがあるから食べてよ」
「じゃあぜひ。ありがとうございます」
「ううん。凌ちゃんが楽しそうだからおまけしちゃう」
「バレましたか。すごい楽しいです」
「見てればわかるよ。ちょっと待っててね、すぐ持ってくるから」
その言葉通り、日本酒とそら豆はすぐに運ばれてきた。店内はほぼ満席状態になっていて、おじちゃんもおばちゃんも生き生きと忙しそうに立ち働いている。ちょっと申し訳ないなと思いながら、おじちゃんおばちゃん、常連客の笑い声を聞いていると、将太が徐に口を開いた。
「先生の理想の自分ってどんな自分なんですか?」
「ん?」日本酒を舐めて、龍河先生が顔を上げる。
「前に仰ってたじゃないですか。理想とする自分はまだまだ先を歩いてるって。追いつけるとは思ってないって」
「ああ」思い出したように呟いて、うーんと宙を見る。「言葉で表せるようなもんじゃねえんだよな。言葉にできるようなことなら俺は追いつけると思ってるし、実際追いついてる。だから俺の言う理想の俺は、俺の中にしかいねえんだよ」
ぽかんとしてしまう。正直、なに言ってんだろう状態。でもなんかわかるような気もする。言葉にできない理想ってなんだろう。俺の理想の俺ってなんだろう。
反応なく見つめられるだけの龍河先生は少し困ったように笑う。
「納得してねえ顔だな」
「いや、そういうわけじゃないんですけど、なんか、わかるようでわからないというか」
「言葉にできねえからうまく言えねえんだよ」
「俺もなにがわかんないのかよくわかりません」
「先生」将太がまた口を開く。その表情はすごく真剣だ。「なにか気を付けてるというか、心がけてることありますか?理想の自分になるために」
その問いかけの奥にあるものを探すように、龍河先生は少しの間将太を見つめた。
「将太が欲しい答えにはならねえかもしれねえが、自分に正直になんなきゃなんもはじまんねえなとは思ってる」
「正直に……」
「よく思われたい、評価されたい、認められたい。誰だってそう思って、見栄を張ることあるだろ。もちろんそうしなきゃなんねえときもあるが、自分の欲を満たすためだけに、自分を偽ることほどみっともねえことはねえよ。そんなこと続けてたら、ほんとの自分がわかんなくなるだろ。自分がなにをしたいのか、なにを目指してるのか、どこに向かって歩けばいいのか。自分に嘘つくってことは、周りの人間にも嘘ついてるってことになる。そんな奴、誰が信じる?たとえ自分の本当が周りに笑われようが蔑まれようが、俺は自分に嘘はつきたくねえ。なりたい自分になるためには、まずは自分が自分自身を受け入れなきゃはじまんねえだろ」
「……そうですね」
神妙な顔で頷く将太。深刻とも取れるその表情に、俺も裕吾も龍河先生も首を傾げた。
どうしたんだろう、なんかあんのかな。
「どうした将太。なんか悩みか?」
裕吾が将太の顔を覗き込むようにすると、将太は慌てて身を引いてその顔に笑顔を貼り付けた。
「ううん、なんもないよ。ただほら、俺らも進路決める時期じゃん。なんか将来のこととか考えちゃって」
「なんだよ、心配すんなって。お前には俺と凌と、先生がついてる!」
裕吾が将太の肩に腕を回し、二の腕をばしばし叩く。
「ちょっと痛いよ」
将太は顔をしかめて裕吾を押しのけようとするが、逆に裕吾に抱きつかれてしまう。
「なんだよ、冷たいな。友達じゃないか」
「はいはい」とうんざり顔の将太。
ほんとに仲いいな、こいつらは。とやっぱり笑っちゃう。
「お前らみんな進学すんの?」
「はい、その予定です」
「正直なにになりたいとかまだわかんないんすけど、大学行っておいたほうが選択肢が広がるかなと思って」
「高卒と大卒じゃいろいろ変わってきますし」
「日本はアホみたいに学歴社会だもんな。ほんとくだらねえ」
「大卒しか雇わない企業もありますしね」
「大学出たから優秀ってことじゃねえのにな。もったいねえことしてるよ」
「うちの父親っすね。高卒バカにしてるんで」
「マジで家庭訪問するか」
「ちょっと見てみたいっす」
「進む道が違えば見える世界はたしかに違う。だが、そこでなにを見つけるかは自分次第だろ。選んだ道で人の価値を勝手に決めんじゃねえよ」
そう言って静かにお猪口を傾ける龍河先生は、見えない誰かに怒りをぶつけているように見えた。
音楽という道を選んだことをよく思わない身近な人がいるのかいたのか。それとも親しい人の中にそういう思いをした人がいるのかいたのか。どっちにしろ、俺は自分のやりたいこと、好きなことにまっすぐ向き合ってる人を間違ってるだなんてこれっぽっちも思わない。むしろかっこいいと思う。そういう生き方をできる人は強いと思う。先生のように。
「この日本酒うまいな」
「へえ。俺らにはまだわかんない世界っすね」
「日本酒飲める男ってかっこいいって思っちゃう」
「あ、わかる。あとブラックコーヒーね」
「なんだそれ」
怪訝な顔に笑顔を浮かべる龍河先生は、昼間会ったときから変わらない顔色で日本酒に口をつける。
「先生お酒強いですよね」
「うん、強いほうだな」
「結構飲んでるように見えるんですけど、まだまだ平気ですか?」
「ああ」
「酔っ払うとどうなるんですか、先生は」
「酔っ払ったぐらいじゃそんなに変わんねえが、すげえ酔っ払うとスキンシップが増えるらしい」
「え……」ちょっと酔わせてみたい。
心の声を読まれたのか、龍河先生は身体を少し俺側に向けると、頬杖ついて俺を覗き込むようにした。その顔にはあの笑顔。
「なに、俺を酔わすつもり?」
「いえいえいえ」嘘、酔わせたい。
「酔ってもいいが、酔ったら凌が介抱してくれんの?」
「はい、もちろん介抱しますよ」全身全霊で。
「ふうん。じゃあもっと飲もうかな」
「え?」マジで?
「介抱してくれんだろ?」
「はい、そりゃもちろん」お任せください。
「可愛いなあ、凌は」
「なんでそうなるんですか」先生が可愛いですよ。
ふふん、と笑った龍河先生は俺に寄りかかってくると、なんと!俺の肩に頭を預けてきた。
ぼふうううううんっ!
ちょっと、こんなこと女の子にもされたことないんですけど。はじめてが先生って嬉しすぎるんですけど!
でもやめてえええ!将太も裕吾も半分意識飛んでるからやめてえええ!
「凌んち泊まろうかな」
「え?」マジで?
龍河先生は身体を戻すと、そのまま俺を見て首を傾げる。
「ダメ?」
どふわばああああああんっ!
可愛すぎるだろおおお!なんでだろう、すごくドキドキしてきたぞ。ドキドキが止まらないぞ。
「いや、ダメじゃないですけど」むしろ大歓迎ですけど。
「マジで?」
「はい、うちでよければ」ようこそ我が家へ。
にやりと笑った龍河先生の手が伸びて、俺の頬をつまむ。
「冗談」つまんだ手が離れた。「明日仕事だもん」
「あ、そうですよね」ちっ、休んじまえ。
「優しいなあ、凌は」
「先生、酔ってます?」まさか……。
「全然」
どこからどう見ても素面の顔で言って、龍河先生はくいっと酒を飲んだ。
くそっ、酔っちゃえばいいのに。
でも先生って素面でもスキンシップ多いほうだよな?ってことはすごい酔っ払ったらどうなっちゃうんだよ。どんだけのスキンシップになるんだよ。ああ、酔わせたい。なんで俺は未成年なんだこんちくしょう!
悔しくて、俺はウーロン茶を飲み干した。
それからも龍河先生は日本酒を淡々と飲み続け、かなり飲んでるはずなのに結局最後まで酔っ払うことはなく、おじちゃんとおばちゃんをたまに交じえながら四人で笑って飲んで食べて、八時ごろにお開きとなった。
ここでもお会計悶着勃発。どう見積もっても通常の半分ぐらいの金額に「安すぎますよ」と龍河先生は抵抗を試みるも、おじちゃんとおばちゃんは「いいのいいの」とまったく取り合わない。年の功とは言ったもので、龍河先生もそれ以上は抵抗できずありがたく厚意を受け取った。俺らもなんだかんだ言いくるめられてまた龍河先生にご馳走になってしまい、三人で「ありがとうございます」と頭を下げた。
駅で別れる。
「今日は来てくれてありがとうございました」
「お店の方にお礼言っといて。将太もご両親に」
「はい」俺と将太の声が揃う。
「気を付けて帰れよ」
「はい、先生も。裕吾、またな」
「おう」
いつもと変わらない龍河先生の背中と、少し距離をとって歩く裕吾の硬い背中を見送る。ふと横を見れば、将太の表情もどこか硬いように見えた。将太が俺に顔を向ける。
「帰ろっか」
その顔はいつもの将太。でもなんかある。飲み屋での深刻な表情といい、今の硬い表情といい、なんかある。でも今はまだ訊いちゃいけない気がする。俺と裕吾に話すこと自体をまだ迷ってるように見えるから。もう少し様子を見て、苦しそうだったら訊いてみよう。
「うん、帰ろう」
二人で歩き出す。いつもの分かれ道で将太と別れ、俺は家までの道を歩きながらなんとなしに空を見上げた。
またいつか、と願わずにはいられない。すぐじゃなくても、またいつか。俺らが酒を飲めるようになって、みんなでべろべろに酔っ払う。そんないつかが来ればいい。
だけど、もしもそれが叶うとしても、その日が来るのは遠い遠い未来なんだろうなって、なんとなくそう思った。
≫≫ 九月へつづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
